志田歩/花よ 大地よ 月よ 銀河よ
制作にいたる20年
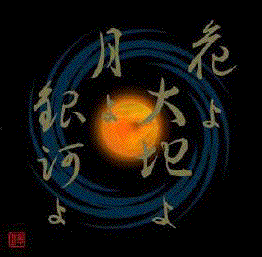
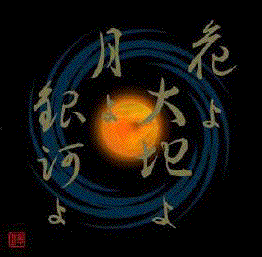
1983年7月30日
志田歩、大学四年生の夏休み。
ZIGZAG
EASTという音楽雑誌のスタッフをいっしょにやっていたカリスマ的な魅力を持つ友人Jが自殺。
その友人は会社を作ろうといい出して多くの人間を集めていた。僕も彼に声をかけられ集められたひとりだった。
当時の僕は自分の青臭さを持て余していたが、その友人はどんなに青臭くて無茶なことでも、ぬけぬけと自信たっぷりに語る口調で僕らを魅了した。
「こいつといっしょなら、何か無謀で面白いことができるんじゃないか」
当時の僕は、そんな風に曖昧で無責任な期待をもってJに接していた。
しかしそれを呼びかけた中心人物が突然、全てを拒否して死んでしまったのだ…。
なすすべもなく僕らは苛立ちをぶつけ合い、彼が集めた人間関係は自然消滅していった。それまでの価値観が崩壊した中で、彼の純粋さをあくまでも正しいと抱え込むなら、僕もまた死ぬしかないと考えるほどに思い詰め、母親をはじめとする多くの人に迷惑をかける。
そうした結果出した結論は、「彼のように純粋なままでいられなくても、生きることを選ぼう。会社員として社会に出ていこう」という、ごくごく凡庸なものだった。
1984年4月
ぴあに入社。以後6年半、ぴあの社員として本誌の音楽記事を担当する。
1986年頃
隔週で雑誌を作る仕事に追われる月日の経つ速さに脅える。自分自身でしっかりと時間の経過を蓄積として感じたいと思った時、思い付いたのは音楽活動だった。83年の時の仲間のひとりで、広告代理店に務めていたSの呼びかけに応じる形で、Trippin'
Musicを結成。
1988年
「BLUE
BOY」を作詞作曲。
クロコダイルで行ったTrippin'
Musicのライヴでは、学生時代のバンド活動では知ることが出来なかった特別な感覚を味わい、ライヴでヴォーカルを担当することが病みつきになる。しかしそのクロコダイルのライヴを最後にバンドは崩壊。とりあえず声を出す環境を維持しながら、新しいバンドを結成するためのメンバーを捜そうと、ヴォーカル・スクールに通い始める。
1989年
荒武靖との出会いを経て、ロック・バンド、Eternal
Heart結成。
1990年
Eternal
Heart崩壊。ぴあ退社。フリー・ライターとして原稿を書き始める。
Eternal Heartの主要メンバーであった荒武靖、久保昭二らと共にロック・バンド、OZma結成。
「BOYS ON THE
EDGE」を作詞作曲。
1991年10月21日
OZmaでミニ・アルバム『Home Sweet
Home』をリリース。
1992年
荒武靖がOZmaを脱退。
当初は残りのメンバーを中心に体制の立て直しを謀るが、結局荒武靖の脱退後、ライヴを行わないまま、OZmaは解散する。
1994年11月30日
学生時代から大ファンだった朴保が、日本でライヴ活動をやっていることを知り、11年ぶりに彼のステージを見る。
以後、フリー・ライターとして朴保を応援するようになる。
このステージでドラマーを務めていたのは伊藤孝喜。
1997年
朴保のスタッフだったY女史の強力な働きかけにより、Teaser結成。
ドラムスは伊藤孝喜、ギターの斉藤ケーシン、ベースのシローという顔ぶれは、全てY女史の紹介によるものだった。
2000年
83年の仲間のひとりであった山中ひとみさんが、たまたま僕が寿について書いた原稿を読み、レコード会社を経由して17年ぶりにコンタクトを取ってくる。これをきっかけに当時の仲間達が不定期に4〜5人集まって、近況報告を行うようになる。
2002年2月17日
NeverNeverLandで行ったアコースティックTeaserのライヴにて「光の中へ」を初演。
2002年3月15日
COUNTER
VILLAGE
外苑の中に、カンボジアに留学して伝統舞踊を学習している山中ひとみさんによるカンボジア・レポートのコーナーを設立。
2002年4月13日
カンボジアからの山中ひとみさんのメールで、Jの20周年の追悼イヴェントを2003年に行おうという提案がなされる。
東京で集まっている当時の仲間の有志も、それを受けて追悼イヴェントを実現しようと意志一致。
僕はそのイヴェントの場で、Jをテーマにした楽曲を収めたレコーディング作品を配布しようという意志を固める。
2002年4月26日
自分のプロデュース・イヴェント“WHO
IS THE Teaser
?”に、伊藤孝喜、ユーピンこと西村雄介との一回だけのプロジェクト、志田歩トリオで出演。
このライヴをきっかけに西村雄介のTeaserへの加入が決定することになった。
2002年10月25日
山中ひとみさんを含む四名で、2003年に予定しているJの追悼イヴェントの打ち合わせ。
何しろ10何年ぶりに逢ったりする人もいるので、つい近況報告や昔話に花が咲き、決めごとには時間がかかるのだが、おおまかなタイミングと場所だけは決定する。なにしろ今月末に発案者の山中さんはカンボジアに戻り、次に帰ってくるのは翌年の夏になるので、この日に決めねばならぬことが多々あるのだ。
風邪で寝込んでいるマスターの松崎さんを呼び出すという無茶までして、結局会場はNeverNeverLandに決定。
2002年10月26日
午前9時半に起床。まず歌詞を書く。今日演奏する「BOYS
ON THE EDGE
」では、出来れば即興で朗読を入れたいのだが、まだ自分の技量ではそこまではできない。ならば本番に近いぎりぎりのタイミングでその歌詞を書こうと思い至ったのである。
そしてそれが曲調にはまるかどうかを実験するため、一人でスタジオへ。一部に手を加える。ただしこれによって、曲順を変えざるを得なくなってしまった。どう考えてもここまで仰々しい「BOYS
ON THE EDGE
」の後に何曲も演奏するのは無理がある。ケーシンに了承してもらうしかあるまい。
会場には4時半入り。店の前に行くと伊藤孝喜とばったり。今回はノー・ギャラであるにもかかわらず、本当に入りの時間もかっちり守って律儀に来てくれる。嬉しい限りだ。
ライヴはアコースティックTeaserの初陣の時にも共演させてもらったSeaMoon、さらにTeaserの初代ベーシストとスタッフがリズム・セクションをやっているFlowerRoadとのタイバンとあって、リハや待ち時間までもがまるでパーティのように楽しい!
そして僕らの本番もミスは多々あったけど、誇るべき内容になったと思う。スタッフ、タイバン、客席にきてくれた友人、選曲、アレンジ、曲順、そうしたものがひとつひとつ確実に噛み合って、ちょっとしたマジックが生まれていた。こんなことは僕みたいな人間がどんなに狙おうとしたってできるものではない。
2002年12月26日・27日
朴保&切狂言のベーシストだった吉田達二の経営するスウィング・バンブー・スタジオで、レコーディングのためのリハ。
2002年12月28日
レコーディング当日。正午にスウィング・バンブー・スタジオに入る。今回レコーディングするのは「BLUE
BOY」「BOYS ON THE EDGE 」「光の中へ」の3曲。
26日に書いたような事情で、この『花よ 大地よ 月よ
銀河よ』の内容はかなりヘヴィだ。しかも「光の中へ」だけは今年完成した曲だが、「BLUE
BOY」は15年前、「BOYS ON THE EDGE」も90年に書いたもの。特に「BOYS ON
THE
EDGE」は、ヘヴィすぎるのでライヴでも数えるほどしかやってこなかった。放ちたいのに放つきっかけがなかった自分の想いをようやくこうして形にできる喜びは格別である。
それにしてもTeaserのリズム・セクションの素晴らしさ! そして一番足を引っ張るのは、やはり自分のギターとヴォーカル(苦笑)。
今回は僕のソロ名義ということで、選曲、曲順、アレンジなどは、僕の独裁。それにもかかわらずメンバー全員が、リズムを録り終わってからも、コーラスでも貢献してくれたし、全ての行程に立ち会い、見守ってくれたのは、ありがたいとしか言いようがない。

↑「光の中へ」でコーラスを入れるメンバー。
(左からユーピン、斉藤ケーシン、伊藤孝喜)
ア〜ンド斉藤ケーシン!! 実は彼はこうした正規のレコーディングは初めてなのだが、本番での強さには恐れ入った。エレキでの活躍はもちろんだが、彼のアコースティック・ギターが、全体にものすごい広がりを出してくれたし、「BLUE
BOY」での彼のコーラスは、ヘヴィな歌詞をポジティヴに聴かせるために素晴らしい貢献をしてくれた。
結果的に「本当に4人だけで演奏しているの?」といわれるくらい振り幅の広い音作りになったと思う。でもこれはこの4人でなければ絶対にあり得ない音楽なのだ。
スタジオでは別の部屋でパンタがリハをやっていたりという状況の中、途中で顔を出してくれた塚本晃に「俺はメンバーに恵まれている!」と思わずのろけてしまった。(一方で塚本と伊藤孝喜の絆の強さにはやけたりすることもあるんですけどね)

↑アコースティック・ギターをダビングする斉藤ケーシン

↑
いっさい力を出し惜しみすることなく、全ての行程を支え、27時レコーディング終了直後に力尽きたリズム・セクションの二人
↓

27時半にラフ・ミックスを受け取り、地獄の底から復活したメンバーと共に渋谷に。29時、居酒屋にて祝宴を終え、帰宅。
31時、ヘッドフォンでラフミックスを爆音で聴きながら、狂喜乱舞してから就寝。
2003年1月12日
午後1時から『花よ 大地よ 月よ
銀河よ』のTD。思いのほか難航し、26時を回った時点で、18日に続きを行うことにして作業終了。ひたすら耳だけに集中して長い時間を費やすのは、むしろレコーディングよりもヘビーであった。帰れなくなるまで付き合ってくれたTeaserのメンバーと共に下北沢に移動し、僕の部屋で電車が動くまで雑談。疲れたけれども楽しい日であった。お付き合いいただいたみんなに感謝。
2003年1月18日
午後2時からスウィング・バンブー・スタジオにて、『花よ
大地よ 月よ
銀河よ』のミキシングの続きとマスタリング。24時前に作業を終了。ミキシングをやった時とは良い意味であまりにも音の印象が違うのでビックリ。こちらが意図していた音の隅々までがすっきりと聴こえるのだ。
12年前に某レーベルで、OZmaのCDを制作した時は、マスタリングに立ち会うことさえさせてもらえなかったが、いかにマスタリングが重要な作業なのか思い知った。
2003年3月14日
『花よ 大地よ 月よ
銀河よ』の音源をもって、Jのご家族が暮らしている名古屋の実家を、一周忌以来、19年ぶりに訪ねる。秋に行う故人の追悼イヴェントにしても、彼に捧げた僕の作品のジャケットのデザインにしても、ご家族を悲しませるようなものには絶対にしたくないので、自分達の意向を先方に伝え、向こうの気持ちをおうかがいしようというのが目的である。
なにしろ19年ぶりということで、僕としてもかなり緊張したが、イヴェントのためにいっしょに動いてくれているOさんが、名古屋行きまで付き合ってくれるという形でプロデュース役を買って出てくれたおかげで、おおいに励まされ、助けられている。
先方の実家に着いたのは午後2時頃。
最初に故人のお母さん、弟さんと話す。ずいぶんと時間が経ってからの再会だが、故人のお通夜、一周忌での僕の表情、発言などを覚えていて下さったのには、驚いた。しかもお母さんは、CD-Rと歌詞カードを見せたら、泣きながら喜んでくれた。後で聞いたところによれば、月一回の墓参りは、20年間一度も欠かしたことがないという。親の愛のすさまじさに改めて頭が下がる。
仏壇にお線香をあげて、CD-Rをそなえたあたりから、僕自身も20年間の時間軸がぐちゃぐちゃに入り交じったような特殊な感覚になっていく。
そんなタイミングで帰宅したお父さんからも話をうかがう。
お父さんはあの事件を機に、それまでネガティヴなイメージを持っていたメンタル・クリニックの大切さを痛感するようになったようだ。 一段落してから、弟さんの車にのせてもらいお墓参りへ。
車中では弟さんから、あの後、ご両親がどれほど悲しみ苦しんでいたか、という話をうかがう。あの事件をきっかけに弟さんや現在は東京で暮らしている妹さんの人生も大きく変わったことが、ひしひしと感じられた。
また、僕らの他にも故人の友人で連絡してくる人がいることを知る。やはり故人の突出した存在感は、僕らだけでなく、多くの人達にずっと影響を与え続けていたのだった。
またかつての友人が連絡してくることで、彼が生きていたことの証を得られるのが、今のご家族にとっては嬉しいことなのだそうだ。
お墓参りを終えて実家に戻ると、お父さんが「あの歌を歌っているのは、どなたですか?」と訪ねてきた。およそロックとは縁の無さそうな方なのだが、お墓参りに出かけた約1時間の間に、さっそく聴いて下さったのだった。
東京駅に着いたのは午後10時ちょっと前。脳味噌フル稼働の一日で、どうしてもアルコールが欲しくなり、駅ビルの中の店で、Oさんと小一時間ほど飲んでクール・ダウン。
下北沢に戻ってからは、久しぶりにひとりでNeverNeverLandへ。
一時期ノドの調子をおかしくしていた店長の松崎さんが、だいぶ回復してきた様子を見て、ほっとしつつ、今日の話をさせてもらってから、帰宅。
2003年5月15日
母親に毛筆で書いてもらった『花よ
大地よ 月よ
銀河よ』のジャケットを受け取りに実家に。とはいえ注文をいろいろと付けてしまい、結局僕の立ち会いのもとで書き直してもらうことになった。僕は別に書について母親のように知識があるわけではないのだが、プロデューサー的に立ち回るうちにいろいろなことを感じた。
はじめは勢いのある書体をリクエストしたのだが、書く方の人間がそこで馴染みのない書体を選ぼうとすると、勢いのある書体をなぞるようなあざとさが出てしまう。そこで途中から発想を切り替え、母親の書きやすいように任せると書体そのものは少々スクエアかなと思っても、筆の動きにはむしろ滑らかな勢いが出るのである。とはいえリハーサルで雑談をしながら書いたものがやたら美しかったりして、いざ本番となると、今度はそれをなぞったような窮屈さが出てきたりするのでややこしい。
<美>は雑念が消えたほんの刹那に訪れる。
このへんの感覚は音楽や文章と<同じ>と言ってしまうのは乱暴すぎるかも知れないが、はっきりと通じるものを感じたし、少なくとも作業中にはその感覚を母親とも共有できていたように思う。
今回わざわざ母親にこうした依頼をしたのは、もちろん僕から見て母親が多少は毛筆で書いた字が多少なりとも仕事になるだけの技術があるからだが、他にも理由がある。
『花よ 大地よ 月よ
銀河よ』を捧げているJに死なれた時の僕の落ち込み方は、母親もしっかりと分かっていた。それならば3月に僕がそのJの実家でお逢いした<Jのご家族の故人への想い>も、母親として想像できるだろう。その気配が文字に出てくるに違いないという直観があったのだ。
それにしても平日の午後に、それで喰えるわけでもない音楽作品のジャケットを依頼して、文字の美しさについていろいろと言葉をかわしながら約3時間もサシで緊張感のあるやりとりをするというのは、40年以上におよぶ母子としての関係の中でも特殊な密度のある経験だった。
これを酔狂ととるか、それとも風流ととるか? もちろん僕としては後者でいきたい。
何はともあれ直観だけで好き勝手な注文を付ける素人プロデューサーに、きちんと応対してくれた母親に感謝の一日であった。
2003年6月13日
『花よ 大地よ 月よ
銀河よ』のプレス仕様の最終確認。
母親に毛筆で書いてもらった書をベースに、BYTZ
DESIGN
&ILLUSTRATIONが、これでもかというくらい、かっこよいジャケットに仕上げてくれた。後は工場から完成品が届くのを待つばかりである。
2003年7月30日
『花よ 大地よ 月よ
銀河よ』の発売日。あえてJの命日から20年後の日にちに設定した。
発売された後の作品は、もう僕の手を放れた独立した存在だ。
いったい、このCDはどのように受け取られることになるのだろうか?