|
大麻の変性意識(7)
前回に続いて『自己探求の心理学』という本をキーにして人類我について考えていく。著者の一連の実験は<知覚の構えの「図ー地」反転>という方法に基づいているのだが、そこから話をはじめていこう。
知覚の構えの「図ー地」反転
通常、自分・自己という自覚(自己意識)は、ひとつだけで、また常に変わらないということになっている。常識的には自分が2人いるとか、昨日の自分と今日の自分が同一でないなんてありえない。約束事や予定、契約が明日になったら、昨日とは同じ自分ではないから無効だといったら社会生活が成り立たなくなってしまう。
しかし、それ(人生は、同一の自己意識が継続しているということ)は疑いようもない事実だと言い切ってしまうのも危ういところがある。久しぶりに会った友人が別人のように人柄まで変わっていたとか、あるいは自分は昔、どうしてあんなことをした(後悔みたいなことだけでなく、「あんなことが出来た」といった僥倖でもいいが)のだろうかとか、10年ひと昔というぐらいのタイムスパンでは、日常意識の世界でも人は常に同一人物だということが疑わしくなるケースがあるだろう。
こういった問いについては、自己意識が継続するのは2分間に満たないということを誰にでもできる簡単な実験で示して、「自分自身を意識しているという錯覚は、記憶と思考過程によって生じるものだ」と述べたウペンスキーの指摘を思い出すが、これについては別の機会にふれよう。
さて、『自己探求の心理学』の中で、最初に離人感や多重人格の話が紹介されているのは、人間の中には自己意識がひとつではないケースや自己意識が時々で変わってしまうケースがあることを示すためだった。著者の心理実験は、自分があたかも過去の時代に生きている人になった気持ちになることからはじまっていた。自己が2つある(「今の自分」と「前世の自分」)と仮定していくところにポイントがある。
そして、2つ目の新しい自己(「前世の自分」)に今の自分を明け渡す、乗り移る――こう書いても、頭で考えるだけではその実感は得られないだろう。ありありと自覚できるなければならない。そのため著者は、幾つかの心理操作を行い実感を得ようとしている。
それは「1.知覚の構えの転換、2.具体的な人間の経験に立脚し追体験すること、3.それもナマの生活経験にもどること、という三つの条件を備えていたわけです」と述べている。
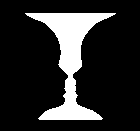 最初にあげている知覚の構えの「図ー地」反転は、今後、人間の文化と変性意識を考える上で、キーになる視点ではないかと思う。そんなこともあり、少しふれておく。 最初にあげている知覚の構えの「図ー地」反転は、今後、人間の文化と変性意識を考える上で、キーになる視点ではないかと思う。そんなこともあり、少しふれておく。
心理学の入門書によく登場する「図ー地」反転の実験図(ルビンの盃)がある。この図を見るとき黒地に白の図という知覚の構えで見るならば、白い杯に見えるはずだ。しかし、白地に黒の図形が描かれていると見ようとすると、二人の人の顔が見えてくる。ここで知覚の「図ー地」反転が起きたわけである。
この本の著者は、集合自己の立場に立つということは、個我(自我)を図とした強固な枠組み(個我意識は肉体に規定されている――日常意識下で、自分・自己とは何か?といった問いを考えたとき、最も確実な答えは身体だという答えだろう――ため普通は自明のこととして疑いようもない)に対する「図ー地」反転を行うことだと述べている。
つまり集合自己(地)ー個我(図)で成立している日常世界を、集合自己(図)ー個我(地)に転換させるのである。これは現実が逆さまになった世界。さかしまの世界といってもいいだろう。ところで世界各地の伝統文化に、さかしまを儀礼化した祭りや、象徴化したアートを見かける。想像を逞しくすると、それらは人間の心性の奥にある個我を超えた(あるいは「別の」「以前の」と言ってもいいが)世界を求める本源的な衝動の現れのように思える。
そして次の段階で、瞬間的に「図ー地」反転を繰り返し、相互翻訳をするような操作をしていく……この一節を読んでも抽象的で具体的イメージが湧かないかもしれないが、先ほどの(ルビンの盃)に即して語ると、黒い人の顔を図として認知しているときでも、同時に白い杯の図を感じるような知覚のあり方を言っている。それは集合自己を図としながら、同時に個我が健在であるようなリアリティ、あるいは逆に個我を図としながら、同時に集合自己が健在であるようなリアリティ、さらに両者が瞬間的に入れ替わり続けるリアリティである。
こういった心理実験を経て著者は「比較的簡単な努力によって我執を超え、人類において生きているような大らかな気持ちにもどれるようになったのです。このような図ー地反転が行われやすくなるということは、図だけの統合を考えていた従来の人格統合の考え方とは異なった統合の一面を示すっものであり、無の境地における非統合の統合といわれているものに一歩近づく道なのかもしれません」とまとめている。
大麻とイメージ喚起力
ところで大麻には、イメージ喚起力を強める効果がある。それは大麻をある程度、体験したことのある人なら、ほとんどの人が実感していることだろう。……ある記憶の想起がありありと強烈に甦えったとか、ふと思い浮かべた想念・過去の一場面の情景・空想した架空のストーリーなどへの集中感・没入感が普段ではありえないぐらい強くなったといったケースをあげれば思い当たるはずだ。
脳裏に浮かび上がったある夢想した場面が現実以上にありありと感じられる。まるでその状況下を生きているように臨場感が強まって感じられるなど、いろいろな言い方ができるだろう。
イメージ喚起力を強めるということを別の角度からいうと、被暗示性を強めるといってもいい。いま述べたような内からのイメージを喚起するのも、あるいは心を集中・投影するのも、さらには受け身になって外からの暗示を受容するのも、どれも心の作用として同じ「部品」(物質ではないが、あえて比喩として)が関わっている。
「自己」(自我、個我意識)は、感覚、感情、思考、想念、記憶想起といった「部品」によって作られている。それは作られたものとすれば、「自己」には歴史的な起源があることになる。人類がチンパンジーなどと共通の古い類人猿と分岐したのは650〜550万年前頃とする説が最近では有力だとのことだが、おそらくその頃のことだ。どのようにして「自己」が作られたか、当然ながら資料は皆無だが、(無我レベルでの)変性意識を手がかりにして推測はできる。これについては、次回にふれる。
家が、鉄やアルミニウム、炭素、窒素……物質の原料からできた柱や壁、屋根、床、ドアなどを組み合わせ建築されているように、「自己」は神経シナプスの反応という原料から生まれた思考や、感覚、感情、想念、記憶想起といった「部品」を組み合わせて形成されている。
これら「部品」の働きが強まる、濃くなる(こう書いていて、「強まる」にしても「濃くなる」にしても物質的現象を表現するときに用いる言葉を流用するしかなく、心の世界の「働き」を表現するのに適切な言葉がないことを痛感する)ことによりイメージ喚起力、集中力、被暗示性が強まる。
大麻は「自己」を作っている「部品」の働きを強める、濃くするから、もしそのとき知覚の構えの「図ー地」反転を行えば、2つ目の自己や集合自己はよりはっきりと、圧倒的なリアリティで現出されることになる。
これは非常にスリリングな試みであるが、同時にバランス感覚の成熟した人でないと危ういということもいえる。それこそ前回の「大麻の変性意識(6)」の冒頭でふれたように自己喪失や妄想的な非現実感に陥ることがありうるからだ。
|