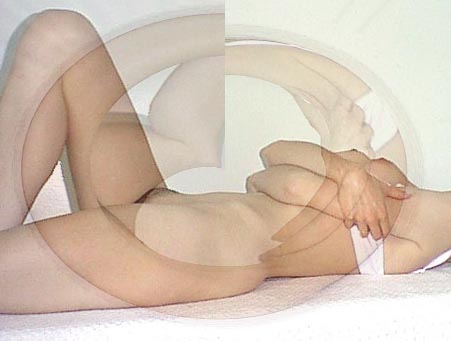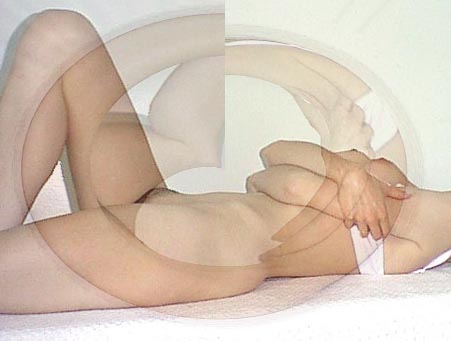
『7年目のReplay』
Written by Evo-GODZILLA
1.Autumn Leaves 〜SOMETHIN’ELSE〜
さすがに平日の高速道路の下り線は、走っているクルマも少ない。
覆面パトカーにさえ注意していれば、快適なドライブだ。
常々、思っているのだが、何のために高速道路で覆面パトカーによるスピード取締をするのだろう。
スピードを出させないようにするなら、白黒ツートンのパトカーを走らせておけばいい。パトカーがいるとわかっていて、無謀なスピードを出す奴はいないだろう。それが本来の事故防止ではないのかと思う。
大体が交通取締はそういった類が多い。一方通行の取締でも、確信犯はともかく、知らずに進行してくるクルマだっているはずだ。しかし、その入口で注意を促すのではなく、出口で待っていて、違反してきたクルマを捕まえる。だからアンタは嫌われる、というやつだ。交通違反の取締を適正かつ公平にやるだけで、一般庶民の警察官に対するイメージは、相当変わるはずだ。
そんなことを考えながら、快適に飛ばしていた。
このクルマの中でジャズを聴くのはミスマッチだと皆に言われるのだが、好きなものは仕方がない。
今も車内に流れているのは、 ”Autumn leaves” by Cannonball Adderley & Miles Davis。
愛車は、三菱ランサー・エボリューション。それも吸排気系やコンピューター、足回りに至るまで手を入れた、チューンド・エボである。その気になれば260km/hは出る。
確かに図太い重低音の排気音を響かせて走っている、見るからにラリーカーという外見のこのクルマの中で、こんな音楽を流しているヤツは、そうはいないだろう。
運転している本人は、至ってご機嫌なのだが。
ある大きな病院の救命救急センターに勤務している俺にとって、こんなにゆっくり休むことができるのは、久しぶりのことだ。
「たまにはゆっくり休んだらどうだ? 2、3日、温泉にでも浸かって、リフレッシュし
て来いよ」
そう言ってくれた医局長に、他のドクターやナースたちも同意してくれた。
「そうですよ。この何ヶ月か、全然、休みらしい休みも取っていないんですから、たまにはいいじゃないですか」
担当していた患者も回復に向かい、今日、ICUから一般病棟に移すことができ
たところだった。
『・・・たまにはいいか。ホントに久しぶりだし』
俺は皆の言葉に甘えて、3日間の休暇を取ることにした。
帰り際に「じゃあ、明日から3日、休ませていただきます」と言って医局を出る俺に、医局長がニヤニヤ笑いながら、「ゆっくりしてこい。ただし、携帯の電源は切るなよ」と言う。
俺は首をすくめた。
「せっかくの休みだから、圏外になる場所に行きますよ」
精一杯の切り返しは、あっさりと返り討ちにされる。
「じゃあ、宿に着いたら電話を入れて、連絡先を教えておいてくれ」
緊急呼び出しなど、毎度のことだ。病院内でもポケベルを持って歩かなければならない。
事件・事故や急病などで消防庁からのホットラインが鳴り、患者の状態が伝えられた時点で準備を始めるが、救急車が到着すれば、初療室はまさに戦場である。救命救急センターに搬送されてくる状態ということは、三次救急、文字通り秒を争っての救命処置が必要という場合がほとんどだ。
多い時には、同時に何件も重なったりすることがある。そんな時は、どこにいても呼び出される。
宗教団体が地下鉄で起こした事件の時は、多数の患者が搬送されてきた。あの時も俺は休暇の初日だったが、久しぶりにたっぷりと睡眠を取った後につけたテレビで第一報が流れた時点で、発生した場所からして、これはウチにも来ると判断した俺は、呼び出しを待たずにすぐに病院に急いだ。案の定、次々と患者が搬送されてきて、病院中がパニックになった。患者はセンターだけではとても収
容しきれずロビーにまで溢れ、診療科を問わず、手が空いていたり、不在でも連絡のつくドクターやナース全員に非常呼集がかかったのだ。
もちろん、その後の休暇は自然消滅的に取り消しになった。今回はそんなことが起きないことを祈るだけだ。
途中で立ち寄ったサービスエリアでコーヒーを飲んで一休みをし、クルマに戻った時だった。
ドアを開けようとした時、3台奥に止まっていたポルシェ・カレラ4が出ていくところだった。
ドライバーは女性で、一人で乗っている。目の前を通り過ぎていくそのポルシェの女性ドライバーを見た時、俺は硬直した。
『えっ?・・・祐子?・・・まさか』
7年前に別れた女性。単なる見間違いか、他人の空似だろうか。
別れは、最初から決まっていたことだった。知り合った時点で、すでに婚約者がいることを承知の上で、俺は祐子と付き合っていたのだ。
あれから7年になるのか・・・。
2.Left Alone 〜MAL WALDRON & JACKIE McLEAN〜
いつも二人で行った渋谷のバー。きれいに磨かれた真鍮のテーブルの上のジャック・ダニエルズ。
スピーカーから流れるMal Waldron&Jackie Mcleanの"Left Alone"。
それが、最後の夜のシチュエーションだった。あまり言葉も交わさずにグラスを傾ける俺と祐子の姿は、はたから見れば、完璧にお互いを理解し合った恋人同士に見えたことだろう。
その日が来ることは、初めから判っていたことだ。祐子にもうすぐ結婚するという婚約者がいることを承知の上で、俺は祐子と付き合ってきたのだ。だが俺も祐子も、『遊び』という意識はなかった。
それでも祐子がその相手と結婚するというのは、婚約を白紙撤回することに伴う多くのリスクを負うところまで踏み切れないからだった。相手とのことはもちろん、双方の親兄弟や親戚のことなど・・・。
本人が自分の意志で踏み出せないのなら、どうすることも出来ない。自分のことを決めることが出来るのは、自分自身でしかない。本心はどうであれ、結果として祐子はその相手を選択したということだ。
俺は未練がましい真似はしたくないし、三面記事に載るような修羅場を演じる気も、もちろんなかった。
俺と祐子が出会うのが、少し遅かったということなのだ。
「お前は、本当にそれでいいのか?」
俺と祐子の関係を一部始終知っている友人は、そう言った。
「いいわけはないだろう。しかし彼女が全てを振り切って来るのなら、俺はどんなことをしてでも受け止めてやれるが、祐子がそこまで踏み切れないなら、俺には
どうすることも出来ない」
「・・・・・」
「映画じゃあるまいし、ダスティン・ホフマンが、教会からキャサリン・ロスをかっさらったような真似をするわけにもいかないだろ」
古い映画のラスト・シーンだ。あの映画は一見ハッピー・エンドに見えるが、あの後で二人はどうなるのか。教会から逃げだして飛び乗ったバスを降りた時からが、二人の試練の始まりになるのだ。
祐子は、手にしたオン・ザ・ロックスのグラスを見つめて言った。
「とっても透明で、きれいな氷ね」
トーンを落とした照明の下で、琥珀色の液体の中のロック・アイスが輝いていた。
「見ている者のことなんかには、まるで関係なく光っている・・・」
「・・・ごめんなさい・・・」と、俺の言葉の裏を読み取った祐子が、小さく言った。
「祐子が謝ることはない。こうなることは、初めから承知の上さ。なるようになった。それだけのことだよ」
「・・・あなたは、他人に弱いところを見せようとしないのよね。転んだ子供が、本当は痛くて泣きたいのに、人の見ている前では『痛くないやい!』って我慢している。その子は一人になって誰も見ていない所で、傷を押さえて涙を流すのよ。あなたはそういう人だから、私とのことも平気な顔でいるように見えるけれど、きっと一人でいる時は違うと思う・・・」
「・・・それは、俺自身の問題だよ。祐子が気にすることはない・・・それより、飲もう。祐子の幸せを祈って、乾杯しよう」
「・・・あなたにそんな乾杯はして欲しくない。今夜のために、私とあなたの今のために乾杯して・・・」
俺が頷くと、祐子は俺のショット・グラスにジャック・ダニエルズを注ぎ、自分のオン・ザ・ロックスも作った。
見つめ合ったまま、軽くグラスを合わせた。ショット・グラスの中のジャック・ダニエルズを、喉の奥に放り込む。喉から鼻腔に広がる、独特の香り。
「・・・私、ジャック・ダニエルを飲むのは、今夜で最後にするわ・・・」
グラスを置いた祐子が、相変わらず輝いているロック・アイスを見つめて言った。
「・・・ジャック・ダニエルの味は、あなたに教えられたのよ。飲めば、そのたびにあなたを思い出すことになるわ。だから、もう飲まないことにする・・・」
「飲むたびに何かを思い出す。そんな酒があってもいい。それを気にしていたら、俺はとっくにこいつを飲むのをやめていなくちゃならない」
もうこいつを飲んで何年になるだろう。
このバーで飲む時、祐子はいつも、俺が最初の一杯を飲み干すのを見つめていた。
「いつも美味しそうに飲むのね。本当にジャック・ダニエルが好きなのね」
「うん。酒の中では、一番好きだな」
「私も、最初は癖の強いお酒だと思ったけれど、慣れてきたら普通のウィスキーが美味しいと思えなくなっちゃった」
祐子は、かなり酒は強い方だった。二人でジャック・ダニエルズを一本空けたこともあった。
『バーボン』ではなく、『テネシー・ウィスキー』。芯まで燃やしたサトウカエデの木に少しづつ水をかけ、何日もかけて作った炭をぎっしりと詰めた、3mもの厚さの濾過層。そこをじっくりと濾過された140プルーフ・・・70度・・・のウイスキー。その工程で得られた、独特の味と香り。
今夜のことだけでなく、この黒いラベルとチャコールの香りの中には、色々な思いが溶け込んでいる。
何かがあったことで飲むのをやめていれば、俺もジャック・ダニエルズを見るたびに、それを思い出すことになっていた。プライベートなことはもちろんだが、長いこと救命救急センターなんていう所に勤務しているおかげで、目の前で消えていく生命の灯を、いやと言うほど見てきた。これだけは何年経っても慣れることはない。
個々のケースにそうしていたらとても仕事にならないから、できるだけ感情移入を避けるようにはしているが、俺だって感情のある人間だ。飲まなければやっていられないような場面に遭遇することも少なからずあるのだ。
もう一杯、ショット・グラスを満たす。キャップを閉めてボトルを置くと、祐子は俺の手から離れた所にボトルを移した。
「どういうことだ。まだストップをかけられるほど、酔っちゃいない」
「わかってるわ・・・ジャック・ダニエルの他に、私にはもう一つ、あなたに教えられたものがあるのよ。ジャック・ダニエルの味は憶えておくわ。もう一つのことも、しっかりと憶えておきたい。だから・・・」
そう言って俺を見つめる祐子の瞳の中に、淫らな炎が光っていた。
3.青らむ雪のうつろの中に 〜姫神〜
初めて祐子を抱いたのは、二人でスキーに行った白馬村のホテルだった。
ゲレンデを見下ろす場所にある、スイートルーム。ディナーの後にラウンジで少し飲んでから、部屋に戻ってきた。夜も更けてナイターの照明も消え、窓の外は雪が降り続けていた。
窓際のソファーに並んで腰掛け、暗い闇から舞い降りてくる白い雪を眺めながら、持ってきたジャック・ダニエルズを二人で飲んだ。
「・・・静かね。雪が、音を吸収しちゃうのね」
「うん。しかしよく降るなあ・・・」
昼間、滑っている間は晴れていたのだが、夕方から雪に変わり、降り方は次第に激しくなってきていた。
「あなたのスキーの腕前は、聞いていた通りだったわね。カッコよかったわ、フフフ」
もうかなり前に、俺はホームゲレンデにしているこの八方尾根スキー場で、1級を取得していた。
昼間、一緒に滑っている間、急斜面でのハイスピードのウェーデルンやコブの中で見せた派手なジャンプに、祐子は何度も歓声をあげていた。
「リフトに乗っている人たちも、みんな見ていたわ。私まで、何だか得意な気分になっちゃった」
祐子が俺に寄りかかり、肩に頭を乗せてきた。リンスの香りが漂ってくる。
「祐子・・・」
祐子の肩を抱き寄せると、祐子は顔を上げ、俺の方に体を向けて目を閉じた。
知的に整った美しい顔を見つめ、唇を重ねる。祐子は俺の背中に両腕を回し、唇を開いた。重ねた唇の中でお互いの舌先が触れ合い、すぐに濃密に絡み合った。長いキスだった。
唇を重ねたまま、鼻から漏れる祐子の息遣いが乱れていく。祐子と舌を絡ませ合いながら、俺も突き上げるような欲情を感じ、ペニスが一気にそそり立っていく。
突然、祐子が唇を振りほどき、「ああ・・・」と小さな声をあげて、ハアハアと激しく息をついた。
「どうしたのかしら・・・こんなの、初めて・・・キスしてるだけで、イキそうになっちゃった・・・」
そう言って、祐子は恥ずかしそうに俺を見つめる。顔は上気し、目が潤んでいた。
知的な女性の欲情した表情は、ぞくっとするほど色っぽく、淫らなものだ。
俺は祐子の両脇に腕を差し入れて立たせた。クイーンサイズのベッドまでは、ほんの数歩の距離だった。
抱き合ったまま祐子を押すようにしてベッドまで歩き、祐子の脚がベッドの端に触れると、祐子は俺の首に両腕を回して、俺が押し倒すのと同時に自ら俺を引き寄せるようにベッドに倒れ込んだ。
再びキスを交わす。キスをしながら、セーターの上から祐子の胸の膨らみを掴んだ。外見以上の量感が掌に伝わってくる。ゆっくりと揉みしだく。
「んんん・・・」
キスをしたまま、祐子は喉の奥で声を洩らした。
唇を離し、両手を祐子の両の脇腹をからくびれた腰へ撫で下ろし、セーターの中に手を入れると、そのまま上へ上げて脱がせる。祐子は両手を上げて袖から腕を引き抜くようにし、頭が抜けると、軽く左右に頭を振った。
セミロングの髪がふんわりと広がる。そしてまた、キス。深く舌を絡ませ合いながら、祐子のスカートの脇のフックを外し、ファスナーを下ろして脚から抜いた。薄いピンク色のスリップのストラップを肩から外し、熟した桃の皮を剥くように、めくるようにして脱がせた。シルクの光沢を放つ、セクシーなピンクのブラジャーとパンティー。窓の外に降りしきる雪のような、白い肌。素晴らしいプロポーションだった。お椀型の美しい乳房が勢いよくブラジャーを押し上げている。滑らかな白い腹、見事にくびれた腰、スラリと伸びた脚は足首がキュッと引き締まっている。その付け根には、黒い靄のような上品なヘアが透けて見えている。
「きれいだ・・・すごく色っぽいよ」
「・・・私ばっかり脱がされて、恥ずかしいわ・・・」
祐子の言葉に、俺も服を脱ぎ捨てた。祐子が潤んだ瞳で俺を見つめる。
「ああ・・・素敵よ・・・引き締まっていて。これが鍛えた体なのね」
祐子は、俺が空手をやっていることは、もちろん知っている。
お互いに下着姿で抱き合った。雪のように白い祐子の肌は、雪とは違って燃えるように熱かった。
「ああん、こんな体、抱かれただけでうっとりしちゃう・・・」
片手を背中に回してブラジャーのフックを外し、祐子の肩から抜き取った。形のよい白い乳房がブルンと悩ましく揺れながら露わになった。柔らかいが張りがあり、仰向けのままでも崩れない。先端には小さめのピンクの乳首がピンとそそり立っている。その乳首を唇に挟み、舌で転がした。
「あんっ!・・・ああ」
祐子が裸身をピクッと震わせ、悩ましい声をあげた。
左右の乳首を交互に舐め、しゃぶり、吸いながら右手で祐子の脇腹から腰、太腿へと撫で下ろしていき、内腿へと滑り込ませる。祐子は僅かに脚を開くようにして、俺の手の侵入を許した。すべすべしていながらも、しっとりと掌に吸い付くような柔らかい肌を撫で、ついにパンティーの上から祐子の秘部に触れた。中指と薬指をあてがうと、その部分はパンティーの上からにもかかわらず、指にぬめりを感じるほどになっていた。乳房を舐めしゃぶりながら、ぐっしょりと濡れたパンティー
の上からその部分を指でなぞると、祐子はさらに激しく喘ぎ、裸身をよじらせる。
「ああっ! ああん! い、いいっ・・・」
「祐子・・・感じやすいんだね・・・うれしいよ」
「いやあ、ん・・・ねえ、もう・・・もう、脱がせて・・・」
張りのある柔らかい尻の方から、めくり下ろすようにしてパンティーを引き下ろした。祐子が腰を浮かせてくれ、小さく丸まったシルクのパンティーを、スラリと伸びた脚から抜き取った。
俺も全裸になり、横から祐子を抱き締める。祐子の太腿に、もう痛いくらいに怒張しきったペニスを押し付けると、それを感じた祐子が、悩ましい吐息を洩らした。
「ああ・・・すごい・・・すごく、硬くなってる・・・熱くて・・・ドクン、ドクンって・・・」
「祐子が、すごく魅力的だから・・・こんなになってるんだ」
俺はまた祐子の乳房にしゃぶりつき、薄目のアンダーヘアを分けるようにして、肉の花びらに指を這わせる。
「ああんっ!」と声をあげ、祐子が裸身をのけぞらせた。祐子の肉の花びらをなぞると、俺の指はたちまち熱い蜂蜜にまみれたようになった。小さな肉の芽を指先に捉え、それを転がすようにすると、祐子は高い声をあげてブルブルと裸身を震わせた。さらに俺の中指は祐子の熱い密壷の入口を探り当て、ズブリとのめり込ませる。
「ああっ!・・・あ、あ・・・ああん!」
祐子がのけぞる。俺の指は、祐子の素晴らしい感触を感じていた。熱くぬめる肉が幾重にもみっちりと詰まったようで、容易に指の侵入を許さないのだ。それでも力を込めると、たっぷりと溢れ出している祐子の愛液に助けられ、根元まで指が入っていった。
「あううぅっ!」と祐子は呻き声をあげ、片手で俺にしがみつき、もう一方の手はシーツを握りしめている。
俺の指は祐子の熱く濡れた肉に包み込まれ、締め付けられていた。
「すごいよ・・・祐子のここ・・・」
快楽に喘ぐ祐子の耳に熱い吐息とともに囁きかけ、中指に加えて薬指ものめり込ませ、親指ではクリトリスを捉えて愛撫しながら、二本の指を抜き差しさせる。
濡れた卑猥な音が響き、祐子は絶頂に駆け上がっていった。
「あんっ! あんっ! いっ、いいっ! ダメ、ダメよ! ああ、イッちゃう! ヒッ、イ、イクうぅっ!」
祐子の裸身がビクン!と反り返り、硬直して小刻みに痙攣した。俺の指を呑み込んでいる熱い肉襞も、短い周期で収縮を繰り返している。
のけぞり、こわばっていた祐子の裸身からフッと力が抜け、ぐったりとベッドに落ちた。祐子は溺れる寸前で水面に顔を出したように、ハアハアと激しく息をつき、美しい乳房を波打たせている。
まだ快楽の余韻にヒクついている祐子の密壷の中から、指を抜き出した。指の間に糸を引くほどに祐子の愛液にまみれている指をしゃぶる。甘酸っぱいような悩ましい味と匂いが広がり、それはまるで媚薬のように俺の欲情をかき立てるものだった。
「・・・ああん、すごい・・・こんなの、初めて・・・」
ハアハアと荒い呼吸を繰り返す祐子に覆い被さるようにし、きれいに伸びた脚の間に体を割り込ませる。
白い太腿を押し広げ、まだヒクヒクしている祐子の肉の花びらに唇を押し当てた。
「あ、はあっ! ああ!」
ゆっくりと快楽の頂点から降りてきていた祐子を、再び押し上げていく。
サーモンピンクの肉の花びらを舌でなぞり、濡れて輝くクリトリスを転がす。止めどもなく溢れ出してくる熱い愛液を啜り、舌を突き入れるようにしたりもした。
祐子は喘ぎ、のけぞり、激しく身悶えしながら二度目の絶頂を極めた。それでも俺は愛撫を止めず、のけぞり、裸身を痙攣させて絶頂感を噛み締めている祐子に容赦なく快楽を与え続けた。祐子が立て続けに昇りつめる。
「ああっ! もう、もうっ! 許して!・・・ああん、いや、また、また、イクうっ!」
祐子は強烈なオルガスムスに痙攣しながら、両手で俺の頭を下に押し戻すようにして股間から離した。
俺が顔を上げると、祐子はぐったりと全身の力を抜いて、激しく息をつく。
「ああっ・・・すごすぎる・・・狂っちゃうかと思ったわ・・・ああん・・・」
祐子の裸身は、本人の意思とは無関係に、まだ時折ビクッ、ビクッと震えを繰り返していた。
「・・・恥ずかしいくらい、乱れちゃったわね、私・・・」
「その方がいいよ。特に、祐子みたいな知的な女性が激しく乱れる姿には、余計にそそられる・・・」
「フフフ・・・ねえ、今度は、私が・・・あなたも楽しませてあげる・・・」
祐子はベッドに手をついて体を起こし、俺にのしかかるようにして唇を重ねてきた。濃厚なキスを交わしてから祐子は唇を離し、そのまま俺の胸から腹へと唇を這わせていく。そうしながら、祐子はいきり立ち、脈打っている俺のペニスに指を絡み付かせてきた。
「すごいわ・・・すごく、硬くて・・・とっても熱い・・・」
祐子の細くしなやかな指に、優しく、しかし、しっかりと握られ、そのまま祐子はゆっくりと手を上下に動かし始めた。
「う・・・ん・・・祐子・・・」
祐子の柔らかい手に握られ、しごかれて、甘美な痺れが広がってくる。祐子の柔らかいセミロングの髪が腹筋をくすぐり、やがて祐子の唇は俺のペニスに押し当てられた。
キスをした後、祐子は根元の方から幹に舌を張り付かせ、ゆっくりと舐め上げてくる。それから、膨れ上がった亀頭が暖かな口の中に含まれた。
「うっ、んん・・・」
祐子の舌が亀頭に絡み付き、さらに深く呑み込まれていく。唇でしっかりと締め付けられ、根元まで達すると、今度は顔を上げていく。先端のくびれに唇が引っかかるくらいになったところで、再び顔を沈めていく。
その動きが次第に速さを増していった。その間も祐子の舌はまるで別の生き物のように幹に絡み付き、亀頭を舐め回し、すでに溢れている俺の興奮の透明な液も舐め取っていく。頭を上下させて唾液を潤滑油にして唇でしごき、唇から出ている部分は白く柔らかい指で握って、顔の動きに合わせて上下させる。さらにはもう一方の手をその下の球体に伸ばし、優しく揉みたててくるのだ。
「ああ、祐子・・・いいよ・・・上手だ・・・んんっ、ん・・・」
祐子の髪を撫でながら言うと、その言葉を聞いた祐子の愛撫は、一段と激しく濃厚になってくる。セミロングの髪が俺の太腿をリズミカルにくすぐり、ジュプ、ジュプ、ズズッと唾液の音も立つほどになっていった。
俺ももう、これ以上我慢できなくなっていた。
「祐子・・・もう、いいよ・・・それ以上されたら、祐子の口の中でイッちゃいそうだ」
祐子がゆっくりと顔を上げ、悩ましい上目遣いで俺を見上げる。
「いいのよ、イッちゃっても・・・あなたがイッたら・・・全部、飲んであげるわ・・・」
祐子のその言葉が、俺の興奮と欲情を限界まで沸騰させた。
「ダメだ。それより・・・祐子と一つになりたい・・・祐子の中に入りたいよ・・・」
祐子の両脇の下に手を差し入れ、引き上げるようにして上に来させた。下から抱き締め、そのまま体を反転させて祐子の上になりながら、白い太腿の間に腰を割り込ませていく。祐子は太腿を開き、俺の腰を受け入れる。
しっかりと抱き合い、見つめ合った。興奮と快楽の中で上気している祐子の知的な顔は、例えようもなく淫美なものだった。猛り狂う俺のペニスは、祐子の柔らかい下腹部に押し付けられている。
「・・・祐子」
「・・・いいわ・・・来て・・・」
そう言って、祐子は目を閉じた。
祐子の熱く濡れた肉の花びらに、膨れ上がった亀頭を押し当てる。
「あ・・・ああ、ん・・・」
快楽の期待に、祐子が声をあげ、息を乱す。
俺は祐子の美しい顔を見つめながら、ズブリと祐子の中にのめり込ませた。
「あっ! あんっ!」
祐子がビクッと裸身を震わせ、目を閉じ、きつく眉を寄せた悩ましい表情になる。
「う、んっ・・・熱いよ、祐子のここ・・・」
祐子の中は、熱かった。亀頭が、熱い葛に浸されたような感覚。
「ああ! 来て! もっと、もっと・・・深く・・・来て!」
祐子が俺にしがみつき、俺はぐっと腰を突き出していった。
みっちりと詰まった、熱くぬめる肉を亀頭で押し分けるように、俺は深々と祐子の中に入っていった。
そこは驚くほどきつく締まっていたが、シーツを濡らすほどに溢れている祐子の熱い愛液に助けられ、窮屈だが滑らかに、俺は祐子の奥深くに到達することができた。
「ああう! ううっ、あ、あ・・・すごい・・・すごいわ!・・・張り裂けそう・・・あああ!」
祐子は高い声をあげてのけぞりながら、自らも腰を浮かせて俺を迎え入れてくれた。深々と、根元まで祐子の中に埋め込み、しばらくはきつく抱き締め合ったまま、お互いの感触を味わった。
祐子の中はとても熱く、熱くぬめる肉襞が隙間なく密着し、まるで奥に引き込もうとするかのように収縮を繰り返しながら締め付けてくる。
「祐子・・・いいよ、祐子のここ・・・最高だ」
「ああん・・・あなたも・・・ああ、すごく硬くて・・・太いの・・・」
抱き締め合ったまま、舌を絡ませ合った。キスをしながら、ゆっくりと腰を動かし始める。
「んっ! ん、んっ!」
キスをしたまま、祐子が喉の奥で声をあげ、ビクッと裸身を震わせる。ゆっくりと、抜け出そうになるところまで引き抜く。祐子の熱く濡れた肉襞が離すまいとするかのように締め付け、絡み付いてくる。それから、ぐっと腰を沈めて深く埋め込む。今度は、きつく閉ざした祐子の肉襞を押し分けるようにしてのめり込む。熱くぬめる肉襞との摩擦感は強烈だった。
数回、その動きを繰り返すと祐子の呼吸は一段と激しくなり、ついに耐えきれなくなって唇を振りほどき、
「ああっ! あ、ああん!」
と声をあげて、嫌々をするように頭を左右に振った。
腰の動きを次第にリズミカルにしていく。ベッドが悩ましいリズムで軋み、繋がり合った部分からは、泥の中を歩くような濡れた音が立ち始めた。
キスをしたり、乳房を揉みしだいたりしながら、浅く、深く、祐子の中で動き続ける。祐子は俺にしがみついたり、シーツを鷲掴みにしたりしながら裸身をよじらせ、悶え、のけぞる。そうしながら、俺の動きに合わせるように、腰を突き上げ、くねらせるのだ。
悩ましい喘ぎ声をあげ続ける祐子は、汗ばんだ額や頬に髪が乱れて張りつき、美しい顔にきつく眉を寄せた表情で快楽に酔い痴れている。淫らで美しく、たまらなくそそる表情だ。
俺と祐子は、今夜が初めてなのに、もう何年もお互いの体を知り尽くしているかのようにリズムを一致させ、興奮と快楽をシンクロさせて濃厚な交わりを続けた。
祐子の素晴らしい感触と反応に、何度も射精感が迫ってくる。それに身を任せて弾けてしまいたい気持に襲われるが、それよりもできるだけ長くこの快楽を味わいたくて、俺は時々動きを止めて大きな波をやり過ごし、少し引いていくとまた動き出すことを繰り返した。
長く濃厚な交わりが続き、やがて俺の腕の中の祐子の裸身が、震え始める。
「ああん! もう、もう・・・イキそう! ねえ、私・・・ダメ! イッちゃう!・・・ああ!」
祐子が激しく喘ぎ、切羽詰まった声をあげて俺にしがみつく。
「いいよ、祐子・・・イッていいよ・・・ああ、俺も・・・イキそうだ! ううっ・・・」
祐子の裸身を抱き締めて、肌と肌を擦り合わせるようにしながら動きを速める。
「祐子!・・・外に・・・お腹の上で、いい?・・・」
俺が祐子の耳に囁きかけると、祐子は俺の背中に両手を回してしがみついてきた。そして熱い吐息とともに、俺の耳に唇をつけて言った。

「いいの、このまま・・・いいのよ! 中に、私の中に・・・出して!」
祐子の言葉に、一気に快楽が沸騰する。
好きな女性と濃厚に交わり、体の中で果てることを許されればたまらない。
「祐子! いいんだね・・・ああ、祐子!」
「ああ! イクわ! イク! ねえっ、一緒に、一緒にイッてぇ! お願い! 私の中
に、いっぱい出して!」
「ううっ、祐子!」
汗ばんだ祐子の裸身をきつく抱き締め、爆発的に腰を動かす。祐子が絶頂に達した。
「ああんっ! イクっ、イク!・・・ああ、イクうっ! ヒッ、イ、イイッ!」
祐子の裸身がビクンと強張り、頭でブリッジを作るように反り返った。俺の腕の中でブルブルと激しい痙攣を繰り返して、息をつまらせる。深々と俺のペニスを呑み込んだ肉襞が強烈な収縮を繰り返し、ペニス全体が一段と熱い蜜に包まれたようになったのを感じた瞬間、俺の快楽も弾けた。
体の奥から湧き起こるような快楽が、脳天へ突き抜けていく。祐子の熱い肉襞のきつい締め付けに反発するようにペニスがビクン!と跳ね上がり、精液が祐子の子宮めがけて勢いよく噴き出した。
「祐子っ! うううぅ! ゆう、こ! んううう!」
目の前が真っ白になるような強烈な快楽が走り抜け、祐子を抱き締めて激しい呻き声が洩れてしまう。
「ヒイッ! 熱いっ、熱いわ!」
体の奥に叩き付けられる熱い精液を感じた祐子が、さらに大きな絶頂感の波にさらわれ、俺の腕の中で激しく裸身を痙攣させる。
ペニスは何度も何度も祐子の中で跳ね上がり、熱く濃厚な精液が猛烈な勢いで祐子の体の中に噴き出していった。自分でも驚くほど射精は長く続いた。俺は祐子をきつく抱き締め、甘い匂いのする首筋に顔を埋めるようにして、全身を強張らせ、腰を引きつらせながら強烈な快楽を味わった。
祐子の裸身の痙攣は、俺が激しく射精している間、ずっと続いていた。
やがて、ようやく射精が終わり、俺は荒い呼吸をしながらぐったりと力を抜いた。
祐子ものけぞっていた背中をベッドに落とし、ぐったりしたまま、ハアハアと激しく息をつく。
俺も祐子も身動きする気にもならず、ぐったりと重なり合ったまま、強烈な絶頂感の余韻に浸っていた。
大量の精液を祐子の中にぶちまけたにも関わらず、俺のペニスはまだ祐子の熱い肉の中で力を失わず、間欠的に脈動を繰り返す。ビクンと脈打つたびに、ぐったりとした祐子もブルッと裸身を震わせ、「あん!・・・」とかすれた小さな声をあげる。女性と、これほど強烈なオルガスムスを分かち合ったのは初めてだった。
「・・・祐子・・・」
俺が祐子の耳に囁きかけると、祐子はまだ言葉も出ないのか、息を弾ませたまま、俺の背中に回している両手に力を込めることで応えた。
5分ほどもそうしていただろうか。ようやく俺は体を起こし、まだ硬いままのペニスをゆっくりと祐子の中から引き抜いて、祐子の隣に横になった。祐子が体を俺の方に向け、見つめてくる。髪は乱れて上気した顔に張り付き、目は潤んでいる。いかにも激しいセックスで強烈な絶頂を極めた後という、色っぽい表情だ。
「すごく、よかったよ・・・祐子・・・」
「私もよ・・・こんなの、初めて・・・体がドロドロに溶けて、流れ出すみたいだったわ・・・」
顔にまとわりついた髪を指でかき上げながら、祐子がかすれた声で言った。
「あ・・・」と祐子が、何かに気付いたような声をあげた。俺を見つめたまま、恥ずかしそうに笑う。
「どうした?・・・」
「・・・溢れて来ちゃった・・・あなたのが・・・」
視線を下に向けた。祐子は横向きになって俺を見つめている。下になっている方の太腿を、祐子の体の中から溢れ出した白く濃厚な精液がドロリと垂れ流れ、シーツを濡らしていた。
「とっても濃いのが、いっぱい・・・うれしい・・・私の体でよくなってくれた証なの
ね・・・」
祐子は自分の太腿に手を伸ばすと、ねっとりと流れ落ちる精液を指に絡め取り、その指をしゃぶった。
「・・・ウフ・・・おいしい・・・」
「・・・祐子」
祐子の淫らな行為は、俺の欲情の炎を再び燃え上がらせるものだった。
「こんなにいやらしいことするなんて、がっかりしちゃった?」
「いや、その反対だよ。インテリの女性ほど、淫らになった時はすごいって言うけど、本当なんだなと思う。いやらしい祐子には、とってもそそられるよ・・・ほら、これが証拠だ・・・」
俺は祐子の手を取り、怒張しきって脈打っているペニスを握らせた。
「・・・ああん、すごい・・・また、こんなになってる・・・」
「祐子みたいな、いい女とベッドにいるんだから・・・当たり前だよ・・・」
祐子を抱き寄せて、キスを交わす。祐子が積極的に舌を絡ませてくる。
「ああ、私、どうかなっちゃったみたい・・・こんなに淫らになっちゃうなんて・・・ねえ、来て・・・」
再び一つになると、祐子は先ほどにも増して激しく乱れていった。途中で祐子を俯せにした。祐子は肘をついて体を起こし、張りのある白い尻を高く掲げるようにした。祐子の後ろに膝をつき、見事にくびれた腰に手をかけて深々と貫くと、祐子は滑らかな白い背中を反り返らせ、両手でシーツを握り締めて高い声をあげた。
祐子の腰をしっかりと掴まえ、動き始める。下腹部に当たる祐子の柔らかい尻の感触が心地よかった。動きをリズミカルにしていくと、重く垂れ下がった形のよい豊かな乳房が、ブルンブルンと悩ましく揺れ続ける。
動きながら、きれいに窪んだ祐子の背筋に舌先を這わせたり、背中に覆い被さるようにして揺れる乳房を揉みしだいたりする。知的な美しい女性を這わせて犯しているようで、俺の興奮も高まり、動きが激しくなる。
「あんっ!・・・深くて・・・ああ、あなたのが、喉から出てきそうな感じよ! ああっ、
いい、いいっ!」
祐子は枕に顔を押し付け、シーツを掴んで裸身をよじり、引きつらせる。
前後の動きだけでなく、深々と押し込んだまま、こねくり回すように動くと、祐子は絞り出すような呻き声をあげて快楽に痙攣した。祐子の裸身が痙攣すると、俺のペニスをきつく咥え込んだ肉襞も小刻みに収縮する。
「うう、ん・・・祐子・・・いいよ・・・ああ・・・締まる!」
「ああ、ダメ! また、またイキそうっ! 」
祐子の快楽の喘ぎと裸身の痙攣が激しくなる。俺はこねくり回すように動きながら結合部分に指を這わせ、クリトリスを探り当てて指で転がす。
「ひっ、い、いいっ! いや、いやあ! イクわ、ああ、イクっ! ヒイイッ、イッ、クうぅっ!」
祐子が達した。全身を強張らせ、ブルブルと震わせる。
ペニスを深々と呑み込んだ肉襞も、俺を快楽の道連れにするかのように締まりながらピクつきを繰り返す。
「ううっ、祐子!・・・んんっ!」
祐子の白い尻を、赤く指の跡が残るほどに掴み締め、快楽の渦に引きずり込まれそうになるのを何とか踏み止まった。やがて祐子の裸身から力が抜け、上体がぐったりとベッドに伸びた。俺が祐子から離れると、祐子は脚を伸ばし、高く掲げていた尻も落として俯せになり、ハアハアと激しい呼吸を繰り返している。
汗ばんだ白い裸身は時折ブルッと震えを繰り返し、そのたびに祐子は「あんっ・・・」と声を洩らす。
俺は祐子の隣に横になり、俯せのまま絶頂感の余韻を味わっている祐子の髪や背中を撫でていた。
「・・・気が遠くなりそうだったわ・・・体がドロドロに溶けて、弾け散るみたいな感じがして・・・」
呼吸が落ち着いてくると、祐子が言った。
「よかったよ・・・祐子を犯しているみたいで、すごく興奮したよ」
「フフフ・・・私も、いかにもあなたのものにされているっていう感じがして、でも、あなたはイカなかったのね・・・」
「祐子と一緒にイキそうになったけど、何とか堪えたんだ・・・祐子の中でイクのは最高だけど、祐子と、もっと楽しみたいから・・・」
祐子は片手をついて体を起こし、乱れて顔に絡み付いた髪を指でかき上げながら俺に覆い被さってくる。
俺は下から祐子を抱き締め、唇を重ねてきた祐子と深く舌を絡ませ合った。
「ねえ、今度は、私があなたを犯してあげる・・・うんと淫らな女になって、あなたを楽しませてあげるわ」
祐子が俺を見つめたまま、俺の腰をまたいできた。祐子の愛液にまみれて脈打っているペニスにしなやかな指を絡み付かせ、上体を起こすと、亀頭を熱く濡れた肉の花びらに押し付ける。
瞳の奥に淫らな炎を湛えた祐子は、俺を見つめたままゆっくりと腰を落としてきた。亀頭が呑み込まれ、熱い密壷に浸されたような感触に包まれた。そこで祐子は一呼吸おいてから、一気に俺の腰の上に座り込むようにした。ぬかるみに足を突っ込んだような音とともに、ペニスは熱くぬめる肉襞にヌルヌルッと擦りたてられながら、深々と祐子の中に呑み込まれた。
「ああんっ!・・・う、ううん・・・深いわ!・・・」
祐子はビクッと裸身を引きつらせ、天井を仰ぐようにしてペニスの量感を噛み締めているようだった。
「ああ・・・祐子・・・すごく、熱いよ・・・ああ、締まってくる・・・」
祐子の肉襞が痙攣しながら収縮している。腰から腿の辺りに感じられる祐子の重みも心地よかった。
祐子が溶ろけたような目で俺を見下ろし、見つめたまま、身震いするほど淫らで美しい微笑を浮かべた。
「ああん・・・ねえ、動いていい?」
「いいよ、好きなように動いてごらん・・・」
「ああ・・・私、いやらしい女になるわ・・・」
そう言って祐子は、ゆっくりと腰を上下させ始めた。その動きが次第に速さを増していく。
荒い息づかいと悩ましい喘ぎ声をあげ、美しい豊かな乳房がブルンブルンと揺れ続ける。祐子は裸身を上下に弾ませるだけでなく、俺の上に座り込んで深々と呑み込み、腰をくねらせるようにもした。
「ああっ、どう?・・・ねえ、気持いい?・・・」
「いいよ、すごく、いい・・・ああ、祐子・・・上手だ・・・」
俺は下から手を伸ばし、悩ましく揺れ続ける祐子の白い乳房を揉みしだく。
「いいっ、いいわ・・・すごく、いい!・・・ああ・・・あんっ!」
祐子の動きが激しさを増していく。俺の上で喘ぎながら裸身を弾ませ、くねらせる。
美しい白い裸身は汗ばみ、スタンドの灯りの中で、オイルを塗ったように悩ましくぬめり光っている。
知的に整った美しい顔は快楽に歪み、額や頬に髪が乱れてまとわりつく。その髪をかき上げながら俺を見下ろす視線は、凄艶なものだった。知と淫のアンビバランスが、俺の興奮と快楽を一層高めていく。
祐子の見事にくびれた腰に手をかけ、下から突き上げるようにすると、祐子は喉の奥から絞り出すような呻き声をあげて、裸身を硬直させ、震わせる。
「ああっ! もう、もうダメ・・・また、イキそうっ! ああん、すごい!」
祐子が俺の顔の両脇に手をつき、シーツを握り締めて裸身を引きつらせる。

「ああ、イク、イクわ! ああっ、狂っちゃうっ! イク、イクぅっ! んあああ!」
祐子が天井を仰ぐように顔をのけぞらせ、絶頂に達した。汗に光る白い裸身が
ビクビクと痙攣した。ペニスを深々と呑み込んだ熱い肉襞も震えながら収縮する。
さっきは何とか堪えたが、今度は祐子の絶頂に引きずり込まれるのを踏み止まることはできそうもなかった。
腹筋を使って上体を起こし、快楽に痙攣している祐子の上半身をきつく抱き締めた。祐子も俺にしがみつき、汗ばんだ柔らかい肌がしっとりと吸い付いてくる。
祐子の重みが交わる部分にかかって強烈な密着感となり、俺の快楽も一気に爆発した。
「ああ、祐子!・・・ダメだ、イクよ! ううっ、祐子っ!」
抱き締めた祐子の裸身の痙攣を感じながら、強烈な射精感に身を任せた。祐子の熱い肉の締め付けに反発するかのようにペニスが脈打つたびに、目の前が真っ白になるような快楽とともに、精液が勢いよく祐子の体の中に噴き出していく。俺の射精を感じた祐子が、息をつまらせるようにしてさらに激しく痙攣した。
俺と祐子はきつく抱き締め合ったまま、強烈な絶頂の快楽を分かち合った。長く激しい射精がようやく終わっても、まだペニスは祐子の中で脈動を繰り返し、そのたびに祐子もビクッと裸身を震わせる。
俺は祐子を抱き締めたまま、ベッドの上に仰向けになった。祐子はまだ荒い呼吸を繰り返しながら、俺の上でぐったりとしている。
強烈な快楽の余韻の中で、俺は祐子の柔らかなセミロングの髪を撫でていた。
雪の夜の静寂に包まれた部屋の中で、俺と祐子の息遣いだけがしばらく続いた。
窓の外は、相変わらず雪が降りしきっている。さらに激しさを増してきたようだ。
「ねえ、私のこと・・・どう思っている?」と、祐子が低くかすれた声で言った。
「好きでもない女を二人きりでスキーに誘ったりしないし、まして抱いたりしないよ」
そう言うと祐子は頭を上げ、そんなことはわかっているという顔で俺を見下ろしてきた。
「そうじゃなくて、結婚するっていう相手がいるのに、あなたとこうなったことを言っているの」
「後悔しているのか?」
俺は祐子の目を見つめて言った。
「・・・そうね・・・後悔しているわ・・・」
祐子も俺の目を見つめたまま言い、微かに笑った。目は笑ってはいない。
「後悔していることは二つ・・・もう少し早くあなたと知り合って、こうなっていたらっていうことと・・・今まで知らなかったほどの歓びを教えられてしまったっていうこと・・・こんなになったの、初めてよ・・・さっきなんか、失神寸前だったの。ホントに、スーッと気が遠くなっていったわ・・・」
そう言って祐子は、また俺の胸に頭を乗せた。
「それで、どう思っているの?・・・悪い女だと思っているわよね」
「確かに悪い女だよ・・・普段は清楚で知的な祐子がベッドではこんなに淫らで、最高の女性だってことを俺に教えたんだから、祐子は悪い女だ」
「ウフフ・・・いつも思っていたんだけれど、結構キザに聞こえる科白を平気で言うのよね」
「おかしいかな」
「ううん。似合っているわ・・・ね、外はまだ雪が降っているのね」
「とても熄みそうもないな、この勢いじゃ」
「明日はどうするの? この雪じゃ、スキーは無理よね。ゲレンデに出たって、前も見えやしないわ」
「明日の朝、起きてから考えることにしよう。今夜は、そんなことを考えている場合じゃない」
そう言って、俺は祐子を抱いたまま体を入れ替えた。俺の胸の下で、祐子の形のよい豊かな乳房が柔らかく潰れた。祐子の柔らかな下腹部に、すっかり力を取り戻しているペニスを押し付ける。
それを感じた祐子が、瞳の中に小さな欲情の炎を灯らせて俺を見つめてくる。
「・・・明日は雪が熄んだしても、スキーが出来なくなるわ・・・」
「俺が? それとも、祐子の方が?」
「・・・二人とも、よ・・・足腰に力が入らなくなって・・・フフフ」
俺と祐子は、熱く、長いキスを交わした。
「それもいいかも知れない。明日も二人で一日中、こうして過ごすことにしようか」
「・・・悪くない考えだわ・・・」
再び情熱的なキス。そのまま俺と祐子は、また熱い渦の中に呑み込まれていった。