|
丂戙昞揑側彈惈墲棃暔嶌壠偲偟偰傑偢巚偄晜偐傇偺偼丄嫃弶捗撧偲挿扟愳柇鏪偱偁傠偆丅
丂柇鏪偼丄廬棃偺惓摑揑彈昅偺怣曭幰偵偼庴梕偝傟側偄傛偆側丄撈摿側嶶傜偟彂偒偱堦彂棳傪側偟偨彈棳彂壠偱偁傞丅偄傢偽峕屗拞婜偺彈昅僽乕儉傪姫偒婲偙偟偨挘杮恖偱偁偭偰丄斅峴偝傟偨庤杮偺悢偼栺擇乑揰偲懠偺彈棳彂壠偺捛悘傪嫋偝側偐偭偨乮偙偺曈偺帠忣偵偮偄偰偼亀峕屗婜偍傫側峫亁戞幍崋強廂偺愘峞乽嬤悽姧峴偺彈昅庤杮偵偮偄偰乿傪偛嶲徠捀偗傟偽岾偄偱偁傞乯丅
丂堦曽丄嫃弶捗撧偲偄偊偽丄嬤悽拞婜埲崀偵懡偔偺斅庬傪惗傫偩亀彈幚岅嫵丒彈摱巕嫵亁偺嶌幰偲偟偰桳柤偩偑丄偦偺傎偐偵傕偄偔偮偐偺墲棃暔傪庤妡偗偰偍傝丄摿偵亀彈彂娝弶妛彺亁偼屻悽偺彈梡暥復偵懡戝側塭嬁傪媦傏偟偨揰丄傑偨捗撧偺帠愓傪抦傞桞堦偺婰弎傪嵹偣偰偄傞揰偱嬌傔偰廳梫偱偁傞丅
丂崱夞偼偦傫側嫃弶捗撧偺彈梡暥復傪拞怱偵徯夘偟丄嬤悽偵偍偗傞彈惈偺庤巻偺嶌朄丄偄傢備傞彈惈彂嶥楃乮彈暥偺宍幃傗梡岅偵娭偡傞婯掕乯偺撪梕偲曄慗偵偮偄偰彮偟偽偐傝弎傋偰傒偨偄丅
仜捗撧偺嶌昳偲帠愓
丂偝偰丄嫃弶捗撧偵偼偳偺傛偆側嶌昳偑偁傞偺偱偁傠偆偐丅埲慜丄巹偼亀峕屗帪戙彈惈暥屔亁戞榋乑姫乽彈弶妛暥復丒彈彂娝弶妛彺乿偺夝戣偱師偺敧揰傪徯夘偟偨丅
丂丂乮侾乯掑嫕屲擭乮堦榋敧敧乯嶰寧姧亀彈昐恖堦庱亁擇姫丂嫗搒丒枩壆彲暫塹傎偐姧
丂丂乮俀乯尦榎擇擭乮堦榋敧嬨乯埲慜姧亀彈暥復娪亁擇姫丂仏尰懚偣偢丅
丂丂乮俁乯尦榎嶰擭乮堦榋嬨乑乯堦寧姧亀彈彂娝弶妛彺亁嶰姫丂嫗搒丒彫嵅帯敿塃塹栧斅丂仏夵戣杮偵尦暥嶰擭乮堦幍嶰敧乯嶰寧姧亀彈暥椦曮戃亁堦姫偁傝丅
丂丂乮係乯尦榎幍擭乮堦榋嬨巐乯嶰寧姧亀彈嫵孭暥復亁擇姫丂嫗搒丒暥戜壆帯榊暫塹斅
丂丂乮俆乯尦榎敧擭乮堦榋嬨屲乯嶰寧姧亀彈幚岅嫵丒彈摱巕嫵亁擇姫丂嫗搒丒暥戜壆帯榊暫塹斅丂仏嫗搒丒慘壆彲暫塹屻報杮偁傝丅
丂丂乮俇乯墑嫕巐擭乮堦幍巐幍乯堦堦寧姧亀彈暥復搒怐亁堦姫丂戝嶃丒埨堜栱暫塹斅丂仏尦榎擭娫嶌
丂丂乮俈乯曮楋屲擭乮堦幍屲屲乯堦寧姧亀彈捠梡暥戃亁堦姫丂嫗搒丒慘壆彲暫塹斅丂仏尰懚偣偢丅亀柧榓嬨擭彂愋栚榐亁亀峕屗弌斉彂栚亁偵傛傞丅亀彈暥椦曮戃亁偺夵戣杮偐丅
丂丂乮俉乯柧榓嬨擭乮堦幍幍擇乯埲慜姧亀彈梫崱愳嫵孭娪亁擇姫丂仏尰懚偣偢丅亀柧榓嬨擭彂愋栚榐亁偵傛傞丅
丂埲忋偺偆偪乮俀乯丄乮俈乯丄乮俉乯偺嶰揰偼夝戣幏昅帪揰偱尨杮偑妋擣偱偒側偐偭偨傕偺偱偁傞丅
丂偪側傒偵亀崙彂憤栚榐亁挊幰暿嶕堷偵偼乽嫃弶乿偁傞偄偼乽嫃弶偮側乮捗撧乯乿偺挊嶌偲偟偰乮俁乯偺夵戣杮亀彈暥椦曮戃亁偲乮係乯丄乮俉乯偺傎偐偵丄拀攇戝杮亀埳惃暔岅彈擔梡暥復亁傪嵹偣傞偑丄拀攇戝杮偼媽憼幰丒壋抾娾憿偵傛傞壖戣偱丄乮俇乯偺亀彈暥復搒怐亁偑尨戣偱偁傞丅傑偨丄亀屆揟愋憤崌栚榐亁挊幰暿嶕堷偵偼乽嫃弶搒壒乿偺挊嶌偲偟偰乮俁乯偩偗傪嵹偣傞丅偦傟偵偟偰傕丄亀崙彂亁亀屆揟愋亁偲傕偵亀彈幚岅嫵丒彈摱巕嫵亁傪捗撧偺嶌昳偲偟偰偄側偄偺偼晄壜夝偱偁傞丅
丂偄偢傟偵偟偰傕丄椉栚榐偺挊幰暿嶕堷偱偼忋婰敧揰偺敿暘偟偐捗撧偺嶌昳傪偁偘偰偄側偄丅屻弎偡傞傛偆偵丄偦偺屻偺挷嵏偱乮俀乯偑怴偨偵妋擣偝傟偨偨傔丄枹敪尒偼乮俈乯偲乮俉乯偺擇揰偵側偭偨丅傑偨丄尰懚偡傞乮侾乯乣乮俇乯偺偆偪乮俁乯乣乮俇乯偼塭報偱弌斉偝傟偰偄傞乮乮俁乯偑亀峕屗帪戙彈惈暥屔亁丄乮係乯偲乮俆乯偑亀墲棃暔戝宯亁丄乮俇乯偑亀婬鍽墲棃暔廤惉亁丅偄偢傟傕昅幰曇廤乯丅
丂偙傟傜捗撧偺嶌昳偼偄偢傟傕彈巕梡墲棃偵暘椶偝傟傞傕偺偱偁傞偑丄彈棳墲棃暔嶌壠偺拞偱偼孮傪敳偔嶌昳悢偱偁傞丅偦偟偰偦傟埲忋偵廳梫側偺偼丄偦傟偧傟偺嶌昳偑撈憂揑偐偮屄惈揑偱偁傞偙偲偲丄偦偺傎偲傫偳偑帺昅丒帺夋偱偁傞偙偲丄偮傑傝杮暥傪挊偟偨偆偊偵斉壓偺惔彂偐傜憓奊傑偱傕堦恖偱偙側偡偲偄偆丄斵彈偺懡嵥偝偱偁傞丅
丂偙偺傛偆偵摉帪婬偵傒傞彈惈偱偁偭偨偵傕偐偐傢傜偢丄斵彈傪徯夘偟偨傕偺偼奆柍偵摍偟偄丅亀崙彂恖柤帿揟亁傪巒傔偲偡傞恖柤帿揟偵傕丄捗撧偺帠愓偵娭偡傞婰帠偼堦偮傕尒弌偡偙偲偑偱偒側偄丅
丂偦傟偱偼丄忋婰嶌昳拞偵庤妡偐傝偼側偄偺偐丅
丂幚偼朻摢偱怗傟偨傛偆偵丄捗撧偑帺傜偵偮偄偰弎傋偨傢偢偐側婰弎偑亀彈彂娝弶妛彺亁彉暥拞偵尒偊傞丅
揤崀傞擔撨偵惗側傞妺偺梩偺偆傜傓傞帠偼廻悽偺偊偵偟偧偐偟丅懘摴乆偺偙偲傢偞傪業偟傜傑傎偟偒偵偼丄妿楒偟偒偼搒側傔傝丅杔憇擭偺斾丄寗偁傞恎偲側傟傝丅傛傝偰丄擔斾偺杮堄偙乀側傝偲敧廳偺幀楬傪偟偺偓偰丄崱丄崯嬨廳偵偄偨傝偸丅廧帠擇廫偲偣偵媦傋傝丅偮傤偵巚傆摴乆傪偨偳傝偰丄懘偐偨偼偟傪偆偐乁傂丄変恎偵偼懌傟傝偲惀傪偨偺偟傒丄寗峴嬵偺偁偟側傒傪憪偺偲偞偟偵偐偧傊丄榓崙偺晽夒傪枴傆側傜偟丅
唰偵偟傟傞恖丄堦恖偺彈巕傪傕偰傝丅惀偑偨傔偵彈暥復偺偟傞傋側傜傫帠傪彂偰傛偲朷傔傞帠悢懡搙側傝丅帿偡傞偵帉側偔偰丄廔偵擇嶥偺暥傪彂偰偁偨傊偸丅斵恖傛傠偙傃偰亀彈暥復娪亁偲柤晅傝丅偦傟傕偄偮偟偐彂椦偺庤偵搉傝偰埐偵挙偰悽偵峴傊傝丅崱堦恖偺彈巕偁傝偰丄枖崯彂傪朷傔傝丅傛偮偰丄偮偨側偒帉傪捲偰亀彈彂娝弶妛彺亁偲柤晅丅偙傟曃偵弶怱偺偨傔側傝偲偄傆帠偟偐傝丅
嫃弶巵彈搒壒彂擵 丂
丂偙偺抐曅揑側婰帠偐傜戝嶨攃偱偁傞偑丄嫃弶捗撧偺摦岦偵偮偄偰師偺傛偆側悇棟偑壜擻偱偁傠偆丅
丂乽彅摴傪妛傇側傜嫗搒傊徃傞偺偑堦斣偱偁傞偲偄偆怣擮傪帩偪偮偮傕丄偙偺巹偑揷幧偵惗傑傟偨偺偼慜悽偐傜偺場墢偱偁傠偆乿劅劅偦傫側捗撧偺婅朷偑偐側偭偨偺偼乽憇擭乿偺崰偱偁偭偨丅偦偟偰杮彂傪挊偟偨尦榎嶰擭乮堦榋嬨乑乯傑偱栺擇乑擭娫偙偺嫗偵廧傒懕偗偨偲偄偆丅壖偵乽憇擭乿傪暥帤捠傝嶰乑嵨崰偲偡傟偽丄尦榎嶰擭偱栺屲乑嵨丄媡嶼偟偰丄姲塱堦幍擭乮堦榋巐乑乯崰偺惗傑傟偲側傞丅偙傟偑惓偟偗傟偽丄捗撧偺嵟弶偺挊嶌亀彈昐恖堦庱亁偑弌偝傟偨掑嫕屲擭乮堦榋敧敧乯偱巐敧嵨埵丄惗慜嵟屻偺弌斉暔偲巚傢傟傞亀彈幚岅嫵丒彈摱巕嫵亁偺姧峴偑尦榎敧擭乮堦榋嬨屲乯偱屲屲嵨埵偲側傞丅嶰乑嵨崰嫗搒傊堏廧偟偨捗撧偼乽寗偁傞恎乿偲偟偰彅寍傪妛傫偩丅偙偲偝傜彂昅丒奊夋偵偼懪偪崬傫偩偺偱偁傠偆丅巐乑戙屻敿傑偱偵偼彂壠偲偟偰偺柤惡傪攷偟偰偍傝丄夋壠偲偟偰傕姧杮偺憓奊傪昤偔傎偳偺堟偵払偟偰偄偨丅傑偨丄抦恖偺摱彈悢恖偵庤廗偄巜撿傪偟偰偄偨條巕傕塎傢傟傞偐傜丄庤杮偺幏昅傪媮傔傜傟傞偙偲傕懡偐偭偨偼偢偱偁傞丅
丂偙偺傛偆側嫗搒偱偺斢擭惗妶丄偡側傢偪丄掑嫕乣尦榎婜偵斵彈偺挊嶌偑廤拞揑偵弌斉偝傟偨偺偱偁傞丅枩帯擭娫偵孍揷傗偡昅偺庤杮乮亀彈掚孭亁亀彈弶妛暥復亁乯偑姧峴偝傟偰埲棃丄嫗搒偱偼彈昅庤杮偑懕乆姧峴偝傟偨丅尮彈昅偺揤榓擇擭姧亀摉棳
彈梡暥復亁丄孍揷偮側乮傗偡偺柡乯昅偺掑嫕巐擭姧亀彈崱愳亁丄挿扟愳掑乮柇鏪偲摨堦恖偐乯昅偺尦榎幍擭姧亀偟偺偡乀偒亁丄戲揷媑昅偺尦榎巐擭姧亀彈昅庤杮亁側偳偵壛偊偰丄慜帪戙偺彂壠偱偁傞彫栰捠偺昅愓傕尦榎巐擭偵亀巐婫
彈暥復亁偺彂柤偱忋埐偝傟偰偄傞丅亀彈掚孭亁骐暥偺乽搒偵偼傛傠偟偒彈昅偁傑偨偍偼偟傑偡傊偗傟偼乿乮掑嫕巐擭亀彈崱愳亁偵傕摨偠骐暥傪晅偡乯傗丄亀摉棳
彈梡暥復亁骐暥偺乽悽忋彈昅庩峏懡乿偲偄偭偨昞尰偼慡偔屩挘偱偼側偐偭偨丅搒偱偼彈棳彂壠偺妶桇偑傔偞傑偟偔丄忋嫗偟偰帺傜偺嵥擻傪杹偒偨偄偲婅偭偨彈惈偼堦恖捗撧偽偐傝偱偼側偐偭偨偱偁傠偆丅
丂惏傟偰嫗搒偵傗偭偰偒偨擇乑擭慜傪丄姶奡怺偔夞憐偟側偑傜捲傞捗撧偺偙偺彉暥偵偼丄彂夋傪巒傔偲偡傞彅摴傊偺巭傓偙偲偺側偄扵媮怱偲丄偦偺堦曽偱乽寗峴嬵偺偁偟側傒乿丄偡側傢偪旘傇傛偆偵夁偓偨寧擔傪嬃偒夨傗傓婥帩偪偑堨傟弌偰偄傞傛偆偵巚偆丅偄偢傟偵偟偰傕丄捗撧偺屄惈揑側墲棃暔偼丄堦偮偵偼嫗搒偵偍偗傞彈昅偺惙峴偲偄偆搚忞偺忋偵惗傑傟偨傕偺偱偁偭偨丅
丂偲偙傠偱偦偺彉暥拞偱婥偵側傞偺偼丄偁傞抦恖偺擬怱側埶棅偵傛傝捗撧偑彈巕妛廗梡偵彂偒梌偊偨偲偄偆乽擇嶥偺暥乿偱偁傞丅偦傟偼抦恖偵傛傝亀彈暥復娪亁偲柤晅偗傜傟丄傗偑偰弌斉偝傟傞偙偲偵側偭偨丅偪側傒偵亀尦榎屲擭彂愋栚榐亁乽墲棃庤杮椶乿枛旜偺乽彈庤杮乿崁偵乽彈彂娝弶妛彺乿偲暲傫偱擇嶜杮偺乽彈暥復偐乀傒乿偑尒偊傞偑丄偙傟傪巜偡偺偱偁傠偆丅廬偭偰丄捗撧偼亀彈彂娝弶妛彺亁埲慜丄偡側傢偪尦榎擇擭埲慜偵暿偺彈梡暥復傪彂偄偰偄偨丅偦偺弌斉偼丄彉暥偺捠傝斵彈偺梊婜偟側偄傕偺偩偭偨偲尒偊傞偑丄偦偺斅尦偼摉慠側偑傜嫗搒彂沔偱偁偭偨偱偁傠偆丅
丂妋偐偵亀彈暥復娪亁偼懚嵼偟偨丅偦傟偼暣傟傕側偄帠幚偲偟偰傕丄亀崙彂憤栚榐亁亀屆揟愋憤崌栚榐亁傗奺婡娭偺憼彂栚榐傪扥擮偵挷傋偰傕尨暔傪敪尒偱偒偢丄巹帺恎丄嵟嬤傑偱亀彈暥復娪亁傪尪偺彂偲峫偊偰偄偨丅扨弮偵彂柤偩偗偱峫偊傟偽丄嫕曐屲擭乮堦幍擇乑乯偵嫗搒彂沔丒拞懞懛嶰椙偵傛偭偰斅峴偝傟偨亀彈拞暥復娪亁乮尓摪暥屔憼乯偑嵟傕嬤偄偑丄偦傟偵偼昅幰偺彁柤偼側偔丄傑偨姧婰偺擭戙偺僘儗偐傜傛傕傗奩摉彂偲偼巚傢偢丄廬偭偰惛嵏偡傞偙偲傕側偐偭偨傢偗偱偁傞丅
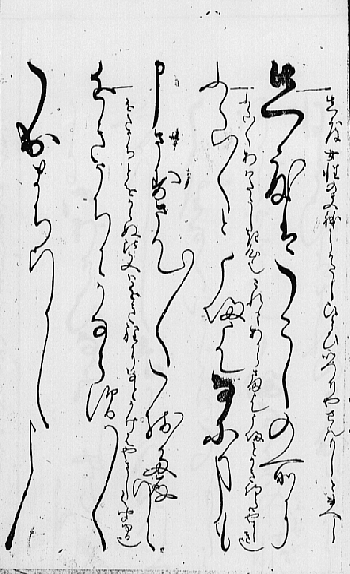 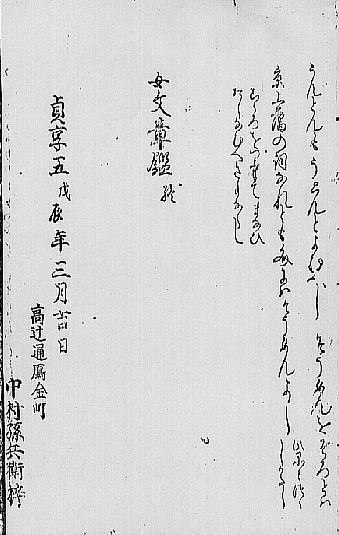 丂偲偙傠偑嵟嬤丄曣棙巌楴巵壦憼杮拞偵掑嫕屲擭乮堦榋敧敧乯嶰寧姧偺亀彈暥復娪亁擇嶜杮偑偁傞偙偲傪抦偭偨丅巵偺偛岲堄偵傛傝僐僺乕傪捀偒憗懍挷傋偰傒偨偲偙傠丄幚偼亀彈拞暥復娪亁偼亀彈暥復娪亁偺夵戣杮偵夁偓側偄偙偲偑敾柧偟偨丅懠偵慡偔強憼偺側偄婬鍽彂偱偁傞偆偊偵丄曣棙巵憼杮偼尨憰丄尨戣庥晅偒偱嬌傔偰忬懺偑椙偄丅忋姫偵乽彈暥復娪乿丄壓姫偵乽彈暥復偐乀尒乿偺戣庥傪晅偟丄壓姫枛偵 丂偲偙傠偑嵟嬤丄曣棙巌楴巵壦憼杮拞偵掑嫕屲擭乮堦榋敧敧乯嶰寧姧偺亀彈暥復娪亁擇嶜杮偑偁傞偙偲傪抦偭偨丅巵偺偛岲堄偵傛傝僐僺乕傪捀偒憗懍挷傋偰傒偨偲偙傠丄幚偼亀彈拞暥復娪亁偼亀彈暥復娪亁偺夵戣杮偵夁偓側偄偙偲偑敾柧偟偨丅懠偵慡偔強憼偺側偄婬鍽彂偱偁傞偆偊偵丄曣棙巵憼杮偼尨憰丄尨戣庥晅偒偱嬌傔偰忬懺偑椙偄丅忋姫偵乽彈暥復娪乿丄壓姫偵乽彈暥復偐乀尒乿偺戣庥傪晅偟丄壓姫枛偵
掑嫕屲曡扖擭嶰寧媑擔
丂丂丂丂丂丂丂丂崅捯捠婂嬥挰
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂拞懞懛暫塹埐
偺姧婰傪桳偡傞丅偪側傒偵嫕曐屲擭斅亀彈拞暥復娪亁偺姧婰偼丄
嫕曐屲峂巕擭嶰寧媑擔
丂丂丂丂丂丂丂丂崅捯捠婂嬥挰
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂拞懞懛嶰椙埐
偲側偭偰偍傝丄擭崋丒斅尦柤偺堦晹傪夵崗偟偨傕偺偱偁傞丅傑偨丄彉戣丒旜戣傕乽彈暥復娪乿偐傜乽彈拞暥復娪乿偲夵崗偝傟偨揰傪彍偗偽椉幰偼摨堦偱偁傞乮偨偩偟亀彈拞暥復娪亁偺奜戣偼晄柧乯丅
丂偩偑掑嫕斅偵傕嫃弶捗撧偺彁柤偼尒偁偨傜側偄丅偟偐偟丄偁傜偨傔偰専摙偟偰傒傞偲丄偙偺掑嫕斅偑嫃弶捗撧偺挊嶌偱偁傞偙偲偼傎傏娫堘偄側偄傛偆偵巚傢傟傞丅
丂傑偢丄彂柤丒嶜悢丒姧峴擭戙丒姧峴抧堟偺揰偱慡偔柕弬偑側偄偙偲丅偝傜偵亀彈暥復娪亁偵偼亀彈彂娝弶妛彺亁偲摨條偺婰弎偑彮側偔側偔丄撪梕柺偱堦憌偺嫟捠惈傪尒弌偟摼傞偙偲偱偁傞丅
丂椺偊偽丄亀彈暥復娪亁壓姫枛乮嶰嬨挌僆乯偺彂嶥楃偵偼師偺傛偆側婰帠偑尒偊傞丅
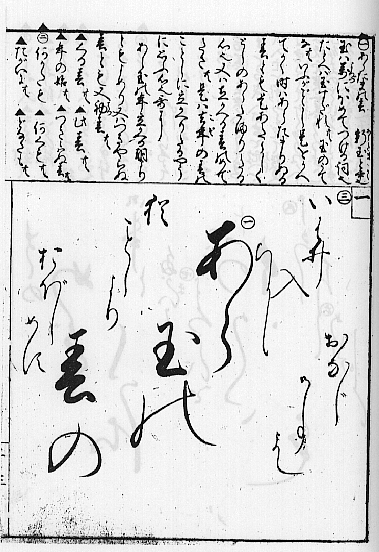 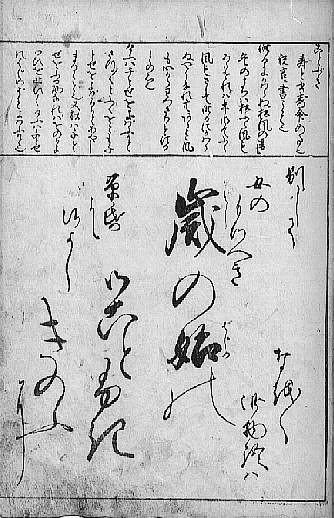
仭乽彈彂娝弶妛彺乿乮嵍乯偲乽彈暥復搒怐乿乮塃乯
堦丄偁傜偨傑偺弔偺傔偰偨偝丅偁傜偨傑偲偼乽怴嬍乿偲偐偔栫丅偁偨傜偟偒嬍偲偄傆怱栫丅嬍偲偼暔傪傎傔偰晅偨傞帉栫丅廲偽乽嬍偺偡偩傟乿乽嬍偺珥乿乽嬍庤敔乿側偳乀偄傆傕傎傔偨傞帉栫丅乽嬍偺偍偺偙屼巕乿偲亀尮巵亁偵傕偐偗傝丅偁傜偨傑偺偼傞偼丄傔偱偨偒偲偟偺巒栫偲傎傔偨傞帉栫丅壧乽偁傜嬍偺擭偨偪偐傊傞偁偟偨傛傝丂傑偨傞乀暔偼轵偺偙傦乿乧
丂偙傟偵懳偟亀彈彂娝弶妛彺亁忋姫朻摢偺摢彂拲偵偼丄
偁傜偨傑偺弔丄乽怴嬍乿偲彂栫丅嬍偼枩偵傎傔偰偮偗傞帉栫丅偨偲傊偽乽嬍偡偩傟乿嫟丄乽嬍偺偆偰側乿嫟偄傆偑偛偲偟丅惀傪偐傊偰偐偔帪偼丄乽偁傜偨傑傝偸傞弔乿偲傕丅惀丄偁偨傜偟偔偲偟偺偁傜偨傑傝偨傞怱栫丅枖偼乽棫偐傊傞弔偺傔偱偨偝乿嫟丅惀偼嫀擭偺弔偺偙偲偟偵棫偐傊傝偨傞傗偆偵巚傆怱栫丅壧偵乽偁傜嬍偺擭棫偐傊傞挬傛傝乿偲傕傛傔傝丅枖偼乽偮偒傗傜偸弔乿偲傕丄枖乽弶弔乿嫟丅
偲偁傝丄椉彂偑摨堦恖嶌偱偁傞偙偲傪暔岅傞丅
丂傑偨丄亀彈彂娝弶妛彺亁壓姫枛偺乽暥偐偒傗偆偺巜撿乿戞堦忦偵
堦丄彈暥偼偄偐偵傕傗偝偟偔偁傞傋偟丅変愭偺彂偵偄傂偨傞偛偲偔丄彈惈偺暥偼帉傪偙傦偵偮偐偼偢丄撉偵偰偮偐傂媼傆傋偟丅乧
偲偁傞偑丄亀彈暥復娪亁壓姫枛乮嶰幍挌僂乯偵傕
堦丄彈暥復偼丄偲偐偔壒偵偰傛傓傗偆偵偼偢偄傇傫偐乀偸偑傛偟丅乧
偲偄偆婰嵹偑偁傝丄傛偔晞崌偡傞丅偮傑傝丄亀彈彂娝弶妛彺亁偵尵偆乽愭偺彂乿偲偼亀彈暥復娪亁偵傎偐側傜側偄偺偱偁傞丅
丂偙傟傜偺帠幚偐傜曣棙巵憼杮偺掑嫕屲擭斅亀彈暥復娪亁偑嫃弶捗撧偺挊嶌偱偁傞偙偲偼傎偲傫偳媈偆梋抧偑側偄偱偁傠偆丅廬偭偰丄朻摢偱帵偟偨嶌昳堦棗乮俀乯偺乽尦榎擇擭埲慜姧乿偼乽掑嫕屲擭嶰寧姧乿偲彂偒懼偊偹偽側傜偢丄偙偺亀彈暥復娪亁偼亀彈昐恖堦庱亁偲暲傫偱捗撧偺嵟弶偺挊嶌偱偁傞偙偲傪妋擣偟摼偨偺偱偁傞丅
仜嶰庬偺彈梡暥復
丂師偵丄尰懚偡傞捗撧偺彈梡暥復嶰庬乮愭偺乮俀乯丄乮俁乯丄乮俇乯丅側偍乮係乯亀彈嫵孭暥復亁偼亀娪憪亁偺庡巪傪捲偭偨庤杮偱偁傝彈梡暥復偱偼側偄乯傪偁偘側偑傜丄偦偺奣梫丒摿怓側偳傪尒偰峴偙偆丅
亂彈暥復娪亃
丂彂帍偵偮偄偰偼婛偵娙扨偵徯夘偟偨丅杮彂偼塭報丒東崗偺偄偢傟傕側偝傟偰偄側偄偑丄偦偺夵戣杮偱偁傞亀彈拞暥復娪亁偑亀墲棃暔戝宯亁偵塭報廂榐偝傟偰偄傞偺偱丄偦偺撪梕傪抦傞偙偲偑偱偒傞丅偨偩亀彈拞暥復娪亁偼忋壓姫傪崌嶜偡傞偑丄亀彈暥復娪亁偼擇姫擇嶜偱偁傞丅忋姫擇堦挌偵偼彉暥媦傃徚懅椺暥擇乑庬丄壓姫擇嶰挌偵偼徚懅椺暥堦擇庬偲彈惈彂嶥楃偲偄偆峔惉偵側偭偰偄傞丅
丂杮彂偼亀彈彂娝弶妛彺亁彉暥偱柧傜偐側傛偆偵丄彈惈偺庤巻偺婎杮椺暥丒婎杮嶌朄傪庡偲偟偨弶怱幰岦偗偺彈梡暥復偱偁傞丅捗撧偑弶怱幰偵嵟傕嫮挷偟偨偐偭偨偙偲偼偄偐側傞揰偱偁偭偨偐丅偦偺摎偊傪杮彂彉暥偵撉傒偲傞偙偲偑偱偒傞丅
丂丂彈暥復娪彉
帉偵偁傗傑傝偲懎岅偲偁傝丅偁傗傑傝偼偐偨偙偲丄懎岅偼壓攜偺偄傂傆傜偡偙偲側傝丅偮偹偵偐傗偆偺偝偐傂傪傢偒傑傊偨乁偡傊偟丅暘偰彈惈偺偙偲偽丒暥復側偲偼丄偨偲傂惓尵
偵偰傕抝偺偙偲偽偲丄偍傫側偺偙偲偽偲偺偐偼傝偁傟偼丄偍偲偙偙偲偽傪傆傒偵偼偐偔傊偐傜偢丅崱崯暥復偼丄偍傕偰偵偝傑偺偁傗傑傝暥復傪偐偒丄偐偨偼傜偵拲傪偔偼傊丄偆傜偵惓晽鏪傪偐偒偸丅偡傦偺姫偵偼彈偙偲梩偺徚懅偵傕偪備傞帠丄側傜傃偵巐婫偺帉傪峫偟傞偟帢傝偸丅怱傪偮偗偰傑偹傂媼偼乀丄惀丄彈偺摱偺暥復偵怱偞偟偁傜傫丄偁偝偒傛傝傆偐偒偵帄傝媼傆偨傛傝偲傕側傜傫偐偟丅
丂庤巻偼丄岆偭偨尵梩傗懎岅丄抝尵梩傪巊傢偢偵丄巐婫偵傆偝傢偟偄尵梩偱彂偔傋偒偱偁傞偲尵偆丅梫偡傞偵丄惓偟偔彈惈傜偟偄尵梩尛偄偲偄偆偙偲偵恠偒傞偺偱偁傞丅偦偟偰丄偦傟傪嬶懱揑偵帵偡偨傔偵斵彈偑嵦偭偨曽朄偼丄奺挌偺昞偵岆傝偺椺暥傪宖偘偰晄揔摉側売強傪嵶帤偺拲偱巜揈偟丄偝傜偵摨撪梕偺惓偟偄暥復乮捗撧偼乽惓晽鏪乿偲屇傇乯傪偦偺棤偵宖偘傞偲偄偆傕偺偱偁偭偨丅椺暥偼慡晹偱嶰擇庬偩偑丄偦傟偧傟偵偮偄偰惓丒岆偺擇捠傝傪嵹偣偰偁傞丅椺暥偺撪梕偼憡庤偺埨斲傪栤偆庤巻傗朘栤帪偺楃忬丄偦偺懠彅帠偵偮偄偰偱丄庡戣偑帡捠偭偨椺暥傕娫乆尒庴偗傜傟丄堦斒揑側彈梡暥復偲斾妑偡傞偲亀彈暥復娪亁偼椺暥偺朙晉偝偑姶偠傜傟側偄丅偙偙偱偼丄懡條側暥柺偺妛廗傛傝傕丄惓偟偔彈惈傜偟偄昞尰偺廗摼偙偦偑廳帇偝傟偰偄傞偺偱偁傞丅
丂忋姫朻摢偺椺暥傪尒偰傒傛偆丅撪梕偼抦恖偺嶐擔偺朘栤偵廫暘側偍傕偰側偟偑偱偒側偐偭偨偙偲傪榣傃偮偮丄傑偨偍墇偟壓偝偄偲偺庤巻偱偁傞丅傑偢晄揔愗側暥柺偲偟偰師偺暥復傪嵹偣傞丅
愭搙偼屼偙偟偺強偵傆偨偲屼婣岓偰丄側偵帠傕怽偝偡丄偝偰屼巆懡懚傑偄傜偣岓丅嬤偒偆偪偵偐側傜偡屼弌傑偪傑偄傜偣岓丅偐偟偔
丂尨杮偱傕傢偢偐屲峴偺抁暥偱偁傞乮懠偺椺暥傕摨條乯丅偙偺椺暥偺偆偪丄摿偵捗撧偑巜揈偡傞栤戣揰偼乽愭搙乿乽傆偨乿乽嬤偒偆偪乿偺嶰僇強偱丄偦傟偧傟師偺傛偆側拲彂偒傪巤偡丅
仜乽愭搙乿丄彈惈偺暥鏪偵偐偨偟丅乽傂偲傂乿乽偄偮偦傗乿乽偣傫傕偟乿偲彂傊偟丅
仜乽傆偨乿丄偁偼偨乀偟偒怱栫丅偙傟傕乽偁偐傜偝傑偵偰屼婣乿偲偐偒帢傜偼傗偝偟偒栫丅
仜乽嬤偒偆偪乿丄乽偲傪偐傜偸斾乿枖偼乽嬤偒掱偵乿側偲偐偗偼丄傗偝偟偔暦備傞栫丅
丂偦偟偰丄師暸偵偼揔愗側暥復偲偟偰丄
擔偲傂偼丄傑傟偺屼弌偵屼偝岓偵丄偁偐傜偝傑偵偰屼婣丄側偵偺晽忣傕屼嵗側偔丄偄偐偽偐傝屼偺傕偟偵巚傂傑偄傜偣岓丅墦偐傜偸斾丄偺偲傗偐偵屼偁偦傂側偝傟岓傗偆偵屼弌懸傑偄傜偣岓丅偐偟偔
丂庤捈偟偝傟偨屻幰偺暥復偼丄暥帤帉傕巊傢傟丄傛傝彈惈傜偟偄沀嬋揑側暥柺偵側偭偰偄傞丅
丂傕偆堦椺徯夘偟偰偍偔丅忋姫戞嶰捠栚偱丄嶐擔媞偲偟偰彽偐傟偨媞偐傜偺楃忬偱偁傞丅傑偢埆偄椺偱偁傞丅
嶐擔偼傔偟傛偣傜傟丄偄傠屼抷憱丄偙偲偵堦擔偁偦傂岓偰屼婐偟偔偦傫偟傑偄傜偣岓丅傑偮屼楃偺偨傔丄堦昅怽傑偄傜偣岓丅偐偟偔
丂偙偙偺拲婰偱丄乽堦擔乿偼乽廔擔乿偱傕傛偄偲愢柧偡傞丅偙傟偼扨偵乽懼偊尵梩乿傪椺帵偟偨傑偱偺偙偲偱偁傞丅偟偐偟偦偺屻偺乽傑偮屼楃偺偨傔乿偼慡偔偺抝暥復偱偁傝丄彈暥復偱偼乽傑偮屼楃偲偟偰堦傆偰偲傝傓偐傂乿偺傛偆偵偡傋偒偱偁傞偲拲堄偟偰偄傞丅偙傟傪惓偟偨柾斖暥偼師偺傛偆側傕偺偱偁傞丅
嶐擔偼傑偄傝丄偝傑屼抷憱側偝傟岓丅偦偺偆傊丄傂傔傕偡梀傂岓偰丄怱傪偺偼偟傑偄傜偣岓丅偐偡屼偆傟偟偔懚傑偄傜偣岓丅愭屼楃偵堦昅偲傝傓偐傂傑偄傜偣岓丅偐偟偔
丂懠偺椺暥傕尵梩尛偄偵娭偡傞庬乆偺拲婰傪敽偭偰偄傞丅椺暥偵偼尒弌偟岅偑側偔丄傑偨栚師傕梡堄偝傟偰偄側偄偙偲偐傜傕丄偙偺亀彈暥復娪亁偼幚梡揑側埬暥偲偄偆傛傝傕丄弶怱幰偵彈惈傜偟偄尵梩尛偄傪廗摼偝偣傞偨傔偺僥僉僗僩偲尵偭偨曽偑揑妋偱偁傞丅
側偍丄壓姫枛旜堦堦挌偼彈惈偺彂嶥楃傗彂娙梡岅偵娭偡傞婰帠偱偁傞丅偙偙偱傕捗撧偼彈惈傜偟偄尵梩尛偄偵偮偄偰孞傝曉偟弎傋偰偄傞丅梫巪傪徯夘偟偰偍偔丅
仜彈暥復偼乽傔偯傜偟偒帤乿傪彂偄偰偼側傜側偄丅壖柤暥帤偱彂偔偺偑桪偟偔偰椙偄丅偨偩偟壖柤尛偄偵傕嶌朄偑偁傞偺偱偦傟傪曎偊偰偍偔昁梫偑偁傞丅傑偨丄杮棃偼岆傝偱偁傞偑彈暥偵姷椺偲側偭偰偄傞尵梩尛偄傕偁傞丅椺偊偽乽偄偼傂乮廽偄乯乿偼丄乽傤偼偄乮埵攙乯乿偲撉傒堘偊傗偡偄偺偱丄傢偞偲乽偄傢傤乿偲彂偔偺偼愄偐傜屼強曽偱傕峴傢傟偰偒偨姷廗偱偁傞丅
仜彈暥復偵偼偲偵偐偔帤壒傪梡偄側偄傛偆偵偡傞丅乽偙傫偵偪乿乽傒傗偆偵偪乿乽偣傫偳偼乿乽偣傫寧乿乽嫀擭乿乽摉擭乿乽棃弔乿乽傃傫偓乮曋媂亖壒怣乯乿偲偄偭偨尵梩偼寴偄昞尰偱暦偒擄偄丅乽偗傆乿乽偁偡乿乽偁偝偰乿乽偒偺傆乿乽偄偮偦傗乿乽偝偒偺偮偒乿乽偙偧乿乽偙偲偟乿乽偔傞弔乿乽偁偗偺偼傞乿乽偨傛傝乿側偳偼廮傜偐偄昞尰偱椙偄丅
仜彈暥偵乽梉乿偼埆偔側偄偑乽傛傋乿偲偡傞偲傛傝桪偟偄丅乽偐偼傞屼帠側偔乿傕椙偄偑乽偨偑傆帠乿偺曽偑桪偟偄丅乽屼偒偁傂偁偟偒傛偟乿傛傝傕乽屼偒偦偔偮偹側傜偸傛偟乿乽傟偄側傜偸乿乽偡偔傟偢屼偼偟傑偟岓傛偟乿側偳偺曽偑桪偟偄丅媡偵乽偗偝掱乿傪乽偗偝偑偨乿偲偟偨傝丄乽偑偰傫乿傪偮傔偰乽偑偮偰傫乿偲偡傞偺偼嫠偟偄尵梩尛偄偱偁傞丅乽屼暔墦乿偼巊傢偢乽屼偆偲偟偔乿乽屼偲傪偟偔乿偲彂偔偺偑椙偄丅偙偺傎偐憤偠偰彈暥偵偼乽屼乿偺帤傪晅偗傞偲椙偄丅
亂彈彂娝弶妛彺亃
丂杮彂偺幏昅偐傜弌斉傑偱偺宱堒偼婛偵徯夘偟偨捠傝偱丄抦恖偐傜惪傢傟傞傑傑偵挊偟偨弶怱幰梡偺彈梡暥復偱偁傞丅幏昅摦婡傗懳徾幰傕亀彈暥復娪亁偲摨條偲巚傢傟傞偑丄師偺揰偱堎側傞丅
丂乮侾乯亀彈暥復娪亁偵偔傜傋偰亀彈彂娝弶妛彺亁偼椺暥偺懡條惈偵攝椂偑尒傜傟丄奺椺暥偑栚師偵傛偭偰堦棗偱偒傞傛偆偵側偭偰偄傞丅傑偨庡戣偵崌傢偣偰嶶傜偟彂偒丒暲傋彂偒丄傑偨捛怢暥偺桳柍側偳傪揔媂巊偄暘偗傞側偳丄慡懱偲偟偰傛傝幚梡揑丒幚嵺揑側彂娙宍幃偲撪梕傪旛偊偨傕偺偵側偭偨丅
丂乮俀乯亀彈彂娝弶妛彺亁偺岅拲偼慡偰摢彂偵宖偘傜傟丄屄乆偺椺暥偵懄偟偰徻嵶偵巤偝傟偰偄傞丅椺暥偲拲庍暥偺懳墳娭學偼娵晅偒悢帤偱柧夣偵帵偝傟丄拲庍撪梕傕擭拞峴帠屘幚傗彂娙梡岅丒嶌朄丄柤強媽愓丄堎柤丄屆揟丄晽懎丒廗姷丄暓嫵側偳懡曽柺偵媦傇丅摿偵弌揟傪柧婰偡傞側偳峫徹揑巔惃偼懠偺彈梡暥復偵偼偁傑傝尒傜傟側偄嵺棫偭偨摿挜偱偁傞丅
丂乮俁乯彂娙梡岅傗彂娙嶌朄偵偮偄偰偺婰弎偑惍棟偝傟丄傛傝尒傗偡偔側偭偨丅乮侾乯傗乮俀乯偲傕娭楢偡傞偑丄亀彈彂娝弶妛彺亁偵偼曇廤忋偺拲堄偑傛偔峴偒撏偄偰偄傞丅偙傟偼杮彂幏昅帪偵弌斉偺梊掕偑偁偭偨偐丄偦傟傪堄恾偟偰偄偨偙偲傪帵嵈偡傞傕偺偱偁傞丅側偍捗撧偺嶌昳偵偼彉暥丒骐暥丒姧婰偺偄偢傟偐偵彁柤偑偁傞偺偑忢偩偑丄椺奜揑偵亀彈暥復娪亁偵偼彁柤偑側偄丅偦傟偼傕偲傕偲弌斉傪栚揑偲偟偨傕偺偱側偐偭偨偨傔偲峫偊傜傟傞丅
丂側偍彂柤偵偮偄偰尵媦偡傞偲丄亀彈彂娝弶妛彺亁偼尵偆傑偱傕側偔亀彂娝弶妛彺亁偵場傫偱捗撧偑晅偗偨傕偺偱偁偭偨丅亀彂娝弶妛彺亁偼丄娍暥偺徚懅暥乮広喁乯偲榓條偺徚懅暥偺擇庬椶偺暥復傪暲傋側偑傜曇傫偩撈摿偺梡暥復偱丄姲暥嬨擭乮堦榋榋嬨乯偵嫗搒丒扟壀幍嵍塹栧偵傛偭偰忋埐偝傟丄戝栰栘巗暫塹斅丄堜摏壆揱暫塹斅丄撝夑壆嬨暫塹斅側偳偺屻報杮傪娷傔姲暥嬨擭斅偩偗偱傕巐庬埲忋偁傝丄偦偺屻丄墑曮幍擭斅丒揤榓巐擭斅丒嫕曐堦屲擭斅側偳悢庬偺斅庬偑惗傑傟丄庡偵姲暥乣嫕曐崰偵棳晍偟偨墲棃暔偱偁傞丅廬偭偰丄捗撧偺帪戙偵偼嫵梴偁傞抝惈彅巵偵峀偔岲傑傟丄惙傫偵梡偄傜傟偨梡暥復偺堦偮偱偁偭偨丅
丂捗撧偑偙偺亀彂娝弶妛彺亁偐傜亀彈彂娝弶妛彺亁偺彂柤傪晅偗偨攚宨偵偼丄亀彂娝弶妛彺亁偺恖婥偵偁傗偐傠偆偲偡傞婥帩偪偑偁偭偨偐傕偟傟側偄丅偁傞偄偼丄嬤悽彈昅庤杮偺愭嬱偺堦恖偱偁傞孍揷傗偡昅偺亀彈弶妛暥復亁偑亀弶妛暥復彺乮弶妛暥復暲枩鏭曽乯亁偵場傫偩彂柤偱偁偭偨偙偲偵曧偭偨傕偺偐傕偟傟側偄丅戝捗偺孍揷壠偼孍揷廆曐偺柡丒傗偡傪昅摢偵彮側偔偲傕擇戙丄傑偨偼嶰戙偵傢偨偭偰彈惈偺擻彂傪弌偟偨壠暱偱偁傝丄嫗搒廃曈偱偼傛偔暦偙偊偨柤栧偱偁偭偨丅捗撧偼亀彈暥復搒怐亁偺摢彂偱乽彈拞偺屼強帩杮乿偲偟偰孍揷傗偡昅偺亀彈掚孭亁傪宖偘傞偐傜丄傗偡偼捗撧偵偲偭偰栚昗偲偡傋偒愭払偱偁偭偨偱偁傠偆丅
丂妋偐偵偙偺傛偆側悇應傕壜擻偱偁傞偑丄偙偺彂柤偼傓偟傠斵彈偺帺怣偺尰傟偱偼側偐偭偨偐丅亀彈彂娝弶妛彺亁偼弶怱幰岦偗傪彞偭偰偄傞偵傕娭傢傜偢丄偦偺巤拲偼摨帪戙偺偁傜備傞彈巕梡墲棃偵戩墇偟偰偄傞偽偐傝偐丄抝巕堦斒偺墲棃暔偵傕堷偗傪偲傜側偄傎偳徻嵶側傕偺偱偁傝丄斵彈偵偲偭偰偼帺怣嶌偱偁偭偨偲巚傢傟傞丅偦偺揰偵拝栚偡傟偽丄娍暥懱偺暥復傪娷傓僀儞僥儕岦偗偺亀彂娝弶妛彺亁偐傜偁偊偰彂柤傪嵦偭偨揰偵偙偦丄斵彈偺屄惈傗帺屓庡挘偲偄偭偨傕偺偑塎偊傞偺偱偼側偄偐丅
丂偝偰丄亀彈彂娝弶妛彺亁偺椺暥偼慡偰寧師弴偵攝楍偝傟偰偍傝丄忋姫偵偼堦寧偐傜屲寧傑偱偺椺暥丄偡側傢偪乽惓寧弶偰尛暥擵帠乿埲壓擇堦捠傪丄拞姫偵偼屲寧偐傜堦乑寧傑偱偺椺暥丄偡側傢偪乽屲寧塉偵尛暥擵帠乿埲壓擇堦捠乮戞堦榋忬乽峠梩傪憲傞暥擵帠乿偺曉忬偼摢彂棑偵宖嵹偝傟偰偄傞偨傔丄偙傟傪娷傔傟偽擇擇捠乯丄壓姫偼堦堦寧偐傜堦擇寧傑偱偺椺暥丄偡側傢偪乽愥偺傆傝偨傞帪尛暥擵帠乿埲壓堦屲捠偲晅榐婰帠榋崁傪偦傟偧傟廂榐偡傞乮崌寁屲幍捠乯丅偄偢傟傕巐婫帪岓偺庤巻偑拞怱偱丄梡審傪庡偲偟偨椺暥傗挗忬側偳傕悢捠娷傓丅傑偨丄椺暥偼忋姫偺傎偲傫偳偑嶶傜偟彂偒側偺偵懳偟偰丄拞丒壓姫偺戝敿偼暲傋彂偒偱偁傞丅
丂嬶懱揑側椺暥傪擇捠偽偐傝徯夘偟偰偍偙偆丅慜幰偼忋姫朻摢偺乽惓寧弶偰尛暥擵帠乿丄屻幰偼壓姫枛旜偺乽偲傆傜傂暥尛帠乿偱偁傞丅
偁傜嬍偺弔偺傔偱偨偝壗偐偨傕偍側偠屼帠偵偰丄偄偼傤擖傑偄傜偣岓丅桺偙偲偟傛傝偍傏偟傔偡傑乀偺屼帠偲偨偑偄偵傛傠偙傃傪怽偐偼偟岓傋偔岓丅傔偰偨偔偐偟偔丂仏嶶傜偟彂偒
扤條屼帠丄屼斚丄廔偵偆傞偼偟偒屼婥怓側傆屼廔偺傛偟丄寭偰傛傝偮偹偞傑偵偼傂偒偐偊丄偐傠偐傜偸屼帠偲偼懚岓傊嫟丄崱峏偺傗偆偵懗偟傎傞偽偐傝偵岓丅暘偰偐偨條屼帠傪偟偼偐傝丄屼偄偲偍偟偔懚岓丅嫀側偑傜丄忢側偒偼嶰奅偺側傜傂丄埀暿棧嬯偺偔傞偟傒偼壩戭偺偍偒偰偵偰岓傑乀丄偲偐偔屼廌彎傪偲乁傔傜傟丄堦楡榣惗偺屼捛慞偙偦杮堄偵偰偍偼偟傑偟岓丅仏暲傋彂偒丅彂巭偺乽偐偟偔乿偼側偄丅
丂埲忋偺椺暥偺偆偪慜幰偵偼丄愭弎偟偨乽偁傜偨傑偺弔乿偺愢柧傪巒傔丄乽壗偐偨傕乿乽偄偼傤擖乿乽傛傠偙傃乿偺尵偄懼偊昞尰丄傑偨乽怽偐偼偟乿偺堄媊丄偝傜偵師偺傛偆側乽傔偱偨偔偐偟偔乿偺桼棃側偳偵偮偄偰巤拲偟偰偁傞丅
彈暥偺偍偔偵晄媑側傜偸帠偼偄偮偵偰傕偐偔偺偙偲偟丅愄偼乽偁側偐偟偙乿偲彂偗傞栫丅拞斾傛傝偐傗偆偵彂帠栫丅
愄湙偲塢拵丄恖傪偝偟偰側傗傑偡娫丄埥恖崯拵傪寠傊傪傂擖丄寠傪暵傆偝偓偰嶦備傊偵丄拵偨偊偰側偔側傝偸丅恖傒側墄丄寠尗柍儗湙側傝偸偲塢怱栫丅崯屘偵暥偺傪偔偵乽偁側偐偟偙乿偲彂棷傞偙偲栫丅枖丄壗帠傕側偒帠傪乽偮乀偐側偟乿偲塢傕崯媊栫丅亀壓妛廤亁偵傒備丅丂
丂亀壓妛廤亁偺傛偆側揟嫆偺徯夘偼彈巕梡墲棃偱偼摿堎偱偁傞丅偙偺傎偐偺摢彂傕摨條偵峫徹揑丒妛栤揑側巤拲撪梕偱偁傞丅
丂埲忋偺傎偐丄椺暥丒拲婰偲傕偵摿昅偟側偗傟偽側傜側偄偺偼丄拞姫戞堦忬乽屲寧塉偵尛暥擵帠乿丄戞擇忬乽摨偐傊傝帠乿偺擇捠偱偁傞丅偄偢傟傕屲寧塉偺婫愡偺撉彂傪庡戣偲偡傞椺暥偱丄暥拞偵懡偔偺彈惈嫵梴彂傪宖偘偰偄傞丅偦偺墲忬偼丄
惏傑側偒屲寧塉偵偰屼嵗岓丅崯搆慠偄偐乁屼傢偨傝岓嵠丅唰尦偺帠屼偡傕偠媼傝岓傋偔岓丅偝傗偆偵屼偞岓傊偼丄怽寭岓摼偳傕丄亀尮巵傕偺偑偨傝亁亀嫹堖亁亀埳惃暔岅亁亀塰壴傕偺偐偨傝亁亀枍憃巻亁丄偙偺偆偪偄偯傟偵偰傕屼偐偟偨偺傒擖傑偄傜偣岓丅偐偟偔
偲偄偆傕偺偱丄摢彂偵偼暔岅摍偺嶌幰偦偺懠偵偮偄偰拲婰偡傞丅偦偺曉忬傕摨條偱丄亀搚嵅擔婰亁亀柍柤彺亁亀愶廤彺亁亀懢巕揱亁亀偆偮傏暔岅亁亀抾庢暔岅亁亀廧媑暔岅亁側偳傪暥拞偵楍嫇偟丄摢彂偱偦傟傜偺彂偵偮偄偰娙扨偵夝愢偡傞丅
丂偙偺椺暥偱憐婲偝傟傞偺偑丄屆揟偺抦幆傪枮嵹偟偨堎怓偺彈梡暥復亀彈暥復搒怐亁偱偁傞丅徻偟偔偼屻弎偡傞偑丄亀彈暥復搒怐亁偼亀彈彂娝弶妛彺亁偺偙偺擇捠偺庯岦傪慡曇偵奼挘偟偨傕偺偲峫偊傜傟傞丅
丂側偍丄亀彈彂娝弶妛彺亁偑屻悽偵梌偊偨塭嬁偼廳戝偱丄偙偺揰偱傕彈巕梡墲棃拞悘堦偺懚嵼偱偁傞丅杮暥偲晅榐婰帠偺戝敿傪娵幨偟偟偨傕偺偐傜丄杮暥偩偗傪柾曧偟偨傕偺傑偱傪娷傔師偺巐庬偺夵戣杮偑偁傞丅
丂乮侾乯尦榎堦堦擭乮堦榋嬨敧乯姧亀彈梡暥復戝惉乮彈梡暥復峧栚乯亁乮戝嶃丒攼尨壆惔塃塹栧斅乯仏杮暥偼壓姫枛偺挗忬偺堦捠傪嶍彍偟偨傎偐偼亀彈彂娝弶妛彺亁偵慡偔摨偠丅摢彂偲慜晅偼慡偰夵傔傞偑丄壓姫枛偺婰帠偼亀彈彂娝弶妛彺亁偐傜偺彺榐丅捗撧偺帺彉傪徣偒丄嶌幰柤傪枙徚偟偨奀懐斉丅
丂乮俀乯尦榎堦擇擭乮堦榋嬨嬨乯姧亀摉棳彈昅戝慡乮憹塿彈嫵暥復乯亁乮嫗搒丒榓愹壆栁暫塹斅丅屻報杮偵戝嶃丒攼尨壆惔塃塹栧斅偁傝乯仏杮暥偼壓姫枛偺挗忬偺堦捠傪彍偔慡椺暥傪娵庢傝偟丄摢彂傪慡偰乽彈嬀旈揱彂乿偵夵傔偨夵戣杮丅壓姫枛偺婰帠偼亀彈彂娝弶妛彺亁偐傜偺彺榐丅捗撧偺帺彉傪嶍彍偟丄捗撧尨嶌傪塀暳偟偨丅
丂乮俁乯嫕曐榋擭乮堦幍擇堦乯姧亀彈暥屔崅帾奊亁乮戝嶃丒攼尨壆惔塃塹栧斅乯仏亀摉棳彈昅戝慡乮憹塿彈嫵暥復乯亁偺慜晅婰帠偺傒傪嵎偟懼偊偨夵戣杮丅
丂乮係乯尦暥嶰擭乮堦幍嶰敧乯姧亀彈暥椦曮戃亁乮嫗搒丒慘壆彲暫塹斅乯仏亀彈彂娝弶妛彺亁偺媽斉壓偺堦晹傪夵崗偟偰丄晅榐婰帠傪夵傔偨夵戣杮丅捗撧尨嶌傪婰嵹偡傞丅摢彂偺堦晹傪嶍彍偟丄戙傢傝偵惣愳桽怣偺憓奊堦屲揰傪偼傔崬傓偲偲傕偵丄奺寧朻摢偺堦擇寧堎柤偺婰帠傕慡偰妱垽偟偨丅偦偺寢壥丄暥帤偺攝抲偺傾儞僶儔儞僗側挌偑惗偠偨傝丄拲庍偺娵晅偒悢帤偑旘傫偩傝偟偰偄傞丅偝傜偵丄椺暥拞堦捠乮傕偲壓姫戞堦嶰忬乽偄偼偨懷塢乆乿偺堦忬乯偑枛旜傊堏摦偟偨傎偐丄壓姫姫枛婰帠偺慡偰偑嶍彍偝傟偨丅
丂偙偺傛偆偵丄栺敿悽婭偵巐杮偺夵戣杮偑搊応偟偨帠幚偩偗偱傕丄亀彈彂娝弶妛彺亁偺暲乆側傜偸塭嬁偑憐憸偱偒傛偆丅側偍壓姫枛偺彈惈彂嶥楃傕忋婰奺杮傊傎傏偦偺傑傑柾曧偝傟偨偑丄偦偺徻嵶偼暿崁偵忳傞丅
亂彈暥復搒怐亃
丂杮彂偼捗撧偺堚峞傪弌斉偟偨傕偺偱丄墑嫕巐擭乮堦幍巐幍乯堦堦寧偵戝嶃彂沔丒埨堜栱暫塹偵傛偭偰斅峴偝傟偨丅偦偺姧婰偵偼
昅嶌丂丂嫃弶巵捗撧
曗捲丂丂揷拞桭悈巕
夋岺丂丂帥堜廳怣恾
偲偁傞丅杮暥偵娭偡傞拲婰偑摢彂偵惙傝崬傑傟偰偄傞偑丄昅愓偐傜杮暥偲摢彂偼捗撧偺帺昅偱丄慜晅婰帠偑桭悈巕偍傛傃廳怣偵傛傞傕偺偱偁傞丅姧峴擭戙偐傜偄偭偰捗撧杤屻偺弌斉偱偁傞偙偲偼柧傜偐偩偑丄捗撧偺挊嶌偵偼晅偒暔偱偁偭偨帺彁傕尒偊偢彉暥傕側偄側偳丄惗慜拞偺弌斉暔偲偼懱嵸偑堎側傞丅
丂偦傟偱偼愶嶌擭戙偼偲偄偆偲丄摢彂拞偵亀彈崱愳亁擇嶜杮偺昞婰偑偁傞偺偱掑嫕巐擭埲崀偱偁傞偙偲偼媈偄側偄偑丄尦榎堦嶰擭姧偺亀彈崱愳亁偺堎杮乮戲揷媑嶌乯偵偮偄偰偼慡偔怗傟偰偄側偄偺偱丄杮彂偼尦榎堦擇擭埲慜偺壜擻惈傕崅偄丅傑偨丄亀彈彂娝弶妛彺亁彉暥偐傜憐憸偝傟傞捗撧偺挊嶌偺幏昅弴彉傗弌斉偺宱堒偐傜丄亀彈彂娝弶妛彺亁埲屻丄偡側傢偪尦榎嶰擭埲屻偺傕偺偲峫偊偨偄丅愭弎偺傛偆偵杮彂偼丄亀彈彂娝弶妛彺亁拞偺乽屲寧塉乿偺椺暥偺庯岦傪慡曇偵奼挘偟偨傕偺偲偄偊傞偐傜偱偁傞丅埲忋偺悇榑偐傜丄亀彈暥復搒怐亁偺愶嶌擭戙傪尦榎嶰乣堦擇擭偺堦乑擭娫偲壖掕偟偰偍偔丅
丂偄偢傟偵偟傠丄杮彂偼徚懅暥傗摢彂偵屆揟偺抦幆傪悢懡偔惙傝崬傫偩堎怓偺彈梡暥復偱偁傞丅庤巻偺椺暥廤偲偄偆傛傝傕丄亀埳惃亁亀尮巵亁亀枍憪巕亁亀枩梩廤亁亀昐恖堦庱亁側偳偺屆揟偺嫵壢彂偲尵偭偨曽偑揑妋偱偁傞丅堦椺傪宖偘偰偍偔丅戞擇忬偺怴擭忬曉忬乮幍挌僆乯偱偁傞丅
弔偺偼偠傔偺傔偰偨偝偺昳乆丄嬄偺捠偵怽偍偝傔傑偄傜偣岓丅亀埳惃暔岅亁戣崋偺帠偼丄嵼拞彨偺帺嶌嫟丄埳偣傊偐傝偺巊偵峴媼偟屘側偲丄偲傝怽岓傊嫟丄嫗嬌墿栧偺偙乀傠偼埳惃偲怽彈偺昅嶌偵掕傜傞乀桼丄暦撻傑偄傜偣岓丅嬈暯偺屼帠傪偮乀傒偰丄偦傟偲偼側偟偵彂偨傞傛偟丄傑偙偲偵桪側傞帉偯偐傂丄崱偺悽偵偼椶偁傜偟偲妎偊岓丅庩偵廫嶰偺偲偟丄偄偲偗側傆偟偰偲屼嵗偝傆傜傊偼丄愄恖偲怽側偐傜丄偨傔偟傑傟側傞屼帠嫟偵岓丅桺丄屼偗傫偵偰丅傔偰偨偔偐偟偔
丂偙偺傛偆偵斾妑揑挿暥偱丄屆揟拞怱偺暥柺偱偁傞丅偦偺摢彂偵偼丄亀埳惃暔岅亁偺戣崋丄嶌幰峫乮彅愢偍傛傃棯揱乯丄摨暔岅拞偵搊応偡傞彈惈柤傗峜掗柤側偳丄娭楢婰帠傪惙傝戲嶳偵廂榐偟偰偁傞丅懠偺椺暥傕慡偰屆揟偺嫵梴傪庡娽偵偟偨傕偺偱丄偦偺奣梫偼師偺傛偆側傕偺偱偁傞乮側偍丄慡擇乑捠偺偆偪嶰捠偑暲傋彂偒丄巆傝偼慡偰嶶傜偟彂偒偱偁傞丅傑偨椺暥偺尒弌偟傗栚師偼側偄乯丅
乮堦乯彈偺帩偮傋偒杮偲偟偰亀埳惃暔岅亁傪憽傞怴擭忬
乮擇乯亀埳惃暔岅亁戣崋偺桼棃傪弎傋偨怴擭忬偺楃忬
乮嶰乯巼幃晹傪幟傇愇嶳寃偺姶憐傗亀尮巵暔岅亁偵偮偄偰偺暥
乮巐乯嶲寃惉廇偺廽媀偲偲傕偵亀尮巵暔岅亁幏昅傑偱偺宱堒傪弎傋偨暥
乮屲乯怺傑傝備偔廐偵亀嫹堖暔岅亁傪撉傫偩姶憐偲丄朘栤傪惪偆暥
乮榋乯嶐斢偺朘栤偺屼楃偲亀枍憪巕亁傪徯夘偡傞暥
乮幍乯崶楃廽媀偵亀塰壴暔岅亁傪憽傞暥
乮敧乯崶楃廽媀偺偍楃偲偲傕偵亀塰壴暔岅亁偺奣梫偵偮偄偰弎傋偨暥
乮嬨乯榓壧弶妛幰傊亀枩梩廤亁偺嶌幰側偳偵偮偄偰弎傋偨暥
乮堦乑乯偦偺曉忬偲偟偰亀枩梩廤亁偺奣梫偵傆傟偨暥
乮堦堦乯弶傔偰夛偭偨恖傊偺垾嶢偲偲傕偵亀昐恖堦庱亁偺嶌幰偵偮偄偰弎傋偨暥
乮堦擇乯偦偺曉帠偵亀搆慠憪亁偵偮偄偰崸択偟偨偄偲朘栤傪惪偆暥
乮堦嶰乯寢擺廽媀偲偲傕偵崶楃摴嬶偺壧彂丒憪巕椶嬦枴偺埶棅傪彸抦偡傞暥乮亀屆崱廤亁傗亀戝榓暔岅亁側偳偺懡偔偺彂柤傪楍婰乯
乮堦巐乯偦偺曉忬偱揔愗側慖掕傪婅偆偲偺暥
乮堦屲乯捒媞偺拠夘偵懳偡傞楃偲亀懢暯婰亁傪徯夘偡傞暥
乮堦榋乯偦偺曉帠偵亀曐尦暔岅亁亀暯帯暔岅亁偵偮偄偰弎傋偨暥
乮堦幍乯擔懸偪乮慜栭偐傜寜嵵偟偰怮偢偵擔偺弌傪懸偭偰攓傓峴帠偱廔栭庰墐傪嵜偡乯偺嵺偺楃偲亀暯壠暔岅亁偵偮偄偰弎傋偨暥
乮堦敧乯偦偺曉帠偵朘栤偺楃偲偲傕偵亀尮暯惙悐婰亁傪慐傔傞暥
乮堦嬨乯彈晳尒暔偺曬崘偲亀媊宱婰亁偵偮偄偰偺暥
乮擇乑乯偦偺曉帠偵亀慮変暔岅亁偵偮偄偰弎傋偨暥
丂埲忋偺傛偆偵丄擔忢傗傝偲傝偡傞庤巻偺懱嵸傪曐偪偮偮丄慡偰偺椺暥偵屆揟偺抦幆傪嵦傝擖傟偰偁傞偺偑摿挜偱偁傞丅拞偱傕堎怓側偺偑亀懢暯婰亁埲壓偺孯彂傪埖偭偰偄傞揰偱丄偙偺傛偆側婰帠傪敽偭偨彈巕梡墲棃偼懠偵椺偑側偄丅
丂偝傜偵摢彂偵偼丄屼壘憪巕丒暔岅乮壧暔岅丒楌巎暔岅丒孯婰暔岅丒愢榖暔岅丒嶌傝暔岅摍乯丒悘昅丒壧廤丒椶戣榓壧廤丒壧妛彂丒巎彂丒彈孭彂側偳丄幚偵敧乑偵媦傇彂柤偑搊応偡傞偺偱偁傞丅捗撧偺嫵梴偺堦抂傪抦傞偲偲傕偵丄捗撧偑彈惈偺嫵梴彂傪偐側傝峀斖埻偵峫偊丄撈帺偺尒夝傪帩偭偰偄偨偙偲傪帵嵈偡傞丅偦偺偆偪捗撧偑憡墳偺愢柧傪晅偗偨傕偺偼摿偵廳梫側彈惈嫵梴彂傪堄枴偟偰偄偨偲巚傢傟傞偑丄婰帠偺偄偔偮偐傪尒偰傒傛偆丅
仦暥偟傗偆偺偝偆偟乮暥惓憪巕乯
乽惀偼偝偟偨傞徹傕側偒嶌暔岅栫丅偁傑偨偺偝偆偟偺拞偵偲傝暘傔偱偨偒帠傪偐偒偨傞偝偆偟側傞備傊丄彈拞偺暥偼偠傔偵偼惀傪傛傓偲惉傋偟丅乿
仦埳惃暔岅
乽嬈暯堦戙偺帠丄偆傤偐偆傆傝乮弶姤乯傛傝偼偟傔偰廔鄟枠偺帠傪偁傜偼偣傞暔岅側傝丅乿
乽彈偺傕偮傋偒偝偆偟
丂偁側偑偪偵彈偵尷傝岲怓偺摴傪偟傜偟傓傋偒偵偁傜偡丅彈偼怱傗偼傜偐偵丄偡側傪側傞傪傕偮偰杮偲偡丅偐傞偑備傊偵丄戞堦偵壧摴傪傪偟備傞栫丅壧摴傪偡偗傞恖偼偁傜乀偐偵丄傛偙偟傑側傞帠傪偐傝偵傕巚偼偸暔栫丅屘偵崯暔岅偼梋杮偵彑偰壧摴嵟堦偲掕偨傞栫丅亀塺壧偺戝奣亁偵傕亀屆崱亁亀埳惃暔岅亁亀屻愶亁亀廍堚亁傪妛傆傊偒傛偟偁傝丅偟偐傟偽丄傗偡傜偐偵偡側傪側傜傫偨傔丄亀屆崱亁亀屻愶亁亀廍堚亁傪偼傑偯偝偟抲偰崯暔岅傪彈偵傪偟備傞傕偺栫丅偝傟偽丄擇忦壠嶰戙廤偺揱庼偵傕丄愭崯亀埳惃暔岅亁傪巒偵傛傓帠偲偁傝丅乿
仦尮巵暔岅
乽巼幃晹丄愇嶳帥偵饽偰丄嶌傞傊偒憪巻巚埬偣偟偵丄敧寧廫屲栭偺寧偙偲偵柧傜偐側傝偟偵丄嵍偺偮傑屗偺偐偆傜傫偵傛傝傤偰孹偔寧傪偍偟傒偟偵丄尮巵偺孨恵杹傊偝偡傜傊媼傆屼偝傑偺傑偺偁偨傝怱偵偆偐傂偟偐偼丄傆偲暔岅偵怱偮偒偰懃昅傪偲傝偰恵杹柧愇偺姫傛傝彂偼偟傔偗傞偲側傫丅乮埲壓棯乯乿
仦偝堖偺偝偆偟乮嫹堖暔岅乯
乽巐姫偁傝丅嬤斾傛傝嫹堖壓昍偲偰廫榋嶜偵偣偟栫丅偝堖偺孨堦惗偺帠傪婰偣偟嶌傝暔岅栫丅乿
仦惔彮擺尵枍憪巻乮枍憪巕乯
乽幍嶜偁傝丅懃丄惔彮擺尵偑偮偔傝偟備傊丄嶌幰偺柤嫟偵偐偔塢丅亀枍偞偆偟亁偲偼丄強乆偵枍尵梩傪彂偰彅帠傪偐偒偮偗偨傟偼偄傆焍丅乮埲壓棯乯乿
仦塰壴暔岅
乽崯暔岅偼丄恖偺傔偱偨偔偝偐傊丄偼傫偠傗偆傪偐偒偰偼偍偲傠傊傪偟傞偟丄惗傟媼傆帠傪偐偒偰偼枖懘偐偔傟媼傆傪偟傞偟偮傞擔婰偺偁傜傑偟栫丅備傊偵偟偆偓側偳偵偼屆崱偝偟偰傕偪傤偸傪丄偙傟偼撪偺帠偼偲傕偁傟偐偔傕偁傟丄塰壴偲偄傆奜戣偺傔偰偨偒偵偮偒偰偮偐偼偡偲偺帠偍傕偟傠偟丅崯傔偰偨偒戣崋偺偙偲偔峴枛偝偐傊媼傊偲偺媀側傝丅乿
丂埲忋偺傎偐丄師偺彂柤乮宖嵹弴乯偑尒偊傞丅
枩梩廤丒悽宲暔岅乮戝嬀乯丒昐恖堦庱丒怴昐恖堦庱丒晲壠昐恖堦庱丒彈昐恖堦庱丒搆慠憪丒屆崱榋挓乮屆崱榓壧榋挓乯丒怴愶榋挓丒榓壧幍晹彺丒戝榓暔岅丒敧塤屼彺丒懗拞彺丒榋壠廤丒擇敧柧戣丒戝柤傛偣丒彫柤婑丒塅帯廍堚暔岅丒榓壧戣椦嬸彺丒壧愬丒彈壧愬丒摨拞屆壧愬丒怴壧愬丒拞屆壧愬丒庍嫵壧愬丒晲椦壧愬丒懢暯婰丒曐尦暔岅丒暯帯暔岅丒暯壠暔岅丒尮暯惙悐婰丒搶娪乮屷嵢嬀乯丒媊宱婰丒慮変暔岅
丂偝傜偵乽彈拞偺屼強帩杮乿偲偟偰捗撧偑宖偘偨彈孭彂丒彈巕梡墲棃偼師偺敧揰偱偁傞丅
彈巐彂丒彈孭彺丒偐乁傒憪丒彈偐乁傒丒彈掚孭丒彈崱愳丒楍彈揱丒彈彅楃
丂埲忋丄捗撧偺彈梡暥復嶰庬傪娙扨偵尒偰偒偨偑丄偦傟偧傟嶰庬嶰條偱偁傞偲摨帪偵丄偳傟堦偮傪偲偭偰傕丄懠偵椺偺側偄彈梡暥復偱偁傞偙偲偑暘偐傞丅
丂傑偢亀彈暥復娪亁偼丄彈惈傜偟偄丄惓偟偄尵梩尛偄傪揙掙偟偰儅僗僞乕偡傞偨傔偺僥僉僗僩偱偁偭偨丅偦偺乽惓岆暥椺懳徠朄乿偲傕屇傇傋偒曽朄偼慡偔怴偟偄傕偺偱偁偭偨偑丄杮彂偼偁偔傑偱傕弶曕嫵嵽偱偁偭偰丄擔忢偺庤巻偺埬暥偲偟偰廫暘偵棙梡偱偒傞傕偺偱偼側偐偭偨丅栚師傕側偗傟偽尒弌偟傕側偔丄戞堦丄椺暥偺庬椶偑彮側偡偓傞偐傜偱偁傞丅
丂偟偐偟丄乽彈惈傜偟偄尵梩尛偄乿偵幏拝偟偨捗撧偺彂嶥楃偼丄偦傟傑偱偺彂嶥楃偲偼庯傪堎偵偡傞傕偺偩偭偨丅媡偵捗撧埲崀偺彈惈彂嶥楃偵偍偄偰偼丄庤巻偵偍偗傞彈惈傜偟偝偑嫮挷偝傟傞傛偆偵側偭偨姶偑偁傞丅嬤悽偺彈惈彂嶥楃偼丄帪戙偲偲傕偵嶌朄偑峀斖偐偮嵶晹偵峴偒搉傞偲摨帪偵尵梩尛偄偵娭偡傞婰弎偑懡偔側偭偰偄傞偑丄偦偺嵟弶偺傕偺偑亀彈暥復娪亁偱偁偭偨丅
丂偝傜偵擇擭屻偺亀彈彂娝弶妛彺亁偼丄椺暥偺撪梕傕偢偭偲朙晉偵側傝丄彂巭岅乽偐偟偔乿傗嶶傜偟彂偒丒暲傋彂偒傪揔媂巊偄暘偗傞側偳幚梡彂娙偺椺暥廤偲偟偰廫暘側撪梕傪旛偊偨偩偗偱偼側偔丄峕屗帪戙偺彈巕梡墲棃拞嵟傕徻嵶側拲傪梡堄偟偰偁偭偨丅摢彂偺懼偊尵梩偱椺暥偺暥尵傪悘帪曄偊傜傟丄堦憌僶儔僄僥傿偵晉傫偩昞尰偑婜懸偱偒偨丅傑偨丄壓姫枛偺梡岅廤傗彂娙嶌朄廤側偳偲暲峴偟偰巊梡偡傞偆偪偵丄岅渂偦偺傕偺傗娭楢抦幆偺棟夝傕恑傒丄揑妋側庤巻暥傪廗摼偟摼偨偱偁傠偆丅庬乆偺夵戣杮偺塭嬁椡傕娷傔傟偽丄亀彈彂娝弶妛彺亁傎偳懡偔偺彈惈偵撉傑傟偨彈梡暥復偼側偄偲偄偭偰傕夁尵偱偼側偄丅
丂偙偺亀彈彂娝弶妛彺亁偑懡偔偺椶彂傪惗傫偩偺偼壗屘偐丅
丂偄偔偮偐棟桼偑峫偊傜傟傞偑丄堦偮偼幚嵺偵庤巻傪彂偄偰偄偰栶棫偮忣曬偑懡偐偭偨偲偄偆幚梡惈偱偁傠偆丅尵偆傑偱傕側偔姫枛傗摢彂偺晅榐婰帠偱偁傞丅偟偐傕拲斣崋傪晅婰偟偰栤戣偺売強偑懄嵗偵暘偐傞傛偆偵側偭偰偄偨丅
丂傕偆堦偮偼彈惈帺恎偺挊嶌偱偁偭偨偙偲丅杮彂偺彂娙嶌朄偼乽暥偺朄幃偝傑偁傞帠側偑傜丄彈惈偼偝偺傒偙傑偐側傞朄傪偨乁偟媼偼偢偲傕墇搙偵偼側傞傑偠乿偲偄偆曽恓偵娧偐傟丄昁梫嵟彫尷偺抦幆偵峣傜傟偰偄偨丅偦偺斀柺丄彈惈傜偟偄尵梩尛偄偵偼嵟戝尷偺拲堄偑暐傢傟偰偄偨丅抝惈懁偐傜偺彈惈彂嶥楃偼懡偔乽抝惈乿嶌朄偺娙棯斉偺偛偲偒傕偺偱丄乽彈惈乿傜偟偝傊偺拝栚偼朢偟偔側傝偑偪偱偁偭偨丅拞悽埲棃偺彂嶥楃偺揱摑偑偦傟傪暔岅偭偰偄傞偟丄捗撧偺尵偆乽偙傑偐側傞朄乿偺曽岦偵堦憌恑傫偱峴偭偨峕屗拞婜埲崀偺彈惈彂嶥楃偼傎偲傫偳抝惈偵傛傞傕偺偱偁偭偨丅
丂偝傜偵戞嶰偵丄惈嵎傪廳帇偟恎暘嵎傪嫮挷偟側偐偭偨偙偲丅捗撧偼丄摿掕奒媺偺彈惈偲偄偆傛傝傕偁傜備傞彈惈傪堄幆偟偰彂偄偰偄傞丅偮傑傝亀彈彂娝弶妛彺亁偼慡偰偺彈惈偺偨傔偺彈暥偺婎杮偱偁傝丄斈梡惈偵晉傫偩彈梡暥復偱偁偭偨乮偙傟埲屻丄彈梡暥復偺堦斒孹岦偲側傞偑乯丅廬棃偺彂娙嶌朄偺娭怱帠偼傕偭傁傜懜斱丒忋拞壓暿偺嶌朄偱偁偭偨丅峕屗慜婜傪戙昞偡傞戙昞揑彈惈彂嶥楃傪娷傓亀傪傓側偐乀尒亁傗亀彈幃栚亁偱偼丄忋攜丒摨攜丒壓攜偺偦傟偧傟偵忋壓偺嵎傪晅偗偨榋抜奒傑偨偼屲抜奒偺椺暥傪嬶懱揑偵宖偘偰丄彂娙梡岅傗尵梩尛偄偺堘偄丄嵎弌恖柤丒埗柤丒榚晅摍偺岅嬪偺崅偝丄傑偨丄乽屼乿偺帤偺偔偢偟壛尭傑偱傪峫椂偟偨婰弎偑尒傜傟偨丅偙傟傜偵斾傋傞偲丄捗撧偼懜斱偺嵎傪偙偲偝傜嫮挷偡傞偙偲偼側偐偭偨丅偁傞偄偼弶怱幰梡偲偟偰偁偊偰庢傝忋偘側偐偭偨偺偐傕偟傟側偄丅彮側偔偲傕妋偐側偙偲偼丄捗撧偑懜斱偺暿傛傝傕抝彈偺暿偵嵟戝偺拲堄傪暐偭偰偄偨偲偄偆偙偲偱偁傞丅
丂懠曽丄徚懅暥拞偵屆揟抦幆傪惙傝崬傓偲偄偆亀彈暥復搒怐亁偺庯岦偼丄婛偵亀彈彂娝弶妛彺亁拞偵偦偺朑夎偑尒傜傟偨丅徚懅暥拞偵彅抦幆傪娷傑偣偰丄偦偺椉幰傪摨帪偵妛廗偝偣傞偲偄偆僗僞僀儖偼丄傑偝偵墲棃暔偺忢搮庤抜偱偁偭偨丅亀掚孭墲棃亁傪巒傔懡偔偺墲棃暔偑徚懅暥拞偵奺庬偺扨岅廤抍傪嫴傓偲偄偆宍偱丄彅抦幆偺暲峴妛廗傪払惉偱偒傞傛偆偵栚榑傑傟偨丅傗偑偰扨岅偽偐傝偱側偔丄偦傟偵娭楢偡傞彅抦幆傗嫵孭側偳傕娷傓傛偆偵側偭偨丅
丂椺偊偽姲暥嬨擭姧亀峕屗墲棃亁偼丄怴擭忬晽偺乽梲弔擵宑夑捒廳乆乆乿偲偄偆彂偒弌偟偱巒傑傝丄峕屗偺抧棟傗抧帍側偳彅抦幆傪楍婰偟偨屻偱乽柶揱懡媣寠尗乿偲彂偒棷傔傞傛偆偵慡曇偑堦捠偺庤巻暥僗僞僀儖偱彂偐傟偰偄傞丅
丂傑偨丄乽徚懅墲棃乿宆偺愭嬱偲峫偊傜傟傞掑嫕崰姧亀昐岓墲棃亁偼慡擇榋捠偺彂忬傪廂榐偡傞偑丄偄偢傟傕
堦昅抳擇椷孾忋丄孾払丄孾擖堦岓丅怴弔丄擭曖丄夵楋丄擭巒擵屼宑夑丄屼媑宑丄屼壝椺丄屼壚帠丄廳忯丄栚弌搙丄捒廳丄晄儗壜儗桳擇恠婜丄嵺尷丄媥婜堦岓丅乧
偺傛偆偵丄徚懅偵懡梡偡傞椶岅傪師乆楍嫇偟丄彂巭偵乽嫲乆嬣尵乿傑偨偼乽嬣尵乿傪抲偔傕偺偱偁偭偨丅
丂偮傑傝丄椉幰偺椺偐傜柧傜偐側傛偆偵丄朻摢岅乮抂嶌乯偲彂巭岅偺傒偼堦墳彂娙宍幃偵偟偰偁傞偑丄暥柺偺傎偲傫偳偑岅渂傗抦幆丄嫵孭偺梾楍偱偁偭偰丄徚懅暥偦偺傕偺偱偼側偄丅偙偺傛偆側暥懱偼墲棃暔摿桳偺傕偺偱乽墲棃暥乿偲傕屇傇傋偒傕偺偱偁傞丅廬偭偰偙偺乽墲棃暥乿僗僞僀儖偼捗撧偺撈憂偱偼偁傝偊側偄偑丄乽墲棃暥乿傪梡偄偰屆揟偺抦幆傪庬乆徯夘偟偨揰偑儐僯乕僋偱偁偭偨丅
丂偙偺傛偆偵尒偰偔傞偲丄埲忋偺捗撧偺彈梡暥復偼偦傟偧傟丄懠偺彈梡暥復偵偼尒傜傟側偄尠挊側撈帺惈偲塭嬁椡傪帩偮傕偺偱偁偭偨偙偲偑抦傟傛偆丅
仜嬤悽弶摢偺彈惈彂嶥楃
丂偝偰杮峞偺偟傔偔偔傝偵丄捗撧偺愢偄偨彈惈彂嶥楃偵偮偄偰怗傟偰偍偐側偔偰偼側傜側偄丅
丂彈惈偺庤巻偵偮偄偰偺宍幃傗嶌朄偼帪戙偵傛偭偰懡條側曄壔傪悑偘偰偄傞偑丄堦斒偵彈惈偺偨傔偺乽彂嶥楃乿偼幒挰拞婜埲慜偵偼懚嵼偣偢丄堦擇悽婭埲崀偵惉棫偡傞奺庬彂嶥楃偼椺奜側偔岞壠傑偨偼晲壠偺抝惈彂嶥楃偱偁偭偨丅
丂廬偭偰拞悽傑偱偼丄抝惈彂嶥楃拞偵乽抝惈偐傜彈惈埗乿偺庤巻偺嶌朄偑帵偝傟傞掱搙偱偁傝丄偙傟偼彈惈杮棃偺彂嶥楃偱偼側偐偭偨丅偟偐偟丄傗偑偰懱宯揑側彈惈彂嶥楃傕搊応偟偨丅偦傟偑亀彈朳恑戅亁偁傞偄偼亀彈朳昅朄亁偱偁傝丄偄偢傟傕幒挰枛婜偐傜峕屗弶婜偺愶嶌偲尒傜傟傞乮亀懕孮彂椶廬亁姫戞幍乑堦強廂乯丅偙偺帪婜偼丄彫妢尨棳側偳晲壠楃朄偵偍偄偰傛偆傗偔彈惈楃朄偑惍旛偝傟巒傔偨崰偱偁傞丅亀彈朳恑戅亁傗亀彈朳昅朄亁偵偼彂嶥楃埲奜偺楃朄傕娷傓偑丄偲傕偵彈惈彂嶥楃偑廳梫側埵抲傪愯傔傞偙偲偵曄傢傝偼側偄丅
丂偙偙偱偼亀彈朳恑戅亁傪徯夘偟偰偍偔丅偦偺戝敿偼乽彈朳廜偺偟偮偗偺帠乿偐傜側傝丄怘楃傗媼巇嶌朄丄巐婫堖憰丄傑偨彂娙嶌朄偵偮偄偰婰偟丄偦偺枛旜偵乽傒偮偟偨側偺偐偝傝暔擵帠乿乽偔傠偨側偺偐偝傝暔擵帠乿偺擇崁傪壛偊傞丅偦偺拞偐傜彂嶥楃偺庡梫晹暘傪彺弌偡傞偲師偺傛偆偵側傞丅
丂乮侾乯宧偆傋偒彈惈偵偼乽乧怽偝偣偨傑傊乿偲彂偔偑丄偦傟埲忋偺宧偄偵偼乽斺業彂偒乿偲偄偭偰丄懁嬤偔巇偊傞彈惈偺柤慜傪彂偄偰乽乧恖乆屼拞乿側偳偲彂偔丅乽屼曉帠乿偼憡庤傪壓偘偨昞尰偱偁傞丅傑偨丄乽傑偄傜偣岓乿偲彂偄偰憡庤偺柤傪彂偐側偐偭偨傝丄帺暘偺柤傪彂偄偰乽仜仜傛傝乿偲彂偔偺偼丄憡庤偑帺暘傛傝壓埵偺応崌偱偁傞丅
丂乮俀乯庤巻偺忋姫偼擇枃曪傒偑忋埵偱堦枃偼壓埵偱偁傞丅傂偹傝栚偵杗傪晅偗偰挿乆偲堦嬝堷偔偙偲傕偁傞丅墦曽傊偺庤巻偵偼寧擔傪忋彂偒偡傞丅棫暥偺忋壓偼摨偠掱偵偡傞丅
丂乮俁乯宧偆憡庤偵偼丄乽屼彈偼偆廜丄側傪偨傟揳乿偲彂偒丄暥枛傕乽屼怱傊岓偰怽偝偣偨傑傊乿偲偐乽屼怱傊岓偰壜旐怽擖岓乿乽屼怱摼岓偰壜旐怽擖岓乿偲彂偔丅
丂乮係乯抝惈傛傝彈惈傊偺庤巻偵偼丄偄偐偵傕偦偭偗側偄抝尵梩偱彂偔丅抝暥傪壖柤偵夵傔偰彂偔偺偱偁偭偰丄抝暥偺拞偵壖柤傪崿偤偰偼偄偗側偄丅
丂乮俆乯寽憐暥乮楒暥乯偼捠忢偺尵梩偑椙偄丅傑偨恖偵傛傝屆壧側偳傪嵦傝擖傟丄嬄乆偟偔側傜側偄傛偆偵彂偔丅榓壧偼嶶傜偟彂偒偵偟偨傝丄暥復拞偵偲偗崬傑偣偰偳傟偑榓壧偱偁傞偐暘偐傜側偄傛偆偵彂偄偨傝偡傞丅
丂乮俇乯抝彈偲傕椏巻傪巐婫偵傛偭偰巊偄暘偗傞丅婱恖偵偼忋幙偺椏巻丄摨攜丒壓攜傊偼帺暘偲摨奿偺椏巻偵偡傞丅
丂乮俈乯忋彂偒偼崅婱側憡庤傎偳忋偘偰彂偔丅埲壓丄摨攜丒壓攜偲壓偘偰彂偔丅傑偨丄暥柺偺杗怓偼忋傎偳敄杗偱丄壓傎偳杗崟偵彂偔丅憡庤偑帺暘傛傝忋埵偱偁傟偽丄帺暘偺柤慜偼擹偔彂偒丄憡庤偑壓埵偱偁傟偽帺暘偺柤傪敄偔彂偔丅
丂乮俉乯彈惈偺庤巻偼丄忋曪傒偵怓悈堷傪偡傞丅抝偼敀悈堷偱偁傞丅
丂乮俋乯暥偺抂偺偁偒嬶崌偼栺擇悺敧暘偐嶰悺傎偳偵偟丄庤巻偺墱乮枛旜乯偼嶰峴傎偳棤偵曉偟偰愜傞丅
丂乮侾侽乯崢暥傕宧偆憡庤偵偼忋曽偱晻傪偟丄壓攜偵偼壓偘偰晻傪偡傞丅晻偠栚偺杗傕擇杮偑宧偄偱偁傞丅
丂乮侾侾乯挗忬偵偼曉帠偼晄梫偱偁傞丅傑偨丄晻偠栚偺杗傗抂彂傕嬛暔偱偁傞丅
丂乮侾俀乯崶楃廽媀忬偵偼丄乽傗偑偰乿乽枖岓乿乽側偍乿偲彂偄偰偼側傜側偄丅
丂乮侾俁乯暥柺偺帤摢偺忋偵彂偄偰偼側傜側偄丅忋偑傝偡偓傞偺傕尒嬯偟偄偺偱丄椏巻偺掱椙偔彂偔丅
丂埲忋偺傎偐偵傕丄庤巻偺忋曪傒傗梡巻偺梋敀偺峀偝丄晻偺巇曽丄挗忬傗崶楃忬側偳庬乆偺嶌朄偑婰偝傟偰偄傞丅抝惈偺彂嶥楃偵斾傋傞偲娙扨側傕偺偩偑丄堦捠傝偺彈惈彂嶥楃傪弎傋偨揰丄傑偨彈惈楃朄彂偺愭嬱偺堦偮偲偟偰杮彂偼戝偄偵偦偺堄媊傪擣傔傜傟傞傋偒傕偺偱偁傞丅
丂偙偺傛偆偵丄幒挰帪戙枛婜偁傞偄偼嬤悽弶摢偵媦傫偱弶傔偰撈棫偟偨彈惈彂嶥楃偑曇傑傟傞傛偆偵側偭偨偑丄峕屗慜婜偺姧杮拞丄彈惈偺彂嶥楃偵偮偄偰弎傋偨嵟弶偺暥專偼宑埨嶰擭乮堦榋屲乑乯姧偺亀傪傓側偐乀尒乮彈嬀旈揱彂乯亁偱偁傞丅摨彂拞姫戞堦崁乽傆傒偺彂傗偆忋拞壓偺帠乿偵偼懜斱暿偺嬶懱揑側徚懅椺暥偑帵偝傟丄偦偺堄枴偱傕杮彂偼拞悽偺彂嶥楃偵偼尒傜傟側偄傎偳偺嬶懱惈偲幚梡惈偵晉傫偩彈孭彂偱偁偭偨丅杮崁偺枛旜偱丄彂娙嶌朄偺怱摼偼乽撪偺傪傫側偲傕偺傗偔偨傞備傊丄偦偺恎偟傜偣偨傑偼偢偲偰傕偔傞偟偐傜偸帠側傝乿偲弎傋偰偄傞偙偲偐傜傕丄杮彂偺庡側撉幰懳徾偼忋棳奒媺偺彈惈偱偁傞丅偦偺傛偆側崅婱側彈惈偺偨傔偺彂娙嶌朄偼偍偍傓偹師偺傛偆側傕偺偱偁偭偨丅
丂乮侾乯彈惈偺庤巻偼壖柤彂偒偱側偔偰偼側傜側偄丅傑偨帤壒偱偼側偔帤孭傪梡偄傞傋偒偱偁傞丅
丂乮俀乯庤巻偼憡庤偵傛偭偰彂偒暘偗側偔偰偼側傜側偄丅
丂乮俁乯垽宧偺偁傞暥柺傪怱妡偗傞丅庒偄偆偪偼偁傑傝偵嵶傗偐偱墣傔偐偟夁偓偢丄壐摉側偺偑傛偄丅擭攜側傜嵶傗偐偱垽宧偺偁傞偺偑椙偄丅
丂乮係乯乽曉偡彂偒乮捛怢暥乯乿傪昁偢彂偔傛偆偵偡傞丅摿偵廽媀暥偵偼昁梫偱偁傞丅偨偩偟丄崶楃廽媀偵弶傔偰憲傞庤巻傗挗忬偵偼乽曉偡乿乽廳偹偰乿偲偄偆尵梩偼嬛暔偱偁傞丅
丂乮俆乯梡巻偼堦廳偹偟偰丄忋曪傒傪偟丄偝傜偵悈堷偱寢傃丄鄳搇側偳傪揧偊傞丅嫑側偳傪憽傞暥傗挗忬偵偼鄳搇偼晄梫偱偁傞丅弌壠偵偼鄳搇偱偼側偔崺晍傪揧偊傞丅偦偟偰丄庤巻偼暥敔偵擖傟傞丅恊巕偺傛偆偵恊枾側娭學側傜寢傃暥偱傛偄丅
丂傑偨丄忋攜丒摨攜丒壓攜暿偺暥柺傗嶌朄偺憡堘傪榋捠偺椺暥偱帵偟偰偁傝丄摿偵彂嶥楃偺梫偱偁傞忋強丒彂巭丒榚晅偺堘偄傪柧夣偵偟丄嬶懱揑偐偮娙寜偵梫揰傪弎傋偰偄傞丅偨偩偟丄杮彂偵尒傜傟傞椺暥偼堦偮偺柾斖偵夁偓偢丄幚嵺偺徚懅偵偼憡庤偲偺娭學傗偦偺帪偦偺帪偺忬嫷偵墳偠偰旝柇偵曄偊側偔偰偼側傜側偄偲偟偽偟偽拲堄傪懀偟偰偄傞偺傕丄尰幚揑偱峴偒撏偄偨攝椂偱偁傞丅
丂偝傜偵枩帯嶰擭乮堦榋榋乑乯擇寧姧偺亀彈幃栚丒庲暓暔岅亁嶰姫嶰嶜偺偆偪乽彈幃栚乿壓姫戞擇崁乽暥偐偒媼傆傋偒忋拞壓偺帠乿丄摨戞嶰崁乽暥偙偲偼偍側偠傗偆側傞帠乿偵傕摨條偺婰弎偑尒傜傟傞偑丄摿偵丄屲捠偺椺暥偵寧擔傪晅婰偟偨揰偑怴偟偔丄偙傟偵傛傝埗柤傗榚晅偺埵抲娭學傪傛傝柧妋偵偟偨揰偼幚梡柺偱偺慜恑偱偁偭偨丅傑偨丄宧堄偺掱搙傪乽屼乿偺帤偺偔偢偟壛尭偱丄忋丒忋偺壓丒拞丒拞壓丒壓丒壓偺壓偺榋抜奒偵暘偗偰帵偟偰偄傞偑丄椺暥拞偺乽屼乿傕偙偺婎弨偵傛偭偰揑妋偵偔偢偟曽傪曄偊偰偁傞偺偑拲栚偝傟傞丅偙傟傕廬棃偺彈惈彂嶥楃偵偼尒傜傟側偐偭偨摿怓偱偁偭偨偑丄偙傟埲屻偺彈惈彂嶥楃偱偼偝傎偳廳帇偝傟偰偄側偄丅
丂偙偺傎偐壖柤尛偄傗丄屲愡嬪傪巒傔偲偡傞徚懅梡岅側偳傕宖偘傞側偳丄亀彈幃栚亁偺彈惈彂嶥楃偼峕屗慜婜偱偼嵟傕傑偲傑偭偨傕偺偱偁偭偨丅
丂偦偺屻丄巐敿悽婭偵傢偨偭偰尒傞傋偒彈惈彂嶥楃偼側偄丅尦榎婜偺彈惈嫵梴彂偺敀旣偨傞亀彈廳曮婰亁偵傕彂嶥楃偵娭偡傞婰帠偼堄奜側傎偳朢偟偔丄嬶懱揑側偙偲偼壗堦偮彂偐傟偰偄側偄丅嬤悽慜婜偺偙偺傛偆側忬嫷偐傜丄夵傔偰捗撧偺帵偟偨彈惈彂嶥楃傪尒偰傒傛偆丅偦傟偼偄偐側傞堄媊傪扴偆傕偺偱偁傠偆偐丅
仜捗撧偑愢偄偨彈暥偺婎杮堦乑僇忦
丂亀彈暥復娪亁偵傕彈惈彂嶥楃偵偮偄偰銅乆弎傋傜傟偰偄傞偑丄傓偟傠偦偺屻偺亀彈彂娝弶妛彺亁偺彂嶥楃乽暥偐偒傗偆偺巜撿廫儢忦乿偺傎偆偑傛偔傑偲傑偭偰偍傝丄懡偔偺夵戣杮偵傛偭偰傕岼娫偵憡摉棳晍偟丄峕屗拞婜偺彈惈彂嶥楃偺婽娪偲側偭偨揰偱廳梫偱偁傞丅埲壓偵偦偺慡暥傪宖偘丄揔媂亀彈暥復娪亁摍偐傜堷梡偟側偑傜庒姳偺愢柧偟偰偍偙偆丅
丂丂擇廫丄暥偐偒傗偆偺巜撿廫儢忦
堦丄彈暥偼偄偐偵傕傗偝偟偔偁傞傋偟丅変愭偺彂偵偄傂偨傞偛偲偔丄彈惈偺暥偼帉傪偙傦偵偮偐偼偢丄撉偵偰偮偐傂媼傆傋偟丅廲偽乽偒偺傆乿偲偄傆傪乽嶐擔乿偲偄傊偽偙傦栫丅乽崱擔乿傪乽偗傆乿丄乽堦嶐擔乿傪乽偍偲偮傂乿丄偐傗偆偵桳傋偟丅彂暔偝偆偟側偳傛傒媼偼傫傕崯怱側傝丅
堦丄杗偮偓偼偄偐偵傕偙偔彂偼宧側傟偳傕丄偁傑傝杗偺擹偼偄傗偟偗傟偽丄拞埵傛傠偟偐傞傋偒栫丅
堦丄暥帤偔偩傝偼嬪愗傛偔桳傋偟丅忋傊偮偒偨傞帤傪壓傊偮偗偰偐偔偼旕嫽偺帠栫丅廲偽乽尒帠偺屼丒偝丒偐側壓偝傟岓乮楢柸懱偱偼側偔乽屼丒偝丒偐側乿偲愗傟偰偄傞丅埲壓摨條乯乿丄偐傗偆偵偒傟偨傞帠栫丅乽偝偐側乮偙偺嶰暥帤楢柸懱乯乿偲偮乁偔傋偟丅枖偼乽傂偲傂偼偨傑偝偐偺屼弌偵偰岓傊偳傕乿傪乽偝偐丒偺丒屼弌丒偵偰丒岓傊嫟乿丅乽偨傑偝偐偺丒屼弌乿栫丅偐傗偆偺強偵偰愗丄枖偼杗傪偮偓偨傞丄偁偝傑偟偒帠栫丅戝帠偺恖偺柤偑偒丄枖偼懘暥偵戞堦偵偄傂傗傞帠側偳偼杗傪偮偖傋偒栫丅懘奜偮偓偺偔偩傝偺忋傊偁偘偰偐乀偸帤偁傝丅乽偐乮壜偺偔偢偟乯乿側偳偺帤栫丅惀偼偼偠傔偵偄傂偨傞帉偵偮偒偨傞帉側傟偽丄懘偔偩傝偵偰偐偒偼偨偡傋偟丅庒壓偮傑傝偰偐乀傟偢偼堦帤偵偰傕偦傊偰偐偒傪偔傞傋偟丅廲偼乽壗偺帠惤偵偰屼嵗岓傗乿丄乽屼嵗岓乿傛傝偁偘偰彂傋偒栫丅
堦丄暥帤偺巔傪傗偝偟偔偐乀傫偲偰丄怓乆偵偪傜偟偰撉傢偒偑偨偒偼晄楃偺偄偨傝丅偝偰偼揰丄堷丄幪丄偼偹側偳偺強傪側偑偔彂傑偠偒栫丅
堦丄暥復傗偝偟偐傜傫偲偰丄偁傑傝偵巕嵶偁傞帉偼暔偟傝偩偰偵偰傒傞傔傕偔傞偟偒栫丅偝偰偼崱傗偆偺帪峴帉側偳悘暘偐乀偸條偵偟偨傑傆傋偟丅
堦丄崸斾偺帉偐偔帠丄偝偟傓偐傂偰偄傆傛傝傕昅偵偼偄偼偣傛偒傑乀扤傕偐偔帠惉傋偟丅偝傟嫟丄偮偹偞傑偵懘恖偲偺偁傂偝偮傎偳偵桳傋偟丅忢偺偁傂偝偮傛傝暥偵偰傓偮傑偠偒偼婾傝奜偵偁傜偼偵偟偰丄怱偹偮偨側偔梀彈傔偒偨傝丅偮乀偟傒媼傆傋偟丅
堦丄暥偺朄幃偝傑偁傞帠側偑傜丄彈惈偼偝偺傒偙傑偐側傞朄傪偨乁偟媼偼偢偲傕墇搙偵偼側傞傑偠丅嫀側偑傜丄戞堦廽媊偺暥偵偼曉偡彂偹傫斾偵桳傋偟丅椃傊偺暥偵偼晻傪偲偒偰偝偒偺柤偲変柤偺偒傟偸傗偆偵傆偆偠偰偐偒媼傆傋偟丅忋乆偆傗傑傂偺曽傊偼丄栜榑斺業暥側傞傋偟丅偝偒偺傔偟偮偐偼傟恖偺曽傊偺偁偰柤偵偟偰丄彂偲傔偵偼乽崯傛偟傛傠偟偔屼斺業偨偺傒傑偄傜偣岓乿偲傕乽崯傛偟傛偒偵屼怱摼乿偲傕乽屼怽忋乿偲傕丄偦傟傛傝偮偓偵偼乽屼怽媼傝岓傋偔岓乿偲傕乽屼怽媼傊丂傔偰偨偔偐偟偔乿偲傕桳傋偟丅晻暥偵傕忋乆偺偆傗傑傂偼恑忋彂惉傋偟丅傢偒晅偵偼乽嶲傞恖乆屼怽媼傊乿乽扤偵偰傕怽媼傊乿乽恖乆怽媼傊乿丄杴偐傗偆偵桳傋偟丅
堦丄偲傆傜傂暥偼杗偆偡偔偐偒偰丄偐傊偡彂側偐傞傋偟丅傕偲傛傝乽傔偱偨偔偐偟偔乿傕側偐傞傋偟丅暥偺偆偪偵乽桺乿偺帤丄乽枖偼乿側偳偺偨偖傂丄偐傗偆偺帉偐偒媼傆傋偐傜偢丅
堦丄愵側偳偵壧偐偒媼偼傫偵偼丄奊傪傛偗偰偐偒媼傆傋偟丅彂偗偟偨傞丄杮堄側偒傢偞側傫傔傝丅
堦丄抁嶜偼忋傛傝擇悺偽偐傝傪偒偰彂弌偟媼傆傋偟丅壓偺嬪偺偐偟傜偵偰杗傪偮偑偸傕偺側傝丅
丂傑偢戞堦忦偼丄捗撧偑嵟傕廳帇偟偨崁栚偲峫偊偰傛偐傠偆丅斵彈偼丄彈惈偺庤巻偺婎杮拞偺婎杮傪彈惈傜偟偄暥柺偵媮傔偰偄傞丅傗偝偟偔彂偔丄帤壒偱偼側偔帤孭傪巊偆丄偲偄偆傕偺偱偁傞丅尵偭偰傒傟偽丄亀彈暥復娪亁偼偙偺戞堦忦傪儗僢僗儞偡傞偨傔偺傕偺偱偁偭偨丅偙偺傛偆側彈惈傜偟偄暥柺偵偮偄偰偺拲堄偼嬤悽丄摿偵峕屗拞婜埲崀偵偼偟偽偟偽巜揈偝傟傞揰偱偁偭偨丅
丂戞擇忦偼杗宲偓偺擹扺偵偮偄偰偱偁傞丅亀彈暥復娪亁偵傕婱恖偺柤慜傗庤巻偺庡梡審偼杗宲偓傪偟偰擹偔彂偔偙偲傪拲堄偟偰偄傞丅堦斒揑偵擹偔彂偔偺偑宧偄偱丄媡偵壓攜傊彂偔応崌偼挗忬偱側偔偰傕敄杗偱傕傛偐偭偨丅傑偨丄廽媀忬偼擹偔丄挗忬偼敄偔彂偔偺偑楃媀偱偁偭偨偑丄峕屗屻婜偺亀怴憹
彈彅楃埢嬔亁偵偼丄昦婥尒晳忬偺乽屼杮暅乿側偳偺尵梩偼杗崟偵戝偒偔彂偒丄昦柤傗乽屼擸傒乿偲偄偭偨岅嬪偼偐偡傝昅偱彫偝偔彂偔巪偺婰帠偑尒偊傞丅偙偺傛偆偵杗怓偵偮偄偰偺婰帠偼嬤悽慡婜傪捠偠偰廳帇偝傟偨丅
丂戞嶰忦偼丄杗宲偓偲傕戝偄偵娭學偡傞偑岅嬪偺嬫愗傝偵偮偄偰偱偁傞丅扨岅偺搑拞偱夵峴傗杗宲偓傪偟偨傝丄楢柸懱傪抐愨偝偣偨傝偟偰偼側傜側偄偲偺拲堄偱偁傞丅捗撧偼丄庤巻偵偍偗傞尵梩尛偄偲偲傕偵丄乽暥帤偔偩傝乿偡側傢偪夵峴丒杗宲偓丒楢柸懱側偳偵偙偲偝傜拲堄傪暐偭偰偄傞傛偆偵巚傢傟傞丅亀彈暥復娪亁偵傕丄摨條偺婰帠偺傎偐乽峴偺戞堦帤傪敄偔偟偰擇帤栚偱杗宲偓偟偨傝丄峴偺嵟屻偺堦帤偱杗宲偓傪偟偰偼側傜偢丄擇峴栚偵巐帤懕偗偰偐偡傝昅乮乽巐帤偑偡傝乿乯偵偟偰偼側傜側偄丅傑偨丄杗宲偓偺埵抲偑奺峴偱摨偠崅偝偵側傜側偄傛偆偵偡傞乿偲偄偭偨拲堄偑婰偝傟偰偄傞丅
丂戞巐忦偼丄嶶傜偟彂偒偵娭偡傞婰弎偱偁傞丅乽庤巻偺梡審偑憡庤偵揱傢傜側偄偺偼杮枛揮搢偱偁傞偐傜丄撉傒偵偔偄傎偳嶶傜偟偰偼側傜側偄乿丄傑偨乽摿偵巕偳傕埗偺庤巻偼傒偩傝偵嶶傜偝偢丄堦帤堦帤棧偟偰撉傒傗偡偔彂偔乿偲偄偭偨怱摼偼峕屗拞婜埲崀偺彂嶥楃偵偼傛偔尒傜傟傞丅傑偨杮忦偺婰嵹偱嫽枴怺偄偺偼丄捗撧偑乽暥帤偺揰丄堷偒丄幪偰丄挼偹傪挿偔彂偄偰偼側傜側偄乿偲偡傞揰偱丄偙傟偼摉帪偙偺傛偆側彂偒曽偑娫乆尒庴偗傜傟偨偙偲傊偺斸敾偲巚傢傟傞丅嬶懱揑偵偼尦榎幍擭姧亀偟偺偡乀偒亁乮亀彈妛斖亁偼挿扟愳掑昅偲偡傞偑丄柇鏪偺昅愓偲傎偲傫偳摨偠偱偁傝丄挿扟愳柇鏪偲摨堦恖偲傕峫偊傜傟傞乯側偳偵尒傜傟傞傛偆側昅朄偑尦榎弶擭偵偼嫗搒拞偵峀偑偭偰偄偨偺偱偁傠偆丅曮塱尦擭姧偺彈昅庤杮亀傒偪偟偽亁骐暥偵偼乽悽偵傕偰廗傆亀偟偺偡乀偒亁傒偨傟偰強乆偺偨偐傜偲側傟偼乧乿偲偁傞傛偆偵丄偙偺亀偟偺偡乀偒亁偑憡摉偵棳晍偟偨傜偟偄偙偲偑暘偐傞丅捗撧偺寈崘傕傓側偟偔丄偙偺傛偆側昅朄偼乽柇鏪棳乿偲屇偽傟丄偦偺屻敿悽婭埲忋偵傢偨傝悽偺彈惈払偵棳峴偟偨偺偱偁傞丅
丂戞屲忦偼乽巕嵶偁傞帉乿傗棳峴岅偺巊梡傪嬛偠偨堦忦偱偁傝丄戞榋忦偼恊偟傒偺尵梩偵傕愡搙偁傞傋偒偙偲傪桜偟偨傕偺偱偁傞丅慜幰偼懠偺彂嶥楃偵傕尒傜傟傞偑丄屻幰偼撈摿偱偁傞丅偲偵偐偔捗撧偺彂嶥楃偼尵梩尛偄偵偮偄偰揙掙偟偰偄傞偺偑摿怓偱偁傞丅
丂戞幍忦偼丄乽曉偡彂偒乿偐傜巒傑偭偰丄晻偠栚丄斺業忬丄恑忋彂偒丄榚晅傑偱偺彂娙宍幃傗丄忋攜埗偺庤巻傑偱偺嵟彫尷偺怱摼偱偁傞丅偄傑偩弾柉壔偟偰偄側偄峕屗慜婜埲慜偺彂嶥楃偱偼忋拞壓暿偺庤巻偺彂偒曽偑嬌傔偰廳梫偱偁傝丄偦偺揰偵偙偦彂嶥楃偺懚嵼棟桼偑偁偭偨偲傕尵偊傞偑丄偙偙偱偼捗撧偼婱恖丒忋攜傊偺庤巻偺嶌朄傪偐側傝娙棯壔偟偰彂偄偰偄傞丅亀彈暥復娪亁偵偼乽忋攜傊偼傂偹傝暥丄壓攜傊偼寢傃暥偵偡傞乿偙偲傗丄乽庡恖偺嬄偣傪拠娫乮摨偠庡恖偵巇偊傞拠娫乯傊揱偊傞帪偵偼丄埗柤偵乽偝傑乿乮摉帪乽揳乿傛傝傕宧堄偑嫮偐偭偨乯傪巊偭偰偼側傜偢丄乽揳乮憪彂懱乯乿偲彂偔乿偲偄偭偨拲堄丄傑偨丄乽庡恖丒婱恖傊偺庤巻偼乽杮暥復乿偵彂偔傋偒偱丄捛怢暥偱彂偄偰偼側傜側偄乿側偳偺婰弎偑偁傞偑丄亀彈彂娝弶妛彺亁偱偼堦愗徣偐傟偨丅
丂戞敧忦偺挗忬偼丄廽媀忬偲偲傕偵嬤悽偺彈惈彂嶥楃偱偼廳帇偝傟偨崁栚偱偁傞丅
丂堦斒偵挗忬偺彂巭岅偼丄乽傔偱偨偔偐偟偔乿偼晄揔摉偩偑乽偐偟偔乿側傜椙偄偲偡傞愢偲丄偦偺偄偢傟傕傛傠偟偔側偄偲偡傞愢偺椉曽偑摉帪尒傜傟偨乮愭偺挗忬傪尒偰傕柧傜偐側傛偆偵捗撧偼屻幰偺愢偱偁傞乯丅彂巭傗暥柺偵乽傔偱偨偔乿乽傛傠偟偔乿傪晄揔摉偲偡傞偺偼帄嬌摉慠偱偁傞偑丄偦傟埲奜偺晄岾偛偲乮椺偊偽昦婥乯偵偼乽傔偱偨偔偐偟偔乿傪巊偆椺傕尒傜傟傞偺偱丄巰嫀偺応崌偲偦傟埲奜偺晄岾偵偼堦慄傪夋偡堄幆偑懚嵼偟偨傛偆偱偁傞乮亀峕屗帪戙彈惈暥屔亁戞榋乑姫夝戣嶲徠乯丅
丂埲忋偺傎偐丄挗忬偵偼抂嶌乮朻摢岅乯傪彂偐偢偵偡偖偵挗偄偺暥復偵擖傞偙偲丄懠偺梡審傗捛怢暥偼彂偐側偄偙偲丄傑偨丄乽傑偄傞恖乆乿偲偄偭偨榚晅岅傗嵎弌恖傪帵偡乽仜仜傛傝乿偺昞婰傪偟側偄偙偲丄擇峴栚偵巐暥帤偐偡傝昅偱彂偔偙偲丄暥柺偼幍峴偐嬨峴偱彂偔偙偲乮偙偺揰丄愭偵宖偘偨捗撧偺挗忬偼尨杮偱堦幍峴偲嬌傔偰挿偄乯丄偝傜偵丄晻偠栚偵杗傪堷偐側偄偺偑尨懃偩偑墦曽傊偺庤巻側傜晻偠栚傪乽僜乿乮捠忢偼乽乊乿乯偺傛偆偵偡傞偙偲側偳庬乆偺嶌朄偑偁偭偨偑丄偙傟偵偮偄偰傕捗撧偼杗怓丄彂巭岅丄婖傒尵梩偩偗偵峣偭偰偄傞丅
丂戞嬨忦丄戞堦乑忦傕丄揱摑揑側惓幃偺嶌朄偱偼幚偵嵶乆偲偟偨偒傑傝偑偁偭偨偺傪丄傢偢偐擇峴偵傑偲傔偰偄傞丅
丂偙偺傛偆偵丄捗撧偺彂嶥楃偼娙寜柧椖傪巪偲偟偰彂偐傟偰偄傞丅彈惈偺庤巻偺尵梩尛偄丄杗宲偓偺埵抲丄岅嬪偺嬪愗傝傗峴摢偵抲偐側偄帤丄嶶傜偟彂偒丄斺業暥丄恑忋彂偒丄挗忬丄愵丒抁嶜偺彂偒曽側偳丄彈惈彂嶥楃偺婎杮傪堦乑僇忦偵傑偲傔偨揰偱暘偐傝傗偡偔丄懡偔偺恖乆偵庴偗梕傟傜傟偨偺傕摉慠偱偁偭偨丅
丂梫偡傞偵丄捗撧偺彂嶥楃偼婎杮帠崁偵峣偭偰彂偐傟偨堦斒彈惈偺偨傔偺傕偺偩偭偨丅戞幍忦偺乽彈惈偼偝偺傒偙傑偐側傞朄傪偨乁偟媼偼偢偲傕墇搙偵偼側傞傑偠乿偲偄偆偺偼丄堦斒彈惈偵懳偟偰偺庡挘偱偁偭偰丄塃昅側偳摿庩側棫応偺彈惈偵懳偡傞傕偺偱偼側偄丅偙偺屻峕屗屻婜偵帄傞傑偱偺娫丄偝傜偵徻嵶側彈惈彂嶥楃傕搊応偡傞偑丄彈惈彂嶥楃傪乽偙傑偐側傞朄乿偺曽岦傊偲摫偄偰偄偭偨偺偼戝曽抝惈偱偁偭偨丅
丂捗撧偼堦斒彈惈偺偨傔偵庤巻偺婎杮帠崁傪娙寜偵愢偄偨愭嬱幰偱偁傝丄彂嶥楃偺弾柉壔偵懡戝側峷專傪偟偨偲偄偊傞丅捗撧偺墲棃暔偼丄偄傢偽彈惈偵傛傞彈惈偺偨傔偺撈憂惈偲屄惈偵枮偪偰偍傝丄彂嶥楃偺傒側傜偢彈惈偺怱摼傗嫵梴偺柺偱嬤悽彈惈偺戝偒側巜恓偲側偭偨偺偱偁傞丅
丂嬤悽弾柉暥壔偵偍偗傞捗撧偺懚嵼偼悳傞戝偒偄偺偱偁傝丄斵彈傪墲棃暔巎忋摿昅偡傋偒彈惈偲偟偰丄傑偨丄嬤悽嵟弶偺彈惈孾栔壠偲偟偰嶿偊傞強埲偱偁傞丅
亂嶲徠暥專亃
仜塭報斉偵側偭偰偄傞捗撧偺嶌昳乮慡偰戝嬻幮姧乯
乽彈彂娝弶妛彺乿乮亀峕屗帪戙彈惈暥屔亁榋乑姫丂暯惉敧擭乯
乽彈嫵孭暥復乿乮亀墲棃暔戝宯亁敧擇姫丂暯惉榋擭乯
乽彈幚岅嫵丒彈摱巕嫵乿乮亀墲棃暔戝宯亁敧幍姫丂暯惉榋擭乯
乽彈拞暥復娪乿乮亀墲棃暔戝宯亁嬨擇姫丂暯惉榋擭乯
乽彈暥復搒怐乿乮亀婬鍽墲棃暔廤惉亁堦敧姫丂暯惉嬨擭乯
乽彈暥椦曮戃乿乮亀墲棃暔戝宯亁嬨擇姫丂暯惉榋擭乯
仏埲忋偺傎偐丄亀彈昐恖堦庱亁偲亀彈暥復娪亁傪亀峕屗帪戙彈惈暥屔亁偵廂榐偺梊掕偱偁傞乮暯惉堦乑擭姧峴梊掕乯丅
仜偦偺懠塭報斉乮慡偰戝嬻幮姧乯
乽傪傓側偐乀尒乿乮亀墲棃暔戝宯亁敧嶰姫丂暯惉榋擭乯
乽彈幃栚乿乮亀墲棃暔戝宯亁敧堦姫丂暯惉榋擭乯
乽彈暥屔崅帾奊乿乮亀墲棃暔戝宯亁嬨擇姫丂暯惉榋擭乯
乽峕屗墲棃乿乮亀墲棃暔戝宯亁屲擇姫丂暯惉屲擭乯
乽昐岓墲棃乿乮亀婬鍽墲棃暔廤惉亁堦堦姫丂暯惉嬨擭乯
仜尨杮
亀彈暥復娪亁乮掑嫕屲擭斅丂仏曣棙巌楴巵憼乯
亀彈梡暥復峧栚亁乮尦榎堦堦擭斅丂仏尓摪暥屔憼乯
亀摉棳彈昅戝慡亁乮尦榎堦擇擭斅丂仏撧椙彈巕戝妛憼乯
仏尨杮傪挷嵏偝偣偰捀偄偨忋婰屄恖丒婡娭娭學幰偺曽乆偵岤偔屼楃怽偟忋偘傞師戞偱偁傞丅
仜偦偺懠弌斉暔
亀峕屗帪戙 彂椦弌斉彂愋栚榐廤惉亁乮宑滀媊弇戝妛晬懏尋媶強巣摴暥屔曇丂徍榓嶰幍丒嶰敧擭丂堜忋彂朳乯
亀曗掶斉 崙彂憤栚榐亁乮娾攇彂揦曇丂暯惉尦乣嶰擭乯
亀屆揟愋憤崌栚榐亁乮崙暥妛尋媶帒椏娰曇丂暯惉擇擭丂娾攇彂揦乯
曣棙巌楴乽亀彈梡暥復亁峫乿乮婒晫戝妛亀崙岅崙暥妛亁擇堦崋丂暯惉屲擭乯
亀彂娙梡岅偺尋媶亁乮恀壓嶰榊挊丂徍榓榋乑擭丂宬悈幮乯
乽彈朳昅朄乿乮亀懕孮彂椶廬亁姫戞幍乑堦乯
|