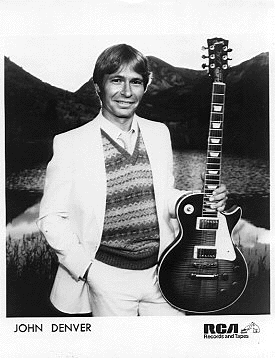
|
|
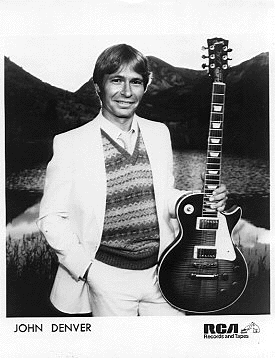
●1983年6月2日、東京NHKホールでこの上なく素晴らしいコンサートを終えたジョン・デンバーは、その足で、当時の人気洋楽番組『ベストヒットUSA』のインタビュー収録のため、テレビ朝日のスタジオへと向かった。その模様は、翌1984年1月に放映された。また1985年春、同番組のゲスト・ミュージシャンたちのインタビューを文字起こししたムック『ベストヒットUSA・WELCOME』がテレビ朝日から出版され、ジョン出演の回も掲載された。内容は以下に紹介する通り。(※無断転載につき、チクらないでちょ。)
「時の流れというものをそれほど重視しない。
ぼくの歌はぼくの中からでてくるんだ。」
聞き手:小林克也
小林:ようこそ、ジョン・デンバー。
ジョン:どうも、小林さん。楽しく話しましょう。
小林:それがいい。ところで、間近にお目にかかるのは、今回が初めてだね。服なんかみると、どうやら相当減量しているようにお見受けするけど。たしか眼鏡をかけていたんじゃない?
ジョン:最近、コンタクト・レンズに変えてみたんだ。それに、いうところの“マクロビオティック”という食餌療法を実行中でね。生活をその線でやっているんだ。確かに体型が変わったと思う。150ポンド少々というところかな。もうちょっと少ないかも。いちばん調子がいいんだよ。
小林:ところで、最近のファンのために、ざっとおさらいしたいんだけど、まずあなたのスタートは?僕の記憶では「チャド・ミッチェル・トリオ」じゃなかったかな、デビューは…。
ジョン:そもそも遡れば、ということになると、祖母にギターをプレゼントされた時が第一歩だよ。12歳だった。レッスンを受けながら同時に歌もね。そのうち、ポピュラーなんかも教わったかな。そうして、すぐ歌を作り始めたんだ。父は空軍勤務でね。それで各地を転々。そのたびに、こちらは新参者になったわけだけど、音楽がとても役に立った。知らない家の扉も簡単に開けられた。友達もすぐにできたんだ。みんなとすぐに友人関係を結べたね。音楽のおかげだよ。そのうちに大学に入ったんだけど、この頃はいっそうギターや歌に時間を費やすようになった。そうすれば、当然学校の成績にも影響する。それでしばらく学校をやめて歌でやってみようと思ったんだ。そうすれば、歌でいけるか、ダメなら学校に集中できる。まじめにならなければ大学は出られない。両立はしないんだよね。自分としては音楽の道で、どれだけやれるか試してみたかった。まったくついていたんだね、大学をやめたらすぐにランディ・スパークスと仕事をするようになった。「ニュー・クリスティ・ミンストレルズ」のね。そういうチャンスが重なって「ミッチェル・トリオ」で歌うことになった。トリオでは2年半仕事をしたかな。トリオが解散して、また自分でやるようになった。そして「ピーター、ポール&マリー」が「悲しみのジェット・プレーン」をレコーディングしてくれた。これが大ヒット。運がついていたんだね。4枚目のアルバムに入っていた「故郷へ帰りたい」が、ぼくの最初のヒットとなった。
小林:そうそう。で、「ジェット・プレーン」の前には何か書いていなかったの?
ジョン:あれは僕の2曲目だよ。
小林:じゃあ、1曲目は?
ジョン:ピーター、ポール&マリーの「フォー・ベイビー(フォー・ボビー)」だよ。いや、実際にはその前にもう2曲ばかり作っていたかな。この曲についてはまったく取り上げていないけどね。それは「もの憂い小川の土手に腰掛けて(Sitting
On A Banks Of A Lazy Little Stream)」というんだけど。ぼくがアリゾナの教会キャンプにいたときに作ったんだ。ぼくにとって自然がとても大きな要素になる。
小林:では、1971年の曲「カントリー・ロード」です。
(VTR「カントリー・ロード」。1982年6月、レッド・ロック・シアターでのライブ映像。)
小林:大きな会場ですね。何ていうところ?
ジョン:「レッド・ロック・シアター。」
小林:あなた専用なの?
ジョン:いやいや、20年前に建てられたものだよ。自然の地形を利用した円形劇場。山ふところのね。コロラドのデンバー郊外にあるんだ。ここを舞台として使っている。コンサートに耳を傾けながら腰をおろしていると、その向こうには町の景色が拡がっている。なかなかいい眺めだよ。じつに美しい場所なんだ。ぼくは、ここで歌うのが好きでね。できるなら、世界中からファンの皆さんを招待して、思う存分に歌いたいと思っている。理想的な劇場なんだな。
小林:ところで1971年頃の話になるけど、当時は、シンガー・ソングライターが話題になっていたね。作詞、作曲、歌手をこなすという。あなたとか、ジェームス・テイラー、キャロル・キングなどが活躍した。LPはミリオンセラーになったりした…。
ジョン:そう、まったく満ち足りていたよ。世界中の人たちが、彼らの歌の中に自分というものを見出していた。その曲にかかわり詞にかかわっていく。ぼくはね、自分の歌がちょっといい節だとか、時流にのっているということだけで受け入れられたとは思ってない。歌がその人の心と深く関わっていればこそ、人々になじんだのだと思う。そういうことはとても大切なんだと教えられたよ。近頃は、誰だって生活がクレイジーになっちゃっている。電話のベルが人々を追い立てる。人間が人間を追いつめているんじゃないかな。だから人間は自分の正気を保っていくために、“ノー”という勇気を持つべきだ。そういうことがぼくのひとつの大きな課題だよ。
でもデンバーにいて、フィールドのトップに立つというのもいいことだ。大いにチャレンジしたい。デンバーにいてやりたいことがいっぱいあるんだよ。
小林:最近のアメリカ音楽の現状について、ひとつ診断を下してもらえる?
ジョン:いやぁ、そいつはとてもむずかしい。アメリカに限らず、音楽の変化の早さといったら、すごいものだ。あなたも言ったように、じつにさまざまな傾向があってね。オーストラリアのミュージシャンなんかが大きな波となっている。「メン・アット・ワーク」なんかがそれでしょうね。それに音楽はますます国境を超える存在になっている。いろいろなグループが現れている。ボブ・マーリー、ジミー・クリフなどのグループとか、それは荒削りではあるけれど。それに、ぼくは時流というものをね、時の流れというものをそれほど重視していない。ぼくの歌はぼくの中からでてくるんだ。ぼくは自分が書きたい歌しか作らない。ヒットを目指すというようなことはないね。ぼくの曲はホンネが身上。正直に明確にホンネを表現したい。自分の心に、ふと訪れたもの、感じたもの、あるいは自分の目が見たものを表現するんだ。その曲を聴いた人たちは、それぞれの心の中でそいつを自分流に消化してくれれば、ぼくはいい。まあ、その結果としてたまたまヒットすれば、ぼくとしては何もいうことはないね。ぼく流の対処のし方ということだ。だからね、特に現在の音楽状況に注意を払うとか、ビジネスの動向に神経をとがらせる、とかいうことはない。ただ、それらの音楽に注意深く耳を澄ませているだけなんだ。自分の音楽を時の流行に合わせて変えるようなことはしないよ。
小林:レコード界の人は大体がそうなんだけれど、もちろんビデオにも興味はあるんでしょう。
ジョン:そう、皆やってるね。テレビとの関連は、僕も十分に重く見ている。ビデオについては、一定の考えも持っているよ。いちばん新しく完成したアルバムを中心にやりたいと思っている。
小林:“イッツ・アバウト・タイム”だね。
ジョン:“タイム”とそれに“シーズンズ・オブ・ザ・ハート”。この2枚がいちばん新しいアルバムだよ。
小林:プロデュースもしているの?
ジョン:そう、前向きに考えているよ。新しい芸術形式というのかな、一本のテープの中に歌もあり、いろいろな要素が詰まっている。素晴らしいだろう。マイケル・ジャクソンの“ビート・イット”なんかは素晴らしい。ぼくもああいった仕事がしたいね。
小林:東京みたいにごみごみしたところについては、どう感じているかな。
ジョン:東京は好きな街だね。ありとあらゆる要素の対比、対立がある。東京でいちばんいいのはね、車のクラクションが聞こえないことだね。クラクションのない街というのは、これは素晴らしい。運転する人が、それぞれ相手の気持ちをくんで運転しているからだろうね。それに車がきれいだ。傷のある車がほとんどない。ともかく、東京はいい。日本は好きだね。日本の人たちも好きだよ。この国に来るたびに深いものを感じるし、楽しい。日本文化、日本人、みんな気持ちのいい、尊敬に値するものがあるね。できれば、何度でも来たいよ。
|