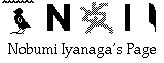
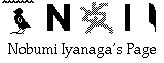
若い日の内村鑑三のオプティミズムは、その後の日本および世界の歴史によって次々と裏切られていく。日清戦争(一八九四−九五年)、日露戦争(一九〇四−〇五年)、そして第一次世界大戦(一九一四−一八年)……。アメリカは、内村が第二の故郷とも思い最も深く愛した国だったが、日露戦争以降、日米関係は対立の一途を歩んでいた。そして一九二四年――松沢氏が書いておられるように――
アメリカ連邦政府と議会は日本人の移民を差別し、受け入れを事実上拒否する新移民法案を制定した。〔……〕
内村にとってはなお、「世にたよるに足る国があるとすれば、それは米国」にほかならぬ、という期待があった。内村にとって、アメリカは、神の世界計画において、いっさいの人種差別を撤廃して、「異人種の融合」「東西文明の融合」を実現する「天職」を与えられていた。〔……〕したがってアメリカの日本人移民閉め出しは、内村にとって単なる「日米問題」にとどまらず、「世界問題」であり、「人類全体の失望」を意味した【松沢、前掲「解説」 p. 71.】。
こうした深い絶望のなかで、内村にとっての「日本の天職」は内容を変えざるをえなかった。日本は、もはやたんに東西の文明の「媒介者」という以上に、より根源的な宗教的使命を帯びた国でなければならない。ふたたび松沢氏によるなら、
……内村は、『地理学考』を書いたころから、日本が、「東洋」と「西洋」という二つの異質な勢力と文化の接触する境界に位置することに注目してきた。内村は、このころ〔晩年になってから〕、このような位置をしめる日本を「境界国[ボーダーランド・ステイト]」と呼んだ。日本がそのような位置にもとづいて、世界のためにつくすべき役割を、青年時代の内村は、「東洋」「西洋」両文明の「媒介」にもとめた。しかし、世界と日本の将来を問いつづけた内村は、キリスト再臨論と、それをふまえた「西洋」の近代キリスト教の批判と、アジアとくに日本における「第二の宗教改革」の思想に到達し、さらに、世界における日本の孤立化に直面したのだった。今、内村が「境界国」日本に期待した働きは、文化の次元での「媒介」から一だんと飛躍していた。それは、文化とは区別された、その根本にあるものとしての宗教の次元での「媒介」だった。
「東洋/西洋」という分類が、「宗教の次元」でどのような意味をもちうるのだろう。松沢氏によれば、内村にとって、
……「東洋」のエッセンスは、おのれを全く忘れて絶対的な他者によりたのむ宗教心だった。それゆえに「東洋」は、仏教・キリスト教など世界宗教を、世界に生みおとした。そうして、キリスト教を「西洋」に引き渡した後、「東洋」は、そのような宗教心を地下水のような形で保ちつづけて来た。日本の宗教的伝統〔……〕はそのような宗教心の精髄だった。二〇世紀を経て、「西洋」化されたキリスト教と、「東洋」に保たれて来た純粋の宗教心とは、日本という場で正面から出会った。日本を舞台にして両者はむすびつき、人間の作る制度や文化への埋没から完全に解放された、純粋なキリスト教が生まれるべきだった。それが日本を場とした、世界史的な、「宗教改革のしなおし[リ・リフォーメーシオン]」であり、「日本的キリスト教」だった。内村たちの無教会キリスト教は、その先駆なのだった【同上 p. 73-74.】。
一九二四年十一月、すなわちアメリカで新移民法が制定された年に、内村が『聖書之研究』に掲載した「日本の天職」という文章は、ほとんどイスラエルの預言者のことばのような悲痛な響きに満ちている。三十年前、誉れ高い「媒介者」の国ギリシアやイギリスに擬せられていた日本は、ここでは国を失い世界にさまようユダヤの民に、ほとんど「肉体的に」同一視されている。しかし、たとえ「イスラエルの子孫」のように国を失う危機に見舞われたとしても、その試練の中から真のキリスト教を生み出すことこそが、日本に課せられたまさに最も栄光ある「天職」なのである。「日本の天職」という文章は、『詩篇』百十篇の引用で書きはじめられている。
なんじの勢力[いきおい]の日に、なんじの民は、聖なるうるわしき衣を着け、心よりよろこびておのれをささげん。なんじは朝[あした]の胎[はら]より出ずる壮[わか]き者の露をもてり(詩篇百十篇三節)。
日本の天職は何か。日本はとくに何をもって神に仕うべきか。世界は日本より何を期待するか。日本は人類の進歩に何を貢献すべきか。これ日本人各自にとりて切要なる問題であるはもちろん、世界各国の識者が今日まで知らんと欲して努め、また今なお解答を求めつつある大問題である。国に天職あるは人に使命あると同様である。エジプトとバビロンとは世界に最初の物質的文明を供し、フェニキアは商業をもって太古時代の文化を助け、ギリシアは美術、文芸、哲学を生み、そしてユダヤは、今日に至るもいまだ廃[すた]れざる宗教を与えた。国に特産あるがごとくに、民に特種の才能がある。世界人類は各国の産物才能の貢献によって進歩し、その究極の目的に達するのである。
そして貢[みつぎ]をもとむる者は人にあらずして神である。神はその造りたまいし万国の民より、その最善を要求したもう。〔……〕
では、その「日本人は特別にいかなる民であるか」――。
……私は答えて言う、宗教の民であると。かく言いて、私は私の田に水を引き入れんとするのではない。日本の歴史と日本人の性質を考えて見て、かく言わざるを得ないのである。〔……〕日本人は英国人のような商売人にあらず、また米国人のような、肉と物とにあこがれる民にあらざることに目覚めつつある。日本人は英米人とは全く質の異なった民である。そこに彼らの天職があり、偉大なる所があると信ずる。
日本今日の仏教は腐敗せる迷信であると西洋のキリスト教徒らは言う。されども腐敗せる点においては西洋のキリスト教も異ならない。そして腐敗せる仏教界に誠実なる真の信者の潜[ひそ]んでいることは、西洋のキリスト教界におけると同じである。日本の仏教界に多くの尊むべき信者があった。その模型として、私は常に恵心僧都[えしんそうず]源信を思う。その信仰の純潔にして思想の高遠なるにおいて、私は西洋の宗教家にして彼にまさりたる者あるを知らない。〔……〕また神道においても、本居宣長、平田篤胤らは、西洋に多く見る信仰的愛国者の秀[ひい]でたる者であって、国の誇り、民族のほまれである。彼らはいずれも、私がここに唱うるがごとくに、日本国の天職の道義をもってする万国指導にあると唱えた。彼らが日本を神国ととなえたのはこの意味においてである。そしてその聖[よき]理想を言い表したものが平賀源内の有名なる一首である。
さしのぼる朝日の本の光より 高麗[こま]唐土[もろこし]も春を知るらん〔上述参照〕この聖望たる、これを国自慢[くにじまん]としてしりぞけてはならない。こはイスラエルの民のいだきし望みであって、日本人たる者は何人もこの高き理想をいだくべきである。武をもって、シナ朝鮮を征服せんとするのではない。またアジア大陸をわが勢力範囲に置かんと欲するのではない。日本にのぼる道の光をもって、世界の暗を照らさんと欲するのである。これよりも高きまた聖き愛国的志望はない。これは預言者イザヤの言の遠き響きと称して不可なきものである。
起きよ。光を放てよ。なんじの光栄たり、エホバの栄光なんじの上に照りいでたり。見よ、暗きは全地を掩[おお]い、闇はもろもろの民を覆[おお]わん。されどなんじの上にはエホバ照りいでたまいて、その栄光なんじの上に現わるべし(イザヤ書六十章一、二節)。
その「光を放つ」者は、極東において最も純粋なる信仰を保ちつづけてきた日本、「さしのぼる朝日の本の光」の国、「神国」日本でなければならない。――「日本の天職」の結論部分は、「再臨するキリストに仕える日本の聖徒」のイメージを喚起し、古代ヨーロッパ以来の神秘的終末論の戦慄的な高揚の息吹を感じさせる――。
そして世界は再び純信仰の復興を待ちつつある。いわゆる西洋文明はその全盛に達して、これは世を救う者にあらずしてかえって滅ぼす者であることがわかった。〔……〕全生涯を金もうけ事業のために費やせし者が、老年に近づいて、実業界を去って精神界に入らん事を願うと同じく、今や人類全体が憧憬[あこがれ]の目を純信仰に注ぐに至った。誰かこれを供する者ぞ。
日本人ではあるまいか。仏教がインドにおいて亡びし後に、日本においてこれを保存し、儒教がシナにおいて衰えし後に、日本においてこれを闡明[せんめい]せし日本人が、今回はまた欧米諸国において捨てられしキリスト教を、日本において保存し、闡明し、復興して、再びこれをその新しき形において世界に伝播[でんぱ]するのではあるまいか。日本は神国であり、日本人は精神的民族であるとは、自称自賛の言ではない。恥を知り名を重んずる点においては日本人は世界第一である。我らは自分に多くの欠点あるに省みて、神のこのたまものを看過[みすご]してはならない。日本人が信義に鋭敏なるは、これ精神界において、神と人とに尽くさんためではあるまいか。
ここにおいてか、前に掲げたる詩篇百十篇三節の言が光を放つのであると思う。「なんじの勢力[いきおい]の日うんぬん」とある「なんじ」は、受膏者[じゅこうしゃ]すなわちキリストを指して言うのである。神の子キリストが最後に勢力をふるいたもう時には、彼の民すなわち従者は、聖なるうるわしき義の衣を着て、心より喜びておのれをささげ、その命[めい]に当るとのことである。そして彼キリストは「朝[あした]の胎[はら]より出ずる壮[わか]き者の露をもてり」という。「朝の胎」とは、「日を産み出だす所」との意味であって、極東の国をさして言う。「壮[わか]き者」とは、信仰に燃ゆる信仰的勇者と解し得べく、「露をもてり」とは、「奉仕を受くる」とか、または「利益にあずかる」とかの意である。「彼キリストが最後に世を治めたもう時に、極東、日出ずる国の彼の御弟子たちが、その熱心熱誠をもって彼に仕えまつり、彼の聖旨をしてこの世に成らしむべし」と解して、少しも無理の解釈でないと思う。「なんじは朝の胎より出ずる壮き者の露をもてり」。キリストは日本人の信仰の奉仕を受くる特権を有したもう。彼の栄光は我らの名誉である。我らは感謝して彼の召命[めし]に応ずべきである。
大震災に次いで友邦米国の排斥起こり、わが国の万事非ならざるはなき状態である。しかしながら悲境はすべて我らの肉とこの世にかかわる状態である。誰か知らん、日本国の真の隆起は彼が悲境の極に達した後にある事を。国としての存在を失った後の今日、イスラエルの子孫はその宗教と信仰とをもって世界の最大勢力である。多くの人類学者によって、イスラエルの血をまじえたる民なりと称せらるる日本人の世界的勢力もまた、亡国とまでは至らざるも、その第一等国たるの地位を抛ちての後の事であると思う。神が今、日本国をむち打ちたまいつつあるは、この準備のためではあるまいか。
この悲痛でしかも高らかな結語に、内村はさらに短い「付録」を加えて、「日本人=ユダヤ人」説の補強を試みている。
付録 日本人の内にユダヤ人の血が流れているとは、早くより学者の唱えた所である。かつてある有名なる西洋の人類学者が京都の市中を歩きながら、行き交[か]う市民の内に、まぎろうべきなき多くのユダヤ人あるを見て、指さしてこれを案内の日本人に示したとの事である。その他、日本人の習慣の内にユダヤ人のそれに似たるもの多く、また神道とユダヤ教との間に多くの著しき類似点ありという。今回、米国の日本人排斥に対して、かの国一派のキリスト信者が「日本人イスラエル説」を唱えて、大いに日本人のために弁じたことを余輩は知る。日本人の敬神にユダヤ人的の熱誠あるは、人のよく知る所である。キリスト教の宣教歴史において、日本人のごとくに真実にこの教えを受けた者は他に無いと信ずる。宣教開始以来六十年後の今日、キリスト教はすでに日本人の宗教となった。キリスト教は日本において、他国において見ざる発達を遂ぐるであろう〔……〕【以上、同上書 p. 463, p. 466-467, p. 468-470.】。
内村のこうしたことばのどこまでがアジテーションのための修辞で、どこまでを「文字通り」に理解すべきなのかは、必ずしも明確ではない。しかしそれは「荒野に呼ばわる預言者」のことばの通例であって、本質的な問題ではない。日本人こそが『旧約聖書』に預言された世界を救済する民にほかならないという、内村のこうしたことばは、たとえば、フランス国王こそはエルサレムに君臨して世界帝国の帝王となり、再臨するキリストに仕えて世界を支配しなければならない、と説いた十六世紀の「碩学にして狂気[ドクト・エ・フォル]」の神秘家ギヨーム・ポステルの語調に酷似している【『幻想の東洋』第十五章、および p. 参照。】。「極東」の「日の本」に位置する日本こそが、その世界史的使命を負っている、という修辞は、最も純正のキリスト教的オリエンタリズムの表現であり、同じ「極東の日本」で信仰された宗教に、真正のキリスト教の名残りを見い出したポステルの説にも通じるものがある。さらにそこには、「日本人=ユダヤ人」という奇妙な神話的モティーフが加えられるが、これももとに遡れば、先にも言及した「イスラエルの失われた十の支族」の伝説に基づいたもので、その伝説のゆえに、昔ヨーロッパを襲った蒙古の民はこの終末の民に同定され、またインドで、中国にユダヤ人的習俗を有する民があることを伝え聞いたフランシスコ・ザビエルは、中国に渡ることを考えたのだった(そして驚くべきことに、中国には事実、九世紀頃から広いアジアを流浪してきたユダヤ人の一群が住み着いていた……。「十二世紀に成立した開封の組合は、その土着の文化と同化・融合した特例としてあげられる」という)【河野純徳訳『聖フランシスコ・ザビエル全書簡』(平凡社、一九八五年) p. 239 ; 平凡社刊『アジア歴史事典』IX, p. 100a ; A. C. Moule, Christians in China before the year 1550, London, 1930 [reprint , Taipei, 1972], p. 1-4 ; 「日本人=ユダヤ人」の神話は、現代に至っても消滅していない。たとえばヨセフ・アイデルバーグ著、中川一夫訳『大和民族はユダヤ人だった――出エジプトから日本への道』(たま出版、一九八四年)は、現代に生き残ったこの神話を「学問的」に再話するものである。】。
中世以来、ヨーロッパの人々を惑わし、東へ、東へと惹きつけつづけてきたオリエンタリズムの伝統は、こうしてキリスト教思想とともに明らかに日本にもたらされ、内村の悲劇的なことばの中にその姿を現わしているのである。
「神国」たる「日本国の天職の道義をもって万国を指導」し、「日本にのぼる道の光をもって、世界の暗を照らさんとする」こと、これをもって「これよりも高きまた聖き愛国的志望はない」と考えること――。内村鑑三がこうしたことばを書き連ねてから十五〜六年たって、これとほとんど同じ理想をみずからのものとし、それを現実の世界に実現することに全力を傾けた人々があった。すなわち、「近代の超克」というモットーのもとに結集して「大東亜戦争」への知識人の協力の姿勢を鮮明にした学者、批評家、文学者たち、特に西田幾多郎とその門下のいわゆる京都学派の哲学者たちである【周知のように、「固有の意味での『近代の超克』は、雑誌『文学界』が一九四二年(昭和十七年)九、十月号にのせたシンポジウムを指す」。しかし同時に、「『近代の超克』というのは、戦争中の日本の知識人をとらえた流行語の一つであった。あるいはマジナイ語の一つであった。『近代の超克』は『大東亜戦争』と結びついてシンボルの役目を果たした」(竹内好稿「近代の超克」、前掲書 p. 53, 54)。――ここでは、「近代の超克」という語は、この「シンボル」の意味として用いたい。『文学界』のシンポジウムでは、京都学派の哲学者たちは必ずしも主導的な役割をもったわけではなかった。しかし、当時の「戦争協力の哲学」として最も整備された形をもっていたのは、明らかに彼らの哲学だったと言えるだろう。――京都学派の「戦争協力哲学」に関しては、昭和十七年から十八年にかけて『中央公論』に掲載された三回の座談会(後に『世界史的立場と日本』という題で一冊にまとめて出版された)も重要である。残念ながら、今回はこの座談会は、他の批評家の引用による以外には参照できなかった。たとえば松本健一著『「世界史のゲーム」を日本が越える』(文芸春秋社、一九九〇年) p. 21 以下、p. 30-31 参照。】。
もちろん、一部の表現が似ているからといって、内村の思想と京都学派の哲学を単純に同一視するのは、方法論的に誤りであるだけでなく、最も危険な修辞的詐欺行為であると言うべきである(同じことは、ギヨーム・ポステルと内村の類似についても言わなければならない)。内村は、いま引用した文の直前に「武をもって、シナ朝鮮を征服せんとするのではない。またアジア大陸をわが勢力範囲に置かんと欲するのではない」と明言し、また、ユダヤの民と似たように、日本もまた「亡国とまでは至らざるも、その第一等国たるの地位を抛ちての後」に、はじめて精神的な意味での世界の指導者になりうる、と述べていた。――そもそも、内村は、日清戦争開戦当初の一時期を除いて【松沢、前掲「解説」 p. 38-39 参照。】、ほぼ一貫して断固とした平和主義者だったし、またつねに権力や権威にこびることを拒否した激しい反骨精神の持主だった。こうした個人的資質の差は、社会的現実の中で人間が進んでいく方向を決定的に左右するものであるに違いない。
驚くべきなのは、むしろこうした個人的資質の決定的な差を越えて、ある種のものの考え方の枠組、あるいは「エピステーメー」が、ある種の修辞法とともに伝播し、再生産され、永続していくことである。
一九三〇年代から四〇年代の状況に関して、はじめに思い出しておかねばならないのは、当時の日本では、廣松渉氏が「東西ヘゲモニー史観」と呼ばれたところの、オリエンタロ‐オクシデンタリズムを軸とした一種の極度に緊張した終末観が蔓延していたことである。廣松氏によれば――
“平和ボケ”の昨今〔一九七四〜七五年当時〕では、つい二十数年前の一九五〇年代まで、米ソ戦争(第三次世界大戦)は不可避だというのが世人一般の確信的な既成概念であったことすら忘れられがちであるが、昭和の初年には日米戦争の将来的不可避性ということが絶対確実な既定の事実として人々に意識されていた。当時の常識では戦争というものは謂わば自然法則的な必然であって、特定の一国が世界支配を達成するまでは永久に繰返されるものと思い込まれていた。この前提的確信からすれば、そして、日本の敗退を認めたがらない心情があった以上は、恒久世界平和を確立し、全世界の安寧と秩序を確保するためには日本が戦争に勝ち抜き、最終戦に勝ち残ることが絶対的な要件として意識される。極く一部のマルクス主義的左翼等を除いて、“知識人”たると“大衆”たるとを問わず、それが“日本国民”の共通の了解事項であったと言えよう。
謂うところの“世界最終戦争”は〔……〕昭和の初期には日米決戦(太平洋戦争)になるものと予期されていた。世界最終戦の時期やそれに到る経過などについては一義的に予想されていたわけではないが、〔……〕米国を盟主とする西洋と東亜の盟主たる日本との決戦は、単なる力の対決ではなくして西洋的原理と東洋的原理との理念的対決として思念されていたこと、この事実を併せて銘記しておかねばならない【廣松渉著『<近代の超克>論――昭和思想史への一断片』(朝日出版社、エピステーメー叢書、一九八〇年) p. 149-150.】。
こうした「東西ヘゲモニー史観」は、「かの三月事件、十月事件の立役者の一人でありかつ満州事変を惹き起した陰謀への参劃者で後には『大政翼賛会』の大幹部となった橋本欣五郎」や「満州事変を推進した関東軍高級参謀石原莞爾」などによって構想され、中野雅夫氏が『昭和史の原点』(第一巻)に
世界最終戦はアジアとヨーロッパの決戦である。その時期はヨーロッパの文化と頭脳がアメリカに集中し、アジアの文化と頭脳が日本に集中したとき、そのときは東西の科学者はほとんど同時に極限兵器を発明している。大戦はいま(昭和五年当時)から四十年あるいは五十年以後に起こり、二十年ないし三十年は続くであろう【同上書 p. 151-152 の引用による。】
と書いたような、大衆的レヴェルの「通念」を生み出していた。
これとまさに軌を一にした終末論的「世界戦争」論は、真珠湾攻撃の直後に行なわれたラジオ講演『米英東亜侵略史』(第一書房、昭和十七年)で、「これより十六年前の『亜細亜・欧羅巴・日本』の一節をみずから引用しながら、日米戦争(すなわち大東亜戦争)を東西文明の対抗戦争と位置づけた」(松本健一氏)大川周明のことばにも、明らかに反映されている。
いま東洋と西洋とは、それぞれの路を往き尽くした。然り、相離れては両[ふたつ]ながら存続し難き点まで進み尽くした。世界史は両者が相結ばねばならぬことを明示して居る。さり乍ら此の結合は、おそらく平和の間に行はれることはあるまい。天国は常に剣影裡に在る。東西両強国の生命を賭しての戦が、おそらく従来も然りし如く、新世界出現のために避け難き運命である。この論理は、果然米国の日本に対する挑戦として現れた。亜細亜に於ける唯一の強国は日本であり、欧羅巴を代表する最強国は米国である。この両国は故意か偶然か、一は太陽を以て、他は衆星を以て、それぞれ其の国の象徴として居るが故に、其の対立は宛[あたか]も白昼と暗夜の対立を意味するが如く見える。この両国は、ギリシャとペルシャ、ローマとカルタゴが戦はねばならなかつた如く、相戦はねばならぬ運命に在る。日本よ! 一年の後か、十年の後か、又は三十年の後か、そは唯だ天のみ知る。いつ何時、天は汝を喚んで戦を命ずるかも知れぬ。寸時も油断なく用意せよ。建国三千年、日本は唯外国よりいっさいの文明を摂取したるのみにて、未だ曽て世界史に積極的に貢献する所なかった。此の長き準備は、実に今日のためではなかつたか。来るべき日米戦争に於ける日本の勝利によつて、暗黒の夜は去り、天つ輝く世界が明け初めねばならぬ【松本健一著『「世界史のゲーム」を日本が越える』 p. 214 の引用による ; 同書 p. 157 参照。】。
ここでも、ヨーロッパの伝統的オリエンタリズムの言説と同じく太陽表象の象徴が用いられている。ただ、その太陽表象は、ここでは、「日出ずる国」日本に課せられた世界史的=終末論的使命の光輝を表わすものである。
「ギリシャとペルシャ、ローマとカルタゴの戦い」も、当時の重要な政治的トポスの一つだった。たとえば、昭和十七年から十八年にかけて、京都学派の四人の哲学者と歴史家を集めて『中央公論』誌上に三回に分けて掲載された座談会『世界史的立場と日本』の第二回目「東亜共栄圏の倫理性と歴史性」(昭和一七年四月号)で、歴史家・鈴木成高は次のように発言している。
「(大東亜戦争は)とにかく世界史全体の運命と結びついてゐる小数の戦争の中にはいる。ペルシャ戦争でもあれは一つの世界戦争だつた。単にギリシャ人とペルシャ人との間の戦争ではなくて、西洋と東洋との戦争だつた。或はギリシャのエトスと東洋のエトスとの戦ひだつたといえる。ポエニ戦争。これもやはりカルタゴによつて代表される東洋的世界とローマによつて代表される西洋的世界との戦ひだ。今度だつて日本が生まうとしてゐる東亜の新しいエトス、さういふものの戦争だ」【同上書 p. 155-156 の引用による。】。
これとまったく同じ思想を、高坂正顕は同じ座談会で次のように一般化して表現している。
「今度の大東亜戦争になつてくると、もつと広く、東洋の道徳と西洋の道徳との間の争ひになつてくる。或は、かう言つた方がよい。どちらのモラールの方が、世界歴史の中で将来、より重大な意義を荷なつてくるかの問題なのだ。従来のヨーロッパの文明に対し、どういふ風に東洋の文明を生かしていくか、といふこともあるけれども、一層根本的には、東亜の新しい道徳といふものが大事だと思ふ。〔……〕こゝに現代のモラールの問題の世界史的意義があり、逆に現代の世界史的な課題、或は位置づけといふものからして、新しい大東亜の倫理の内容が考へられる。世界歴史の危機は案外に倫理的な危機であり、だからそれはモラリッシュ・エネルギーを必要とする」【同上書 p. 28-29 の引用による。】。
世界史における「西と東」の対立と、その中での日本の積極的な「貢献」というモティーフは、この時代の西田幾多郎自身の思想にも明確に現われていた。たとえば、昭和八年(一九三三年)二月号の『改造』に掲載された「知識の客観性」と題する論稿で、西田はこんなふうに書いている。
……我国は明治以来孜々として西洋文化を取り入れた。無造作に和魂洋才などと云ふ人は、それらのものを唯、道具の如く用ゐ得ると思うて居るかも知れない、併しそれ等のものはそれぞれの精神を有つたものである。〔……〕
現在の日本は世界の日本として世界に示すものを有たねばならない。古今に通じ中外に施して悖らざるものを明にせなければならない。我々民族は我々民族の心の底から生み出された世界的思想を建設せなければならない。〔……〕世界的思潮に対して自己自身の立場から世界的思想を扱ふことができて、而して後我々は世界的日本として外、世界を服せしめ、内、人心を統一することができるのである。〔……〕私は東洋文化の根柢には、西洋文化に対抗すべき深大なるものがあると信ずるものである。今日の西洋文化はギリシアとユデヤの二大思潮の合流に基くものと思ふが、我々は更に東洋文化の流を加へることによつて世界的に貢献せねばならない。東洋文化の根柢に横たはる世界観人生観といふものは、ギリシア及びユデヤの孰とも異なつたものであり、而も最も深き人間性の一面を示して居るものと考へることができる。〔……〕我々は貴き金属を含む東洋文化の鑛石を近代的に精錬せなければならない。〔……〕我々は過去の日本人の思想を祖述するのみならず、現在の日本人の中に萌え出る思想の芽生を尊重せなければならない。現在の日本人の仕事に同情し、現在の日本人の仕事を育て上げて行かなければならない……【廣松渉、前掲書 p. 203-204 の引用による。】。
昭和八年の状況では、「日本の貢献」は文化の次元で語られていた。しかし、それから数年の後には、まさに「世界史の現実」そのものが問題になってくる。
古代のペルシャ戦争もポエニ戦争も、たしかに「西と東」の優劣を決する「世界的」戦争だったかもしれない。しかし、この場合の「世界」とは、まだ真の地球大の世界ではなく、ヨーロッパ的世界史観の中の小さな「世界」でしかなかった。「大東亜戦争」は、その意味で、はじめて真に地球規模の世界、「世界的な世界」を「実現」するための戦争である……。それはもちろん、「西と東」の対決であるが、その目的は、単純に一方の勝利と他方の消滅を決することにあるのではなく、むしろその両者を、それぞれの独自性を損なわぬまま、それぞれの「世界史的使命」という目的に向けて統合し、そうして真の「八紘一宇」の理念を「実現」することにある。――西田幾多郎が昭和一八年(一九四三年)「国策研究会」で行なった講演を文章化した「世界新秩序の原理」では、「世界」という語がほとんど呪文のように繰り返されている。
今日の世界は、私は世界的自覚の時代と考へる。各国家は各自世界的使命を自覚することによつて一つの世界史的世界即ち世界的世界を構成せなければならない。これが今日の歴史的課題である。第一次大戦の時から世界は既に此の段階に入つたのである。然るに第一次大戦の終結は、かゝる課題の解決を残した。そこには古き抽象的世界理念の外、何等の新らしい世界構成の原理はなかつた。これが今日又世界大戦が繰返される所以である。今日の世界大戦は徹底的に此の課題の解決を要求するのである。一つの世界的空間に於て、強大なる国家と国家とが対立する時、世界は激烈なる闘争に陥らざるを得ない。科学、技術、経済の発達の結果、今日、各国家民族が緊密なる一つの世界的空間に入つたのである。之を解決する途は、各自が世界的使命を自覚して、各自が何処までも自己に即しながら而も自己を越えて、一つの世界的世界を構成するの外にない。私が現代を各国家民族の世界的自覚の時代と云ふ所以である。各国家民族が自己を越えて一つの世界を構成すると云ふことは、ウィルソン国際聨盟に於ての如く、単に各民族を平等に、その独立を認めるという如き所謂民族自決主義ではない。さういう世界は、十八世紀的な抽象的世界理念に過ぎない。かゝる理念によって現実の歴史的課題の解決の不可能なることは、今日の世界大戦が証明して居るのである。いづれの国家民族も、それぞれの歴史的地盤に成立し、それぞれの世界史的使命を有するのであり、そこに各国家民族が各自の歴史的生命を有するのである。各国家民族が自己に即しながら自己を越えて一つの世界的世界を構成すると云ふことは、各自自己を越えて、それぞれの地域伝統に従つて、先づ一つの特殊的世界を構成することでなければならない。而して斯く歴史的地盤から構成せられた特殊的世界が結合して、全世界が一つの世界的世界に構成せられるのである。かゝる世界的世界に於ては、各国家民族が各自の個性的な歴史的生命に生きると共に、それぞれの世界史的使命を以て一つの世界的世界に結合するのである。これは人間の歴史的発展の終極の理念であり、而もこれが今日の世界大戦によつて要求せられる世界新秩序の原理でなければならない。我国の八紘為宇の理念とは、此の如きものであらう。畏くも万邦をしてその所を得しめると宣らせられる聖旨も此にあるかと恐察し奉る次第である。十八世紀的思想に基く共産的世界主義も、此の原理に於て解消せられなければならない【西田稿「世界神秩序の原理」、『西田幾多郎全集』第十二巻(岩波書店、一九六六年)p. 427-429 (傍点・原文) ; この文章の由来については同書 p. 470-473 参照。】。
「古き抽象的世界理念」によって構成されていた世界が、すなわち近代世界、「超克」されるべき近代世界だった。西田がここに言う「八紘為宇の理念」は、柄谷行人氏が指摘されているとおり、ライプニッツ的な「個が個でありながら全体を表出するというモノドロジーの原理」に相当すると考えられるだろう。しかし、それはより直接的には聖徳太子の「十七条憲法」の「和」の原理であり、華厳の「事事無礙の世界観」に基づくものとも考えられる。にもかかわらず、柄谷氏が正しく指摘されているように、「西田が、これが『人間の歴史的発展の終極の理念』であるといい、『今日の世界大戦によつて要求せられる世界新秩序の原理』を達成するための闘争(戦争)を必然化するとき、ヘーゲル的である」。なぜそうなるのか。「それは『終り』をもちこむから」(柄谷氏)であると同時に、「世界」(「西と東」によって構成される「世界」)をもちこみ、「世界史」をもちこむからである【柄谷行人、前掲論稿 p. 144-145 参照。――ライプニッツおよび仏教哲学に関しては、たとえば西田著『日本文化の問題』、『全集』同上巻 p. 316-318 ; p. 361-372 などを参照。】。「世界史的使命」を説く者は、「世界」に呪縛される。
いまの文に続けて、西田がさらに「ヨーロッパ民族に圧迫せられてゐた」「東亜民族の世界史的使命」を説き、「ペルシア戦争」の世界史的意義を説き、「万世一系の我国体」の優越を説くことは、「世界」すなわち<近代>世界に呪縛された者の論理として当然のことと言えるだろう。
今日の世界大戦の課題が右の如きものであり、世界新秩序の原理が右の如きものであるとするならば、東亜共栄圏の原理も自ら此から出て来なければならない。従来、東亜民族は、ヨーロッパ民族の帝国主義の為に、圧迫せられてゐた、〔……〕各自の世界史的使命を奪はれてゐた。今や東亜の諸民族は東亜民族の世界史的使命を自覚し、各自自己を越えて一つの特殊的世界を構成し、以て東亜民族の世界史的使命を遂行せなければならない。これが東亜共栄圏構成の原理である。今や我々東亜民族は一緒に東亜文化の理念を提げて、世界史的に奮起せなければならない。而して一つの特殊的世界と云ふものが構成せられるには、その中心となつて、その課題を擔うて立つものがなければならない。東亜に於て、今日それは我日本の外にない。昔、ペルシア戦争に於てギリシアの勝利が今日までのヨーロッパ世界の文化発展の方向を決定したと云はれる如く、今日の東亜戦争は後世の世界史に於て一つの方向を決定するものであらう。
今日の世界的道義はキリスト教的なる博愛主義でもなく、又支那古代の所謂王道といふ如きものでもない。各国家民族が自己を越えて〔……〕世界的世界の建築者となると云ふことでなければならない。我国体は単に所謂全体主義ではない。皇室は過去未来を含む絶対現在として、皇室が我々の世界の始であり終である。皇室を中心として一つの歴史的世界を形成し来つた所に、万世一系の我国体の精華があるのである。我国の皇室は単に一つの民族的国家の中心と云ふだけでない。我国の皇道には、八紘為宇の世界形成の原理が含まれて居るのである【『西田稿「世界神秩序の原理」p. 429-430. ――「皇道」や「八紘為宇」に関して、西田は『日本文化の問題』(p. 340-341) で次のように書いている。「我国の国民思想の根柢には、肇国の事実があった〔……〕。皇室と云ふものが矛盾的自己同一的な世界として過去未来を包む永遠の今として、我々が何処までもそこからそこへと云ふのが、万民輔翼の思想でなければならない」。「……併し今日の日本はもはや東洋の一孤島の日本ではない、〔……〕世界の日本である。〔……〕此処に現今の大なる問題があると思ふ。最も戒むべきは、日本を主体化することに外ならない。それは皇道の覇道化にすぎない、それは皇道を帝国主義化することに外ならない」。「……我々は我々の歴史的発展の底に、矛盾的自己同一的世界そのものの自己形成の原理を見出すことによつて、世界に貢献せなければならない。それが皇道の発揮と云ふことであり、八紘為宇の真の意義でなければならない……」。】。
これを単純に、日本の全体主義的‐帝国主義的権力におもねる哲学と断罪することはできないだろう。事実、西田は、「大東亜戦争」がたんなる帝国主義的侵略戦争であってはならないことを、繰り返し訴えている。結果から見るならば、西田のこうした哲学が「日本帝国主義の東亜政策、ひいては世界政策をイデオローギッシュに追認しつつ、それを合理化するもの」(廣松渉、前掲書 p. 58)であったことは明らかだが、同時に西田自身としては、(象牙の塔の一学者としての)最大限の力を使って、この戦争の帝国主義的性格を修正しようと試みたことも事実だろう。また、こうした文章からもし「八紘為宇の聖旨」とか「万世一系の我国体の精華」などという<時代遅れの天皇神秘主義(?)>の用語を取り去り、「戦争」ということばを「経済戦争」または「経済競争」と読み換えるなら【とはいっても、実際にはこの<天皇神秘主義>を欠いた西田の<戦争哲学>はまったく成立しなくなってしまうかもしれないが……。】、これはほとんどそのまま、戦後五十年間、世界の「経済戦場」にいかなる(過労)死をも恐れない「経済戦士」を送り出し、ありとあらゆる「経済戦略」を駆使して「ジャパン・アズ・ナンバーワン」を築き上げてきたこんにちの日本の理想‐原理を述べたものと言ってもおかしくないとも思われる(事実、現在のいわゆる「新京都学派」の論者が展開する言説も、基本的にこれと変りないと言うことができるだろう)……【こうした論点は、松本健一氏の前掲書に大きく展開されていて興味深い。】。
にもかかわらず、こうして西田やその門下の学者たちが呪文めいたことばを唱えているうちにも、少なくとも一部にはそのことばによる正当化を心のよりどころにした兵士たちが戦場に出陣し、そうしてアジアの、アメリカの、日本の無数の人々が戦争の炎の中で悲惨な死をとげていったという事実を消すこはができない【そしてもちろん、戦後五十年、世界最大の経済大国の一つとなった日本が、(日本の「経済戦士」自身を含めた)数えきれないアジアの人々を苦痛と悲惨の中に投げ込んでいるという事実も消すことはできない。】。まさに犯罪的であり、悲劇的であり、狂気としか言いようがないのは、生涯を思索に賭けてきたこれらの学者たちが、こうした単純な事実を見る目を失い、彼らのことばが現実の人々を死に追いやる可能性があるということに対する恐れをいっさい忘れ去っていたということである……。
竹内好は、京都学派の哲学のこうした性格を批判して、西田門下の最大の論客の一人であり、昭和十七年に大著『世界史の哲学』(岩波書店刊)を著した高山岩男の戦後のことばを引きながら、こう書いている。
京都学派にとっては、教義が大切なのであって、現実はどうでもよかった。〔……〕事実は眼中になかった。「私は自分が世界史の根本理念としたものに誤謬があったとは思わない。私は戦争の有無や勝敗によって左右されるような理念を考えたのではないからである」(高山岩男「世界史の理念」、『理想』一九五一年六月号)。まさにそのとおりだと私も思う【前掲書 p. 96.】
これは「まさにそのとおり」であると同時に、実は決して「そのとおり」ではないだろう。たしかに、西田や高山、あるいは高坂などが構築したのは、「理念」であり、「哲学」であり、さらにいうならば「机上の空論」だった。たとえば、『世界史の哲学』の最終章に「歴史創造の業に顕現して而も歴史を超出してゐる永遠は、絶対の無である。それは論理的思惟を超越せるものとして概念的言表を拒否するもの、何らの意味でも対象的・客体的に捉へ得ないものでなければならぬ……」などなどと書く場合(前掲書 p. 536)、高山の言説はまったくの思弁であり、「戦争の有無や勝敗によって左右されるような」哲学ではなかっただろう。しかし、その同じ著書の「序」の冒頭に、
今日の世界大戦は決して近代内部の戦争ではなく、近代世界の次元を超出し、近代とは異なる世界を劃さうとする戦争である。〔……〕今次のヨーロッパ大戦は近代に終焉を告げる戦争であり、またさうなければならぬ。このことは我が日本を主導者とする大東亜戦争では極めて明白であつて、何らの疑義をも挟まない。〔……〕昨年十二月八日、対米英宣戦と共に疾風迅雷の如く開始せられた大東亜戦によつて、旧き近代の世界秩序を打破し、新たな世界秩序を建設しようとする精神は、愈々本格的な姿を現し、これは今日の世界史の趨勢にもはや動かすべからざる決定的方向を与へるに至つた……【高山岩男著『世界史の哲学』 p. 1-2.】
と書く高山は、その「世界史の哲学」について「戦争の有無や勝敗によって左右されるような理念ではなかった」とは決して言えないはずである。歴史を理念化し、その理念を歴史化(=「実現」)しようとする――それが、高山の「世界史の哲学」であり、西田の「世界新秩序の原理」であり、そしてそれがヘーゲルの歴史哲学の原理であったことは、もはや言うまでもないだろう。
それがまた、<近代>そのものの原理であり、ほかならぬその原理に基づく者が、「近代の超出」や「近代の終焉」、「近代の超克」、「人間の歴史的発展の終極」あるいはまた「ポストモダン」の理念を説くのである……。
明治以来、太平洋戦争の末期まで、日本のオリエンタロ‐オクシデンタリズム的思想構造は、ドラマティックな緊張の度合を高める一途をたどってきたように思われる。その緊張の頂点におけるもっとも顕著な表現が、たとえば先に引いた大川周明の終末論的東西最終戦論であり、また京都学派を中心とした「近代の超克」論だったことは明らかだろう。
戦後のはじめの数十年、こうしたオリエンタロ‐オクシデンタリズム的な思想の緊張度は、一気に下がっていったように思われる。あらためて「追いつき追い越せ」の時代に入った日本は、「世界」を見ることをまったく中断し、ただやみくもに新たな<近代化>を目指して突き走っていった。そこで何よりもまったく見落とされていたのは、「東洋」の存在だった。「東洋」に対して目をつぶったからこそ、「世界」が存在しなくなっていたのである。そうした状況に変化のきざしが見えてくるのは、六〇年代後半、「所得倍増」の狂奔が一きりつき、一方でヴェトナム戦争が荒れ狂い、もう一方でアメリカを中心としたカウンター・カルチャーの波の中から、「ネオ・オリエンタリズム」とも言えるような新たな東洋志向のオカルト神秘主義の潮流が台頭してきた頃からである。こうして、右翼も左翼もひっくるめた新しい反近代主義の波の中から、あらためてエグゾティックでおどろおどろしい「魅惑する東洋」の姿が現われてきた……。
熾烈な経済戦争に勝ち抜いてきた日本は、八〇年代前半あたりからあらためて「世界」の舞台に踊り出てきた(たとえば大平内閣の「国際化論」、一九八〇年)。しかしそのときには、「西洋」は事実「没落」の状態にあったし、また資本と情報のネットワーク化によって「世界」は事実一種の「一体」の形をとるようになっていた。そこでは、古典的なオリエンタロ‐オクシデンタリズム的世界表象の構造が、他のすべての問題意識に優先するような状況は薄れてきていると言うべきかもしれない。だからこそ、「『ジャパン・アズ・ナンバーワン』として世界の最前線を疾駆する現在の日本の『オリエンタリズム』=日本回帰、東洋回帰の思想は、ほとんど卑屈なまでに欧米製『〔ネオ・〕オリエンタリズム』の焼き直しでしかない。東洋の神秘を称揚し、あやしげな『全体性』や『自然』や『本能』の復権を唱え、オカルト・ブームに『最新の物理学』を搗き混ぜる。――『ポスト・モダン』時代の『近代の超克』は、六〇年代のヒッピー思想以後の〔……〕反近代‐反理性主義の大潮流の中で、時代にふさわしく軽佻浮薄、そしてそれゆえに重大な危険、激しい毒を秘めている」……【拙稿「問題としてのオリエンタリズム」 p. 48-49.】。
先に引用した竹内好は、明治以来の近代日本の思想を決定してきた基本的な対立項を「復古と維新、尊王と攘夷、鎖国と開国、国粋と文明開化、東洋と西洋」という形で表現していた。現代の日本で(そしておそらく大部分の「先進国」で)これに対応する基本的な対立項は、たとえば次のように表わすことができるだろう。
理性主義/感性主義 合理主義/神秘主義 テクノロジー礼賛/自然・エコロジー礼賛 進歩主義/保守主義 個人主義/全体主義 機械論/生気論 自由/規律 ロゴス中心主義/パトス中心主義 知/情念 意識/無意識 (各種の)二元論/(各種の)一元論 男性性/女性性…… そしてもちろん 近代主義/反(または超)近代主義 西洋/東洋……【拙著『歴史という牢獄』 p. 16-17 and n. 1 参照。】
これらの対[つい]は、すべて<近代>を構成する基本的な対立項である(それゆえ、もちろん、「近代主義」と「反(または超)近代主義」は、ともに弁証法的‐熱力学的な対立関係を結びながら、<近代>をどこまでも再生産していく「もと」である)。この一連の対立項の関係で特に重要なのは、各対の第二の項(神秘主義、生気論、反〜超近代主義、東洋……など)が、――本来、両項の弁証法的対立によって両項そのものが存在しつづけるにもかかわらず――基本的に、両項の対立を一段と高い次元で「止揚」し、「超越」するもののように考えられていることである。
「大きな物語が終った」ことを宣言する<近代>が始まってから少なくとも二百年が経ち、オリエンタロ‐オクシデンタリズムの構造によって(少なくとも日本において)世界が閉じられてから、百数十年が経った。オリエンタロ‐オクシデンタリズムが、中世的な起源をもちながら、<近代>を支える主要な支柱の一つになってきたことは、ここに書いてきたことだけでも充分に明らかだろう。その<近代>は、「永遠に先送りされる終焉」に向けてひた走る資本主義【柄谷行人著『終焉について』所収「歴史の終焉について」(福武書店、一九九〇年)参照】そのものとともに、永遠に先送りされる「人間の歴史的発展の終極」へ向けて、人々の、国家の、世界の「世界史的使命」を追い求めていくだろう。<近代>を終らせようとするものは、即、<近代>に絡め取られる。ぼくたちにできるのは、最大限の冷静な理性をもって<近代>に生きる自分自身を見つめ、批判し続けていくことでしかないだろう。
六〇年代カウンターカルチャーは、いまや「カウンター」からほど遠い、押しも押されぬメジャーの思想に成り上がってきた。ソ連が崩壊し、日本のバブルが見事にはじけ、そして世界のそこここで原理主義的な民族主義による闘争の炎が燃え上がっているいま、「軽佻浮薄」なポップ文化は、見る見るうちに行き先を知らない攻撃性を秘めた、暗い不安の様式[スタイル]に暗転しようとしているように思われる。地底に潜んでいた「歴史」のもがきが感じられるいま、日本と世界の<近代>を形作ってきたオリエンタロ‐オクシデンタリズムの歴史を振り返り、その新たな動きを監視すること――。そうすることによって、ぼくたちは「超越的歴史」という怪物の正体を、少しずつでも見極めていくことができるのではないだろうか。
1992 年 10 月 23 日
This page was last built with Frontier on a Macintosh on Wed, Sep 10, 1997 at 19:31:18. Thanks for checking it out! Nobumi Iyanaga