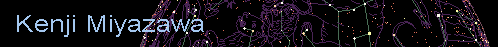
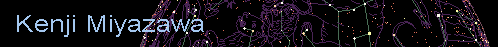
 「宮澤賢治と星」から
「宮澤賢治と星」から
 |
 小さな水精のお宮
小さな水精のお宮
チュンセ童子とポウセ童子が住むという双子のお星様のお宮が、「小さな水精(初期形では「水晶」)のお宮」です。
最近各地で開催された「宮沢賢治の世界展」にも展示されていましたが、この書きだしの部分で賢治が何度か校正を加えています。
新校本全集の校異編などの記載からすると、この「水精のお宮」は、
とあります。 そしてその主要な説は、
ですが、いずれも天の川のそばにあります。 各説ごとのポイントをまとめてみましょう。
| 各説 | 位置 | 星座図/特徴 | 主な根拠( 肯定要因/ 肯定要因/ 否定要因) 否定要因) |
ふたご座 | 天の川の東側 | 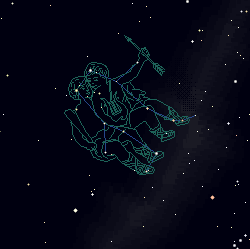 黄道十二星座の一つ |
 名称が同じ「双子」である。 名称が同じ「双子」である。 賢治はこの童話の中で星座名を多用している。 賢治はこの童話の中で星座名を多用している。 「小さな小さな」とか「胞子」のような星ではない。 「小さな小さな」とか「胞子」のような星ではない。 |
さそり座の尾の星 | 天の川中央 | 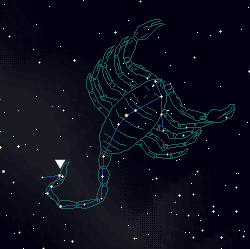 さそり座の尾の星 |
 「すぎなの胞子ほどの小さな星」や「小さな小さな二つの青い(青白い)星」にイメージが合う。 「すぎなの胞子ほどの小さな星」や「小さな小さな二つの青い(青白い)星」にイメージが合う。 童話「銀河鉄道の夜」で引用されているが、出てくる場所が、ちょうど「さそりの火(アンタレス)」の近くである。 童話「銀河鉄道の夜」で引用されているが、出てくる場所が、ちょうど「さそりの火(アンタレス)」の近くである。 さそりを元の居場所に連れて行った時に、自分達のお宮に帰る心配をするが、さそりの尾の星であれば戻るのに心配する必要はない。 さそりを元の居場所に連れて行った時に、自分達のお宮に帰る心配をするが、さそりの尾の星であれば戻るのに心配する必要はない。 |
二重星団 | 天の川中央 | 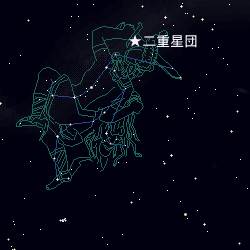 ペルセウス座のh・χ (エイチ・カイ) |
 「すぎなの胞子ほどの小さな星」や「小さな小さな二つの青い(青白い)星」にイメージが合う。 「すぎなの胞子ほどの小さな星」や「小さな小さな二つの青い(青白い)星」にイメージが合う。 初期形にある「青じろくて少しけむって見え...」の表現に良く一致し、肉眼でも淡く見える。 初期形にある「青じろくて少しけむって見え...」の表現に良く一致し、肉眼でも淡く見える。 童子の名前ポウセは、二重星団のあるペルセウス(Perseus)と似ている。 童子の名前ポウセは、二重星団のあるペルセウス(Perseus)と似ている。 童話「銀河鉄道の夜」で引用された場所と大きくかけ離れている。 童話「銀河鉄道の夜」で引用された場所と大きくかけ離れている。 |
とあります。
星好きの方ならもう「かんむり座」の半円形の星の並びを想像しながら想いえがいていることでしょう。
天の川との位置関係もほどよい場所にあり、上記に引用した二人の童子の歌のとおりです。
この辺りは、どの賢治本を見ても異論がないところでした。
ただ、「宮沢賢治語彙辞典」(3)では、「みなみのかんむり座」についても言及していました。
天の川の西側という点に注目すれば、やはり「かんむり座」でしょう。
「かんむり座」は古代ギリシャでは「ステファノス」、つまり「リース」「緑の葉で作った輪」と呼ばれていました。
歴史は古くプトレマイオスの48星座にも含まれていたといいますから、よほどその並びが目をひくものだったと言えます。
日本でも「車星」「太鼓星」「首飾り星」(野尻抱影著「日本星名辞典」(4))と固有の呼び名を持ち、古くから親しまれていたことはそれを裏付けるものと言えましょう。
また、いて座のそばにも「かんむり」と名が付けられた星座があり、これを「みなみのかんむり座」そして北にある方を単に「(北の)かんむり座」と区別しています。
(1)草下英明著「宮澤賢治研究業書1 宮澤賢治と星」学芸書林 空の泉
空の泉
二人の童子が楽しそうに空を行くと、「空の泉」にたどり着きます。
「空の泉」ってどこでしょうか?
その特徴について書かれた場所を抜粋すると、
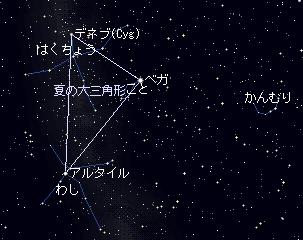
賢治はそんな星を「空の泉」そして「そらの井戸」と名付け、天の川に流れ込む小さなきれいな泉にしました。余談ですが、
詩「〔温く含んだ南の風が〕」の異稿にも「空の泉」が登場しています。
まだ見たことのない方は、ぜひ暗い夜空のもとで探してみて下さい。 天の大烏の星、蠍の星、兎の星
天の大烏の星、蠍の星、兎の星
続いて星座名の動物(?)たちの大出演です。さそりはすでに登場済(次項目参照)ですので、大烏の星と兎の星についてふれてみましょう。
大烏とは「からす座」からの連想でしょうか。
賢治はそれに「大」という形容をつけ、まっくろなびろうどのマントと股引(ももひき)をはかせ登場させています。
なんともユニークな発想ですね。
星座神話では主人に嘘をついて黒くされ天に釘で打ち付けられてしまった哀れな烏の姿が描かれています。
兎は、「うさぎ座」からの引用のようです。
冬の代表する有名な星座「オリオン座」のすぐ下にある星座です。
暗い星しかありませんが、星をていねいに結ぶとなんだか兎の姿に見えてくるから不思議です。
からす座

うさぎ座
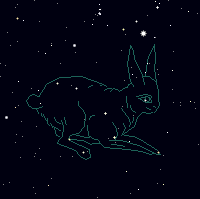
- 注 -
(2)竹内薫・原田章夫著「宮沢賢治・時空の旅人」
(3)原子朗編著「宮澤賢治語彙辞典」東京書籍
(4)野尻抱影著「日本星名辞典」東京堂出版
▲賢治の星の話題ヘ戻る
△双子の星(1)
△双子の星(2)
![]()
メインページへ![]()
宮沢賢治のページへ![]()
☆星のページへ![]()
△山のページへ