党 独 裁 論 か ら 党
・ 国 家 官 僚 制 へ
──超工業化・全面的集団化の過程で定着する党・国家システム
堀込 純一
<目次>
はじめに
ソ連経済における党の位置と役割
党独裁と階級独裁の関係
(1)ロシア・マルクス主義者の党独裁論
(2)党内闘争の激化と書記局位階制の形成
(3)スターリンのプロレタリアート独裁論
(4)スターリンの伝導ベルト論
戦時共産主義とネップ(NEP−新経済政策)
(1)現物経済としての戦時共産主義
(2)混合経済としてのネップ
「上からの革命」期の統治構造
(1)穀物調達危機と非常措置
(2)非常措置の恒常化と強制的集団化へ
(3)超工業化と官僚主義的計画化
(4)急増する労働者と労組の国家機関化
(5)ソヴィエトの超中央集権化と形骸化
党に従属する司法と革命的合法性
固定化する党・国家官僚制
(1)党・国家システムの確立
(2)党・国家システムの下請けとしての社会諸組織
(3)党のヒエラルヒーとノメンクラトゥーラ制
おわりに
はじめに
ソ連経済の構造、その性格を見極めるうえで、生産手段の国有・経済計画とともに、政治とくに党の位置、役割は重要な柱、あるいは重要な枠組みであり、これを欠落した場合は、ソ連経済の階級性を正しく解明することはできない。党を中心とする政治は、経済システムに不可欠な位置を占めており、ソ連経済分析の前提条件である。
以下では、ソ連経済における党の位置・役割を分析し、さらに何故にこのような制度が形成されたかを歴史的にさかのぼり検討する。
ソ連計画経済における党の位置と役割
資本主義経済の無政府性・自然発生性に対置されるソ連経済では、生産手段の国有・集団所有を前提に、目的意識性としての経済計画がなされた。この計画は、あくまでも党の政治路線・当面の政治方針にそったものである。
形式的には党の基本方針は、連邦議会での採択を通して公的な方針となる。しかし、その連邦議会自身、構成する議員の選出方法に問題がある。人民主権に基づく自由な選出・解任ではなく、党の推薦、操作による選出だからである(ソヴィエト代議員は、個人的には立候補できず集団の推薦が必要である1))。
党による経済の支配・統制は、当然にも計画段階にのみ止まらない。執行段階でも常時、各級段階の党の監視・統制がある。
そして、計画段階、執行段階でのそれらの活動の担い手もまた党によって、任命・統制されている。あとで詳述するノメンクラトゥーラ制度こそがこの人事方法の柱となっている。以上にみられるように、ソ連経済においては党組織とその活動なくしては経済は運営できない。
ソ連の各種憲法にみられる民主的な国家機構の規定も、すべてこの党の「指導的役割」なるものが全社会をおおっているため、空文に帰している。36年憲法(いわゆるスターリン憲法)では、党の規定は、第10章「市民の基本的な権利と義務」の第126条で「労働者階級、勤労農民および勤労的インテリゲンチャの陣列のなかで、もっとも積極的で、もっとも自覚した市民は、共産主義社会建設の闘いにおける勤労者の前衛であり、勤労者のすべての社会的および国家的な組織の指導的中核であるソビエト連邦共産党に、自発的に団結する。」となっている。
フルシチョフ時代、個人崇拝を中心としてスターリン批判がおこなわれたが、ブレジネフ時代に採択された77年憲法においても、「党の指導的役割」は変化せず、憲法上の規定ではむしろ36年憲法以上に明確にされている。すなわち、「第一編
ソ連邦の社会体制および政治の基本原則」の「第一章
政治制度」の第六条で「ソビエト社会の指導的かつきょ
う導的な力、ソビエト社会の政治制度、国家機関と社会団体の中核は、ソビエト連邦共産党である。‥‥マルクス=レーニン主義の学説で武装した共産党は、社会発展の全般的展望、ソ連邦内外政策の路線を決定し、ソビエト人民の偉大な創造的活動を指導し、共産主義の勝利をめざすソビエト人民の闘争に計画的な、科学的に根拠づけられたものとしての性格を与える。‥‥」という規定である。
「党の指導的役割」規定を憲法から削除するのは、ソ連崩壊直前の1980年代末であるが、
1930年代に形成・確立したソ連型経済・社会では、社会から超越し、法的にも超越したのが党である。
しかし、この点がソ連社会の根本矛盾であり、ソ連社会を短命に終わらせた最大原因の第一である。つまり、私的なものである党を公的組織(政治であれ、経済であれ)のトップとする体制の矛盾である。すべての分野にわたる路線・政策の決定権を党が排他的に独占するという体制は、党自身が私的なものであるが故に、決定過程に全人民が構造的に参加できない体制である。このことはいかに憲法で明記しようと(憲法に党の指導的役割を明記したことを形式的にとらえれば、公的活動を実質上党のみに「永遠に」、無条件で白紙委任したことを意味する)、公的なものが公的に活動することを完全に封じたということである。
ではこのよう反人民的な体制はいつ、どのように形成されたのであろうか。
注1)ソヴィエト代議員の選出方法は、藤田勇著『社会主義社会論』(東京大学出版会)
によると、以下の通りとなっていた。「ソビエト(連邦最高ソビエト、共和国お
よび自治共和国の最高ソビエト、各級地方ソビエト)の代議員は、それぞれ所定
の人口基準で、人口何人につき一名という割合で選出される。所定の人口数ごと
に選挙区が構成され、各選挙区の代議員定数は一名ということになる。現行の77
年憲法でも、候補推せん権は団体(共産党組織、共産青年同盟組織、共同組合そ
の他の社会団体、生産単位の労働集団、部隊ごとの軍人集団)に帰属することに
なっているのであるが、そのさい、法律上は複数の候補が推せんされるものと想
定されている。ところが、普通選挙制に変った36年憲法による最初の連邦最高ソ
ビエト選挙(1937年)のときから、各推せん団体が統一候補を立てるという運動
が組織され、それが慣行として定着して今日にいたっている。一党制のもとで共
産党員と非党員とが選挙で争うという形を避け、党員と非党員との選挙ブロック
をつくって統一候補を立てるという形を重視したものである。この方式のもとで
は、ある団体の推せん候補が他の諸団体によって支持されるという過程を含めて、
各推せん団体によって構成される選挙区ごとの選挙前協議会において最終的に候
補者が一人に絞られるのである」。
本論で詳述するが、党・国家官僚制の体制
下では、各種団体も党指導部によって支配・統制されているので、結局、普通選
挙という民主的な装いを形式的にもったとしても、各種議会も、党指導部によっ
て支配されるのである。
党独裁と階級独裁の関係
私的なものが公的なものの中核をしめ、公的体制を歪曲する体制のキッカケは、ソ連の歴史をさかのぼると、1党制を前提にした、いわゆる党独裁論にいたる。党独裁と階級独裁に関係する公然たる論争は、ジノブィエフとスターリンの論争が有名である。
(1)ロシア・マルクス主義者の党独裁論
この論争をみる前に確認しなければならないのは、ロシア・マルクス主義者の指導的メンバーのほとんどは、レーニンをはじめとして、党独裁を容認していたことである。
レーニンは、党とプロレタリアート独裁の関係について、「党は、プロレタリアートの前衛をいわば吸収し、この前衛がプロレタリアートの独裁を実現するということになる。」
1)といっている。だが時には論争口調で「彼ら(メンシェヴィキやエスエルのこと−引用者)が一党の独裁だとわれわれを非難して、諸君もお聞きのように社会主義統一戦線なるものを提案するとき、われわれはこう言う。『その通り、一党の独裁だ!われわれは一党の独裁のうえに立っているし、この基盤からはなれるわけにはいかない。』」2)と、「一党の独裁」という表現もつかっている。
しかし、レーニンは1920年7月の共産主義インターナショナル第二回大会でイギリス代表タナーの発言(タナーは、プロレタリアートの独裁は支持するが、レーニンらの考えるそれには賛成できないというもの)に関連して、次のように言っている。資本主義による搾取・抑圧により「ほんとうに自覚した労働者は、全労働者の少数を占めているにすぎない‥‥。だから、われわれは、この自覚した少数者だけが広範な労働者大衆を指導し、率いていくことができるというを、みとめざるをえない。自分は党の敵であるが、しかもそれと同時に、もっともよく組織された、もっとも革命的な労働者の少数者が全プロレタリアートに進路をしめすことには賛成であると、同志タナーが言うならば、われわれのあいだには、実際には違いはないのである。組織された少数者とは、なんであろうか?この少数者が、ほんとうに自覚しており、大衆を率いていく能力があり、日程にのぼっている一つ一つの問題に解答をあたえることができるならば、その少数者は、実質的には党である。
」「もし、少数者が大衆を指導し、大衆と緊密に結びつくことができないならば、たとえ、
その少数者が党と自称し、あるいは職場世話役委員会全国委員会と自称しても、それは党ではなく、まったくなんの値うちもないものである」と。
以上のレーニンの発言をみると、真意は、“「党の独裁」というよりも、プロレタリアートの真の前衛がプロレタリアートを指導し、独裁を実現する”という点にあるといえる。
しかし、ボリシェヴィキ指導者のあいだでは、手っ取り早く「党独裁」の語が独り歩きする。
トロツキーは、内戦のさなかに、カウツキーに反論して「われわれは、一度ならずソヴィ
エトの独裁を党の独裁によって置き換えたといって非難されてきた。だが、ソヴィエト独裁が党独裁によって初めて可能になったということは、全く正しいのだ」3)といっている。
また、「労働者民主主義の見地からレーニン、トロツキー等の中央指導部を痛烈に批判した労働者反対派の指導者シリャープニコフも、『プロレタリアート独裁、その前衛すなわちわが党の独裁』という点については何の異論もないと述べている」4)と、いわれる。
厳密にいえば、「前衛による独裁」と、「党の独裁、あるいは一党独裁」とはおなじではない。「前衛による独裁」の場合は、一党、複数党だけでなく、無党派の先進分子もふくまれる。ただロシア革命の過程は、主客の諸条件によってボリシェヴィキ一党になってしまっただけである。この問題について、当時のボリシェヴィキは必ずしも自覚的とは言えない。すなわちこの問題についての十分な組織討議はなされていないからである。
資本主義の発達の遅れていたロシアでは、10月革命時点でそもそも工場プロレタリアートが少なかったこと、さらに内戦、帝国主義干渉との戦いで先進的プロレタリアートの戦死、戦時の食料欠乏での階級脱落などによって、ソヴィエト権力を維持するためには党が全面的に権力を担わざるを得なかったことによる。ただエスエルとの統一戦線の破綻、ボリシェヴイキにセクト主義がなかったかどうか、などの点については総括が必要であろう。
しかし、マルクスには党独裁の概念はなく(マルクスの時代、未だ近代的政党は未発達だった)、マルクスは“プロレタリアートの解放は、プロレタリアート自身の事業である”という思想を重視している。このことからみると、いわゆる党独裁は、ロシア革命の苛酷な過程が強制したもので、一時的な(プロレタリアート独裁の)代行措置とみるべきである。
だが、ボリシェヴィキの指導者たちがこの点で必ずしも自覚的であったとはいえないであろう。5)
注1)レーニン著『労働組合について、現在の情勢について、トロツキーの誤りについ
て』1920年12月 レーニン全集第32巻大月書店
2)レーニン著『教育活動家および社会主義文化活動家第一回ロシア大会での演説』
1919年7月 レーニン全集第29巻
3)トロツキー著『テロリズムと共産主義』
4)塩川伸明著「スターリンのプロレタリアート独裁論」─『思想』1977年12月号
5)党独裁論の前提には、一党制の問題がある。一党制にいたる経過を簡単に述べる
と、以下のようになる。ブルジョア政党カデットが、「人民の敵の党」として人
民委員会議の法令によって禁止されるのは、1917年11月末である。これはカデッ
トがカレーディンの反革命蜂起を公然と支持したためである。
エス・エルとメンシェヴィキは、10月革命でのソヴィエトの権力奪取を認めず、
憲法制定会議に固執した。この2党との交渉を続けるか否かで、ボリシェヴイキ
中央は分裂し、何回かの討議と採決のすえ、レーニンの提案(2党を中心とする
ソヴィエト少数派の威嚇や最後通牒に譲歩することは誤りであり、多数派の意志
をねじ曲げるものというもの)がようやく12月2日に通る。しかし、ここでは
「中央委員会は第2回全ロシア・ソヴェト大会から1人の除名者も出さず、大会
から引揚げた人びとを呼び戻し、ソヴェトの制限内でそれらの人びととの同盟を
認めるのに万全の準備態勢を今もとっていることを確信する。したがってボリシェ
ヴィキは何人とも権力を分かちもつことを望まないのだとする主張は絶対に間違っ
ていることを中央委員会は断言する。」(シャルル・ベトレーム著『ソ連の階級
闘争 1917−1923』第三書館からの重引)と、一党制の考えを微塵ももっていな
い。現実に革命政府は、17年12月12日の協定でボリシェヴィキと左派エス・エル
の連立政府としてはじまり、これは18年2月末まで続く。1918年4月、日本軍の
ウラジオストック上陸により外国の干渉が開始され、それとともにソヴィエト政
権に不満をもつ勢力の活動が活発化する。同年6月14日、全ロシア中央執行委員
会は、労働者農民に武力攻撃を組織しようとする反革命集団との協力という理由
で、右派エス・エルとメンシェヴィキをソヴィエトから追放すると決議した(エ
ス・エルはすでに戦時中に分裂しているが、左派エス・エルは1917年11月に結成
大会をひらいている)。
だがその後、左派エス・エルはボリシェヴィキが強行しつつあった食糧徴発政
策とドイツとの単独講和に強い不満を表明する。ボリシェヴィキと左派エス・エ
ルの劇的対立は、18年7月6日の左派エス・エル党員であるチェカ(全ロシア非
常委員会。「反革命および怠業と闘う」のを目的として1917年12月に設立される。
チェカの副長官は左派エス・エル党員
)メンバーによるモスクワ駐在ドイツ大
使暗殺とそれに続くモスクワその他の地方での反政府暴動によって、公然化する。
チェカ員たる左派エス・エル党員13人は、銃殺となり、18年7月29日、全ロシア
中央委員会の決議は、大量的テロルを政策として採用することを明示した(溪内
謙著『現代社会主義の省察』
岩波現代選書)。左派エス・エルの反撃も凄まじ
く、ヴォルダルスキー、ウリツキーが暗殺されたほか、8月30日にはレーニンも
重傷を負う。9月2日、全ロシア中央執行委員会の決議は、「労農政府の敵によ
る白色テロに対して、労働者農民はブルジョアジーとその手先に対する大量赤色
テロを以て応えるであろう」と宣言した。以後、チェカを中心とする赤色テロは、
組織的計画的に展開される。だが、左派エス・エル全体が禁止された訳ではなく、
「反革命活動に加わった連中はソヴェトから除名され、蜂起に参加した場合には
逮捕される。‥‥テロ活動に参与しなかった左翼エス・エルの連中の活動は何ひ
とつ禁じられなかったし、彼らに対する抑圧は限定されたものであった」(ベト
レーム前掲書)といわれる。
レーニン時代は後にくらべれば未だ柔軟な政策をとっている。「メンシェヴィ
キやエス・エルの小ブルジョア党が、コルチャックとデニキンに反対行動をとっ
た1919年の終わりには、これらの党の合法的活動はふたたび許された。メンシェ
ヴィキとエス・エルの党の公然の活動は、クロンシュタット叛乱と、メンシェヴィ
キや、とくにエス・エルがもっとも積極的に参加したその他いくつかの反革命行
動ののちになって、不可能となったにすぎない。しかし、メンシェヴィキとエス・
エルの非合法組織は、多年のあいだいくつかの都市と農村地区に存在していたの
であり、ようやく30年代になって、国内では実際に完全に消失し、その活動をや
めた」(ロイ・メドヴェーデフ著『社会主義的民主主義』
三一書房)と、いわ れる。
溪内謙によると、「政党のうちで共産党一党のみをプロレタリアート独裁の権
力体系の有機的構成部分として位置づける見解が指導者の発言や公式の文書に明
示されるのは、著者の知るかぎり1919年以降であって、それ以前には、そのこと
を明確に否定する言明さえも発見することができる。」(『現代社会主義の省
察』)と、一党制と党独裁の時期的関係を述べている。
(2)党内闘争の激化と書記局位階制の形成
民主的中央集権派や労働者反対派などは、戦時共産主義の時代から行政指導、経済指導、
党活動などさまざまな分野について、労働者民主主義の観点からの批判をしていたが、ネッ
プ期(1921年から)にはいると、その批判は一層強まる。
ネップ(新経済政策)の導入を決定した第10回党大会(1921年3月8〜16日)の直前(1920年11月〜21年3月)、党はかつてのブレスト・リトフスク講和をめぐる大論争に匹敵する党内闘争(労働組合論争)を展開していた。この論争でブハーリンは、「労働組合の『国家化』とプロレタリアートのあらゆる大衆組織の事実上の国家化とは、転形過程そのものの内的論理から生ずるものである」1)という観点から労組の国家化を主張した。トロツキーは、労働者国家が雇用主であるから労働組合が労働者を擁護する必要はないといって、
労働組合の軍隊化を提唱した。トロツキーの軍隊化計画にもっとも強く反対したのは、組合の自治を唱える労働者反対派であった。民主的中央集権派はこれを支持した。この論争でレーニンは最初中間派であった。中央集権主義の崩壊を恐れるレーニンは、この2派にトロツキーとともに反対したが、論争の経過のなかで軍隊化と超中央集権主義に内在する官僚主義の危険を強調し、労働組合は「共産主義の学校」であるとして、トロツキー派(ブハーリン派と合同する)と公然と対決する。レーニン派はその巻き返しに成功し、ようやく多数を獲得した。
第10回党大会は戦時共産主義からネップへの転換を決定するとともに、分派の禁止を決定した。大会後の第一回中央委員会は中央人事を大きく変えた。それまで政治局員は、レーニン・トロツキー・スターリン・カーメネフ・クレスチンスキー、同候補ブハーリン・カリーニン・ジノヴィエフ、組織局員はプレオブラジェンスキー・クレスチンスキー・セレブリアコフ・スターリン・ルイコフ、書記局員はプレオブラジェンスキー・クレスチンスキー・セレブリアコフであった。それが今度は政治局員は、レーニン・トロツキー・スターリン・(ジノヴィエフ)・カーメネフ[カッコ内は新任。以下同じ]、同候補ブハーリン・カリーニン・(モロトフ)、組織局員はスターリン・.ルイコフ・(
モロトフ)・
(コマロフ)・(ミハイロフ)・(トムスキー)・(ヤロスラフスキー)、書記局員は(モロトフ−専任書記)・(ミハイロフ)・(ヤロスラフスキー)である。
特徴的なのは労働組合論争で勢力を減少させたトロツキー派が中央人事で大きく後退させたことである。とくに組織局・書記局で完全に力を失った。しかし、プレオブラジェンスキーは、その後の人選と比べてみてももっとも寛容な書記であったといわれる。
ネップは急進主義的な左翼共産主義者を幻滅させた。コムソモール(共産主義青年同盟)
は2年のうちに半減した。労働者反対派・民主的中央集権派などは、討論クラブを組織したが弾圧され解散させられた。(戦時共産主義に理想をかけ、ネップに幻滅するという現象は、党指導部にも責任がある。広範な国有化・食糧没収・貨幣の廃止などの戦時共産主義を共産主義主義の実現とみるのは誤りである。これらの諸措置は内戦によって強いられた一時的措置などであり、あたかも共産主義が実現しつつあるかのような幻想が蔓延したのを指導部は放置した)
書記局機構の統制活動が全面開花したのは、22年の末頃からだといわれる。この間、20年にはウクライナ共産党の指導部が解散され、中央書記局の意にかなう指導部に作り替えられた。21年には、サマラの地方党指導部が弾圧され、反対派幹部は他の地方に左遷され、
新たなサマラ地方党指導部が作られている。サマラは労働者反対派が唯一覇権を握った地方組織であった。
1922年3月27日〜4月2日に開かれた第11回党大会は、レーニンが指導した最後の大会である。大会では民主的中央集権派の指導者・オシンスキーが、「余りにも恣意的に行動する可能性をわが中央指導部に与えているところの規律の誇張」に抗議し、「軍隊式の規律から、厳格ではあるが真に党的な規律へ変えること」2)を主張した。レーニンは、ネップは戦略的な後退と位置付け、「本物の軍隊にこのような退却が行なわれるときは、機関銃をすえる。そして正常な退却が無秩序な退却になっていくときには、『射て!』という命令がくだる。しかもそれは正しいのである」3)といっている。
だが、レーニンはそれだけに終始しているわけではない。レーニンはすでに前年の第10回党大会前後には、今日のソ連が“官僚的に歪曲された労働者国家”にあることを認めている。官僚主義と党の政策・活動とが無関係であるとはいえない。第11回党大会は党内の官僚主義的傾向を認め、「党の諸組織は、党組織に奉仕する大きな機関を備えるに至って、
全体に膨大化しはじめた。そして今後はこの機関自体が徐々に拡大するにおよんで、官僚的蚕食が行なわれ、極端な量の(党の)勢力を呑み込みはじめている。」4)と決議している。
党組織の大きな変化の第一は、党大会、中央委員会のような代議制組織の形骸化傾向である。革命後最初の大会である第7回大会(1918年3月6〜8日)は、「政策上の重要問題を多数決によって決定した最後のものであった。その後も重要な問題について緊迫した論争が党大会でおこなわれるが、それも次第に舞台裏に移されるようになる。」5)といわれる。
第二は、中央統制委員会の形骸化である。中央統制委員会は1920年9月の第9回党協議会で初めて組織された。その任務は、党内民主主義の擁護にある。
第11回大会での労働者反対派、民主的中央集権派の“党の軍隊的規律”への批判は厳しく、リャザノフは規律強化の主要機関たる統制委員会の全面的廃止を要求した。地方統制委員会を廃止し、中央統制委員会を中央委員会によるいっそう徹底した監督下に置くことを提案する反対派の決議は、口頭の投票では賛否が接近していたようにみえた。そこで正式な投票でやり直してみると、523名中、存続賛成が223名、反対89名で、存続が決定した。
後に(24年頃)中央統制委員会のメンバー・グセフは「中央委員会は党の方針を決定し、中央統制委員会は、それから逸脱する者のないように監視し、逸脱を是正し逸脱者を列に復せしめるための手段を取る。」「権威は、活動によるのみでなく、畏怖によって獲得される。そして今や中央統制委員会と労農監督人民委員部は、この畏怖を作り出すことにすでに成功したのである。この点でそれらの権威は増大しつつある」6)といっている。統制委員会は指導部の下請け機関に変質していくのであった。
第三は、書記局の肥大化である。1919年(党員総数約31万人強)には30名でしかなかった党務専従者の数は、20年(党員数約61万強)には150人、21年(党員数約73万強)には602人にふくらみ(23年4月の第12回党大会時には党員数は約38万6000人。これは粛党の結果である)、24年(党員数約73.5万強)には、党装置で働く職員の数は2万3000人にまで至る。1921年3月の第10回大会でトロツキー派が退潮したあと、スターリンは組織局の支配的人物となり、22年5月に書記長職が新設されるとこれに就任し、書記局をも名実ともに支配する。(党員数の推移は、第1表参照)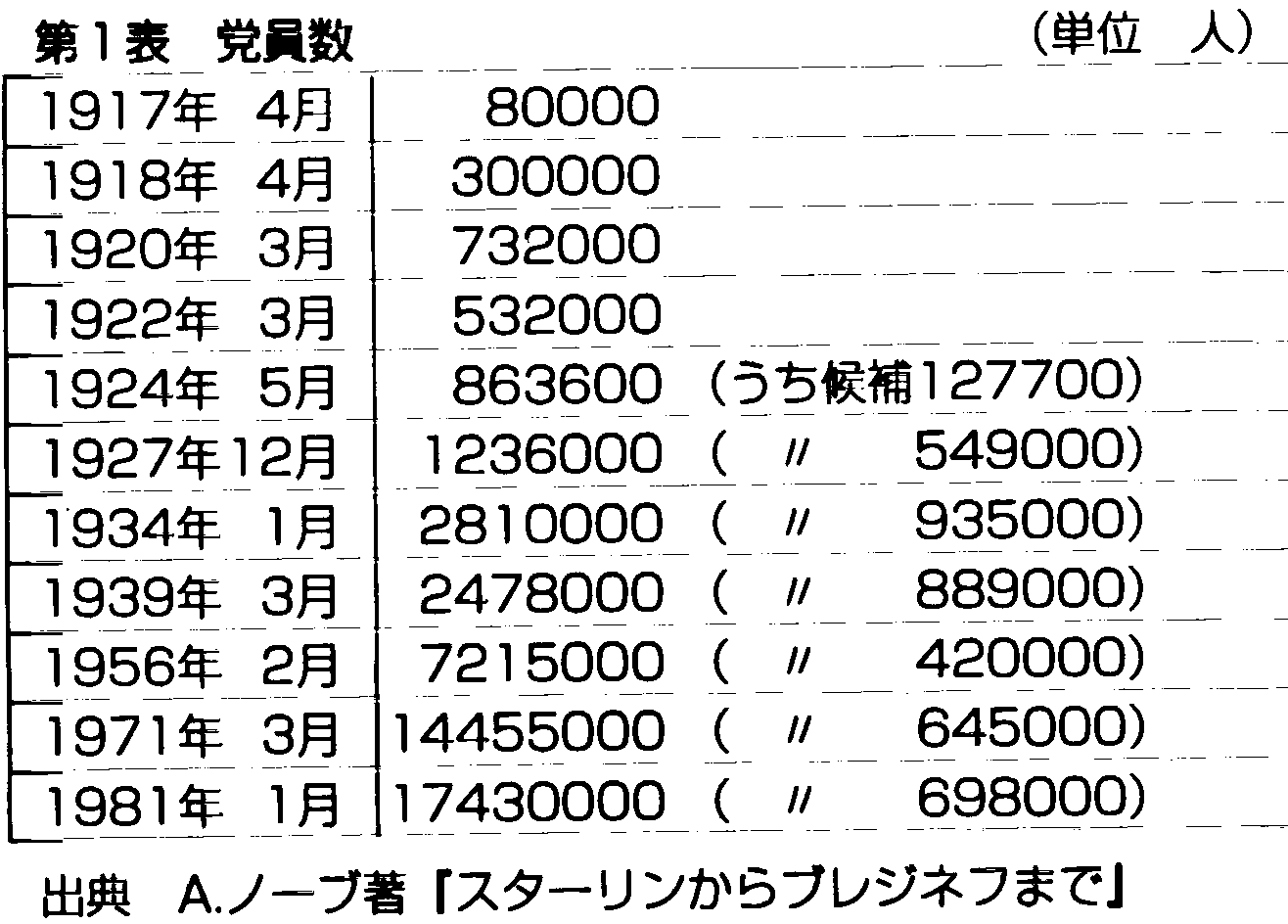
トロツキーは、1923年秋、公然たる反対
派宣言の直前、書記局の任命制を批判し、
「戦時共産主義の最も苛酷な時期にも、党
内における任命制は、現在の10分の1の程
度もなかった。地方委員会の書記の任命は、今ではしきたりとなっている。それは書記
のために、地方組織から本質的に独立した
地位をつくり出す。‥‥書記選出の方法に
よって、党機構の官僚化は前代未聞の程度 にまで発展した。」7)と、書記局機構の独
自な形成を批判している。
党務専従者の肥大化は、それに対する何
らかの措置を講じなれれば、党の官僚主義を固定化するのは必定である。R・ダニエルズは、「軍隊化された党生活から、顕著な社会的効果が生じた。専任の党活動(政府、軍隊、および労働組合における党務の割当てを含む)に従事する党員が特殊な準軍事的規律に服することは、頻繁な左遷の実施とあいまっ
て、専任の党活動家と余暇にだけ党務を手伝う平党員の間に考え方や個人的交際、はぶり、
またしたがって身分における差を生み出しはじめた。党活動は党役員という永続的な別個の集団によって支配されるに至った。」8)と分析・評価している。
注1)ブハーリン著『過渡期経済論』 現代思潮社
2)R・ダニエルズ著『ロシア共産党党内闘争史』 現代思潮社
3)同上
4)R・ダニエルズ前掲書からの重引
5)渓内謙著「ソ連邦の党官僚制」─『現代行政と官僚制』に所収
6)R・ダニエルズ前掲書
7)同上
8)同上
(3)スターリンのプロレタリアート独裁論
23年秋から24年春にかけてのトロツキー派、民主的中央集権派、労働者反対派などの活動が多数派によって敗北させられる。すると今度はスターリン・ブハーリン派とジノヴィエフ・カーメネフ派との間で熾烈な闘争となる。トロツキー派などに対抗したトロイカ(スターリン・ジノヴィエフ・カーメネフ)の分裂である。ここでプロレタリアート独裁論をめぐる論争が闘わされた。
1924年6月、スターリンは名指しではないがジノヴイエフ派を“ソヴィエト体制を「プロレタリアートの独裁」でなく、誤って「党の独裁」と規定している”と、批判する。
確かにジノヴィエフは「ソヴィエト中執幹部会のソヴィエトに対する関係と[党]中央委の党に対する関係とが同じであるかにみなす奇怪な見解に賛成するわけにはいかない。これは全くまちがっている。[党]中央委が中央委たる所以は、それが[党にとってだけでなく]ソヴィエトにとっても、労組にとっても、協同組合にとっても、県執行委にとっても、全労働者階級にとっても中央委であるという点にこそある。ここにこそその指導的役割があり、ここにこそ党の独裁が表現されているのである。」1)と述べている。これが批判されたのである。
ジノヴィエフは、スターリンの批判に直ちに反論した。それは、党独裁とプロレタリアート独裁を対置するのは「手のつけられない混乱」であるというレーニンの『共産主義内の「左翼主義」小児病』に依拠したものである。だが「ジノヴィエフは『プロレタリア独裁の内的機構の複雑さ』という点にふれ、『この機構のいろいろの部分のあいだには一定の分業がある』とものべているが、これはあまり具体的に展開されていない。」2)といわれる。
1925年12月に開かれた第13回党大会ではスターリン・ブハーリン派とジノヴィエフ・カーメネフ派は、全面衝突した。ここでもジノヴィエフ・カーメネフ派は党独裁問題を自己に有利な論点として、とりあげた。しかし、スターリンは相手の論点に長々と反論したが、ついに党独裁問題にはふれなかった。ジノヴィエフらの反論がレーニンに依拠していたこと、当時、党独裁がボリシェヴィキでは常識であったことなどにより、スターリンとしても簡単には反論しにくいものであった。スターリンの全面的な反論はその直後の26年1月である。有名な『レーニン主義の諸問題によせて』である。ここでスターリンは「プロレタリアートの独裁は、本質的には、プロレタリアートの前衛の『独裁』であり、プロレタリアートの基本的な指導力としての、彼らの党の『独裁』であるといっても、さしつかえないであろう。」としている。だが
、スターリンはあくまでもプロレタリアートの独裁と党の「独裁」は、同一視できず、イコールではないという。したがって、スターリンは、
党独裁の「独裁」はすべてカッコ付きで表記し、しかもそれを「党の指導的役割」に言い換えている。そして、レーニンをまねて、プロレタリアート独裁の内的機構について伝導ベルト論を展開するのである。
第14回党大会では、もう一つの重要な論点として書記局機構の問題があった。これをとりあげたカーメネフは、最後に「われわれは『指導者』の理論をつくりだすことに反対であり、『指導者』をつくることに反対である。われわれは、書記局が実質上政治と組織を結合して政治機関[政治局]の上にたつことに反対である。」「同志スターリンはボリシェ
ヴィキ参謀本部を統合する役割を遂行し得ない。」3)と批判する。
だがこの論争は圧倒的多数がスターリンらを支持する。このことは単にスターリン個人によって書記局位階制が形成されたことを意味しない。スターリン的思想傾向が書記局を中心に拡大していることを意味する。したがって、書記局の性格、役割、その権能をかえないで、形式的に政治局の従属化においてもなんらの改善にもならない。政治局員を選出する中央委員会、またこれを選出する大会代議員を選出・操作する力を書記局機構がもつ限り、全く同じことであるからである。
問題は党内の官僚主義をいかに抑制・チェックしつつ、将来的には分業への固定的隷属を解放する諸条件をいかに作り出すかということである。これは近代国家が「行政国家」として肥大化する問題、共産主義の観点からいうと、国家死滅の諸条件をいかに作り出すかという問題と相即的な問題である。
注1)23年4月の第12回大会<レーニン死後の初の大会>でおこなった政治報告の結語
─R・ダニエルズ前掲書からの重引
2)塩川前掲論文
3)同上
(4)スターリンの伝導ベルト論
スターリンは『レーニン主義の諸問題によせて』で、レーニンに依拠してプロレタリアート独裁の構造、機構を「伝導ベルト論」として展開する。
スターリンはプロレタリアートの独裁を実現するには、ベルト・テコと、「方向づける力」が不可欠とする。後者はいうまでもなく、「プロレタリアートの前衛」、すなわち党である。そして、前者は 労働組合、 ソヴィエト、 協同組合、 青年同盟である。つまり、党がベルトを指導し、階級に働きかけることによって、プロレタリアートの独裁が実現するというものである。
だが、レーニンとスターリンの決定的違いは、まず第一に、労働組合などとの「緊密な結びつき」の違いにある。レーニンは『共産主義内の「左翼主義」小児病』でこの点について次のようにいっている。「もちろん、このきわめて緊密な結びつきは、実践上では、宣伝、扇動をおこない、労働組合の指導者とばかりでなく、労働組合の有力な活動家一般とも随時にたびたび協議し、メンシェヴィキと断固としてたたかうといったような、非常に複雑で多様な活動をいみしている。」と。
しかし、スターリンは後述するように組合役員の党による任命、活動方向の党による指令を基本としているのであり、活動家や大衆から学ぶという面が欠落している。つまり、方針作成とその過程の排他性と独善性である。この結果、スターリンにおいては、労働組合をはじめとする諸大衆団体は、党の単なる下請け機関になりさがるだけである。
第二は、下請け機関とされた大衆団体からは、党は学ぶものがないだけでなく、さらにそれが進展すると労働者人民とその大衆団体の創造性・自発性を抑圧し、党がそれを支配するという関係に発展する。
レーニンはプロレタリアートの階級闘争について、「労働組合をつうじ、労働者階級の党と労働組合の相互作用をつうじるほかには、世界中のどこでもプロレタリアートの発達は生じなかったし、また生じることもできなかった」1)と、明言している。「相互作用」というからには、一方が他方を指導し、指導されるという固定的な関係はなく、ましてや下請け関係などということはありえない。「相互作用」というからには、相互に自主的な関係であることは言うまでもない。2)
第三に、スターリンは党の指導的役割を教条化し、ボリシェヴィキ(後にはスターリンとその取り巻き)が指導的役割を排他的に独占するという点である。
レーニンは、第一にでの述言からわずかばかり後に次のようにいっている。「われわれは、労働組合をつうじて『大衆』と結びつくだけでは、不十分なことを認めている。わが国では、革命の過程で、実践によって党外労働者農民会議のような機関が生みだされたのであるが、われわれは、たえず大衆の気分に留意し、彼らに近づき、彼らの要望にこたえ、
彼らのうちのもっとも優秀な働き手を国家の職務に抜擢する等々のために、この機関を完全に支持し、発展させ、拡大しようとつとめている。国家監督人民委員部を「労農監督部」
に改組することにかんする最近の一法令では、各種の監督にあたる国家監督委員会のメンバーを選ぶ権利を、この種の党外会議にあたえている。」と。
レーニンは、国家監督委員会のメンバーの選出権利を党外会議にもゆずり、党によって独占していない。これは他の党や無党派活動家との統一戦線を作り出す思想につうずるものである。スターリンのように党の独占的「指導」という思想とは無縁である。(レーニンは、この他にソヴィエトを通じた農民の組織化についても述べているが、割愛)
スターリンは、「党の指導的役割」を教条化し、前衛党が前衛党の資格をもちうるか否かをも点検せず、一旦前衛党として信頼をえれば、無条件に永遠に前衛党の資格があると思い込んでいるのである。確かにスターリンも党の権威は労働者階級の信頼によって勝ち取られるといっている。「党の権威は労働者階級の信頼によってたもたれるものである。ところで、労働者階級の信頼は、暴力によって得られるものではなく――信頼は、暴力によっては傷つけられるだけである──、党のただしい理論によって、党のただしい政策によって、労働者階級にたいする党の誠実さによって、労働者階級の大衆と党との結びつきによって、そのスローガンのただしいことを大衆に納得させようとする党の準備と能力とによって、えられるものである。」3)と。
しかし、これは紙の上だけであった。「上からの革命」−農業の集団化の過程が、このことを如実に示している。
注1)レーニン著 『共産主義内の「左翼主義」小児病』1920年4〜12月
レーニン全集 第31巻
2)詳しくは海野博之著「スターリンの伝導ベルト論批判
党と労働組合、大衆運動
の誤った関係」を参照−『明日を拓く』創刊号 88年8月に所収
3)スターリン著『レーニン主義の諸問題によせて』 国民文庫
戦時共産主義とネップ(略)
「上からの革命」期の統治構造
レーニンは、ネップへの転換を果たした後で、プロレタリアート独裁は労農同盟が維持されるところに核心があり、ロシア革命における社会主義建設にもっとも不足しているのは文化であるといっている。そして、第11回党大会(22年3月27日〜4月2日)で、1年間退却を続けたが「この時期はおわろうとしている。あるいは、すでにおわっている。いまでは別の目的が提起されている。すなわち、勢力の再編成という目的である。」1)といって、経済問題をふくめ統治能力の向上を重視した。
レーニン死後の7年間の党内闘争で、組織問題をのぞき重要な論点となった最大の問題は、工業化・計画化−その裏腹の問題としての農業問題であった。ネップ政策を推進するスターリン・ブハーリン派への厳しい批判が、反対派から続けられていた。農民一般との同盟政策が、ネップマンをつくりだし、農民内格差を拡大しているだけでなく、都市の労働者を貧困化させているというものである。実際、1928年までの3年間で労働者の平均実質賃金は40%減少したと言われる2)。
反対派のプレオブラジェンスキーらは、工業化・計画化を強調し、「社会主義的原始蓄積」を提唱していた。それは、工業化なくしてはソヴィエト体制の国防自身が危険であり、工業化を基礎に計画化を推進しない限り経済の不安定さが続き、資本主義の復活すらありうるというものである。そのため、農業・農民からの「収奪」によって、工業化の資金をつくりだすというものである。3)
しかし、その政策はネップの核心である農民との同盟を脅かすものであり、その点が「プレオブラジェンスキーのディレンマ」とよばれた。トロツキー派は、このディレンマからの脱出をヨーロッパ革命に求め、世界革命を重視した。しかし、ドイツ革命の流産いらい、先進国革命によるロシア支援は遠のき、自力の社会主義建設にいやおうなく直面する。
注1)レーニン著「ロシア共産党(ボ)第十一回大会」1922年3〜4月
レーニン全集 第33巻
2)R・ダニエルズ前掲書
3)だが、プレオブラジェンスキーは、のちに実施されるスターリンらの暴力的な農 民収奪とは、決定的に異なる。「プレオブラジェンスキーは、社会主義国家が 『本源的蓄積』において資本主義的本源的蓄積において採られた暴力的方法を用 いることを想定していたのではない。その反対に、かれが私営部門から国営部門 への収奪の方法としてあげたのはさまざまな経済的方法であり、とくに『国営工 業のための独占価格政策』を重視していた。」(溪内謙著『現代社会主義の省察』 岩波書店)のである。
(1)穀物調達危機と非常措置
ネップによる経済復興は、必ずしも順調とはいえないが、それでも26〜27年ごろには、戦前水準の生産力を回復しつつあった。
路線転換をうながす情勢変化は27年の秋にあらわれた。27年9月以降、全般的な豊作にもかかわらず、穀物調達の実績は例年とくらべて不調であった。11〜12月は、前年同期比で半分以下に低下した。「1927年初頭から1928年1月の間に、穀物の市場調達率は25パーセント以上減少した」1)。原因は、ネップの数年間で農民は相対的に豊かになった反面、農村向けの工業製品が依然として不足していたこと、農民が穀物販売で貨幣をうるよりも穀物現物を保有する傾向をもったこと(インフレなどで)などにある。党とソヴィエト政権はこの事態を農民による穀物価格値上げの圧力とうけとった。(しかし、スターリン・ブハーリン指導部の25〜27年の政策のいくつかの誤りが、新たな危機を促進していたことを否定することはできない。たとえば、単一農業税の引き下げ<25−26年財政年度>、工業製品の卸売価格の大幅引き下げ<25〜27年>などである。後者では、ネップマンの利益拡大、工業商品の不足・飢饉を促進させた。)
1928年1月13日、事態の深刻さを認めた指導部は、市場関係にもとづく農民との結合という従来の政策を根本的に転換し、非常措置を導入する党政治局指令を発した。この指令はあまりにも突然であった。それは以下のいきさつがあったからである。
27年後半の穀物危機に対し、合同反対派は、「ソヴィエト国家機構の全力をかたむけて、富農に決定的な攻撃をかける時がきたと考えた。彼らは、富農と富裕中農からすくなくとも1.5億プードの穀物を力づくで収用することを提案した」2)。だがこの提案は、27年8月9日の中央委員会と中央統制委員会の合同総会でしりぞけられた。27年12月2〜19日の第15回党大会でも否定された。この大会でスターリンは、「行政的措置によって、ゲー・ペー・ウーを介して、すなわち命令し、印をおし、それで終わりだということで、富農をかたづけることができるし、また、かたづけなければならないと思っている同志があるが、それは正しくない。こうした手段は容易であるが、けっして効果のあるものではない。富農は経済的処置によって、ソヴィエトの法律にもとづいてとらえるべきである。」3)と演説している。だが、スターリンは、メドベーヴェーデフによると、その舌の根も乾かぬ12月14日と24日にすでに非常措置施行の指令を発しているという。
2月13日には、スターリンの名で、穀物調達の強化をもとめる政治局指令がだされた。
非常措置というのは、小田博著『スターリン体制下の権力と法』によると、「(一)、地方(機関)に正確な課題を遅滞なく指示し、期限内に調達目標達成のためにあらゆる措置を講ずること、(二)、自己課税、農民債権の割当、保険や農業貸付の未払金徴収などの遅滞なき遂行のために、強力な手段をとること、(三)、投機者、穀物隠匿者などに対して刑事責任を問い、またはこれを拘禁すること、(四)、亜麻調達地区にカンパニアの時期に指導的活動家を派遣する、ことなどであった。」という。2月15日の『プラウダ』社説は、穀物調達を強化し、いかなる手段を用いても年間計画を達成することを強調しながら、穀物を保有するクラークに対して刑法第107条の適用をふくむ措置をとる必要があるといっている4)。投機師(クラーク)発見を容易にするために、発見者である「村の貧民」に発見穀物の4分の1を報酬として与えるとした。(自己課税というのは、本来、各農家が共同体のための費用、労役を分担する制度であり、農村自治の財政的物質的基盤であった。しかしここではそれを利用して工業化のために農民から余剰貨幣を吸収する手段となった。農民債権の発行とその割当強制も同じであり、債権購入を拒んだ農民は反革命分子として逮捕された。)
農民に対する直接的な調達措置の中心をなしたのは、ロシア共和国刑法典第107条の適用であったといわれる。同法は「買占、隠匿、市場への不放出による商品価値の悪質な引上げを行なった者は、1年以上の自由剥奪に処する。同種の行為を商人が共謀して行なったときは、これを3年以下の自由剥奪に処し、全財産を没収するものとする。」としている。この条項は27年までは農村ではほとんど適用されていなかった。しかも同条項を適用するには、たんに穀物を保有するだけでなく、隠匿などをし価格を引き上げる意図があるという証拠が必要であった。だが実際には穀物を保有しているだけで適用され、「経営が富裕である」「富裕な農民である」ことが有罪の根拠とされた。
強制的な調達は、刑事制裁の圧力だけでなく、闇食糧買出取締隊による特定地区の封鎖、逮捕、拘禁の濫用などの暴力的調達が数多くみられたという。
注1)R・ダニエルズ前掲書
2)ロイ・ア・メドヴェーデフ著『共産主義とは何か』上
三一書房
3)スターリン全集第10巻
4)小田博著『スターリン体制下の権力と法』 岩波書店
党政治局指令による非常措置に対して、当初地方の党組織・ソヴィエト組織、活動家は、
反応がにぶく、不活発であった。それはこれまでネップ政策により、農民との同盟が最優先されていたこと、路線転換が急激であり、しかも党全体の組織討議でなく党政治局による一方的な命令であったことなどによる。
これに対し党指導部は、まず第一に、指令実行に積極的でない場合は、機関・組織の粛清、しかも個々の活動家に対して党規律上の、あるいは法律上の責任追及を行うとした。法律上の追及というのは、調達機関の活動家が非常措置の実施に消極的な場合は、刑法第111条(職務怠慢罪)、調達目標を達成するために、調達価格を勝手にあげるなどの場合は、
刑法第109条(職権濫用罪)などを適用することである。
第二は、現場の活動が不活発なので、その地方の上級党組織から全権委員を派遣し、その指揮のもとで任務を遂行させた。「全権委員は、調達カンパニアの遂行に関して、現地の穀物調達機関、党組織を指揮監督し、これらの機関の活動家が党の路線に違反した場合、あるいは調達カンパニアその他のカンパニアの遂行に関する党の指示を遂行しない場合には、彼らを罷免し、さらには裁判所に送致することができた。」5)のである。
暴力的な、違法な調達に農民たちは、当然にも反発し、ソヴィエト政権に対する反感は農民上層だけでなく全体に広がった。一部では調達員に対する暴行・殺人もおこっている。
28年3月末、穀物危機は一応終息する。2月13日の党政治局指令は、穀物調達の強化を指示する一方で、「行政的手段」の適用を批判し、非常措置の適用にあたっての「行きすぎ」をいましめる動きがでる。4月6〜11日の中央委員会総会では、「行きすぎ」の範囲として 非常措置適用の対象がクラークにとどまらず、中農、貧農にまで及ぶ場合、 たとえクラークを対象とした場合でも、非常措置が過度に農民との間に緊張をもちこむ場合、としている。しかし、外部から入った全権委員などにはクラークのみきわめもできず、しばしば中農にまで強制は及んでいた。さらに総会決議は、非常措置そのものの手続き、方法など全般的な違法性、反民主性については不問にしている。つまり、「行きすぎ」の抑制は、あくまでも穀物調達の完遂が前提である。
4月下旬、再び穀物危機がやってきた。『プラウダ』は「われわれは、富裕なるクラーク層に対する階級的圧力を決してゆるめてはならない」6)と、穀物調達のキャンペーンを再び強めた。農民たちの反抗も6月末から顕著となり、とりわけ穀倉地帯の北コーカサスで反乱がはじまっている。ブハーリン派のスターリン批判は公然化し、政治局でも、モスクワ党組織でも論争は活発となる。
7月の中央委員会総会は厳しい論争となり、全面攻撃の布陣の整わないスターリン派は、
最終的には和解的調子で妥協し、外観的にはブハーリン派が優勢かのごとくみえた。だがその後スターリン派は、ブハーリン派の拠点−モスクワ党組織、コミンテルン指導部、全国労働組合指導部を各個撃破する。党内闘争の激化の中、8月中旬新たな穀物危機がおこる。
その後もスターリン派は、穀物調達キャンペーンをつづけ、中央委員会総会などの席では表面上妥協的態度をしめすもブハーリン派への組織的攻撃を完遂し、29年の前半には名実ともに決着をつけた。
穀物調達は28年末も不振であり、事態は飢餓的状況に近づく。ここに至ってはブハーリンらのいう経済的方法(穀物価格の引き上げ、税の引き上げなど)はすでに非現実的となる。しかし、公式的には強制的暴力的な非常措置は否定されており、袋小路となる。そこに登場したのが「ウラル・シベリア」方式である。「この方式は、自己課税の方法を穀物調達に適用したといわれるように、農村共同体の規制力を利用して穀物を調達する方法とみることができる。それは、理念としては貧農、および中農が主体となり、農村共同体の決議にもとづいて、クラークに穀物の供出を命ずる方式であった。クラークが、この決定にしたがわない場合には、『社会的ボイコット』、すなわち、消費協同組合からの除名、商品供給の拒否などの制裁を科することが予定されていた。」7)という。
「ウラル・シベリア方式」は「社会的方法」ともいわれたが、これは党中央の決定によっ
てすすめられたものでなく、穀物調達に実際的責任をおう地方党組織によって用いられ始めたものである。この方式は29年初頭から新たな調達方式として、各地に広がった。
だが現実にはこの方法を推進する貧農・バトラークの組織は決定的に不十分であり、実際のイニシャチブは、農村外の勢力−地方の上級党組織から派遣された全権委員と、その指揮下の「突撃隊」(都市と工場から派遣された労働者やコムソモール員など)であった。
したがって、共同体の決議は外部勢力によって、権力的強制的におこなわれ、以前と何ら変わりはなかった。たとえば、クラーク(実際には中農も)に対するボイコット決議は協同組合議長や村ソヴィエト議長によって決議され大衆はそれに参加しておらず、決議自身が全権委員の指揮下で権力的かつ違法におこなわれた。
党指導部の描く、“貧農に依拠し、中農を味方につけ、クラークと対決する”という農村方針は、全く机上の空論であった。それは、貧農、中農の組織化が決定的におくれており、そこになにがなんでも穀物調達をしなければならないということで非常措置をクラークから中農、一部では貧農にまで拡大し、しかも権力的暴力的に執行されたためである。
この結果は悲惨なものである。農民の反抗は、実力行使となり、憤激のあまり調達員に対するテロ行為が頻発した。これに対して、党指導部は「農村における階級闘争の激化」とみてとり、さらに党組織と国家暴力を動員して弾圧した。反抗する農民に対しては、逮捕・投獄あるいは銃殺が加えられた。全くの悪循環である。現実の闘いは、党指導部の誤りにより、階級闘争の激化でなく、党・ソヴィエト政権と農民との間の闘争に歪曲されてしまったのである。(ブハーリン派は、これを「軍事的・封建的収奪」として批判した)
注1)R・ダニエルズ前掲書
2)ロイ・ア・メドヴェーデフ著『共産主義とは何か』上
三一書房
3)スターリン全集第10巻
4)小田博著『スターリン体制下の権力と法』?
5)同上
6)同上
7)同上
(2)非常措置の恒常化と強制的集団化へ
最後の反対派=ブハーリン派の失脚とともに、非常措置は恒常化した。1929年6月28日の「全国家的課題と計画の遂行に対する協力に関する地方ソヴィエトの権限の拡大について」の全ロシア中央執行委員会・人民委員会議決定は、「ウラル・シベリア方式」をさらに強化するために、農村共同体の決議に従わない者に対して新たに刑事罰を定めている。すなわち、農村共同体で穀物調達計画の遂行、個々の農家に対する供出額の割り当てが決議された場合、この決議に従わない農家には割り当てられた穀物の価格の5倍以内の罰金が科せられ、必要な時は財産を競売に付す権限が村ソヴィエトに与えられた。また、集団による穀物供出の拒否、反抗が行われた場合には、刑法第61条が適用されるとした。この日、第61条が改正され、それは「全国家的意義を有する課題」の遂行拒絶に対して、第1回目の拒絶には先述したように5倍以内の罰金、第2回目の拒絶には、1年以内の矯正労働を定めるなど、刑を重くしたものである。この他にも29年中には、後述するように刑法のいくつかの部分改正が行われている。
1929〜30年の穀物調達計画では、前年度の計画量をさらに400万トンうわまわる過大な目標が設定された。9月以降、穀物調達のテンポはさらにエスカレートした。これは5カ年計画を4年で実現するという超工業化路線が推進され、工業化のための原料や、都市の穀物需要を満たすためである。今や、「年間計画を半年で遂行する」がスローガンとなり、
ムチャクチャな主観主義・主意主義が横行しだした(第1次5か年計画はそもそも全面的集団化を予定にいれていなかった)。その結果は、人民にとっては、極めて悲惨なものであった。29年7月11日、人民委員会議は非公開決定により、従来、内務人民委員部の管轄下にあった矯正労働施設を再編し、新たに統合国家保安局が直轄する強制収用所を全国各地に創設した。明らかに行刑制度は転換した。これまでは一応、受刑者の矯正を目的としていたものが、受刑者を社会から隔離し、その労働力を生産目的に利用するという制度目的への転換である。用語的にいうと、「社会防衛処分」から「懲罰」への転換である。
8〜10月にかけての穀物調達はかならずしも良好とはいえなかった。農民は強制的調達に対し、各地でコルホーズ・ソヴィエト議長などの建物への放火、調達員へのテロなどが頻発した。党指導部は、調達成果の不十分性が地方党組織・調達機関の不活発と、クラークの抵抗にあるとして、党組織・国家組織をさらにしめあげた。
だが客観的にみて、強制徴発もすでに限界であった。ノルマにおわれ、各地の調達はクラークどころか、ますます中農、貧農にも拡大するばかりであった。10〜11月にかけて、各地の地方党からは「行きすぎ」の現状報告が増大する。
29年11月の中央委員会総会で、スターリンは、集団化が従来考えられていたよりも近い任務であることを示唆した。矛盾の激化を正面突破で、暴力的に一挙的に「解決」するために、集団化の方針を取ったのである。現実には29年の夏から一部で苦肉の策として「全面的集団化」がとられはじめている。
だが、この動きはマルクス主義の農業・農民政策における原則的見地を危うくするものであった。マルクスは、農民にたいしてプロレタリア国家は、「土地の私的所有から集団的所有への移行を萌芽状態において容易にし、その結果農民がおのずから経済的集団所有にすすむ」ような諸方策をとるべきだと、いっている1)。集団化は国家的暴力ではなく、農民自身の自発的意志でおこなわれるように、党や国家は支援すべきなのである。
革命前、ロシアの富農は農村の主力であり、10月革命の結果さらにその地位を改善した。
これにより、全農民の20%、全農地の40%以上を富農が占めることとなった2)。
内戦の時期、多くの富農が白軍、緑軍(赤軍、白軍に対抗した農民運動)に加担し、ソヴィエトに敵対した。1918年8月、レーニンは富農との闘争を主張し、「どんな疑いもありえない。富農はソヴィエト権力の仇敵である。富農が数かぎりなく労働者をころすか、でなければ労働者が、勤労者の権力にたいする、国民のなかの少数の強盗的富農の暴動を、
容赦なくふみつぶすかである。そこには中間の道はありえない。」3)といっている。しかし、19年3月12日のペトログラード・ソヴィエト会議では、「われわれは富農にたいする暴力に賛成するが、しかし彼を完全に収奪することに賛成しているわけではない。なぜなら、彼は土地経営をおこなっていて、一部分は彼自身の労働で蓄積されたものだからである。まさにこの違いをしっかりとのみこまなければならない。地主と資本家にたいしては─完全な収奪、しかし富農にたいしては、財産を全部取りあげるようなことをしてはならない。」4)と、富農にたいする完全収奪を禁止している。
また、19年3月の第8回党大会の「農村における活動についての報告」でも、レーニンは、「地主と資本家にたいしては、われわれの任務は完全な収奪である。だが中農にたいしては、われわれはどんな暴力行為もゆるさない。富農にたいしてすら、われわれは、地主にたいする場合のような決然たる態度で、富農とクラークの完全な収奪とは言わない。われわれの綱領にはこの区別がもうけてある。われわれは、富農の反抗の弾圧、その反革命的傾向の弾圧といっている。これは完全な収奪ではない。」5)と、釘をさしている。
だが、スターリンらは、このマルクス主義、レーニン主義の原則的見地をいとも簡単に放棄する。
党の農村政策のさらなる転換=「クラーク絶滅・全面的集団化」政策は、農村における危機が頂点に達した29年の末に開始された。12月はじめ、政治局特別委員会は富農絶滅の方針をとり、富農経営を3つに分類した。 集団農場の組織に積極的に反対し、反革命的破壊活動を遂行する富農。これらのものは逮捕し、または僻遠の地方に追放すべきである。
全面的集団化をなしとげることを予定した方策に、それほど積極的にではないが反対した富農。これらのものは、その州または地方外に移住さすべきである。 集団化をめざす処置に従い、またはソヴィエト権力にたいし忠誠の態度をとる富農。特別委員会は、このような富農を集団農場の一員として受け入れることを可能と考えたが、3年ないし5年間選挙権をあたえない─というものである。
29年の後半をつうじ、集団化のさいのクラークの取り扱いについて論争が展開された。12月27日、スターリンはマルクス主義農業問題専門家会議で演説し、「最近、我々は、クラークの搾取者的傾向を抑制する政策から、クラークを階級として絶滅する政策へと移った。‥‥クラークの収奪は、それらの地区では、コルホーズを建設し、発展させる仕事の一構成部分である。」「クラークのコルホーズへの加入は認められない。」6)(?)と述べ、すでに政策転換が終わっていることを宣言する。これで論争は終結してしまった。7)
党中央委員会は30年1月5日、「集団化のテンポとコルホーズ建設への国家の援助措置について」という決議をし、初めて党がクラーク抑制政策から階級としてのクラーク絶滅政策に転換したことを宣言した。すでに各地方で広く実施されていた「クラーク絶滅」に、
やっと法制的な根拠が与えられたのは、1930年2月1日のことであった。
政治局特別委員会は、スターリンの宣言に従い、第3部類の富農もコルホーズに加入させないことにした。だが、30年2月4日に発令された、中央執行委員会と人民委員会議の訓令はさらに苛酷なものであった。「たとえば、第1部類は、テロルと反乱を組織した積極的な反革命的富農から成るものとされた。彼らは、監獄と矯正労働収容所にいれることで即時隔離されるべきで、彼らにたいしてはもっとも極端な刑罰処置─銃殺─を実行することをためらってはならない。彼らの家族全員は遠隔の地方に追放されることになっていた。5万世帯以上をこの部類に指定することが提議された。第2部類には、豊かな富農中の積極分子の残りがいれられた。特別委員会は、彼らとその家族を国内の僻遠な地域またはおなじ地方内の僻遠な地点に追放することを提議した。これらの世帯は約11万2000になることが指摘された。第3部類には、それほど有力でない富農経営がいれられた。彼らは自己の地区にとどまるが、コルホーズの田地からはなれて、新たに土地を割り当てて、集団化された村の外部に再定住さすことが提議された。訓令によると、これらの富農は、生産目標と義務が割り当てられることになっていた。富農経営の大多数はこの部類に指定するように提議された。これらの訓令と布告には、『亜富農』すなわち富裕中農という言葉はなかった。」8)という。
(だが実際にはこのレベルさえをも上回った弾圧であった。「1933年の中央委員会1月総会に提出された資料によると、24万757の富農世帯(およそ100万から150万人)が僻遠な地区に追放された。これらの数字がひどく小さくみつもられていると信ずべき十分な理由がある。」と、メドヴェーデフはいっている。)
クラーク絶滅運動は、30年初頭から全国各地で嵐のように展開された。都市からはさらに多くの労働者が農村に派遣された。「農村からの報告では、管区全体を『全権委員、上級全権委員、三人委員会、五人委員会が疾駆し』、村ソヴィエト議長の『胸ぐらをつかみ』
、彼らを解任し裁判所に送致した。全権委員は、村ソヴィエトを補助するのではなく、村ソヴィエト議長を恣に罷免し、『三人委員会』、『五人委員会』などの組織により、村ソヴィエトにとってかわった。活動家の間には、村ソヴィエトが不要になったという『村ソヴィエト死滅論』が広まった。クラーク絶滅は、多くの場合に、農民を『身ぐるみ剥ぐ』こと、すなわち、土地や農器具、穀物に留まらず、衣類、家財の没収にまで至った。プスコフ県では、クラーク絶滅が、『夜襲』によって行なわれた。全権委員は、銃を手に農家に侵入し、農民に10分以内に退去するように命じた。子どもは、裸のまま、街路に抛り出された。農民は、『コルホーズか、ソロフキか』の選択を全権委員に迫られた。」9)という(ソロフキとは、極北の強制収容所がある所)。
クラーク追放には、かなりの中農、貧農も反対した。多くの農民は強制的な集団化に抗して、家畜がコルホーズのものになるのを恐れ自らの手で屠殺した(この影響ははるか後年の第二次世界大戦後までつづいた。畜産部門における28年水準が回復するのは戦後の53年以降である)。これに対処するため一部の地域では家畜の没収が法律的根拠もなく行われたという。同様に屠殺した農民にも処罰が行われた。農民の抵抗も激しく、デモ、放火、
殺人という事態が広がった。これへの権力の弾圧はより強化され、結局、抵抗した農民たちの多くは、銃殺されるか、財産を没収されシベリアの未開地に追放されるかした。家族とともに自殺した例もみられる。
30年の1月中旬から地方党のいくつかは、全面的集団化運動の「行きすぎ」を批判するようになる。3月にはいって、党中央も抑制政策をとりはじめる。3月2日付け『プラウダ』は、スターリンの論文「成功による眩惑」をのせた。スターリンの常套手段であるマッ
チポンプ方式である。党、政府の周到な準備もない集団化は、各地で混乱を引き起こした。
『ソ連経済史』の著者−A・ノーブは、「彼ら(現地の活動家−引用者)の当惑を深め、きわめて乱暴な行きすぎを確実にするかのように、党の扇動・宣伝部の責任者カミンスキーは1930年1月にこう宣言した。『諸君が若干の問題で行きすぎて逮捕されても、革命的行動のために逮捕されたものと心得よ』。スターリンとモロトフは可能なかぎり速くとあおった。」、「ソ連の研究者がアルヒーフの中にみつけた報告書によれば、『行きすぎはかなりの程度まで、州・地方組織が右翼的偏向を怖れ、し足りないよりはやり過ぎる方を選んだことで説明できる』と。同様なことはカリーニンも報告している。全家畜の社会化を現地責任者が実行したのは、『自発的にではなく、右翼的偏向と非難されることを怖れたから』であった」10)といっている。
29年の末からはじまった集団化は、31年には半ばをこえ、30年代半ばにはほとんど完了している(第2表を参照)。
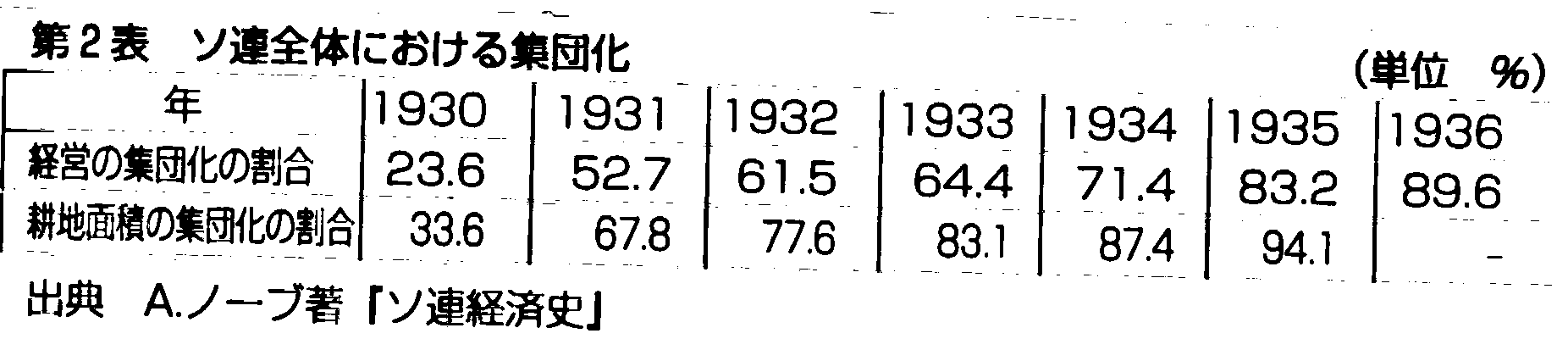
だが、「行きすぎ」を批判するスターリン論文の直後には、一時多くの農民はコルホーズから脱退している。30年3月1日時点では、ソ連邦全体の集団化率(経営の)は、55.0%だったのが、6月1日には、23.6%にまで低落している。攻撃は秋頃から再開された。今やクラークの大半が絶滅されているので、今度の攻撃の対象は残りのクラークだけでなく、「クラーク的」で富裕な」農民に主要に向けられた。農民たちはあらゆる強制によって、再びコルホーズに戻された。
国家的強制による穀物調達は、無慈悲におこなわれたが、この結果は第3表の通りである。
30〜31年は、28年の倍以上の2200万トン台である。工業化のための穀物輸出も、30〜31年は、それ以上に突出し、500万トン前後となっている。
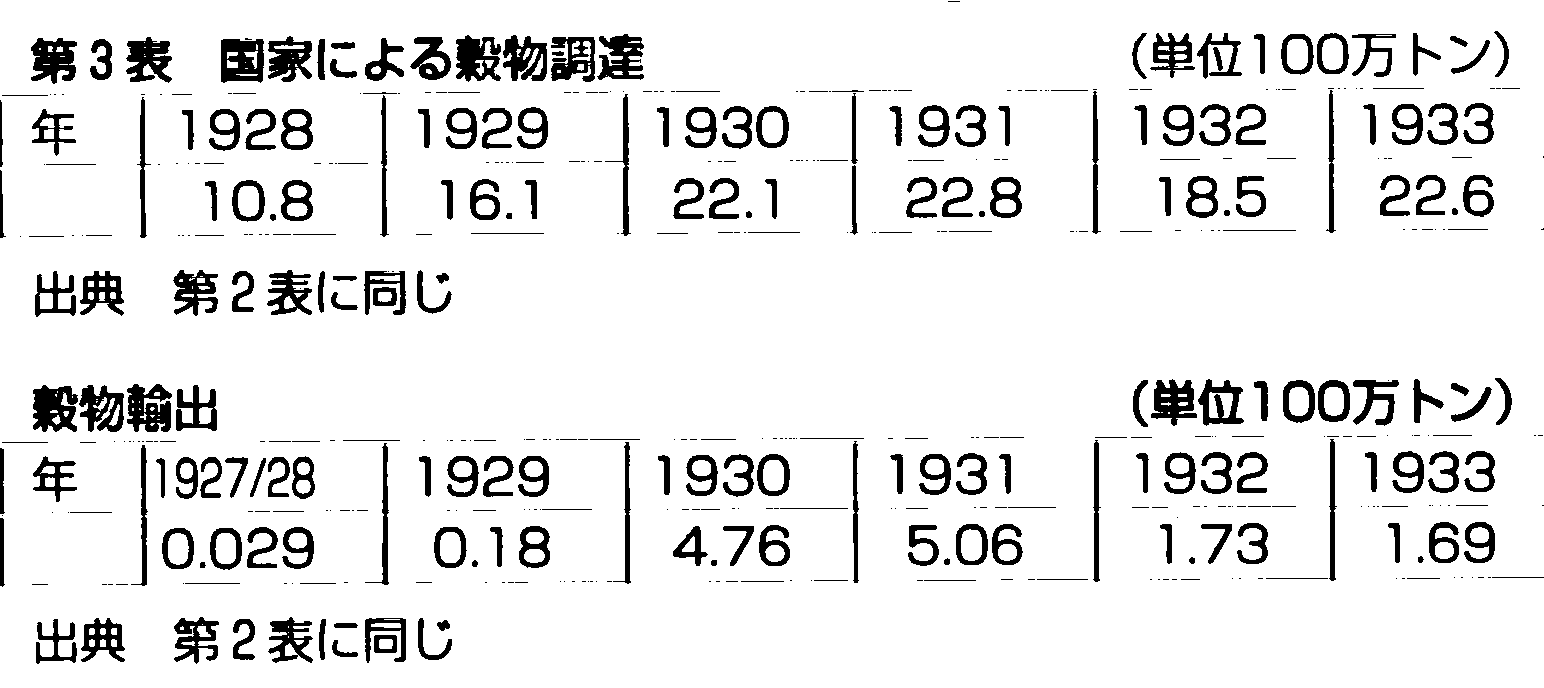 超工業化による都市人口の急増、穀物輸出の異常な増加などにより、穀物余剰は枯渇し、強制的集団化による家畜の一挙的減少などで、食料事情は悪化した。都市住民は配給制の下で、パン・じゃがいもが増え、肉類・バターが減った。しかし、農民はいずれのものも減少した。飢えに駆られた農民などが、合法であれ非合法であれ、食料を求めるのは必然であった。
超工業化による都市人口の急増、穀物輸出の異常な増加などにより、穀物余剰は枯渇し、強制的集団化による家畜の一挙的減少などで、食料事情は悪化した。都市住民は配給制の下で、パン・じゃがいもが増え、肉類・バターが減った。しかし、農民はいずれのものも減少した。飢えに駆られた農民などが、合法であれ非合法であれ、食料を求めるのは必然であった。
ウクライナ、北カフカース、下ブォルガは、ソ連の3大穀倉地帯である。その1つ、北カフカース地方は、ロシア南部に位置し、3000万ヘクタールの面積は、優にイタリア全土の1.5倍である。31年1月、党中央委員会は、「北カフカースにおける集団化について」という決定をおこない、同地方がすでに3分の2以上の経営がコルホーズに加入したとし、
ソ連ではじめて北カフカースを全面的集団化地域に指定した。そして、同年8月の党中央委員会決定「今後の集団化のテンポとコルホーズ強化の任務について」では、北カフカースの集団化が完遂されたとした。穀倉地帯の北カフカースは、集団化の先進地域であり、党指導部にとっては大いに期待する地方であった。実際、「北カフカースのコルホーズは、
収穫が減少した1931年に、前年度よりも77%余計に穀物を供出した。」11)という。
しかし、北カフカース地方でも30年、特に31年末ごろから一部で穀物調達の遅延が目立ちはじめてくる。スターリンが、北カフカース地方の穀物調達と冬播きカンバニアの異常さ、低調さにいつ気づいたのかは明確ではないが、少なくとも32年の10月までには新たな危機を自覚し、再び、みたび強権的対応の必要性を認めたといわれる12)。スターリンは、
「階級としてのクラークの絶滅」政策により、農村における階級対立が基本的には解決したという、第17回党協議会(32年1月30日〜2月4日)の認識とは根本的にことなる態度をとる。この現れの1つが、10月に党中央委員会の代表団=カガノビッチ委員会の北カフカースへの派遣である。
カガノビッチ委員会は、政治局員カガノビッチを団長に、補給人民委員ミコヤン、農産物調達委員会副議長チェルノフ、新ソホーズ人民委員ユールキンといった農業・調達関係の最高幹部と、赤軍政治部長ガマルニク、統合国家保安部(オ・ゲ・ペ・ウ)議長ヤゴダ、
党中央統制委員シキリャートフといった軍、政治警察、党統制機関の最高責任者、さらにコムソモール議長コーサリョフで、構成されていた。これは明らかに穀物調達を促すだけが目的ではなかった。
32年11月2日、カガノビッチ委員会と北カフカース地方党委員会ビューローは、合同会議をひらき、「北カフカース地方における穀物調達の遂行について」という決定をおこなった。これは、調達量を5月の段階より5900万プード減らし、最終的にコルホーズで9700万プードとすること、党地方委員会、ソヴィエト地方執行委員会は、調達・播種の遅れている南部の31地区に1か月以上全権代表を派遣することなどを方針としている。さらに11月4日には、党地方委員会と中央委員会の合同決定「クバン地方における穀物調達と播種の進行について」(クバンは、北カフカースの1地方)がだされた。決議は、遅れの原因と責任を「クラーク反革命分子によって組織されたサボタージュ」、「事実上クラークの先導者となった一部農村コムニスト」として、非難した。そのうえで「第1に、ノボ・ロジェ
ストベンスカヤ村をはじめとする最も遅れた3つの村名を『黒表』に名指しで掲載し(それは『プラウダ』等で公けにされた)、あらゆる商品の輸送・配分の禁止、商業の禁止、とりわけコルホーズ商業の厳禁、信用供与の中止と債務の期限前の取り立て、労農監督部による関連機関の点検、粛清が指示された。『黒表』制度は、コルホーズ商業をはじめとする新政策の適用を一時的に認めず、現有商品を取り上げた上で強制的調達を強いるものであった。更にこれ以上サボタージュが続けば、これらの村の住民を地方から北方に追放すると同時に、悪い条件下の住民のコルホーズをこの地に導入するとすら威嚇した。また約20の地区に対しては商品の搬入、場合によっては倉庫・配給所からの全商品の搬出が禁じられ、それらは調達を完遂した地方の別地区に送られた。特に耕作、播種を拒んだ個人に対しては屋敷付属地が取り上げられ、これらの個人農に対し、生産手段没収の上、北方に追放するよう政府に要請し、また穀物供出、調達の不履行に対して、罰金から自由剥奪に至る厳格な処分を規定した刑法61条を適用するとも指示された。更に社会主義財産保護の指令、いわゆるスターリンの8・7法がこの地方ではきわめて不十分にしか守られないとして、地方検事局、裁判所が、この5日間に少なくとも20件の『事件』を審査し、その判決を公表すること、またこの法令発布からの事件の判決の履行を10日以内に点検すべきことが指示された。」13)という。
同じ頃、党中央委員会と中央統制委員会幹部会の決定「北カフカースにおける農村党組織の粛清について」がだされ、クラークの政策を遂行し、党の政策を遂行しない分子を粛清するとし、粛清された者は追放されることとなった。党は地方の統制委員会への不審から、別に粛清委員会を設置し、農民だけでなく党員をも弾圧した。この手法は翌年、全国に拡大する。
だが、農村の荒廃は、すさまじいものであった。「クバンをはじめとする北カフカーズの農村を支配していたのは無残なまでの荒廃であった。コルホーズの秩序は解体し、圃場は雑草で蔽われ、刈残しの穀物は腐敗していた。馬や牛は食用に屠殺された。コルホーズ農民は食料のなくなった、崩壊した農村を捨て、職場と生存を求めて都市に流入しはじめた。鉄道沿線はこうした大群でうまっていた。」14)といわれる。
スターリン批判後の68年に発表された小説『死』(ヴェ・テンドリャーコフ著)は、次のように描写している。「ペトラホフスカヤでは、飼料がなくて牛が死に、人間はイラクサのパンや、ある雑草のビスケットや、ほかの雑草の粥をつくってたべた。それはペトラホスフカヤだけでなかった。1933年という飢えの1年が国じゅうを移動した。地区の首都ヴォフローヴォの駅付近の小さな公園で、ウクライナから追放された富農清算にかけられた農民たちが臥せやがて死んだ。朝になるとそこに死骸が見られる習慣になった。馬車がやってきて、病院の厩番のアブラムが屍体をつみあげるのであった。すべてのものが死んだのではなく、多くの者はほこりだらけの、みすぼらしいせまい道をさまよい、むくんだ血の気のない、青い足をひきずり、犬のような物ほしげな眼つきで通りがかりの一人一人をさぐった。」と。教条的「宗教的」信念と巨大な権力の結合は、人間を含むあらゆる生き物を駆逐するまでの貫徹力を示したのである。
32〜33年にかけて、飢饉が広がり、大量の餓死者がでたといわれる。この事実はスターリン批判までソ連ではほとんど言及されず(文学作品にわずか述べられた程度)、公認の歴史書はたんに「食料不足」と言うくらいでしかなかった。
全権代表が現地に到着すると、強制的な「集会」が開かれ、決定どおりの強制調達がおこなわれ、調達計画が達成されない所では、容赦なく財産差し押さえ、「偽コルホーズ解体」、地方からの農民追放がおこなわれた。農民に同情的な党員に対してもクラーク支持分子として、粛清の嵐がふきあれ、クバンでは、党除名者は平均で20%強(このほとんどが追放された)、多い所では4割りにも上った。ポルタフスカヤ村の党組織の場合には、組織そのものが解体された。(結局、北カフカースの穀物調達は時期が遅れ、しかも削減された調達目標で、極度の抑圧のもとでかろうじて達成されたということになった。しかし、実際に調達された量は、前年31年の約6割にとどまった)
しかし、抑圧政策によっても調達が達成できない、客観的条件を覆せないところも少なくはなかった。その場合、全権代表自身が党の政策・方針の誤りを認めざるをえなかった。
そういう全権代表は直ちに解任され、処分された。全権代表システムの限界は、新たに政治部の導入に発展する。
クバン事件を教訓にスターリンら党指導部は、問題は北カフカースだけではないとして、
32年12月から33年1月にかけ、農村政策を急旋回させ、更に苛酷な政策・方針をとった。その主要なものは、 穀物調達における予約買い付け契約から租税的意味合いをもつ義務納入制への転換、 パスポート(国内旅券)制導入による農民の土地への緊縛(33年春には、農民の出稼ぎ抑制の法令化)、 「動揺分子」による党政策の停滞化を一掃するための、全党粛清の告示(12月10日)、 機械トラクター・ステーション(MTC)、ソホーズへの政治部の設置などである。(国内旅券制度は、ツァーリズム時代のものである)
クバン事件は、政治部導入の直接的契機の1つとなった。これは、戦時共産主義の時代、
ブルジョア専門家の指揮する赤軍を政治的に統制するための手段であった政治部をまねたものである。
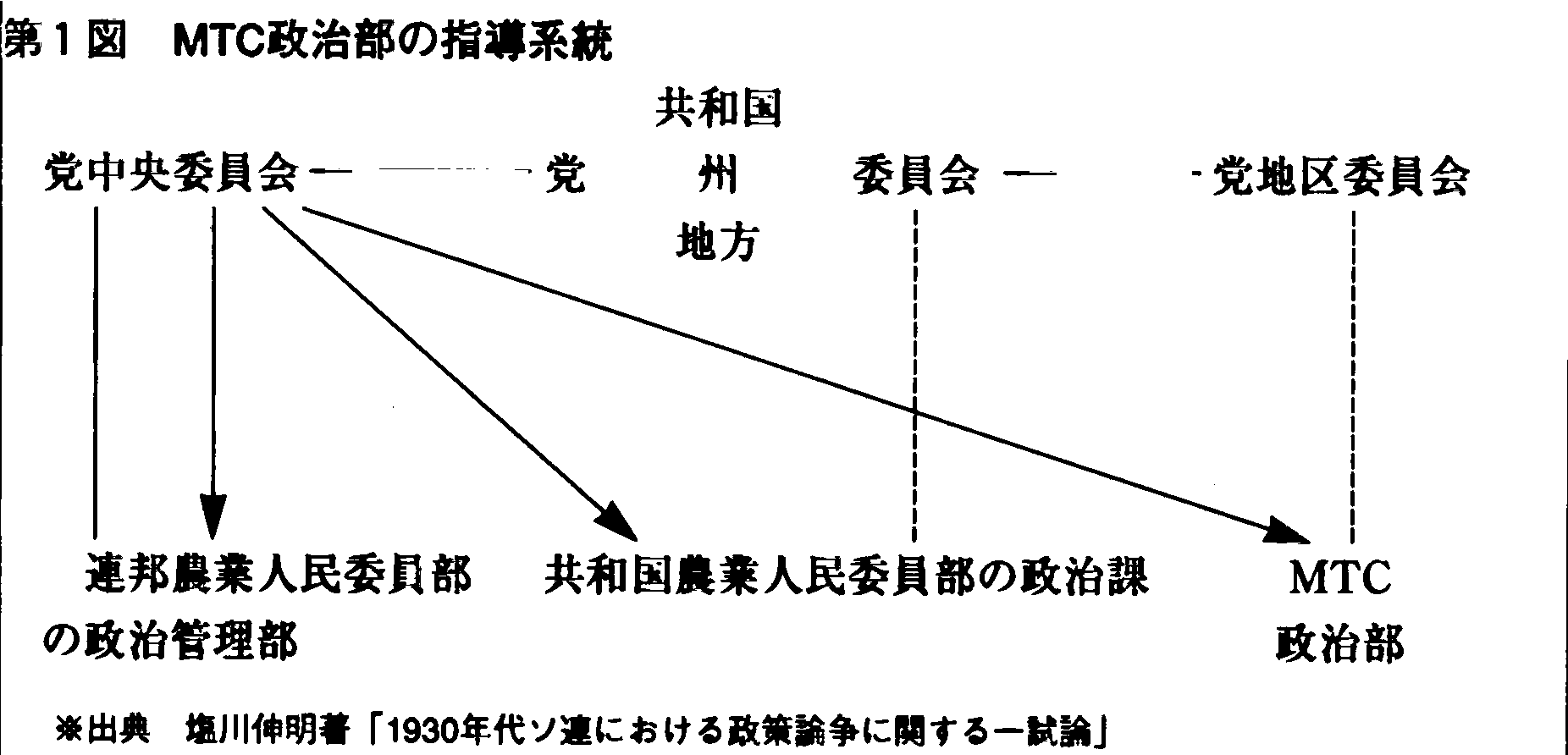 政治部の指揮系統は 第1図に見られるよう
なものである。それは 「中央から末端に至る
独自の指導系列をもっ ていて各級党委員会と
は『連絡』の関係しか
ないこと、部長は直接党中央委員会の任命(但し、人選は共和国・州・地方委員会第一書記の推挙による)によっていること─即ち、最高度のノメンクラトゥーラ(任命職名表)に属すること─」15)などが特徴的である。
政治部の指揮系統は 第1図に見られるよう
なものである。それは 「中央から末端に至る
独自の指導系列をもっ ていて各級党委員会と
は『連絡』の関係しか
ないこと、部長は直接党中央委員会の任命(但し、人選は共和国・州・地方委員会第一書記の推挙による)によっていること─即ち、最高度のノメンクラトゥーラ(任命職名表)に属すること─」15)などが特徴的である。
政治部の幹部は、党機構畑の人間が非常に多く、ついで軍関係者が多い。しかし、農業関係者は少ない。部員は、全権委員と同じように基本的に都市で選抜された者である。
政治部の任務は、全権委員のように特定目的に限定されていない。「政治部の任務はMTCを単なる経済的・技術的指導のみならず組織的・政治的指導の中心にすることにおかれていたのであり、また政治部はMTCだけでなくその下のコルホーズの全活動をも監督するものとされていたから、その権限は広汎にわたるものであった。」16)わけである(普通、1つのMTCは、30〜40のコルホーズにサーヴィスを提供している)。
政治部の最も特異な点は、それ自身としては党の機関でありながら、政治部長は同時にMTCの副所長を兼ねるという規定である。そして、規定にはないが、政治部の副部長2名のうち、1名はオー・ゲー・ペー・ウーの代表、もう1名は、党=大衆活動担当(書記局か?)がなったといわれる17)。これは最も典型的な、党と国家機関の癒着の形態をあらわしている。しかもオー・ゲー・ペー・ウーの代表が副部長となっているように、党の粛清あるいは党機関・ソヴィエト機関の指導におけるテロル体質がはっきりと示されている。
政治部が導入される前の同年8月7日、社会主義財産保護法が採択され、刑法第58条(反革命罪)が改正された。鉄道関係、コルホーズ財産(収穫物、貯蔵物、家畜をふくむ)の窃取は、「社会防衛の最高の措置、つまり銃殺によって、酌量すべき事情があるときには全財産の没収を伴う10年以上の禁固(刑務所あるいは収容所)によって」罰せられることになった(これは実際には穀物の調達を拒んだ者などにも適用された)。強制的な調達は、餓死者をも出すほどの酷さで、下層の農民たちは命をつなぐために、自分たちが作ったものを自分たちが食べて何故悪いと収穫物を襲ったのである。これには現地の党員も同情したといわれる。全権委員ですら同情した者もいた(全体では少ないだろうが)。
政治部導入の政治的意味については未だ明確になっていないが、全権代表システムの限界とおそらくは関係しているとおもわれる。というのは、全権委員とは違って、政治部の場合は党中央委員会と直結している(そのため中央委員会は新たに農業部を作って<農業部長はカガノビッチ>、それが各地の政治部を指導した)からである。つまり、党中央の指導が的確に貫徹するような組織体制への転換である。党中央の締め付け・統制のさらなる強化である。
飢饉の時期でも、強制的な穀物調達も集団化も続けられた。32年5月にコルホーズ自由市場の合法化など部分的な緩和策もとられたが、33年5月8日付けの政治局秘密指令(「行きすぎ」抑制)がでるまで、農民に対する苛酷な弾圧は放置されていた。だが「行きすぎ」が批判されたとはいえ、穀物調達と集団化の目標達成の方針はゆるめられなかった。
この間の33年1月、前述したように党中央委員会総会が開かれ、ここで農業・農村政策の基本的枠組みが決定された。その骨子は 農業人民委員部−ツェントル(中央管理部)−コルホーズという統制機構にかえ、直接農業人民委員部がコルホーズを統括し、コルホーズは、事実上の国家機構になっている(コルホーズ議長などの役員は、党の推薦で決まっ
ており、事実上任免権は党が握っている)。機械・トラクター・ステーション(MTC、エム・ティー・エス)は、国有化された、 農産物の政府による予約買い付け契約制は、租税的意味合いの強い義務的納入制に変えられた、 国内旅券制がしかれ、移動の自由は剥奪された、 全党の粛清、 政治部がMTCとソホーズ(国営集団農場)に導入された─などである。
苛酷な政策の下で餓死者も続出したが、33年の穀物調達は前年より増加した。その後天候にも恵まれ、最悪の線をゆるやかに脱出する。この苛酷な過程を農民はどのように生き延びたのか。それは党・政府と農民の妥協点として、若干の自家用食糧作物栽培、後には若干の家畜保有が認められたからである。1935年にコルホーズ大会が開かれ「模範定款」が採択されたが、ここで“4分の1から2分の1ヘクタールの私的付属地(中国の自留地にあたる)と若干の家畜(牝牛1頭と子牛、牝豚1頭と子豚、羊4匹、および制限なしの兎と家禽)”が正式に承認された。これは無視できない重要な点である。(私的付属地は、ツァーリ時代しかも農奴解放のずっと以前から「屋敷付属地」の名前で存在した。これはあまりにも収奪が厳しすぎたため、農奴が最低限生きて行けるために、もうけられた制度である。)
注1)マルクス著「バクーニンの著書『国家制と無政府』適用」マルクス・エンゲルス全集第18巻、大月書店
2)ロイ・メドヴェーデフ前掲書
3)レーニン著「労働者の同志諸君!最後の決戦にすすもう!」1918年8月
レーニン全集第28 巻
4)レーニン著「ペトログラード・ソヴェトの会議」1919年3月
レーニン全集第29巻
5)レーニン著「ロシア共産党(ボ)第八回大会」1919年3月
レーニン全集第29巻
6)
7)スターリンの農業・農村にたいする政策態度が恣意的なのは、その農民観にすで
に胎胚にしている。このころスターリンは、次のようにいっている。「小農民的
な農村を社会主義的都市のあとについてゆかすためには、社会主義的都市を先頭
として農民の大多数をひきいてゆくことのできる社会主義の基地として、社会主
義的大経営をコルホーズとソホーズの形でうえつけることが必要なのである」
(スターリン全集第12巻
)と。「うえつける」という発想そのものにすでに農
民への不信と農業への無知がある。工業(都市)に従属した農業(農村)という
思想は、その後の歴史が示すように資本主義同様の農業の位置付けとなる。つま
り、超工業化のために、労働力の都市への提供、都市生活者への食料提供、工業
用原材料の優遇などとして農業は措定された。このことはいわゆる「社会主義農
業」の破産のもととなる。
「うえつける」という社会主義建設観は、レーニンの思想と全く異なる。E.
H.カーによると、「レーニンは上からの革命なるものを断乎として信じなかっ
た」といわれる。「すでに1917年の4月に、かれは、『コンミュン、すなわち労
働者・農民ソヴィエトは、経済的現実のうちでも、人民の圧倒的多数の意識のう
ちでも、完全に成熟しきっていないような改革は、どんなものであろうとも、<
導入する>ものではないし<導入>つもりもないし、また導入してはならない』
と書いていた。そして1年後には、ブレスト・リトフスク条約の批准を承認した
党大会で、かれはさらにきっぱりと『社会主義を少数者すなわち党が導入するこ
とはできない。社会主義を導入することは、幾千万人が自分でそうすることを学
びとったときに、かれらだけがなしうることである』と繰り返した」(溪内謙著
『現代社会主義の省察』)といわれる。
8)ロイ・メドヴェーデフ前掲書
9)小田前掲書
10)ノーブ『ソ連経済史』 岩波書店
11)下斗米伸夫著「クバン事件(1932年)覚書き」−『成蹊法学』18〜19号所収
12)同上
13)同上
14)同上
15)塩川伸明著「1930年代ソ連における政策論争に関する一試論」─『社会科学研究』
(東大)32巻2号に所収
16)同上
17)同上
(3)超工業化と官僚主義的な計画化
1926年春、スターリンは、ドニエプルストロイの水力発電計画を、“農民が鋤を調えねばならない時に、蓄音機を買うといった態のぜいたくだ”と、反対した。1926年4月の党中央委員会総会は、一層の資本蓄積の努力を強調しつつ、「計画の強化と、全国家機関の活動に計画的規律の体制を導入する」ことを訴えた。しかし、スターリン・ブハーリン派は、工業の農業的基礎への依存を強調し、資本蓄積の主要な源泉は工業内部の節約と、人民からの借り入れを主張した。
同年10月26日〜11月3日の第15回党協議会は、国家の全経済に対する大規模社会主義工業の経済的ヘゲモニーの強化を宣言し、比較的短い歴史的期間内に最も進んだ資本主義国に追いつき、追い越すよう努力する必要があると主張した。翌27年2月の中央委員会総会は、ついに長期工業計画化の必要性を認め、ドニエプルストロイ計画を承認した。27年12月の第15回大会がひらかれ、スターリン派は、トロツキー派・ジノヴィエフ派らの指導者を除名し、同時にブハーリン派との決別を示唆した。合同反対派の衰退とともにスターリン派は、ますます工業化・計画化を強調しはじめる。
長期計画のための準備作業は、27年から本格的にはじめられ、同年6月8日付け人民委員会議の法令は、「ソ連邦の経済的統一の表現である計画、つまり、経済的特化を基礎として各経済地域の最大限の発展を促すと同時に、国の工業化の目的のため全資源を最大限に利用することを促す、統一された全連邦計画を創出すること」1)を要求した。
労働国防会議のもとの国家計画委員会の役割は、強化された。そして、「計画化」の意味も、23〜26年のころとは異なってきた。以前は、計画にしめされる「統制数字」は、ある意味では予測であり、戦略的な資本投下を決定する指針だったり、優先順位を討議し決定するための根拠だったりした。しかし、これからは、それはますます綿密に組み立てられた生産と分配のプログラムであり、実際的で法律的な「指令」の性格を深めていった。
だが、現場では長期計画化の作業を待ってはおらず、1926/27年経済年度には投資総額は31.7%(対前年度比)増大し、そのうちの新規建設投資は2倍以上にもなっている。28年9月、クイビシェフは、強度の工業化を強調している。
1929年4月、第16回党協議会は、ようやく第一次5カ年計画を採択した(それは計画の開始を、逆上って28年10月とした)。協議会に提案された計画は2つの案であり、原案と最適案の2つに定式化されていた。原案ですら現実を踏まえない楽観主義的なものであったが、協議会はより過大な最適案を採択した。また、この最適案はかつて反対派が主張していたものより、投資規模においてはるかに大きなものであったといわれる。
28/29経済年度は、工業の成果が上乗だった。このためもあって、「29年12月1日の法令で、1929/30経済年度の計画がより高く修正された。1929年12月5日から10日にかけて開かれた『突撃班』大会で、5カ年計画を4年で完遂させるよびかけが採択された。これは公認の政策となり、結局、5カ年計画は1933年9月30日ではなく、それより9カ月早い1932年12月31日に終了したものとみなされた。」2)のである。次から次へと繰り返される過大な計画課題の修正への暴走である。スターリン自身、31年2月4日の演説で、「3年で工業の全ての基本的・決定的部門において」3)、計画を完遂するよう呼びかけた。
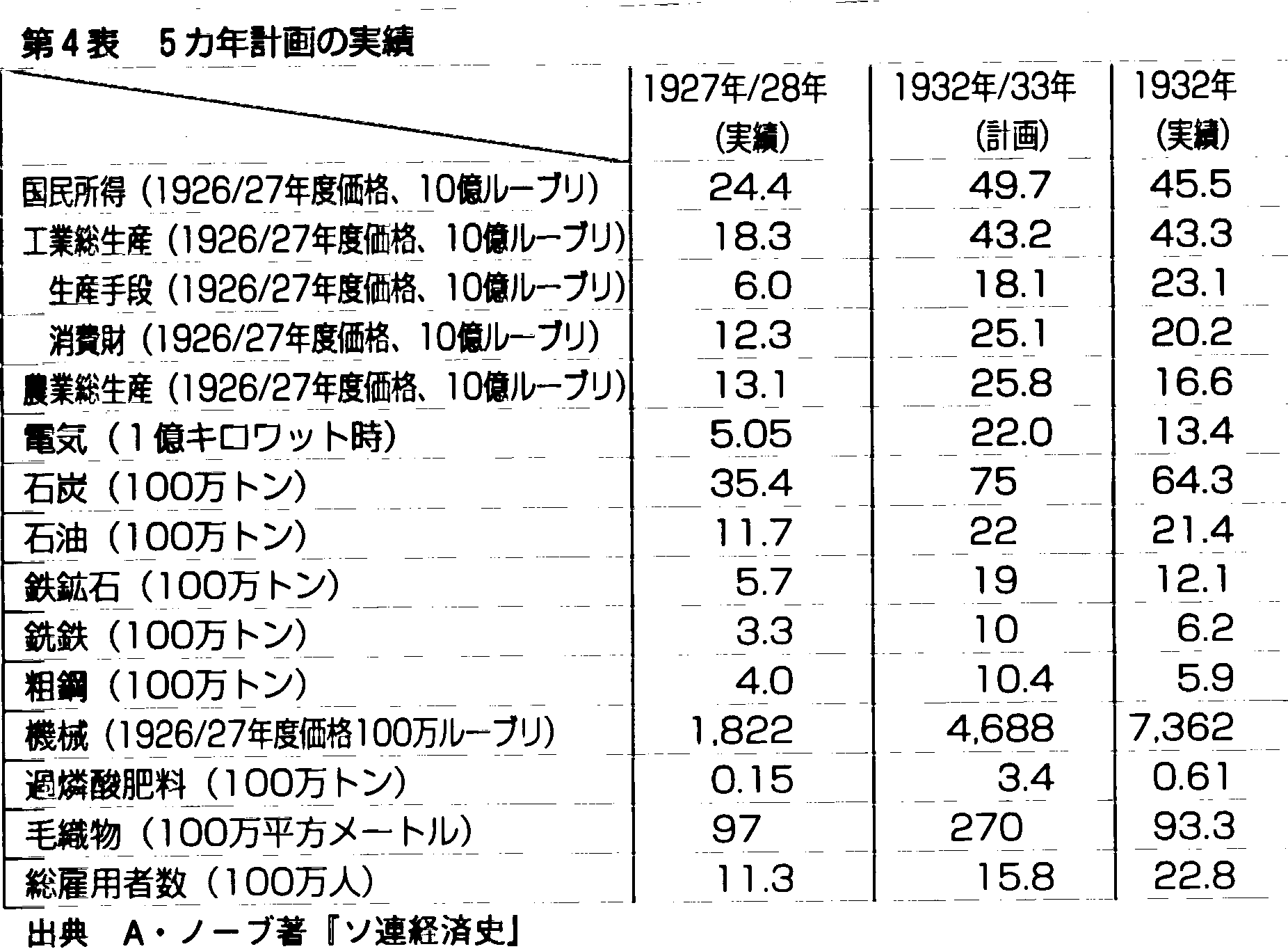 きわめて過大な計画課題を、
しかも3〜4年という高速テンポで遂行するという超工業
化の結果は、第4表のとおり である。大方が最初の最適案
でさえも未達成である。機械 のみが超過達成であるが、こ
れも割り引いてみなければならない。というのは、インフレ率が考慮されていないからである。
きわめて過大な計画課題を、
しかも3〜4年という高速テンポで遂行するという超工業
化の結果は、第4表のとおり である。大方が最初の最適案
でさえも未達成である。機械 のみが超過達成であるが、こ
れも割り引いてみなければならない。というのは、インフレ率が考慮されていないからである。
現実から掛け離れた過大な 課題をいくら政治キャンペー
ン、大衆動員(原価引き下げ、 労働生産性向上のための突撃
班運動、あたえられた計画に呼応し、それをうわまわる計画をたて実践する呼応計画運動など)をおこなおうとも、そのような非唯物論的な主意主義では目的は実現できない。
たとえば、原材料の計画的継続的な生産、規則的な輸送、計画的で良い品質の製品生産など全体的なバランスが絶対的に必要であり、一部の熱心な者のみで突撃的に奮闘しようと、それは雰囲気作りのみで生産体系全体のバランスある発展につながりはしない。
さまざまな混乱と失敗がありながらも、工業化はすすんだ。このなかで工業の管理システムも、ネップ期とは異なるものへ転換する。
第2図は、ネップ期から30年代前半の各段階のシステムの基本を法制上の観点から大江泰一郎氏が整理したもの4)である。
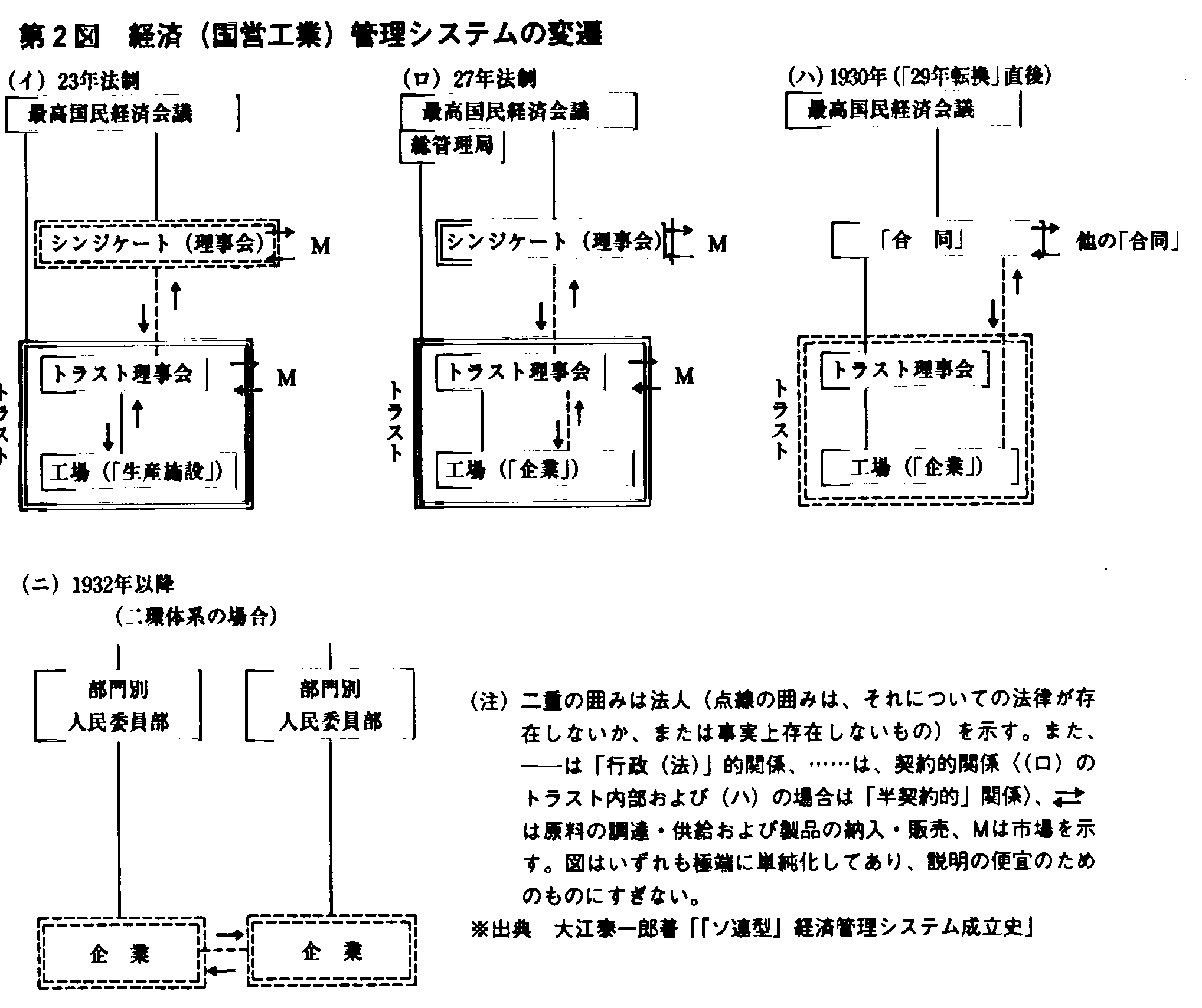 (イ)23法制(ネップ復興期)─22年にロシア共和国民法典、23年にトラスト法が成立する。22年民法典は、市場原理により、見積もり予算方式による国家からの融資をうけない国営企業およびその合同体(トラスト)は、取引関係においては、自律的で国庫との連関をもたない法人として規定される。また、この国営企業およびトラストは、自己の債務については自己の自由な処分権のもとにある財産によってのみ責任を負うとしている。
これに依拠し、23年トラスト法はより具体的に規定し、工業管理の基本環であるトラストは、「商業計算制原理にもとづき、利潤獲得を目的として」活動する「単一の企業」「法人」と規定される(23年法制では、いわゆる企業は自立しておらず、トラストの一部分であり、名称も「生産施設」である)。トラストは、市場で自由に活動し、上級の計画化=規制機関(最高国民会議とその機関)は、「トラスト理事会の経常的行政・運営に介入しない」ものとされている。
(イ)23法制(ネップ復興期)─22年にロシア共和国民法典、23年にトラスト法が成立する。22年民法典は、市場原理により、見積もり予算方式による国家からの融資をうけない国営企業およびその合同体(トラスト)は、取引関係においては、自律的で国庫との連関をもたない法人として規定される。また、この国営企業およびトラストは、自己の債務については自己の自由な処分権のもとにある財産によってのみ責任を負うとしている。
これに依拠し、23年トラスト法はより具体的に規定し、工業管理の基本環であるトラストは、「商業計算制原理にもとづき、利潤獲得を目的として」活動する「単一の企業」「法人」と規定される(23年法制では、いわゆる企業は自立しておらず、トラストの一部分であり、名称も「生産施設」である)。トラストは、市場で自由に活動し、上級の計画化=規制機関(最高国民会議とその機関)は、「トラスト理事会の経常的行政・運営に介入しない」ものとされている。
(ロ)27年法制(改造期)─「計画原理」の強化に対応して再編・制定された27年の新トラスト法は、依然としてトラストが工業管理の基本環であるが、その概念規定から「利潤獲得」という目的規定が削除され(それまでの最大限の利潤獲得から、必要最小限の利潤獲得へ)、トラストは、「商業計算原理にもとづいて」、上級機関の承認する「計画課題に照応して」活動すると、規定し直された。「生産施設」は、「企業」と改称され、生産単位として相対的自立性が強化される。
ネップ初期から工業諸部門の市場において製品、原料、燃料、資材の独占的販売・供給者としての地位を獲得してきたのは、トラストの商業的連合組織であるシンジケートである。そして、この段階ではシンジケートは、原則として「トラストの自発的な協定」にもとづく、「法人」としての商業的連合体と規定されている。
工業化・計画化の急速な進展は、同時に工業における管理システムをも大きく転換させる。(ハ)の「29年転換」である。
(ハ)29年12月5日の党中央委員会決定「工業管理の改組について」を中心に30〜32年の諸法令などで形成されるシステム─29年9月5日、党中央委員会決定は、企業長による単独責任制の原則をふたたび決定する(実際にはなかなか守られないが)。
29年12月5日決定のポイントは、第一に、党は23年いらい企業を重視し、トラスト経営者の抵抗を排除しようとしてきたが、ようやく企業を工業管理の基本環として位置付ける。だが企業はまだ自律的な法人としては認められていない。そして、トラストの「販売・供給機能」を排除し、トラストを「技術的指導、合理化、再建」の指導機関に転化させる。
ポイントの第二は、これまで契約形態(売買契約あるいは委託販売契約)で形成されてきたシンジケート−トラスト間の関係が、この間急速に(とくに27年法制成立後)変化し、トラストの上級機関である最高国民経済会議の部門別総管理局(グラフク)と同じ機能をシンジケートがもつようになり、結局、グラフクとシンジケートが統合し、「合同」となったことである。
こうして、「1929〜30年各工業部門に形成された合同・トラスト・企業の統合体は、もはや国営諸企業の重層的統合体としてではなく、計画化=規制機能および運営(販売・供給)機能を集中的に掌握する行政機関(合同)と直接的な生産活動を遂行する生産単位(企業)との垂直的管理体系として現われ、両者間にかつてのトラスト・企業間関係の形態として残存していた「半契約的」関係(すなわち「納入命令=課題」方式による関係)は急速に垂直的な行政法的関係(「計画課題」という行政行為にもとづく関係)へと『純化』される」5)のである。ここで基本的に従来の市場原理を基礎とした管理関係は、官僚主義的、行政主義的な「計画化」原理を基礎とする管理関係に転換する。
その後、「合同」はその規模が巨大すぎて活動上あまりにも不合理なため、細分化され、さらに組織後退−解体となり、ふたたびグラフクへ再編成される。それは同時に企業の運営的自立性の確立・強化の過程でもあった。(A)
他方、これまで国営工業企業全体に対する計画化=規制機能をはたしてきた最高国民経済会議は、32年いこう部門別人民委員部に解体・再編成される。(B)
ここでネップ期の最高国民経済会議の歴史を整理すると、23年に同会議のもとに、工業全体の統制と共和国国民経済会議の指導を任務とする機関(はじめは経済総管理局、のち何回か機構改革)と、直轄企業の管理を任務とする国有工業中央管理局がつくられた。しかし、直轄の重工業企業の数が増大し、26年に中央管理局は廃止され、代わりに産業別の8つの総管理局と2つの委員会が企業を管理することになった。でも再び直轄企業の増大にともない30年に総管理局は廃止され、代わって30をこす産業別の公団が直轄企業を管理することになった。それでも多くの公団は、かかえる企業の数が100〜200もあり、実際の指導は困難であった。そこで31〜32年にかけ、公団をさらに細かい部門にわけ、この結果、重工業の公団の数は、31年6月の32から32年秋には78とふえた。そして、これらの公団を指揮するために、31年、再びいくつかの産業別総管理局がつくられる。
だが膨張する重工業にともなう絶えざる組織再編、屋上屋を重ねる中間管理機構という事態は、分権をおそれる官僚主義の本性がもたらすもので、官僚自らが官僚主義に振り回されているのである。
1932年1月、ついに最高国民経済会議は、重工業の建設と管理に専念するソ連重工業人民委員部に改組された。そして、ソ連製材人民委員部とソ連軽工業人民委員部が分離・独立した。各県の国民経済会議も地方工業管理局に改組された。しかし、重工業人民委員部はひきつづき分割され、スターリンが死んだときには22に及んだという。
(A)=計画化・管理規制機能と、(B)=運営機能(企業)との「二環体系」を典型とする工業管理システムは、こうして32年ごろに形成される。
「二環体系」のもとで、企業間の経済関係を、計画にもとづく「契約」関係の組織化によって媒介するシステムが定着するのが、33年末の契約法からであるといわれる。
注1)A・ノーブ前掲書からの重引
2)A・ノーブ前掲書
3)『スターリン全集』第13巻、50−51ページ
4)大江泰一郎著「『ソ連型』経済管理法システム成立史<1>」─『静岡大学法経 研究』1978年2月号
5)同上
(4)急増する労働者と、労働組合の国家機関化
超工業化は、雇用者数を大幅に増加させた。1927/28年の全部門での雇用者数は、1135万人だったのが、33年には約2280万人と2倍以上となっている。この中には、集団化から逃れてきた多くの農民もいた。
労働者の急増は労働規律をめぐる、生産撹乱・規律違反者の処分などで紛争を広範に引き起こしている。29年3月6日、労働規律を強化する法令がだされた。
その前年の11月10〜24日に、第8回労働組合大会が開かれ、大会は高速度の工業化をうたい、「社会主義の次の任務の積極的解決のために労働者大衆と農村勤労者を以前よりももっと動員すること」を要求した。そして、人事においてブハーリン派のトムスキーは労組中央評議会議長にまだとどまったが、同評議員にはスターリン派のルズターク、オルジョニキーゼ、クイビシェフ、カガノヴィッチ、ジュダーノフの5人が選出され、スターリン派はモスクワ党組織につづいて労組においてもブハーリン派の勢力を凋落させた(トムスキーは29年4月には正式に議長を解任された)。
労組関係におけるスターリン派の組織的勝利によって、労働組合の主要任務は明確に生産性向上になり、29年4月、党中央委員会は労組に対して、「生産性の向上と労働規律、プロレタリアートの新しい層の階級的強化や、労働者階級の生産的発意および社会主義競争を組織することを、社会主義工業建設における決定的任務」1)とするよう指示した。
こうして、「1930〜33年までの間の一連の規則や法令によって、欠勤者──それは飲酒癖の結果、ありふれた現象であった──は解雇、工場付属住宅からの追立て、さまざまな特典の喪失によって罰せられた。このため欠勤は著しく減少した。」2)といわれる。
1931年、スターリンは、賃金「均等主義」批判の有名な演説をした。熟練労働者が極度に不足している時期なので、これはなにがしかの意味をもっていたが、しかし、この結果最低熟練労働者と最高熟練労働者の賃率比は、1対3.7も格差がでた。これはあまりにも差がありすぎる(ネップ期には各差縮小の政策がすすめられていた)。しかも問題なのは、「スターリンはまた、工業カードルに対する高級と特権の政策を奨励し、レーニンによって確立された、党員は熟練労働者より多額の収入を得てはいけないという古い規則を廃止した。」3)のである。小売店もこうした特権的労働者専用の店をつくった。
労働人民委員部のスターリン派の掌握は、労組に対するときより若干遅れたが、30年6月26日〜7月13日の第16回党大会でのスターリンによる批判、9月3日の中央委員会アピール(労働人民委員部といくつかの労組批判)がなされ、8月3日には、労働人民委員ウグラーノフ(ブハーリン派)が解任された。そして、10月3日には、失業手当てが廃止され、同月20日、党中央委員会は、失業解決を宣言した。失業手当てが廃止された理由は、“職業紹介所に登録されている者の圧倒的部分はエセ失業者であり、渡り者・強欲者その他の生産破壊者であるのに、労働人民委員部旧指導部は彼らの為に1929/30年度に6000万ルーブリもの失業手当てを予定していた。これは労働者国家の資金の無駄遣いである”というものである。労働者の利益を擁護する労組の機能がほとんど無くなるという事態では、経営者と労組間の紛争を調停する立場の労働人民委員部の役割はもはや必要もなくなってきているのである。
労働行政機関の新任務は、30年11月に開かれた全連邦労働機関会議で打ち出された。それはいうまでもなく、労働者を生産へ動員することであり、そのための組織化である。
それまで労働人民委員部の最大の機能は、労働市場調節機能であったが、失業の「解消」とともに(実際は労働力不足の解決・調整の仕事はあるのだが)、労働人民委員部の職業紹介所は30年末にカードル管理部と改称され、経済への労働力の計画的供給と労働力養成の監督を任務とすることになった。
だが経営機関は、労働力調達に関しても労働行政機関を信用せず、直接調達をめざした。そして、31年9月13日の法令は、都市でも農村でも、社会化セクターの企業・施設・組織は、直接労働者職員を雇用することができるように、カードル管理部経由義務制を廃止した。
労働紛争解決については、ネップ期は、第一審は企業レベルの労使対等の「評価・紛争委員会」があり(この委員会の任務は紛争処理だけでなく、賃率表作成・作業ノルマ・出来高歩合作成などにかかわるか否かで論争があったが、結局、後者は企業側の「賃率=規準化ビューロー」があたることになった)、ここで解決しない場合は、中央・地方の労働人民委員部機関に持ち込むこととした。上級審査機関としては、22年4月から調停委員会と仲裁裁判が制度化された。
だが、前述したように労組自身、その機能が変質したため、労使紛争は抑制され(実際30年代にはいると、労使紛争は減少する)、人民委員部の調停・仲裁活動も減少する。
この他の方面もふくめ、労働行政機関の役割は30年以降、衰退し、形骸化する。1933年6月23日、ソヴィエト中央委員会・人民委員会議・全連邦労働組合中央評議会の共同決定は、ついに労働人民委員部とその機関を労働組合に合体させ、労働人民委員部の諸機能を労働組合に移管させることを指示した。労働人民委員部の解体である。この結果、労働組合は、社会保険、労働保護(労働監督局)、団体協約登録、経済計画作成(労働力計画)に関して、正式に国家機能を受け取った。
こうして、労働組合は新たに幾つかの機能を獲得したが、それは経営に対して労働者階級の利益を通す方向性をもったものでなく、逆に、経営とともに生産性向上に労働者を動員していくためのものであった。労働組合は、再び国家機関化していった。
注1)R・ダニエルズ前掲書
2)A・ノーブ前掲書
3)同上
(5)ソヴィエトの形骸化と、党の絶対化
「上からの革命」期は、民主的で自治的なソヴィエト構造が破壊され、極端な中央集権化が進行した。
最大の問題は、前述したように党の専横がまかり通り、各級ソヴイエトは意のままに振り回され、司法機関は完全に党に従属したことである。プロレタリアート独裁の名のもとに法治主義は、粉砕され、公私のけじめもなくなった。いわゆる「スターリン体制の確立」である。
次にソヴィエト機構における極端な中央集権主義は、まず29年には、農業の全面的集団化を前にして農業統制をつよめるために、ソ連農業人民委員部が新設された(それまでは各共和国・各民族の独自性を考慮して、ソ連邦レベルでは農業人民委員部を設置していなかった)。30年には、権力的な全面的集団化にともなう政治的緊張に対処するために、各共和国の内務人民委員部が廃止され、その管轄下にあった警察は、ソ連政府の下の統合国家保安管理局(オ・ゲ・ペ・ウ)に移管された。このオ・ゲ・ペ・ウは、34年にソ連内務人民委員部に改組された。36年になると、各共和国内務人民委員部は復活し、一般の警察は共和国の管轄となったが、しかし、各共和国の内務人民委員部は各共和国政府よりもソ連内務人民委員部のほうに強く従属した。36年には、ソ連司法人民委員部も新設され、同年に制定されたスターリン憲法では、民法典、刑法典は各共和国ではなくソ連が制定することになり、各共和国の権限はせばまった。
ソ連中央執行委員会の活動は、党の方針と人民委員会議の立法を機械的に通過させるだけのものになるが、31年以降は、諸分野の一般的基準を定める法律は、党中央委員会と人民委員会の共同決定によって公布される形となった。
「上からの革命」による「スターリン体制」の確立をまとめた36年憲法(スターリン憲法)は、今までの選挙方法をやめ、直接、平等、秘密の選挙方法に切り替えた。これとともに、ソ連と各共和国のソヴィエト大会および中央執行委員会は廃止され、直接選挙の最高ソヴィエトがそれぞれの最高権力機関となった(第30、57条)。そして、立法権は、最高ソヴィエトだけがもつものとし(第32、59条)、人民委員会議の立法権は否定された。しかし、36年憲法は、ソ連最高ソヴィエト幹部会の地位とその立法権の有無については、不明確であるが、その第49条で「命令」の公布、ソ連の法律の「解釈」権を与えた。
36年憲法施行後、立法活動はソ連最高ソヴィエトに移ったかにみえた。だが大粛清のあとの40年ごろから再び旧習にもどった。ソ連最高ソヴィエトは、「1938年の発足いらい1956年まで120の法律を採択したが、『その大部分はソ連最高ソビエト幹部会令を承認するという法律であった』。しかもこれらの幹部会令の大半は、ソ連大臣会議が用意したものであった。」という1)。(46年にそれまでの人民委員会議、人民委員部、人民委員は、それぞれ大臣会議、省、大臣に改称された)
そして、重要な法律の公布は相変わらず、党中央委員会とソ連大臣会議の共同決定のかたちで公布された。
こうして、党の絶対性、ソヴィエト内での政府の優位性が確立されるにしたがい、ソ連ソヴィエト大会−ソ連最高ソヴィエト、ソ連中央執行委員会の召集は、不規則になっていく。「1924年憲法は当初大会は1年に1回召集されるとしていたが(11条)、1926年にはひらかれなかった。1927年の大会で大会の召集は2年に1回とあらためられたが、しかし1931年に第6回大会がひらかれてから35年の第7回大会までの4年間、大会はひらかれなかった。1924年憲法は、ソ連中央執行委員会の会期は1年に3回召集されると規定していたが(21条)、実際には1929年まで平均して1年に2回しか召集されなかったし、30年には一度も召集されなかった。1931年に中執委の会期は、2年ごとにひらかれるソビエト大会と大会とのあいだに3回と改められたが、31年には一度も召集されず、35年以後は1年に1回しか召集されなかった。1936年のソ連憲法は、ソ連最高ソビエトの会期は1年に2回召集されるものとした(46条)。この規定は、1938年から45年までの第1期最高ソビエトについては、戦時(41〜44年)をのぞきまもられていた。しかし戦後の第2期(1946〜49年)および第3期(50〜53年)のソ連最高ソビエトの会期は、どちらも4年間に5回しかひらかれず、その大半はその年度の予算と幹部会令の事後承認という仕事しかしなかった。そのうえ第二次世界大戦後は、ソ連政府はソ連最高ソビエトに活動報告さえしなくなった。」2)という。パリ・コミューンの教訓などは全く口の端にさえのぼらなくなった。
注1)稲子恒夫著『ソビェト国家組織の歴史』 日本評論社
2)同上
党に従属する司法と<革命的(社会主義的)合法性
10月革命直後、ロシア・マルクス主義者たちの間では、法フェティシズム(法の物神崇拝)はブルジョアジーによる階級支配を隠蔽するものとして批判されていたのが一般的であった。帝政ロシア時代、ツァーリの勅令は法に優先し、ツァーリはもとより、(ツァーリの命令を実行するかぎりでは)大臣、その他の官吏の法違反は免責されていた。こうした伝統的風土では、人民自身の自己統治における法の意義、法治主義の意義は社会全般に認められていなかった。1)
戦時共産主義の時代、合法性への志向性が指導者たちに強まる。しかし、それは単一の政治指導による国家秩序の必要性からであり、この場合の合法性は、革命的規律と同義語であった。権力の乱用防止のための合法性ではなく、ましてや人民諸個人の権利実現のための合法性ではありえなかった。
ネップ時代、革命的合法性(法による支配)が強まり、実際に20年代はじめ種々の法典が編纂された。それは内戦が基本的に終わり、安定的秩序が要請されたこと、外国投資を招くためにも法的安定が要求されたことなどによる。
だが合法性はあくまでもプロレタリア権力の支配秩序の維持のためである。このため、ロシアでは<革命的合法性>の擁護者は裁判所でなく検察官であり、法の維持・執行を全般的に監督をするのは検察官である。だが、検察官の監督は党や中央国家機関には及ばない傾向をもっていた。
20年代前半の<革命的合法性>は、法律の形式的遵守でなく(法フェティシズム批判)、あくまでも<革命的合目的性>にふまえて合目的的でない法律は適用をひかえるというのが、法律関係者たちの多くのとらえ方であった。つまり、プロレタリアート独裁の権力は、非常手段(暴力をふくむ)によっても、また、革命的合法性によっても実現されると考えられた。しかしこの場合、どちらの手段をもちいるかは恣意的に行われるのでなく、その選択はソヴィエト政権を取り巻く種々の条件によって決定されるとした。
こうした<革命的合法性>の原理は、究極においては法がプロレタリアート独裁の権力を拘束しないということを意味し、このことはボリシェヴイキの一般的理解であった。レーニンも「プロレタリアートの独裁とは、このばあい主役を演じている階級と、独裁と呼ばれる、国家権力の特殊な形態─すなわち、法律や選挙ではなく直接住民の武装力に依拠する権力の特殊な形態─とを規定する科学的な用語である。」2)、「独裁は、直接に暴力に立脚し、どんな法律にも拘束されない権力である。」3)といっている。しかし、そこではプロレタリアートと統治者が対立した場合、とくに権力が暴走した場合それをチェックする方法までは、考慮されていない。
20年代半ばになると、革命的変革とともに法は現実から乖離するという矛盾が顕在化する。そこで<革命的合法性>は、“形式的には法違反でも、<革命的合目的性>に基づくものは、<革命的合法性>に違反しない”という形に進化する4)。法律改編の立ち遅れの合理化である。
だが、1928年の非常措置は、形式的な法律と党の政策の正面衝突に発展する。前述したように強権的な非常措置は、違法行為におかまいなしに実行されたからである。このため、<革命的合法性>の理論は混迷し、この時期<革命的合法性>への言及はほとんどなくなる。
その後、非常措置の反復、恒常化にともない、<革命的合法性>原理は、党による違法で強権的な統治、反人民的な統治とも両立するものへと変質する。つまり、司法活動は党の政策に従属する。党の政策が正しいか否かを問わず、党の政策が反人民的か否かを問わず、これに奉仕するものとなる。それは非常措置の実施過程で、農民をかばう検察官、暴力的な非常措置の実施に積極的でない検察官は、次々と党機構の圧力で解任され、抑圧されたからである。
検察官、裁判官などへの弾圧・抑圧は、同時に刑事制裁の強化による穀物調達の推進であった。「ウラル・シベリア方式」は元来、共同体規制による強制であったが、これがでも不十分なため、刑事制裁が強化されたのである。このため29年中は、刑法の部分的改正が数度にわたっておこなわれた。
前述したように、1929年6月28日の全ロシア中央執行委員会・人民委員会決議にともない、第61条が改正され、穀物引き渡しの拒否は「全国家的課題の拒否」として、最高1年の矯正労働または懲役が科せられた。これに先立ち、第62条も改正され、課税目的物の隠匿、数量の不正申告などに対しては、目的物の5倍の罰金が科せられている。また、第73条には、調達員への反抗を罰するため、公務員および社会的活動家に対してその職務を中止、変更させる目的で、殺人の脅迫、財貨の要求、暴行を行った者には、6ケ月以下の矯正労働または罰金に処す内容が追加された。第129条には、コルホーズをつくって優遇措置を受けようとするものは「偽装組合」として、その創設・運営する者に5年以下の自由剥奪と財産没収、「偽装組合」と知って参加した者には2年以下の自由剥奪または1年以下の矯正労働に処す内容が新たに加えられた。第111条aは、組合の創設・運営を監督する公務員による職権の濫用、職権の不行使、職務怠慢について6ケ月以下の自由剥奪を定めている。
刑事制裁の強化は、農村だけではない。都市でも同じである。工業化のテンポがメチャクチャにアップされるとともに、党中央委員会は29年3月、すべての党組織に労働者の労働規律の向上に関する指令を発し、党機関、労働組合、司法人民委員部の「援助」の不十分性を批判している。
刑法の部分的改正とともに、刑事訴訟法もその手続きの簡素化・迅速化をめざして、部分的に改正されている。
だがこの過程で司法界は混乱し、大別すると、法死滅開始論の傾向と“党の政策遂行の一手段としての法の有用性”を唱える傾向に別れた。当時かかげられた「ネップと革命的適法性を葬れ」というスローガンは、前者の傾向を助長した。だが、30年3月、「クラーク絶滅・全面的集団化」の「行きすぎ」が欺瞞的に公式見解となって、結局、後者の見解が公認のものとなった。
新たな<革命的合法性>は、従来のものと次の点で異なっている。第一は、法フェティシズムも法死滅論も批判し、法は「社会主義的変革」を促進する有用な道具として、プロレタリア国家とその統治の道具としての厳格な実施が要求された。法は共産主義の第2段階で死滅されることは否定されなかったが、「国家と法の最大限の強化」(スターリン)として定式化されたことである。第二は、混乱期に地方活動家が独自に裁量して、「法の適用を排除」してきたのを否定し、革命的独裁の中央機関が要求する方法、手続きによる法の実施をおこなうように、上からの統制を強め、下部機関・活動家を絶対的に従属化させたことである。
その後も、法の抑圧的性格は強まる。32年には、「社会主義的財産」の窃取および毀棄に死刑を定めた「社会主義的財産保護法」、34年には、反逆罪に家族の連座制を定めた「国家的犯罪に関する規程」が法律化されている(家族連座制などというは前近代的なものそのものである)。
<革命的合法性>から最終的には<社会主義的合法性>に至る過程は、プロレタリアート独裁の権力の中央機関(実際は党中央あるいはスターリン)に司法が従属する過程であった。これはまさに、「『国家と法の死滅の前に、最大限に強化される権力』の担い手である党・国家官僚制が、法の上に立ち、恒常的に法を侵犯する一方で、すべての市民が『法律の厳格な遵守』を要求される。」5)体制の確立といえる。
こうして、<革命的合法性>は、33年からヴィシンスキーが唱える<社会主義的合法性>に、実質的には転換するのであった。
ロシアの伝統的法文化の特徴に決して自覚的だったといえないロシア共産主義者たちは、法の扱いでジグザグを繰り返し、けっきょくは国家権力の支配の手段としての法という位置付けに終わった。人民自身の自己統治のための法、国家死滅を促進するための法という階級的観点は放棄された。これはロシアの伝統的法文化に対する批判的自覚的態度の欠落による(公平を期すと、それまでのマルクス主義が法にたいする階級的態度を十分に確立しえてないという事情がある)。伝統への回帰である。
注1)諸文明における法文化は、さまざまな学者によって分類されている。例えばアメリカの法学者、R・M・アンガーは、古代中国の律令体系をモデルとする「官僚制的もしくは規制的法」と、近代的西欧法をモデルとする「法秩序もしくは法体系」との対比(諸実定法を正当化または批判する基準としての「高次の法」<神の法、自然法>という観念は、西欧においては近代のみならず前近代にもすでに普遍的である)を行っている。マックス・ウェーバーも、主観的権利(請求権の性質を有する権利)の位置付けに関する「行政規則」的法秩序とレヒト(権利=法)的法秩序との類型的対比(権利を権力の許容するかぎりで認めるものと、権利は国家権力をもこえる高次な次元で認められるというものの対比)を行っている。大江泰一郎氏はその著『ロシア・社会主義・法文化』で、これらの類型的対比は2つに大別できるとして、「これらの二分法のそれぞれにおける第一の類型は、いずれの論者においても、政治的権威の単なる命令と『法』との区別、したがってまた主観的権利の固有性、そしてさらに実定法を正当化または批判する基準としての「高次の法」(自然法、神の法)観念の具有をメルクマールとしており、この点で、法がかかる契機を欠いたまま、もっぱら政治権力の定立する規範(客観法)へと収斂するところの、第二類型と区別される」としている。
この観点からすると、「ロシアの法文化は、その学問的に昇華したレベルにおいては19世紀にヨーロッパ(とくにドイツ)の法実証主義の影響を強く受けはした(このことが一因となって、ロシア法は─したがってまたある意味ではソビエト法も─誤ってしばしば『西欧法』に関係づけられる)が、現実の政治生活と民衆の日常生活のレベルでは、15世紀モスクワ国家成立以来の伝統ロシアの、前述のメルクマールに照らしていえば『アジア的』な、『官僚制的法』類型から離脱することはついになかったのである。20世紀初頭までの帝制中国の法をこの類型の『中心』と見れば、ロシア法はそれと同じ類型の『周辺』に位置づけられる」(大江前掲書)ことになる。(なお、ドイツ自身、西欧法文化の中心ではなく、周辺に位置する)。
諸文明における類型、さらにその偏差は、当該社会の歴史的な経済構造が第一に規定するが、それだけにとどまらない。当該社会の政治・軍事制度、家族制度、共同体、諸団体、さらには宗教などとの複雑な相互作用が歴史的にもたらしたものである。
なお、革命前のロシアの法意識に関して、保田孝一著『ロシア革命とミール共同体』(御茶の水書房)は、次のようにいっている。「ロシアの土地所有の歴史には、所有、相続、家族分割、ミールの割当には秩序がなく規則より例外が多かった。支配者は、規則、勅令を公布したが自らそれを破った。臣民はツァーリの勅令に耳をかたむけ、それに屈服するが遵守しなかった。ロシア農民は慣行にしたがって生活していたのである。」、「ロシアの知識人も、法律を尊重しなかったし、その価値をも認めていなかった。だから革命後の1920年代にたびたび土地政策が変わることが起こりえたし、不思議なことではなかったのである。」という。
2)レーニン著「軽信という伝染病」 17年6月 レーニン全集第25巻
3)レーニン著「プロレタリア革命と背教者カウツキー」 18年10〜11月
レーニン 全集第28巻
4)<革命的合法性>が、革命の利益と法の遵守(法秩序)を比較し、前者に優先性を認めるという発想は、革命の利益と形式的民主主義を比較し、前者に優先性を認める発想と共通している。このことは、ボリシェヴィキ指導者には、共通してある。
たとえば、23年10月、トロツキー派、民主的中央集権派、労働者反対派の指導者たちが『46人宣言』を発表し、トロイカの指導路線を批判するなかで、その1つとして書記局位階制批判・党内民主主義の回復要求を提起したのに対し、ジノヴィエフは「革命の基本的な利害という見地、革命の利益という見地からみれば、われわれに必要なことは、党の真の守護者と言われる人々にのみ、投票権を与えることである。革命の利益─これこそ最高の法律である。革命家は誰でも言う。『純粋』な民主主義の『神聖な』原則などくたばってしまえと。」(R・ダニエルズ前掲書)と、反対派を批判する。ブハーリンも反対派を批判し、「ボリシェヴィキは常にメンシェヴィキの形式的な民主主義と区別をつけてきた。‥‥それは党や労働階級に対して、党が指導者たちに率いられているという事実を隠さない。‥‥意識の程度の高い者が低い者を指導するのである。‥‥意識の低い者、活動力の乏しい者が、意識を高め活動的になっていくのである。こういった内部機構こそが真の民主主義を形づくるのだ。」(同前)といっている。
スターリンも、25年12月の第14回党大会でジノヴィエフ派を批判し、「多分、反対派の同志たちには、われわれにとっては、ボリシェヴィキにとっては、形式的民主主義は零であり、一方、党の真の利益がすべてであるということがわからなかったであろう。」(同前)と、かつてのジノヴィエフと全く同じことをいっている。
トロツキーとて、反対派に転ずる以前は基本的に同じである。彼は内戦が終わって、経済建設が日程に上ったときの「労働組合論争」で、労働組合を国家機関化することを主張し、労働組合を「新しい任務と方法」にむけて「上からのゆすぶ り」政策で追い込むとしている。これに対し、レーニンは「彼の政策全体は労働組合を官僚主義的に引きまわす政策である。」(「労働組合について、現在の情勢について、トロツキーの誤りについて」
20年12月)と、厳しく批判している。トロツキーが10月革命以降において、党内民主主義を強調するようになるのは、少数反対派になってからである。こうしたご都合主義的態度は、トロツキーだけでなく、ジノヴィエフも、ブハーリンもおなじである。
これは、内容(革命の利益)と形式(労働者民主主義)を機械的に分離し、時々の情勢変化を口実に、指導部のみの判断で労働者民主主義を停止したり、指導部の許容する範囲内で採用したりするプラグマティックな態度である。平時はもちろん、緊急時であろうと、最低でも前衛分子の可否を問うべきである。不可能ならば事後においても可否を問うべきである。そうした形式を無視する所では、内容(革命の利益)−プロレタリアートの独裁は強化されず、党の独裁からさらに党の支配、果ては階級の復活に至るであろう。いわゆる“目的のために手段を選ばず”という態度・発想は、党と革命の堕落への道である。
5)小田前掲書
固定化する党・国家官僚体制
「上からの革命」期をふくむ、29年すえから30年代半ばの時期に確立したソ連政治体制を、ここでは党・国家官僚制と名付ける。
党・国家官僚制とは何か。これを一言で規定するのは、難しいが、とりあえず暫定的にいうならば、「上からの革命」期に完成した党・国家システム(このシステムを構成する諸要素はすでに20年代から徐々に形成されてきた)が、全社会をおおい、党の絶対的「指導」権=支配権が全社会的に確立している体制のことである。そして、その組織構造は、党のノメンクラトゥーラ制度に支えられた、官僚制的なヒエラルキーをもつ。
ここでいう党・国家システムとは、「単一支配政党が重要諸政策を排他的に決定し、その政策が国家機関にとって直ちに無条件に義務的となり、かつ党組織と国家機関が機能的にも実体的にもかなりの程度オーヴァーラツプしている─そこには同時に、党自体が権力機関的要素をもつものに変質するという面を内包する─という関係さえ確立しているならば、『党=国家体制』の存在をいいうる」1)という場合の「関係」と同じ意味である。
注1)塩川伸明著「ソヴィエト史における党・国家・社会」─溪内謙・荒田洋編『スターリン時代の国家と社会』
木鐸社 に所収
(1)党・国家システムの確立
党・国家官僚制の特徴を主要な点に限っていうと、まず第1は、「上からの革命」期の全権代表システムや政治部などにより、党・国家システムという複合権力体が基本的に完成したということである。
このシステムの具体例をあげるとすれば、以下のものがある。それは、第17回党大会(34年1月26日〜2月10日)で、ポストィシェフ(党中央委員会書記だったが、後ウクライナ組織の書記に転ずる)が、非常措置から全面的集団化の過程での党の指導方法を振り返って、述べたものである。
「この決定的な数年間、ウクライナの多くの党組織では、抑圧が『指導』の効果的方法であった。それを特徴づけるために‥‥次のような、ウクライナの非常に多くの地域で典型的にみられる例を挙げてみよう。ノヴォグラード・ヴォルィンスク地区では他の地区と同じく播種のための作戦上のトロイカがうちたてられた。それは、(党の─A・ノーブ)地区委員会書記、中央委員会からの全権代表、地区国家保安本部(ゲー・ペー・ウー)部長から成り、トロイカの会議には地区の検事、民警の長、地区統制委員会議長が参加した。トロイカの会議の議事録を抜き出してみよう。『小売協同組合議長を解雇し裁判にかけること。コンドラーチェフに新議長選出を委任し、民警指揮官に裁判の手続きをさだめさせること。村ソヴィエトの議長を解任し裁判にかけること。村ソヴィエトのメンバーおよびすべての農村組織を新聞を通して厳しく譴責すること。コルホーズ第2からあらゆる優遇措置を剥奪すること。(党の─A・ノーブ)細胞ビューローを解散させること‥‥』これが、この数年間に支配的となった露骨な専横なのである‥‥。」1)と。
全権代表、ゲー・ペー・ウー要員、地区党幹部からなるトロイカが、他の国家要員、党の統制委幹部などとともに、村の政治・経済組織の長の任免を勝手におこない、裁判、処罰をも恣意的におこなっている様子がよくうかがえる。このように当時は、党と国家(機関)が癒着し、公私の混同が露骨におこなわれ、みずから定めた司法制度と法すらも無視して、非常措置による穀物調達がおこなわれているのである。そして、その過程で、党が積極的に全面にあらわれ、直接に干渉し、しかも国家機能を代行(党の国家化)しているのである。
全権代表システムの場合は、穀物調達という任務を目標としているため、これに関連した活動に限定されるが、次の政治部の場合には、全面的な集団化という方針の下で、活動範囲はもはや限定もされなかった。
全権代表システムという制度は、「20年代に一定程度定着していた党とソヴィエトの機能的分業と、党およびソヴィエトのそれぞれの階統制的指揮系統とを事実上廃棄することによって、20年代における統治システムを実質的に破壊したのであった。そしてそれは、その後の努力にもかかわらず廃絶されることはなく、30年代における統治システムの基本的要素たりつづけた」2)といわれる。
だが、全権代表にしても政治部にしても、それはあくまでも非常時の機関であり、いずれも長続きしなかった。というのは、既存の正規の党組織の系列があり、非常機関の系列の存在は、党の指導系列としては矛盾関係になるからである(政治部は、結局2年とはもたなかった)。その矛盾は、両者の対立か、現地の下級機関が受動的になり非常機関の指示まちとなるか、である。また、非常機関の専横によって、ソヴィエト組織は破壊あるいは形骸化され、そのことは同時に党活動が国家機関活動・大衆運動に一面化し、「党の本来の活動」を軽視・放棄する結果となる。
こうして、最終的には非常機関は廃止され、正規の党組織の指導系列にもどり、ソヴィエト組織も正規なものとして再建される。
にもかかわらず、内田氏らは非常機関の体質が「30年代における統治システムの基本的要素たりつづけた」という。これは一体どういうことか。
それは第一に、政治部は廃止されたが、政治部活動家の大部分は再編された地区委員会に配属され残って、政治部の体質と農民監視は、違った形で継続されたからである。「地区委員会の再編・強化は、 大きすぎる地区は─MTC活動領域を基礎として─いくつかの新しい地区に分割される、 大きな地区では第2書記のポストをおく、 地区委員会の機構として農業部を設置し、第1書記か第2書記がこれを率いる、というのが主な点である。またMTCについても、政治部の代わりに、政治担当の副所長をおくこととされている。これまでの政治部活動家は、新しくつくられる地区の第1書記、第2書記、旧地区の農業部担当の第2書記、MTCの政治担当の副所長等になることが期待された。なお、地区委員会書記およびMTCの政治担当副所長の任務は党中央委員会の承認によるとして、引続き高いノメンクラトゥーラに位置づけられた。」3)のである。
第二は、党と国家機関の露骨な癒着形態を解消したとしても、重要諸政策の党による排他的決定権の保持─国家機関の無条件の義務的受け入れの関係は、党のテロルを背景とした権威によって、継続されたからである。
農村を中心とする32〜33年の深刻な危機を脱した後、一連の緩和策の時期がしばらく(34〜36年)つづく。それは、第2次5か年計画における工業のテンポ引き下げ・軽工業食品工業の重視(結果としては重工業偏重はかわらなかったが)、配給制廃止、農村における大量弾圧政策の抑制と政治部の廃止、第1回作家大会における古典的文学観の復位、世界で最も民主的とうたわれた36年憲法の準備・制定、リトビィノフ外交の展開と人民戦線戦術への転換などにみられる(ブハーリンはこれを「ソヴィエトの春」とよんだ)。
だがそれは一時的な戦術であった。1934年12月のキーロフ暗殺をきっかけとした大量粛清と「反対派」抹殺が、30年代後半、断続的に繰り返される。大量弾圧と見せしめ裁判劇は、一面では党内引き締め(厳格な序列制の下での一枚岩化と自律的思考の抹殺)であるが、他面では社会全体に対する恫喝とテロルを背景にした権威の保持を画策したものにほかならない。
この権威は、国家機関はもとよりあらゆる社会諸分野において、思考し、決定を出すのは党中央(最終的にはスターリンへの個人崇拝4))であり、国家機関と人民は言われた通りに忠実にそれを実践するという思想と作風を強制しつづけたのである。
注1)A・ノーブ前掲書
2)内田健二著「『党の国家化』の把握の仕方について」−溪内・荒田編前掲書に所収
3)塩川伸明著「1930年代ソ連における政策論争に関する一試論」?
4)マルクスは、1877年11月10日付けのヴィルヘルム・ブロースあての手紙で、「われわれはあらゆる個人崇拝を不快とし、インタナショナルの時代に、いろいろの国からうるさくもちだされた私の功績をたたえる無数の策動をけっして公表させることなく、時おり叱責するほか返事一つしなかった。」と、いっている。個人崇拝は、対等・平等な共産主義的人間関係を破壊するものでしかない。レーニンも同じである。「1918年8月末暗殺の企てにより傷ついたレーニンは、2週間余の静養ののち9月中旬頃政務に復帰した。朝10時、レーニンは自室に到着し、直ちに新聞に眼を通しはじめた。30分たらずの後ポンチ・ブルーエヴィッチは慌ただしく呼びだされた。レーニンは新聞に自己を『天才』とよび『特別の人間』とよんでいる記事を発見して激怒していた。‥‥レーニンは‥‥『これは全く余計なことであり有害である。それは個人の役割についてのわれわれの確信、われわれの見解に反するものであり』直ちに止めるようにと要求した。」(溪内謙著『現代社会主義の省察』)のである。
(2)党・国家システムの下請けとしての社会諸組織
党・国家官僚制の特徴の第2は、党・国家システムが社会全体を支配し、労働者人民の自由と自立した活動が全面的に禁止されたことである。複合権力体としての党・国家システムは、たしかに20年代からその諸要素を形成してきたが(もっとも重要なのは、党書記局の権限肥大化と書記局位階制である)、完備するのは29年末からの「上からの革命」期である。そして、このシステムが社会諸組織をおおい、支配するのは30年代前半である。
下請け機関として最も重視されたのは、労働組合とコムソモールである。労働組合の国家機関化については前述したので繰り返さないが、プロフィンテルンのロゾフスキーのこれに関する発言は批判しておかなければならない。33年に労働人民委員部がその機能(社会保険・労働保護など)を全ソ労評に移管し、廃止されたことについて、彼は「ドイツではナチス政権のもとで『労働組合の国家化が生じている』時に、ソ連では労働組合がその役割を拡大しているのは労働者階級の強大化を物語る」1)といっている。
社会主義建設過程の労組が、生産面で労使協調とならざるをえないとしても、それに一面化し、労働者保護の活動を放棄するのは誤りであろう。だが、ソ連の労組は保護の活動を軽視するどころか、労働者の利益要求を押さえ込み、労組段階での抑圧機能を果たすようになる。これは明確に労組の国家下請け化であり、労組の国家機関化である。これをロゾフスキーのように、労働者階級の強大化とはとても言えない。
マルクスは、国家死滅について国家の機能がじょじょになくなり、最後には国家は社会に再吸収されるといっている。労組の国家機関化とは、国家と同じように抑圧機能をもつということであり、それは国家が社会に再吸収される一過程だとは、とてもいえない。
社会諸組織を党・国家システムの下に従属化させつづけるには、テロルを背景としたその権威の持続化が必須だが、日常的には各級党組織の監視・統制がたえずおこなわれている。
こうして、ネップ期にはあった、社会の多元性、諸組織の自立性は、30年代に入るとほとんどなくなり、人民の不満は内向化あるいは地下化していくのである。
注1)塩川伸明著「ソヴェト社会政策史の一側面」−『社会科学研究』35巻5号に所収)
(3)党のヒエラルヒーとノメンクラトゥーラ制
党・国家官僚制の特徴の第3は、党・国家システムの骨幹が、党書記局機構にあることである。党・国家官僚制は党の書記局位階制を基礎に、党内外に対するイデオロギー的、政治的、組織的統制・支配でなりたっている。
まず第一に、組織面でみると、その中心はノメンクラトゥーラ制である。
1919年3月の第8回党大会は、「10月革命後、党官僚制形成の発端となった」1)ところの「組織問題について」の決議の一節「中央委員会の内部構成」で、中央委員会の下部機構として政治局、組織局、書記局という3つの部局を設立した。その主旨は「中央委員会を党務運営の中心として機能化しかつ強化することにあり、中央委員会の権限をこれらの機関に移譲することにおかれたのではなかった。」2)のである。
この第8回党大会はまた、「党活動家の配置業務全体は党中央委員会の掌中にある」と言明し、「党中央委員会は党活動家を‥‥一つの活動分野から他へ、一つの地区から他へ配転することを任務とする」と決議している。
溪内によると、「1919年には30名を数えるにすぎなかった党務専従者の数は、1920年には150人、1921年には602人に達し、補助的職員をふくめると700人を越えた。この数字は党務専従者が党中央のみでなく、地方党組織においても増加しつつある趨勢を示唆していた」3)という。20年の全ロシア党県委員会代表者会議では書記の役割を強化する問題が中心議題となり、委員会議長制を廃止して書記を「技術書記」から「責任書記」にひきあげることが決定された。
1920年3〜4月の第9回党大会は、書記局で常時活動する中央委員を従来の1名から3名に増やし、書記局の管轄に「組織的、執行的性質を有する当面の問題」をふくめるようにし、組織局の任務は「中央委員会の組織活動の一般的指導」に限定した。
また、第9党大会は、経済建設の前進のために技能資格のある労働者の生産現場への大量動員を定めるとともに、職業、経済・組織活動従事期間などを記した「単一の党員証制度」を導入した。そして、すべての党機関は、有能な党員の推薦目録を上級党機関に提出するとした。
1921年3月の第10回党大会は、前述したように人事においてトロツキー派が退潮し、書記局構成もトロツキー派からモロトフ、ヤロスラウスキー、ミハイロフ(前2者はその後スターリンの忠実な支持者)に替えた。3人は中央委員であるだけでなく、組織局員をも兼任した。さらにモロトフは、政治局員候補をも兼ねた。
21年12月に開かれた第11回党協議会は、第10回党大会決定の党員点検運動を総括し、とりわけ党県・郡委員会書記と労働組合指導部の構成を注視するとした。
この5日後に開かれた「党州委員会、州ビューロー、県委員会書記会議では、党中央委員会(書記局)が下級党機関の活動内容をより全面的に掌握しうるようにするため、党県、州委員会、州ビューローに統計報告義務と情報報告義務(党員の配置等を含め党活動全般にわたる情報について)を課した党中央委員会決議が確認されるとともに、幹部業務の系統化を図る諸措置が具体化された。即ち、記録配員機関の強化(責任者の資格要件の厳格化等)、各級党機関の記録対象となる幹部の範囲の確定(党中央委員会には中央から郡の階梯に至る党活動家と他の特殊な党活動家、党州委員会と州ビューローには州から郡の、党県委員会には県から地区の階梯に至る党活動家がそれぞれ記録される)、経験、党歴、性癖、技能に応じた記録の再分類、党中央委員会による幹部配置計画の作成等が決定された」4)という。内田は、この確認事項をノメンクラトゥーラ制度の原型とする。(記録配員部は、20年に書記局内に設立された部局)
さらにその後、配員業務は個々の職と幹部との対応をより重視する「個別的選抜方法」がつよまり、1922年4月から翌年3月までの間に、党中央委員会記録配員部は、10351名の党員活動家を配置している。そのうちの約半数が郡以上の党機関幹部、労働組合幹部、国家機関幹部、軍幹部などである。「党中央委員会書記局は当時既に郡段階にまで至る党幹部の任免を掌握していた」5)わけである。
1922年3〜4月の第11回党大会は、書記局構成の中央委員をスターリン、モロトフ、クイビシェフとし、しかもこの3人は同格ではなく、新たに書記長制を設け、これにはスターリンがなった。スターリンは、政治局員、組織局員、書記長をも兼ねることとなった。
党内における任命制の発達は、同時に党外に対する任命制をも発達させた。「1923年7月党中央委員会は配員業務のより効果的な遂行のために任命職名表(ノメンクラトゥーラのこと─引用者)を整理し、そこへの任命は『党中央委員会を通して』なされねばならない国家、経済機関の職3500と、その任命は関係諸機関によってなされるが、党中央委員会記録配員部への事前の届けを必要とする職1500の二種類の目録を作成した。」6)という。
こうして、記録配員部局は、「1924年には組織指導部と合同して組織配員部(部長はカガノヴィッチ−引用者)となるに及んで、党幹部の選抜、党内外への配置と党組織活動の指導とを結合するところの党組織の集権化のための最も有力な部局となる。」7)のである。「1925年末から1927年末までの2年間、組織配員部は8761人の党活動家を配員したが、うち7445人が責任活動家であった。また中央委員会すなわち政治局、組織局および書記局により任命された党活動家は1222人であった。」8)といわれる。
党中央委員会の任命職名表は、その後何回も改定されるが「1926年1月には改定と同時に、中央官庁機構の一定の職について官庁任命職名表が定められること、共和国、州、県及び下級の地方党機関もそれぞれ自己の権能に応じて任命職名表を持つこと等が言明された。ここに、党中央委員会書記局任命職名表を頂点とする一つの体系として、任命職名表制度は確立されることになる。」9)のである。
内田によると、任命職名表には、「基本的任命職名表」と「記録・統制任命職名表」の2種類があるといわれる。前者での人事は、当該党委員会あるいは当該委員会ビューローによる決定ないし批准を必要とする。後者での人事は、党委員会内の相当する部の管轄に属し、党委員会あるいは同ビューローの審議と決定を必要としない。
「記録・統制任命職名表は、1923年7月決定の時の事例のように、党外組織の任命職名表の人事を記録し統制するということのほか、下級党委員会の任命職名表を記録・統制するという役割を果たす。下級党委員会基本的任命職名表と上級党委員会記録・統制任命職名表が少なくとも部分的に重複し、前者が後者によって統制されていることを示す事例は少なくない。‥‥更に記録・統制任命職名表は、より重要な職へ有望な職員を抜擢するための幹部供給源としての機能を持つ。‥‥任命職名表制度はこのような2種の目録を持つことによって、各級党機関の任命職名表間の間隙を埋め、幹部任命業務を系統化すると同時に、上級党機関による下級党機関の任命業務を統制する機構(メカニズム)を、内蔵しているのである。」10)と、いわれる。任命職名表制度(ノメンクラトゥーラ制度)が党による、すなわち書記局による党内外の支配において、いかに骨幹的役割を果たしているかを示すものである。(党の各級段階の具体的な任命職名表は、内田前掲書を参照)
党の「統一と規律の強化」のための組織措置は、後述するように党官僚制への権力集中(党・国家全体の官僚制化の要)を促進し、それにあたったものに党統制委員会がある。 これは1920年9月の第9回党協議会で設立された。しかし、「統制委員会の本来の趣旨は、むしろ党の官僚制化とは反対に党内民主主義の擁護におかれていた。すなわちそれは党官僚制による支配に抗議する反対派の要求を宥和することを目的として設立された」11)といわれる。
21年の第10回党大会の決議は、統制委員会が地方にも設立されるべきとし、統制委員会委員は、党委員会委員にも、「責任ある行政的地位」を占めることもできないとした。そして、中央では党大会、地方では党協議会というそれぞれの最高代表機関に対してのみ責任を負うとした。22年の第11回党大会は、統制委員会規則を定め、党行政機関にたいする統制委員会の独立性を保障した。
しかし、党の人事を握る書記局制度を変革しない限り、統制委員会の本来の任務は遂行されなかった。そして、「1923年の党内闘争において統制委員会が中央委員会を代弁してトロツキー反対派を非難して以来、統制委員会は上からの規律の強化、正統的教義の庇護の機関へと急速に転化していった。」12)のである。26年秋には、スターリンの盟友オルジョニキーゼが中央統制委員会議長となり、「1927年末の第15回党大会は、中央統制委員会幹部会が4名の委員と4名の候補とを政治局に代表として派遣することをさだめ、また統制委員会の質問に正しく答えることを拒否した党員は『即座に』除名されるという峻厳な決議をした。1928年以降統制委員会は、最後の反対派であるブハーリン派の一掃、党官僚制の支配にとって障害となるあらゆる分子の党および国家機関からの追放に辣腕をふるった」13)のである。
党書記局機構の党内外に対する支配は第二に、政治的・イデオロギー面での、極度の統制、一枚岩化であり、そのために諸個人の思考能力を剥奪する政策とテロルが行使された。
21年の第10回党大会は分派の禁止を決議したが、それ以降徐々に党内論争の自由は狭められていった(21年の分派禁止は一時的措置とされたが、けっきょくは禁止措置は解除されることなく「スターリン体制」の確立となる)。それでもネップ期には未だ党内外での論争は皆無ではなかった。
だが、「上からの革命」期になると、討論の自由は全くなくなる。
党書記局機構の党内外に対する支配は第二に、政治的・イデオロギー面での、極度の統制、一枚岩化であり、そのために諸個人の思考能力を剥奪する政策とテロルが行使された。
党内においては、20年代半ばにすでに一枚岩主義と「鉄の規律」はほぼ完璧に形成されていた。
21年の第10回党大会は分派の禁止を決議したが、それ以降徐々に党内論争の自由は狭められていった(21年の分派禁止は一時的措置とされたが、けっきょくは禁止措置は解除されることなく「スターリン体制」の確立となる)。
23年4月の第12回党大会は、個々の代議員が用意された原稿なしで自己の意見を述べた最後の大会であるという。しかし、この大会の開催直前、半地下的な極左派の「無署名政綱」が配布された。そこでは産業政策を批判し、官僚的な方法で任命された専門家と管理当局を追放し労働者の管理が理想主義的に主張されていた。『労働者の真理』も文書を配布し、労働者への弾圧批判・官僚批判を展開している。これらの動きに対して、労働者反対派の前指導者・ルトヴィノフは、「無署名の論文が現れたり、ある種の政綱を匿名で発表せざるを得ないのは、ひとえにわがロシア共産党内に、なんらかの問題に関して自分の考察や見解を正常な方法で表明することが許されていないからだ。このことは、もしロシア共産党内で、政治路線でなく単にその路線に沿った実践上のやり方を批判するだけで、直ちにメンシェヴィキとか社会革命党とかその他便利な名前で片付けるという事実から立証される。」14)と、指導部を厳しく批判している。
こうした批判に対し、指導部はかえって分派禁止を継続する口実とする。時の指導部・トロイカの一人であるジノヴィエフは、分派の禁止を「決して例外的な法律ではない─それは、ブルジョアジーおよびプチ・ブルジョアジーの破壊勢力に四面囲まれているプロレタリア政党の自衛の武器なのである‥‥われわれの党内にはどんな意見をも討議しうる十分な自由がある。ただ党を分解させようと欲するものだけ自由が与えられないのだ」15)と、答えている。しかし、帝国主義に囲まれているのを理由とするのは、説得的ではない。敵に囲まれているからといって、党内論争を禁止する理由とはならない。しかも、ジノヴィエフは、討議の自由を形式的に認めながら、禁止対象者を「党を分解させようと欲するものだけ」としているが、すでにこれ自身が恣意的なものでしかない(一体、誰が解党主義者と認定するのか)。指導部批判が即、解党主義となりうるものであり(実際、その後そうした事態となる)、まさに討議の自由はありえないことになる。16)
23年9月の党中央委員会は、鋏状価格差がもたらす経済混乱、とりわけ失業・賃金切り下げによる労働者の不満と動揺という情勢に対処するとともに、このとき政治情勢小委員会は、「地下党派に関係していると認められるものは誰でもゲー・ペー・ウーに告発する義務をすべての党員に課するよう勧告した。」17)という。理論闘争を警察暴力で弾圧するというあからさまな態度である。(党内論争、党内闘争の解決に、国家権力をもちいた)
当時、指導部の反対派弾圧の主要な武器は、1つは、書記局任命制による各級党組織の会議を牛耳り、反対派活動家の配置転換をおこなうこと、もう1つは、新聞を押さえていることである。反対派の意見を公平に載せるところはなく、たまにあったとしても直ちにその編集者は更迭された。
これ以降、実質的に党生活の自由、党内民主主義はなくなって、書記局による党全体の支配が確立する。そして、「1924年には、公的な共産主義者の政治、思考活動は、一枚岩的であると同時に単調になった。第13回党大会(24年5月)と、それに参加した人々のひどい退屈さ─決まり切った主張と非難の際限のない繰り返し、長たらしい自賛と党への賛美─はソヴィエトの知的風土の急激な変化を暗示していた。空虚な単調さ、党の不謬性に関する独断的な主張、絶対的団結の強調が、共産主義者の思考の永続的様相となった。」18)のである。
打ち続く反トロツキスト・キャンペーンと、「党員再登録」運動とむすびついた反対派撲滅キャンペーンは、党生活の自由を奪い、党員の自主性を圧殺していった。
1925年12月の第14回党大会で敗北したジノヴィエフ派は、トロツキー派と妥協し、合同反対派を結成する。激しい党内闘争が展開されたが、スターリン派・ブハーリン派の組織力には勝てず、合同反対派は26年9月から細胞にまで指導者がはいって反対派活動を展開した。10月7日、ジノヴィエフ派の拠点・レニングラードのプチロフ工場で、135対25で敗北した反対派は、ついに10月16日、「党規を侵した罪を認め、以後は分派活動はしない」19)と誓って、降伏声明書に署名した。
だが、スターリンは、合同反対派の対応は戦術的なものだとして処分を強める。10〜11月の第15回党協議会で演説したブハーリンは、「反対派は、『官僚的堕落』という非難を撤回していないと非難し、この論議に即刻結末をつけるよう警告した─党はよりいっそう強力になりつつあり、『テルミドール』などと叫び続ける者は簡単に打倒されるであろう。」20)と、いっている。少数派の意見保留の権利をも否定し、個々人の思想内容までにも干渉する傾向が強まりつつあった。
第15回党協議会での「一国社会主義」論争がおこなわれた以降、論争よりも組織措置がまかり通る。「1927年までに、党の会議における反対派の発言は、文字通り、騒音によって沈黙させられた。党書記局は、反対派の決議案に賛成した者は(投票は公開である)すべて除名すると脅迫した。暴力団が、何人かの書記局員によって組織されたが─特に、モスクワのリューチンによって─それは、反対派が公開の席で演説するのを妨害したり、また、反対派支持者の私的会合をぶちこわすことをすら目的としていた『ファシストのやり口』、『黒百人組』と、反対派は、正当な抗議の叫びをあげたが、しかし、それは無駄であった。」21)といわれる。
こうして、「鉄の規律」「不動の意思統一」が教条的に強調され、党員の信仰箇条となった。26年7月の『プラウダ』は、「党は、ボリシェヴィズムのイデオロギー的純潔性が、いかにすれば、よく保持されるかに考慮を払っている。党は、レーニン主義的統一に対するいかなる分派的な試みも容赦しないであろう」22)といい、26年秋のモスクワ党委員会の決議は、「単に組織的にのみではなく、レーニン主義の基礎に立つイデオロギー的統一が、われわれの党に必要である。組織的統一は、確固たるイデオロギー的統一の基礎の上にある時にのみ、不動になるのである。」23)といっている。ここには、矛盾こそが運動の推進力である、というマルクス主義の基本的見地は少しもみられず、観念的な反マルクス主義的な「統一と団結」が横行しはじめているのである。
だが、こうした観念的教条的な「規律と統一」観をもつのは、スターリン派・ブハーリン派だけではない。極左派をのぞく反対派も共有していたのである。26年10月の一時的降伏のさい、反対派は、「われわれは、『分派とグループ形成の自由』という理論およびその実践を絶対的に拒否する。」「それは、このような理論と実践が、レーニン主義の基礎と党の決定に矛盾することを認めるからである。われわれは、分派主義を認めないという党の決定に効力をもたせるのを義務であると考える。」24)といっている。この思想的背景には、唯一前衛党論の呪縛がある。しかしそれは単なる観念ではない。反対派指導者もかっては同様な論理で弾圧(クロンシュタットの弾圧など)してきたからである。反対派もスターリン派同様に唯一前衛党の物神崇拝25)に陥っていたのである。(分派主義について一言いうと、基本組織での原則的な活動に優先する形での分派活動は、党を混乱させるもので誤りである。しかし、だからといって党内少数反対派の意見の表明、討論の自由を圧殺することも誤りである。)
反対派は、その理論的不十分性(たとえば、工業化と農民組織化の関連など)、組織的な弱さのみならず、党観におけるスターリン派との共有によって著しく劣勢にあったのである。さらにもう一つ特筆すべきことは、革命の利益との関係での民主主義の問題、抽象的にいえば、内容と形式の関係におけるプラグマティズムである。プロレタリア民主主義は軽視され、「革命の利益」なるものによって無視・批判されるか、必要の範囲内で利用されるか、である。それは内容(「革命の利益」)の都合で簡単に取り外し可能な便利な道具(形式)でしかない。この思想はスターリン派のみでなく、ほとんどの反対派指導者に共通している。ただ少数反対派に転落した者の何人かがその時になってはじめて民主主義を強調するというものであった。
以上のように「上からの革命」期を迎えるまえに、党はすでに書記局機構を通じて、党内民主主義も、党内生活の自由も奪われ、「鉄の規律」と「不動の統一」にがんじがらめになっていたのである。
諸個人の自主性、創造性を奪い、党の決定に無批判的に服従する一枚岩主義と「鉄の規律」は、「上からの革命」期に、都市(工業)でも農村(農業)でも社会レベルにまで徹底された。
この典型的例は、非常措置から全面的集団化の時期における農村での「特殊な階級闘争」の推進、とりわけ「階級としてのクラーク絶滅」運動にみることができる。
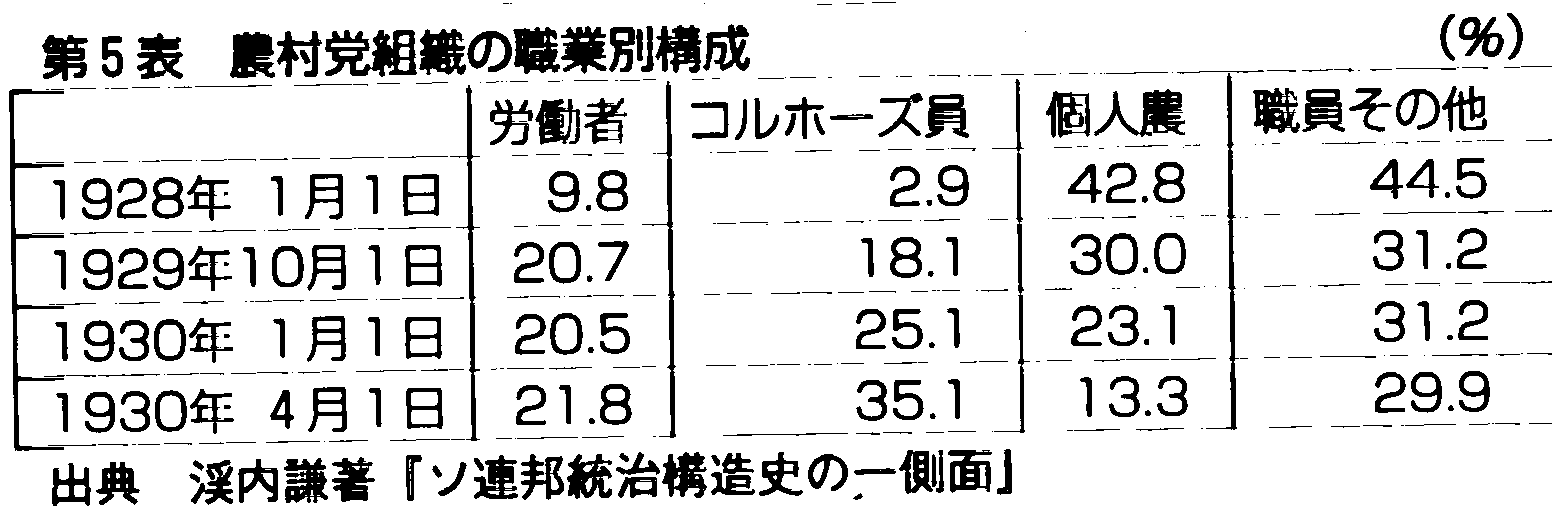 ボリシェヴィキは、元来都市のプロレタリアートに基盤をもっており、農村においては極度に弱体であった。1930年1月1日現在、党員数は157万2161人(ほかに赤軍に10万2749人)で、これを職業別に分類すると、労働者46.3%、農民12.0%、職員その他41.7%である。農民党員は、絶対数でわずかながら増えながらも、構成比では2年前とほとんど変わっていない。農村におけるこの党勢力は、その職業別構成を第5表のように変化させたが、それでも広大なソ連では徹底的に不足している。
ボリシェヴィキは、元来都市のプロレタリアートに基盤をもっており、農村においては極度に弱体であった。1930年1月1日現在、党員数は157万2161人(ほかに赤軍に10万2749人)で、これを職業別に分類すると、労働者46.3%、農民12.0%、職員その他41.7%である。農民党員は、絶対数でわずかながら増えながらも、構成比では2年前とほとんど変わっていない。農村におけるこの党勢力は、その職業別構成を第5表のように変化させたが、それでも広大なソ連では徹底的に不足している。
30年はじめ農村党組織、候補グループ数は、 2万8500で、その構成員は34万2942人である。
だがこの数は、「1930年1月1日現在の村ソ ヴィエト数6万9829に比較して依然少数であり、
住民地点(村落)数59万7359と比較する場合、党組織網の弱体性はさらに明白であり、一細胞が管轄すべき村落数は平均すれば21であった(これに対しソヴィエトは平均8.5の村落を管轄していることになる)。」26)というほどの少なさである。
これをみれば、都市部からの応援が必要なのは理解できる。しかし、前述したように、応援勢力の思想・態度は悪く、行政主義的に農村を支配するというものであった。誤りの根源はここにこそある。それは端的にいうと、中央から「送られた者の多くが、都市、工場、学校から長期、短期の任期をもって送られた者であり、党機関や政治部からの呼びかけに地元で応える積極分子はほとんどいなかった。農村の党書記は、北カフカースの77.3%や下ヴォルガの55.2%をはじめ農村向けの働き手として都市、工業から派遣された者達であり、このことを『罰』とみる者もいた。この党員達が農民に対して『権力』『主人』『官憲』としてたちあらわれることは不可避でもあった。さらに政治部そのものが党員、党細胞を媒介とせず、直接に『行政的圧力』を加えることも、避けがたかった。」27)のである。(ここで「避けがたかった」というのは、宿命論的にいえるのでなく、党員の訓練、教育がなく、農業・農民から学ぶ姿勢がないという前提条件の下では、不可避というべきであろう)
1932年1〜2月の第17回党協議会は農村における「誰が誰を」という階級闘争は社会主義の勝利の方に基本的に解決したとした(一部での激化の可能性は留保されたが)。2月の中央委員会では、コルホーズの「組織的、経営的強化」が強調された。そして、春いらいコルホーズに対する党・政府の一連の緩和政策がとられる。たとえば、コルホーズ商業の合法化、穀物調達量の引き下げ、家畜の強制的社会化の禁止である。6月には「革命的合法性について」の法令がだされ、公職につくものの革命的合法性の侵犯、実施面での歪曲が警告され、農業カンパニアでの「行政的科料」が廃止、「クラーク分子」にたいするソヴィエト法の確立が訴えられた。また、コルホーズ内の選挙制の確立・命令的方法の転換などである。
しかし、夏以降またまた農業危機が顕在化しはじめる(これは大規模な飢饉に発展する)。それは3大穀倉地帯にもあらわれたのであった。指導部の驚きと農民への不信は極度に強まった。
32年11月27日、北カフカースから帰って来たカガノヴィッチらをむかえて政治局と党中央統制委員会幹部会の合同会議が開かれ、北カフカースでの「クラーク・サボタージュ」が総括された。「この会議はクバンでの党の新政策が一地方の問題ではなかったことを示し、党の農村政策全般を変更するための転換点となった。スターリンはこの会議で、当面する危機の性格を、第一に、コルホーズ、ソフホーズへの反ソビエト分子の浸透、それによる妨害行為、サボタージュの組織化、第二に、農村コムニストのコルホーズ、ソフホーズへの正しくない、非マルクス主義的接近、として、特徴づけた。」28)という。
党指導部の集団化における反マルクス主義的な方針は、「1929−30年の『クラークの階級としての絶滅』の適用において『クラーク』なるものの実態が経済的、社会状況に基づき識別、特定化せられた存在としてよりも、むしろ全面的集団化遂行にあって析出された反対者、更に国家に対立する共同体農民の象徴的存在を多分に指示するものであった‥‥。したがってその内容は政策遂行のテンポ、当局者の意図、農民の反抗の度合によって変化した。さらに明らかにバトラーク、貧農間にもみられた集団化への抵抗者の存在は、『クラーク支持分子』なる概念の析出を導いた。」29)のである(クラークはコルホーズへの加入を認められなかったので、危機の原因は「クラークの手先」か、党内にもぐりこんだクラークの仕業という論理になる)。
ここでは明らかな党指導部の農業政策の誤りを自己反省するのでなく、危機の原因を他者に求めそれを追及するものとしての「特殊な階級闘争」がひねりだされるという転倒した事態に至っている。今や、党指導部の思いどおりにならない限り、「クラークの陰謀」「クラークのサボタージュ」「クラークの手先の撹乱」という名目で、「階級闘争の激化」−粛清が党内外に激烈に展開されるのであった。
巨大な書記局位階制を背景に、党内反対派の基本的部分を一掃し、党内民主主義を締め出した党指導部は、「階級闘争の激化」を名目に党の方針に反対するものをテロルと行政圧力で屈服させ、社会全体を「牢獄」ないしは「軍隊」と化したのである。それは党方針に対するいかなる反対をも許さなかった。このことは学問諸領域にたいする弾圧と御用学者の台頭にはっきりと示されている。
「上からの革命」期には、ネップ期に活躍した専門学者は一斉に次々と批判され、自己批判させられた。経済学におけるルービン批判、哲学におけるデボーリン批判、法学におけるパシュカーニス批判、後には歴史学のポクロフスキー批判などである。それらは、自由で民主的なルールの下での相互討論とはいえず、学問を発展させるものとはいえず、ソ連科学の発展を抑圧した。最高の科学者は今やスターリン以外には存在しなかった。
党・国家官僚制の骨幹を占める党・国家システムは、ロシア革命以後のすべての「社会主義国家」に存在するといえるだろう。党・国家システム−党・国家官僚制は、社会主義にたいする魅力を消失させただけでなく、マルクスやレーニンの「国家死滅」の理論を実質的にご破算にさせた。というのは、党・国家官僚制の諸国家では、マルクスやレーニンのいう「国家死滅」の諸条件をいくら建設したとしても、肝心の主体である労働者人民の自律的主体的活動が党によって永遠に阻止されているからである。マルクスやレーニンの著作には、私的な存在である党が、公的体制の中核をしめ、国家諸機関を支配するという国家権力は、当時の世界では、思索の対象にはなかったのである。
注1)溪内謙著「ソ連邦の党官僚制」─『現代行政と官僚制』上
に所収
2)同上
3)同上
4)内田健二著「ノメンクラトゥーラ制度の一側面」−『思想』1977年12月号に所収
5)同上
6)同上
7)溪内前掲論文
8)同上
9)内田前掲論文
10)同上
11)溪内前掲論文
12)同上
13)同上
14)R・ダニエルズ著『ロシア共産党党内闘争史』より重引
15)R・ダニエルズ前掲書
16)第10回党大会は一時的措置として、分派の禁止を決定した。しかし、その統一に関する決議には、次のような第4項がある。「党の各組織は、党の欠陥の無条件に必要な批判や、党の一般方針あるいは党の実践上の経験のあらゆる分析や、党の諸決定の実行の点検や、誤りを訂正する方法などが、なにかある『政綱』にもとづいて結成されたグループの審議にではなしに、全党員の審議に付されるよう、もっとも厳重に監視する必要がある。このために、大会は『討論用リーフレット』や特別の論集をもっと規則的に発行することを指令する。批判をおこなうものはみな、党が敵の包囲のもとにある状態を考慮にいれなければならず、またソヴェトと党の仕事にみずから直接に参加することによって、党の誤りを実地に訂正するように努めなければならない。」
17)R・ダニエルズ前掲書
18)同上
19)同上
20)同上
21)同上
22)R・ダニエルズ前掲書から重引
23)同上
24)同上
25)ロシア革命の過程でどのようにして、「唯一前衛党論」が形成されたのかは、追求すべき価値ある課題であるが、レーニンは少なくともこのような呪縛には陥ってはいない。ブレスト講和の時の党の危機に匹敵する労働組合論争時、レーニンは、次のように明言している。「人々は、われわれに、つぎのように言うかもしれない、──しかし、もし根本的な、深刻な、原則上の意見の相違があるなら、それは、どんなに辛辣な、分派的な発言をしても正当なのではないだろうか?
もし新しい、不可解なことをいう必要があるくらいなら、時として分裂することさえ正当ではなかろうか?
と。もちろん、正当である、‥‥もし、意見の相違が、ほんとうにきわめて深刻なら、もし、党もしくは労働者階級の政策のまちがった方向を是正するのに別な方法がけっしてないならば。」(「ふたたび労働組合について、現在の情勢について、トロツキーとブハーリンの誤りについて」)と。問題は、複数前衛党を承認したあとのことである。統治体制の安定の見地からみると、分裂した党派同士で唯我独尊的に互いに相手を反革命呼ばわりし、殲滅戦に入ることは愚の骨頂であることはいうまでもない。ではどのように解決するのか。それは統治体制にかかわるかぎり、公的に解決する以外にはありえない。 つまり、人民代議員会議などでの民主主義的多数決による決着である。そして、党派間論争を軍事力で解決することは、プロレタリア民主主義を破壊するだけでなく、革命権力を破壊する自殺行為であることを肝に命ずべきである。
このように党問題は、それ自身のみで終わらず、統治体制、統一戦線などに深くかかわっていく問題といえよう。
26)溪内謙著「ソ連邦統治構造史の一断面」−『法学協会百周年記念論文集』第1巻に所収
27)下斗米伸夫著「コルホーズ体制の危機と政治部の導入」−溪内編『ソヴィエト政治秩序の形成過程』に所収)
28)下斗米伸夫著「クバン事件(1932年)覚書き」
29)同上
おわりに
エンゲルスは、晩年次のようにマルクス主義陣営内の経済主義を批判し、それにかかわる自分たちの責任と弁明をおこなっている。
「後輩たちが、時として過度に経済的側面に力点をおいている責任の一半は、マルクスと私自身にあります。私たちは、主要原理を否認する論敵にたいし、それを強調しなければなりませんでしたし、また、相互作用にふくまれているその他の諸要素をそれなりに評価するための時間と場所と機会を必ずしも十分には持っていませんでした。」1)
しかし、その後の歴史は周知のように第2インター指導部にみられる経済主義を全面開花させた。レーニンはこれを厳しく批判し、ロシア10月革命後も闘った。しかし、レーニン死後のソ連社会主義建設は、はたして経済主義から解放されていたのであろうか。ロシア・マルクス主義は何故、生産力主義から解放されていなかったのか。もっとつっこんでいえば、「反スターリン主義」を掲げて登場した日本の新左翼の多くが、社会主義のメルクマールを国有化と計画経済にもとめ、「法律的、政治的上部構造」をなんら問題にしなかったのは何故か。
30年前後に形成され91年に崩壊したソ連経済の分析をすすめるにあたって、自分をふくめ党・国家システムがその経済構造の不可欠の要因としてあることを軽視ないしは無視してきたのが実情だと思う。この反省の上にたって、随分と遠回りをしたが、党・国家システムを大ざっぱではあるが検討してきたのは、このためである。
経済的土台が上部構造を規定するというのは、通史的にいえるとしても、その経済的土台が上部構造と相対的に分離したのは、歴史上唯一資本主義社会のみである。したがって、経済的土台が上部構造を規定する在り方、経済的土台と上部構造の相互作用の在り方は、資本主義社会とそれ以外の社会(資本主義以前の社会ならびに以後の社会)とでは当然にも異なる。これを混同して誤りに陥ることは、歴史分析でしばしばみられる。それは専門家としての歴史学者でもみられることである。現代人の眼で分析するからである。
同様の誤りを回避し、ソ連の貴重な歴史的実験をわれわれの事業の教訓とするために経済分析の前提として、あえて党・国家システムの分析作業をおこなった次第である。
注1)『エンゲルスからブロッホへの1890年9月21日の手紙』
(以上)
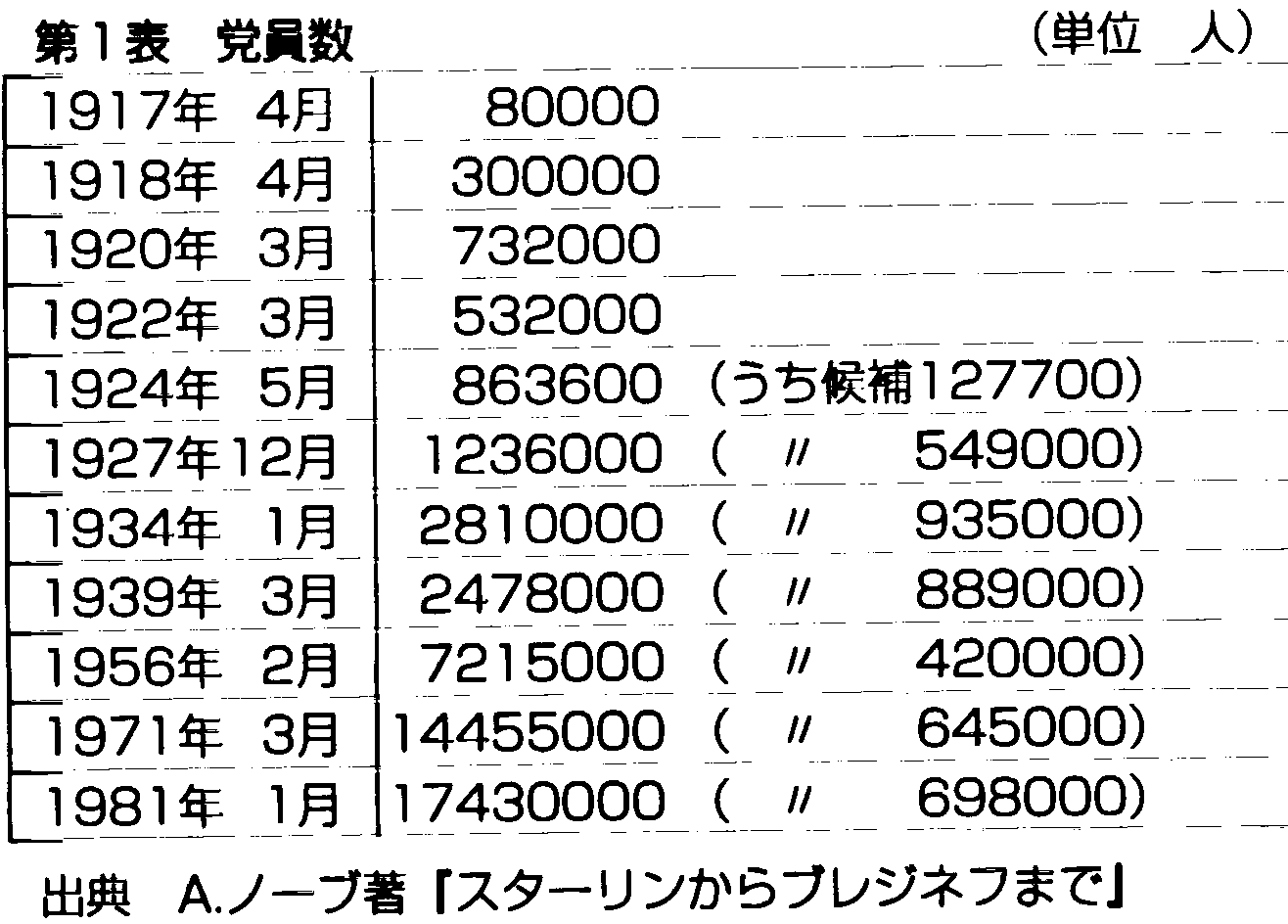
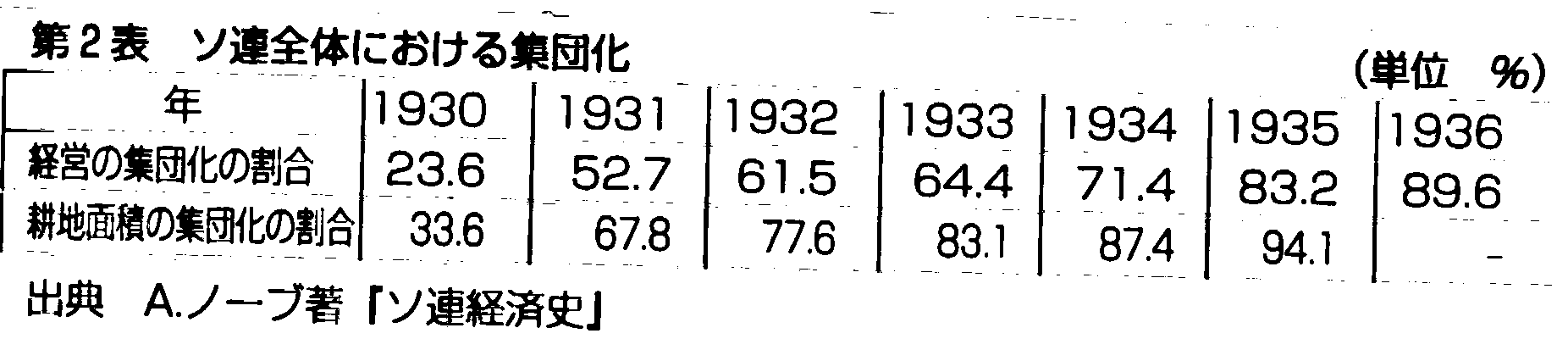
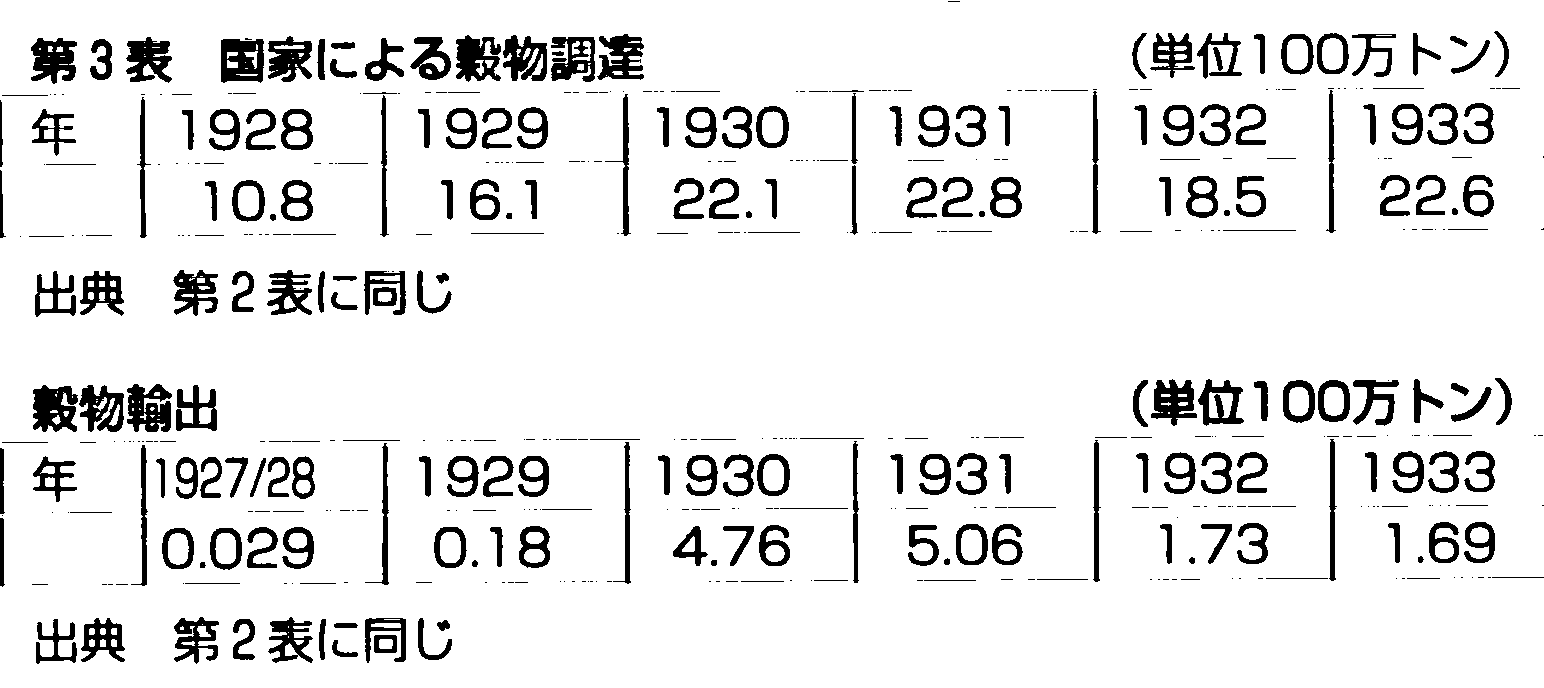 超工業化による都市人口の急増、穀物輸出の異常な増加などにより、穀物余剰は枯渇し、強制的集団化による家畜の一挙的減少などで、食料事情は悪化した。都市住民は配給制の下で、パン・じゃがいもが増え、肉類・バターが減った。しかし、農民はいずれのものも減少した。飢えに駆られた農民などが、合法であれ非合法であれ、食料を求めるのは必然であった。
超工業化による都市人口の急増、穀物輸出の異常な増加などにより、穀物余剰は枯渇し、強制的集団化による家畜の一挙的減少などで、食料事情は悪化した。都市住民は配給制の下で、パン・じゃがいもが増え、肉類・バターが減った。しかし、農民はいずれのものも減少した。飢えに駆られた農民などが、合法であれ非合法であれ、食料を求めるのは必然であった。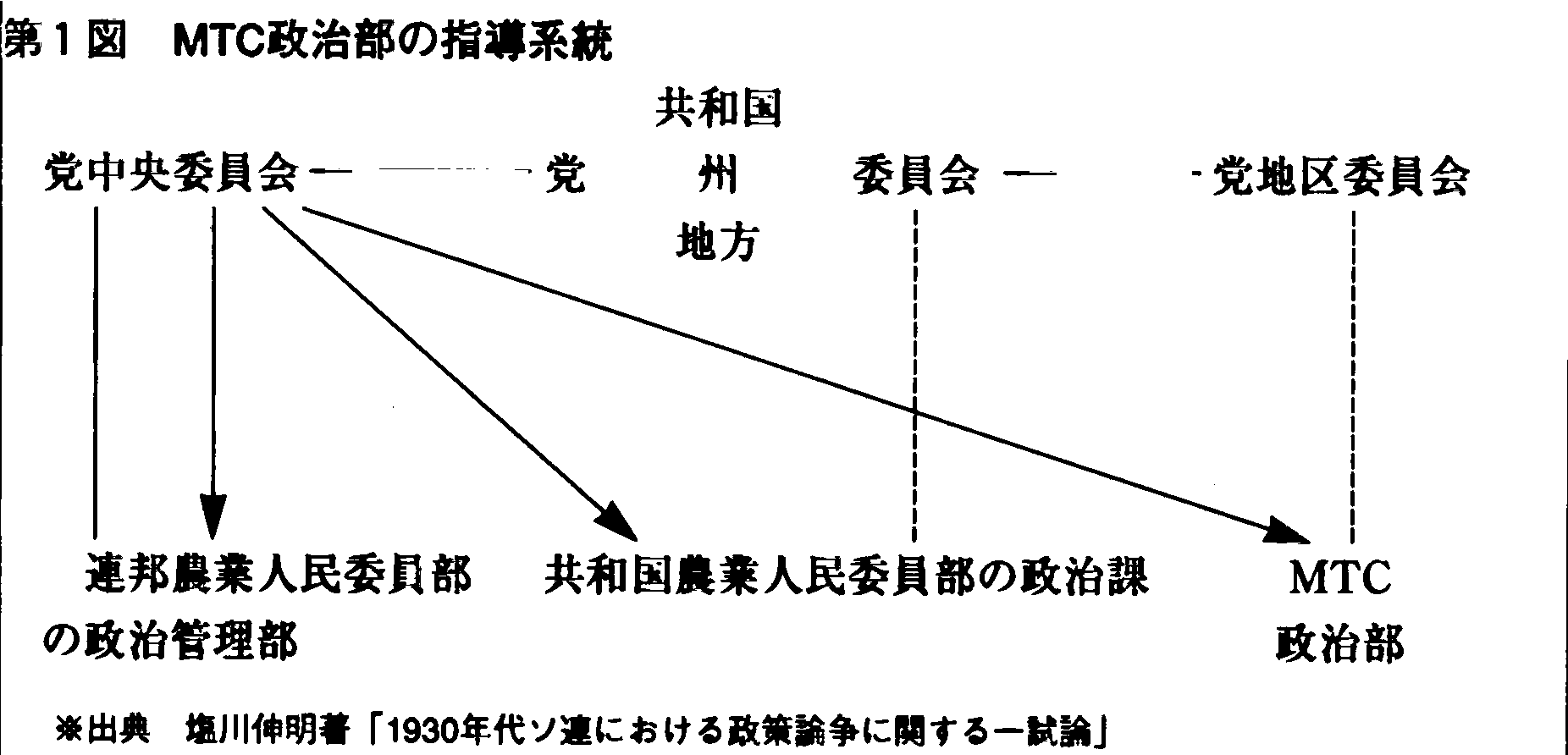 政治部の指揮系統は 第1図に見られるよう
なものである。それは 「中央から末端に至る
独自の指導系列をもっ ていて各級党委員会と
は『連絡』の関係しか
ないこと、部長は直接党中央委員会の任命(但し、人選は共和国・州・地方委員会第一書記の推挙による)によっていること─即ち、最高度のノメンクラトゥーラ(任命職名表)に属すること─」15)などが特徴的である。
政治部の指揮系統は 第1図に見られるよう
なものである。それは 「中央から末端に至る
独自の指導系列をもっ ていて各級党委員会と
は『連絡』の関係しか
ないこと、部長は直接党中央委員会の任命(但し、人選は共和国・州・地方委員会第一書記の推挙による)によっていること─即ち、最高度のノメンクラトゥーラ(任命職名表)に属すること─」15)などが特徴的である。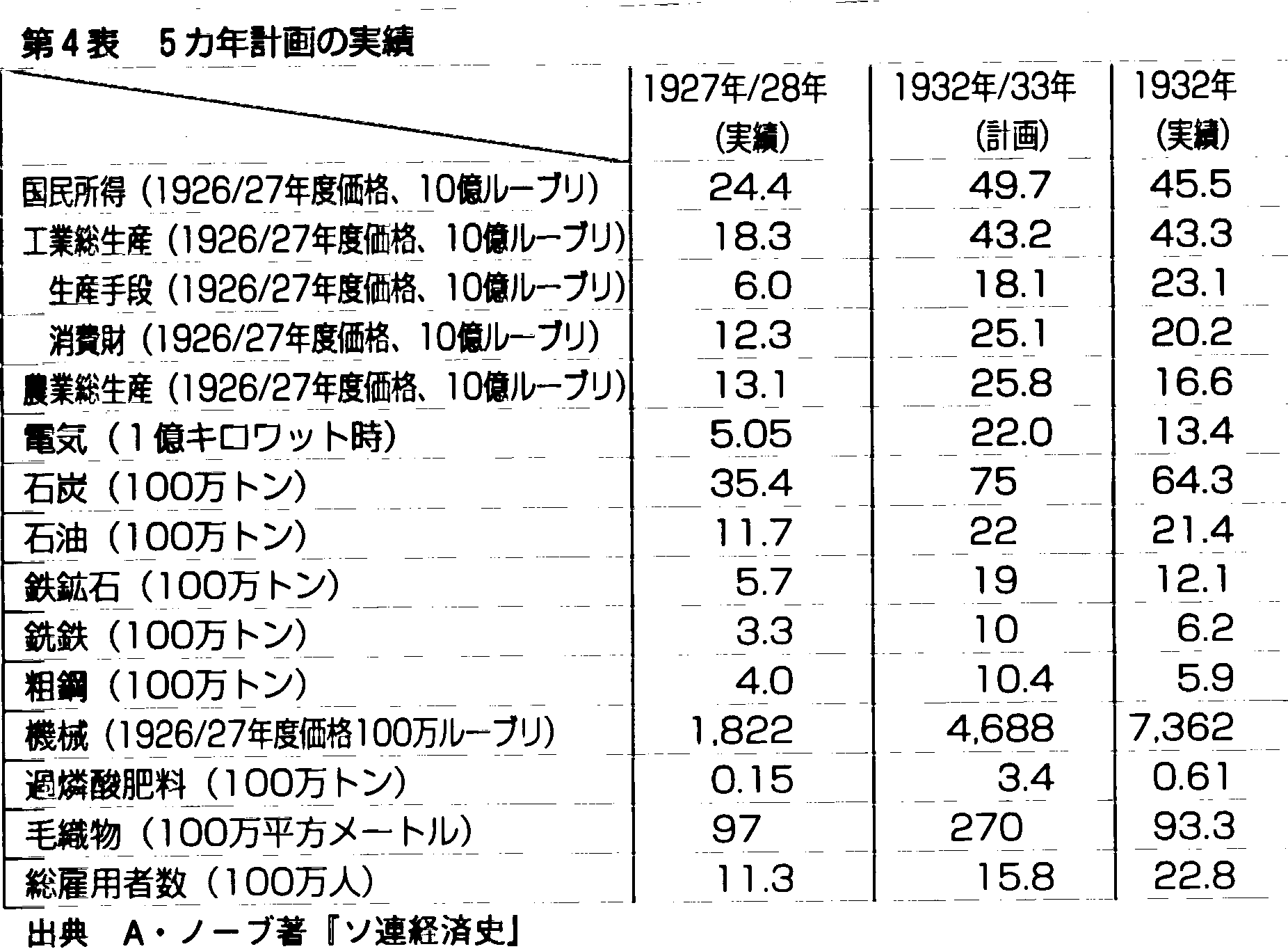 きわめて過大な計画課題を、
しかも3〜4年という高速テンポで遂行するという超工業
化の結果は、第4表のとおり である。大方が最初の最適案
でさえも未達成である。機械 のみが超過達成であるが、こ
れも割り引いてみなければならない。というのは、インフレ率が考慮されていないからである。
きわめて過大な計画課題を、
しかも3〜4年という高速テンポで遂行するという超工業
化の結果は、第4表のとおり である。大方が最初の最適案
でさえも未達成である。機械 のみが超過達成であるが、こ
れも割り引いてみなければならない。というのは、インフレ率が考慮されていないからである。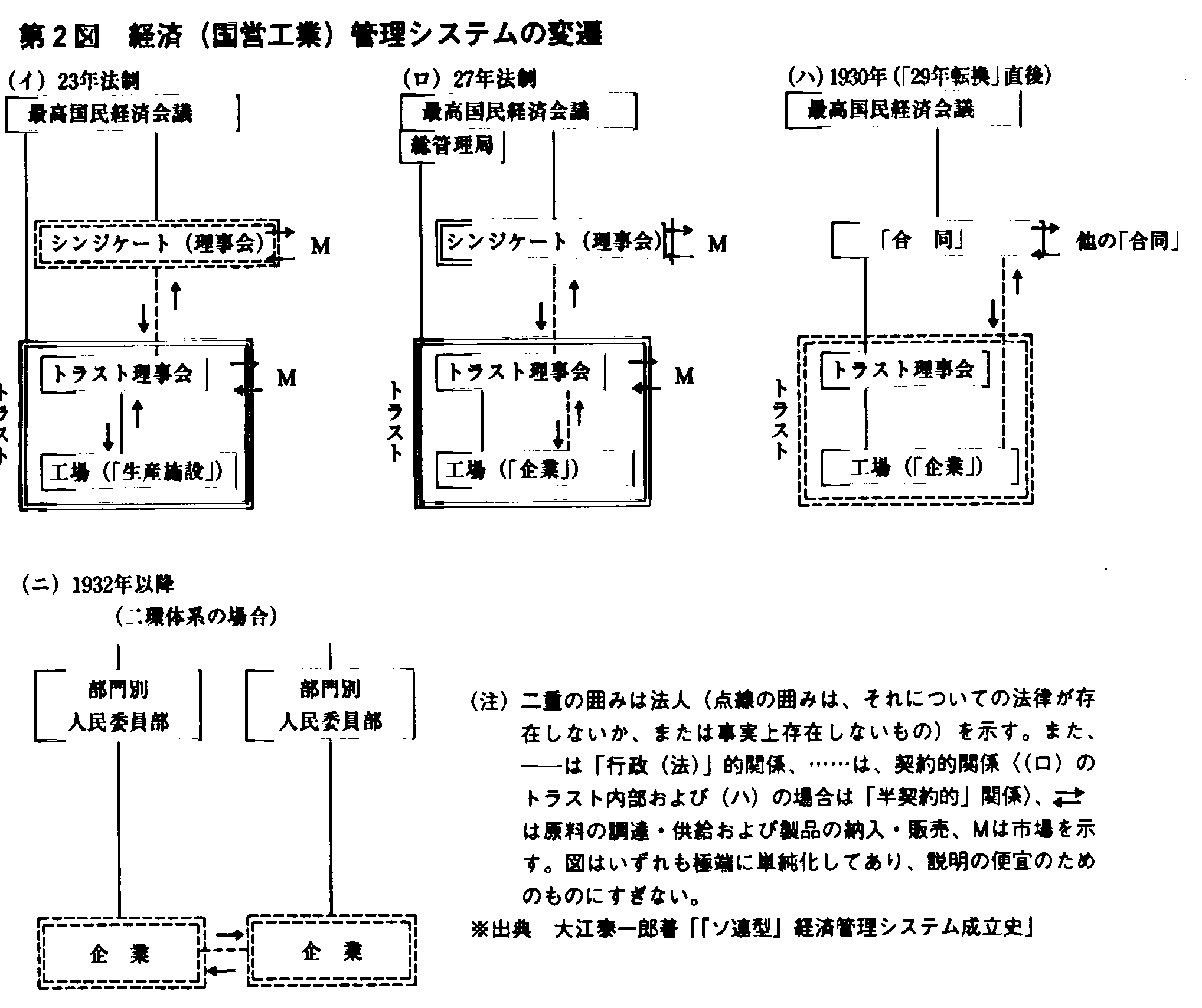 (イ)23法制(ネップ復興期)─22年にロシア共和国民法典、23年にトラスト法が成立する。22年民法典は、市場原理により、見積もり予算方式による国家からの融資をうけない国営企業およびその合同体(トラスト)は、取引関係においては、自律的で国庫との連関をもたない法人として規定される。また、この国営企業およびトラストは、自己の債務については自己の自由な処分権のもとにある財産によってのみ責任を負うとしている。
これに依拠し、23年トラスト法はより具体的に規定し、工業管理の基本環であるトラストは、「商業計算制原理にもとづき、利潤獲得を目的として」活動する「単一の企業」「法人」と規定される(23年法制では、いわゆる企業は自立しておらず、トラストの一部分であり、名称も「生産施設」である)。トラストは、市場で自由に活動し、上級の計画化=規制機関(最高国民会議とその機関)は、「トラスト理事会の経常的行政・運営に介入しない」ものとされている。
(イ)23法制(ネップ復興期)─22年にロシア共和国民法典、23年にトラスト法が成立する。22年民法典は、市場原理により、見積もり予算方式による国家からの融資をうけない国営企業およびその合同体(トラスト)は、取引関係においては、自律的で国庫との連関をもたない法人として規定される。また、この国営企業およびトラストは、自己の債務については自己の自由な処分権のもとにある財産によってのみ責任を負うとしている。
これに依拠し、23年トラスト法はより具体的に規定し、工業管理の基本環であるトラストは、「商業計算制原理にもとづき、利潤獲得を目的として」活動する「単一の企業」「法人」と規定される(23年法制では、いわゆる企業は自立しておらず、トラストの一部分であり、名称も「生産施設」である)。トラストは、市場で自由に活動し、上級の計画化=規制機関(最高国民会議とその機関)は、「トラスト理事会の経常的行政・運営に介入しない」ものとされている。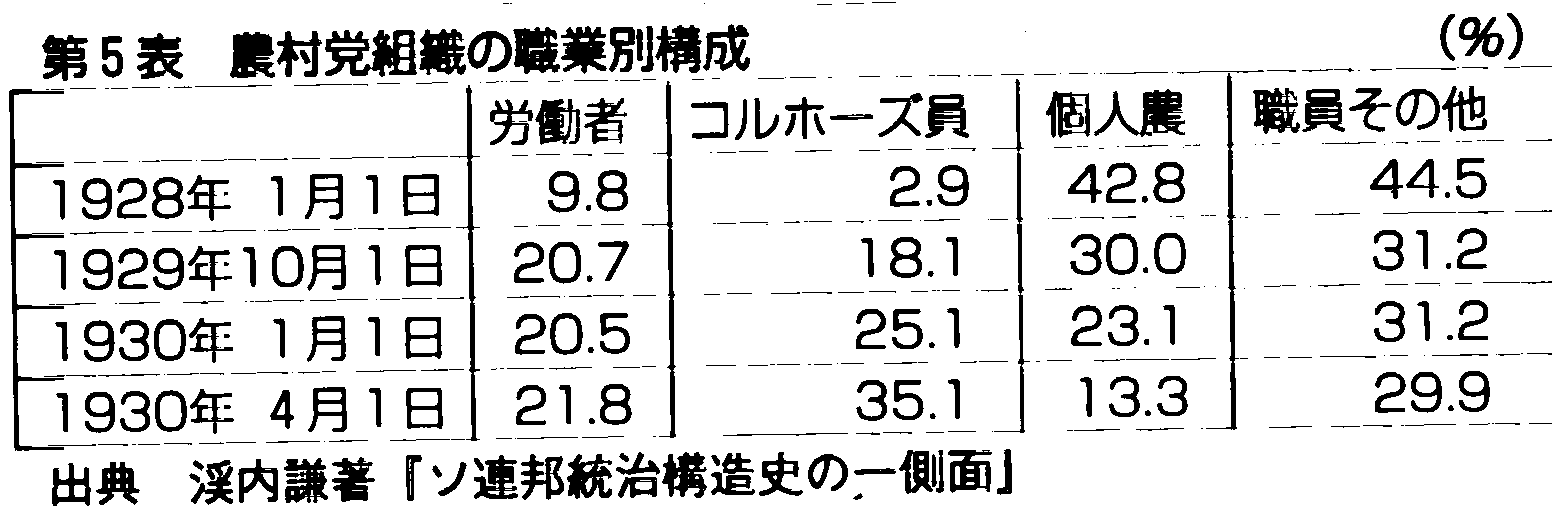 ボリシェヴィキは、元来都市のプロレタリアートに基盤をもっており、農村においては極度に弱体であった。1930年1月1日現在、党員数は157万2161人(ほかに赤軍に10万2749人)で、これを職業別に分類すると、労働者46.3%、農民12.0%、職員その他41.7%である。農民党員は、絶対数でわずかながら増えながらも、構成比では2年前とほとんど変わっていない。農村におけるこの党勢力は、その職業別構成を第5表のように変化させたが、それでも広大なソ連では徹底的に不足している。
ボリシェヴィキは、元来都市のプロレタリアートに基盤をもっており、農村においては極度に弱体であった。1930年1月1日現在、党員数は157万2161人(ほかに赤軍に10万2749人)で、これを職業別に分類すると、労働者46.3%、農民12.0%、職員その他41.7%である。農民党員は、絶対数でわずかながら増えながらも、構成比では2年前とほとんど変わっていない。農村におけるこの党勢力は、その職業別構成を第5表のように変化させたが、それでも広大なソ連では徹底的に不足している。