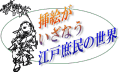 |
S019 → 次へ|トップへ|戻る ●子どもに生き方を教えた心学道話 (寿福庵真鏡編。春亭・柳川重信画。文政6年(1823)〜弘化4年(1847)刊 『主従心得草』。[江戸]和泉屋庄次郎板)*挿絵は3編上巻 |
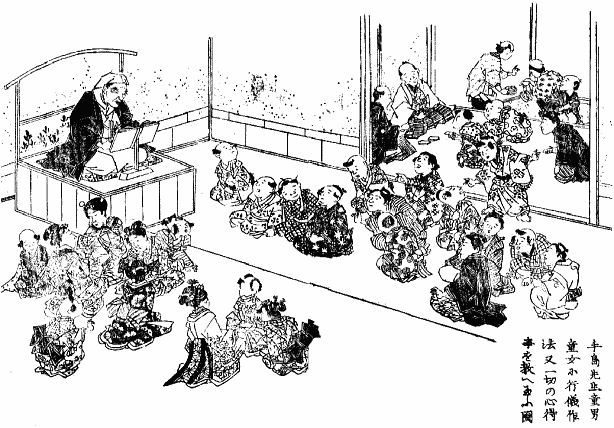 |
|
| ●手島(堵庵)先生、童男・童女に行儀作法、又、一切の心得を教え給う図。 *本書(3編上巻)序文で、石門心学(石田梅岩に始まる町人道徳)について、「心学の道に入る者は、家内和合はもちろん、一家親類とも仲良く暮らし、人との交際も良く、邪見な人と接しても争うようなことはせず、家業に精を出して、足ることや御代の恩沢を知り、御法度を大切に守り、ただ今日の無事を楽しみ、世の中を平穏無事に過ごすための教えである。智者や学者はともかく、家業に忙しい人々は、この教えによらなければ、上手に世渡りすることが難しいので、心学を学がよい」と奨めている。 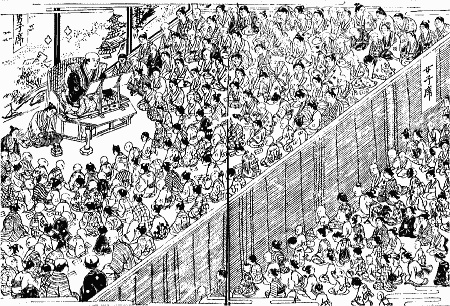 ※下の図は、安永2年(1773)刊の『前訓』の挿絵だが、講師(手島堵庵)席の前側が男子席、簾で仕切られた手前側が女子席となっていて、左右で男女席が仕切られた上の図とは異なる。どちらが実際だったかはさておき、いずれにしても男女別々の席で「前訓」(子ども向けの心学道話)が説かれたのであろう。前訓は、男子は7〜15歳、女子は7〜12歳までの子どもたちに「行儀作法よろしく御成り候ための教」えであった。また、前訓に出席する者への注意として、次の5カ条があった。 ※下の図は、安永2年(1773)刊の『前訓』の挿絵だが、講師(手島堵庵)席の前側が男子席、簾で仕切られた手前側が女子席となっていて、左右で男女席が仕切られた上の図とは異なる。どちらが実際だったかはさておき、いずれにしても男女別々の席で「前訓」(子ども向けの心学道話)が説かれたのであろう。前訓は、男子は7〜15歳、女子は7〜12歳までの子どもたちに「行儀作法よろしく御成り候ための教」えであった。また、前訓に出席する者への注意として、次の5カ条があった。(1)講釈日は、毎月3日、13日、23日、八つ半(寺子屋終業後の午後3時頃)で、席はそのつど案内します。 (2)男女とも衣服は寺子屋やお稽古事に行く時の普段着のままで結構です(羽織着用は無用)。 (3)参加費や贈り物、謝礼は一切受け取りません。 (4)教室では騒いだりふざけたりしてはいけません。出入りも静かにしてください。何事にも神妙を心掛けてください。 (5)各自、くれぐれも火の用心を心掛けてください。 以上、安永2年2月 発起人より |
|