���j�̉��� �u�ߐ������j�u���v �ł��b���܂����i2002/12�j �@2002�N12��7���A�����s���c�J��̒j�������Q��Z���^�[�u��Ղ炷�v�ɂāA�u���M�̎���Ə��������v�Ƃ����e�[�}�ł��b�������Ē����܂����B ���u���M�̎���Ə��������v�u���v�| �i�P�j���M�̈Ӗ��Ə��M��{�̗ތ^ �@�������b������u���M�v�Ƃ����̂́A�����̕M�Ə����܂����A���M�ɂ����R�A�菑���̂��̂Əo�ł��ꂽ���̂�����܂��āA�����̂��b�͑S�ďo�ł��ꂽ���́A���{�ɂ��Ă̂��̂ł��B���ꂩ��A���M��{�ɂ��ĉ��l���̐搶���_����������Ă��܂����A���M�̒�`�����ɞB���ł�������A�ꉞ��`�͂��Ă����Ă����ۂɘ_����ǂ�ł݂܂��ƕK�����������M�łȂ��Ēj���M���������Ă�����Ƃ����ꍇ�������̂ł����A���̏ꍇ�́A�����m�ɋ�ʂ����ق����F�X�Ȃ��Ƃ����炩�ɂȂ�̂ŁA�����u���M��{�v�ƌ����ꍇ�ɂ́A�����M�ł����āA�Ȃ����o�ł��ꂽ���̂Ƃ����Ӗ��ŁA�����̂��b�������Ē������Ǝv���Ă��܂��B �@���ׂ������ԌÂ����M��{�́A�c��5�N�i1652�j���w���삨�ʁi�Â��j��{�x�ł��ˁB���āA���������Y���u�������ɏA���āv�Ƃ����u����ŁA���̖{���Љ���Ǝv���܂����A�N�����͂����肵�Ă��鏗�M��{�ł͍ł��Â��̂��w���삨�ʎ�{�x�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��B �@���삨�ʂɂ��ẮA�F����A�^�c�i�q�������ꂽ�w���삨�ʁx�Ƃ����{�����ɏڂ����āA���m�ȋL�q���Ǝv���܂��B���삨�ʂ͂���܂ł��܂萳�̂�������Ȃ�������������ł����A���ʂ́u���Â��v�Ƒ����ł��ˁc�B���\���ɏo�ł��ꂽ���ʂ́w�l�G�����́x�ɂ��A���ӂ̉��̕��Ɂu����̂��Â��v�Ƃ���A�����ɂ��u�Â��v�Ə����Ă���܂��B���̂ق����삨�ʂ̒��M�{�Ȃǂɂ����炩�Ɂu�Â��v�Ə��������̂�����܂��̂ŁA�u�Â��v�Ƒ���̂��������Ƃ���Ă��܂��B�^�c�i�q����͐^�c�Ƃ̖���ɂ�������ŁA�����ɏ��삨�ʂɊւ��鎑�����F�X�ƈ���Ă��āA�u�ߋ����v�Ƃ��u�n�}�v�Ȃǂ��犄��o���Ă��̂悤�Ȗ{�������ꂽ��ł����A����ɂ��܂��ƁA���삨�ʂ͂܂����쐳�G�̖��ŁA�v��n���J�тƂ����܂��B�����ĉJ�тƂ��ʂ̊Ԃɐ��܂ꂽ�������삨�ʂƏ̂��Ă���܂��āA�Ƃɂ������삨�ʂ�2�l�����Ƃ������Ƃł��B���̂悤�ɂ��ʂ�2�l���݂������Ƃ�������Ȃ��������߂ɁA�������X�Ƃ��Ăł��ˁA�M����G�g�ȂǓ����̌��͎҂����Ƃ̐ړ_���F�X���������߂ɁA�ʂĂ͑S�������̂Ȃ���ڗ���҂ł���Ƃ������������o�ꂵ���悤�ł��B 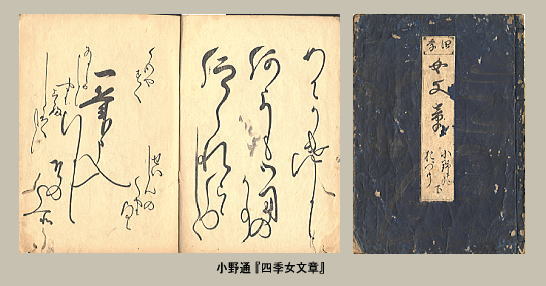 �@��́A���M��{���o�ꂵ�ď����Ă��������17���I������18���I���̂��悻100�N�Ԃł��B����ŁA���̎�����u���M�̎���v�Ǝ��͌Ă�ł��܂��B�m���ɍ]�ˌ���ɂ���������������{���������o�ł���Ă��܂����A�傫�Ȏ���̐����Ƃ��Č������ɁA��̂���100�N�Ԃƌ��Ă悢�Ǝv���܂��B �@�����āA�ŏ��̏��Жژ^�A����2�N�i1659�j�̖ژ^�ŁA�����o�ł��ꂽ�������L�ڂ������̂ł����A���̍ŏ��̖ژ^�ɂ����M��{��2�_�قǍڂ��Ă��܂��B��͕����ʂ�w���M��{�x�Ƃ��������ŁA���炭���삨�ʂ̎�{���Ǝv���܂��B������́w����P�x�ŁA���Ŗ{�͑厚�ŏ����ꂽ���M��{�ł��B����͏��M��{�̒��ł��ł��Â����̂̈�ł��B�]�ˎ��㏉���ɖ{���o�ł����悤�ɂȂ����ŏ����珗�M��{���������Ƃ������Ƃł��B �@���ꂩ��A�u���M�����v�Ƃ�����{�͕K�����������M�ł͂���܂���B��O�����{������܂��āA�Ⴆ�A���\6�N�i1693�j�́w���M�l�G���́x�Ƃ����̂������ł����A����͒����r�V��Ƃ����j���������Ă��܂��B�܂��A�]�ˌ���Ō����܂��ƁA�V��10�N�i1839�j�́w���M�Ԓ����f�x���A���e�͑��n�Ղ�����āA�������R���A���Ƃ����j�����Ƃ������Ă����ł��ˁB���̂悤�Ɂu���M�����v�ƌ����Ă��j�������������̂�����܂��B�܂�A���M�Ƃ������t�ɂ́u�����M�v�Ƃ����Ӗ�������܂����A�P�Ɂu�����p�v�Ƃ����Ӗ��Ŏg���Ă���ꍇ������܂��āA���̕ӂ���ʂ��Ă����Ȃ��ƁA�F�X�ƍ������Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B�������A�������ʂ��Ă��Ȃ��_���̕������|�I�ɑ�����ł��B �@����ŁA���̏ꍇ�́A�������ʂ��������������낤�Ɓc�B�������ʂ��Ă����܂��ƁA�F�X�Ȃ��Ƃ��������Ă��܂��B�܂��傫���u���M��{�ށv�Ƒ��̂����ꍇ�ɁA������������̂������ł��邩�A�j���ł��邩�������́A�����M����łȂ��A�j���������p�ɏ��������̂��܂߂āu���M��{�ށv�ƌĂ�ł����ł��������܂��M�҂̐��ʂŋ�ʂ��܂��B���ꂩ��A�p�r�̖ʂ���A��{�ł��邩�A�p���͂ł��邩�A���̑��ł��邩����ʂ��܂��B���̂ق����͌`�����莆���X�^�C���ł����Ă��A���ۂɎg����莆���ƁA�����łȂ����̂�����܂��B�ڂ��������͏Ȃ��܂����A�ꌩ�莆���X�^�C���ł��A���ۂɂ́u�������v�u����������v�̈Ⴂ������܂��B �@���̂悤�ɕ��ނ��Ă����ƁA�\�̂悤�ɁA�͂�����Ə��M��{�ނ̕ϑJ�����o�����Ƃ��ł��܂��B�\�̓��A���M�ň�ԓ_���������Ȃ��Ă���̂�1700�N�ȍ~�́u��{�v��39�_�ł��B����A�j�M�̕���1750�N�ȍ~�́u�p���́v��36�_�ł��B���M�����ɒ��ڂ���ƁA�ǂ̔N������Ă���Ɂu�p���́v�����u��{�v�������Ă��܂��B�t�ɁA�j�M�ł͂ǂ̔N��ł��u�p���́v�̕��������Ȃ��Ă��܂��B�j�������������͎̂��p�I�Ȏ莆�ᕶ�W�ł���p���͂�������ł��B���ɁA���������������̂́u��{�v��������ł��B �@���̂悤�ȋ�ʂ�����ƁA���i1751�`63�j�������ɂ��āA�����M����j���M�ցA�܂��A��{����p���͂ւƕω����Ă������Ƃ�������܂��B���M��{�ނł��i�X�Ǝ��p�I�Ȃ��̂���d���߂�悤�ɂȂ��Ă����X����������܂��B �i2�j���M��{����������������  �@�ǂ̂悤�ɂ��ď��M��{������ɏ������悤�ɂȂ����̂��Ƃ����A��̔w�i�Ƃ��āA�䌴���߂́w�D�F��㏗�x�ɁA�����ɏ����������鏗�M�w����c�ޏ������o�Ă��܂��B �@����̓t�B�N�V�����ł����ǂ��A���������̎��ۂ̕����I�ȗl�����f���o�������̂Ƃ��āA�����ɋ߂����Ƃ�������Ă���Ǝv���܂��B�����ɋ��s�̏��M�w��̘b���o�Ă��܂��B�䏊������������������ނ�����A���̂悤�ȏ����͗�V��@���ł��Ă���Ƃ��A���{������Ƃ��A�����ԓx��������Ƃ��Ă���Ƃ��A�i��������Ƃ��������ƂŁA���ތ�������肠�܂��ŁA���̂悤�ȏ����Ɏ����̖���ʓ|���Ă��炢�����ƁA������������Ȃ��ė�V��@�������^�Ȃǂ�����邱�Ƃ��ł��Ĕ��ɗǂ��Ƃ������ƂŁA�T���ȉƒ�̏��q�����̂悤�ȏ��M�w��ɒʂ�����ł��ˁB�����āA���̕��ʂɂ�����܂����A�����̎�قǂ��Ƃ��킹�āA�u���ɂ�����̏���v���������Ƃ����b���o�Ă��܂��B �@�������������Ƃ���A���M�w���ʂ��āA�㗬�Љ�̓`���Ƃ��K���Ƃ���@�Ƃ��A���������������I�Ȃ��̂����l���n�߂Ƃ��鏎���Љ�ւƍL�����Ă������Ǝv���܂��B �@��قǏ��삨�ʂ̘b�����܂�������ǂ��A����i����ˎ�j�^�c�M�V��57�̎��ɁA���삨�ʁi����j��55�ŁA���̓����̂��ʂɈ��Ă��M�V�̎莆������Ă���܂��āA���̎莆�̒��ŐM�V�́A���삨�ʂɑ��āu����ɗ�������ǂ��A�����̏��g���Ƃ��ċ��s�̏�����2�`3�l����l�I���đ����ė~�����v�Ɨ���ł��܂��B���삨�ʂɗ��߂������肵�������𑗂��Ă���邾�낤�ƐM���ė��̂ł��傤�ˁB�����āA3�̏������o���Ă���܂��ĂˁB �@��́A���t������������Ƃ��Ă���l�łȂ��ƃ_�����ƁB�����ɂ́u�ނ��Ƃ���������ʁv�Ə����Ă���܂����A�Ƃɂ����s���ӂȔ��������Ȃ������A���t�������T�d�ȏ����Ƃ������Ƃł��ˁB���ꂪ�������ł��B �@���ɁA�u�����҂͂���ɂČ�v�Ə����Ă���܂����A�܂ʂ��҂Ƃ��n���҂̓_���A�܂�A�������łȂ��ƃ_�����ƌ����Ă����ł��ˁB �@���ꂩ��O�ԖڂɁA�u���l�̈�����������ɂČ�v�Ƃ������ƂŁA�e�p�[��łȂ��Ƃ����Ȃ��Ƃ������ƂŁA�C�ɓ���Ȃ�����ɑ���Ԃ��Ƃ܂Ō����Ă��܂��B �@���̂悤�ɔ��Ɍ����������ŗv�]���Ă���킯�ł����A�Ƃɂ������s�̏�������Ȃ��ƃ_�����ƁB���̂悤�ȕ����I�Ȕw�i�A���{�E�f�{�Ƃ����܂����A�v����ɁA�䏊����̌o���������ď��M�w������Ă���悤�ȏ��������ɐM������Ă��܂��B�\���ł��邱�ƁA�䏊����̌o�������Ƃ������Ƃ��Љ�I�ɔ��ɍ����]�����Ă��āA�g�����Ȃ݂Ƃ��������Ƃ��A��V��@���Ƃ��A���t�������Ƃ��c�B��@�ƌ����Ă��F�X����܂�����A�q�Ƃ��ď����ꂽ���̗�@�Ƃ��A�t�ɂ����d������ꍇ�̗�@�Ƃ��A�莆���������̗�@�Ƃ��A�H�������鎞�̗�@�Ƃ��ł��ˁB�������������Ƃ���ʂ�킫�܂��Ă���B �@���̂悤�ɁA���M�w������鏗�����ǂ������ʒu�Â��ɂ��������Ƃ������Ƃ��A���̂悤�Ȏ������番����Ǝv���܂��B �@��i6�N�i1709�j�́w���p���͍j�ځx�́A�������߂Ƃ����������������p���͂̏����Ȃ�ł����A�����ǂ݂܂��ƁA�������߂��A���Ƃ��Ə��M��{�����������āA����ɔ��ɓ�����������킯�ł��ˁA���������̂悤�ɏ�����悤�ɂȂ肽���ƁB�Ƃ������ƂŁA�F�X�ȏ��������������M��{���������������A���N�����N�����K���Ȃ���A�u�\���B�̏����Ȃ�������M���Ă̂���͂����A�e�̖т̂������܂Ȃт����c�v�A�e�̖тƂ����ׂ͍̂��A�ق�̂킸���Ƃ���栂��ł�����ǂ��A�ق�̏����ł����̂悤�ɏ�����悤�ɂȂ肽���Ƃ�����S�ŁA�ꐶ�����A��������A�~�̊��������Ă̏��������C�������Ə����Ă���܂��B �@��i���N�i1704�j�Ɋ��s���ꂽ�w�݂����x�Ƃ�����{������܂��B���\7�N�i1694�j�́w���̂��T���x�Ƃ������J�얭�[�̎�{���o�Ă����ł����A���́w�݂����x�̍�҂́A�s�̐l�ł͂Ȃ��c�ɏo�g�Ȃ�ł��ˁB�s�ł́w���̂��T���x���]���ɂȂ��Ă��邯��ǂ��A���͓s�̐l�Ԃł͂Ȃ��̂ŁA���ꂻ�̑����ɂ��y�Ȃ����A�������Z��ł���n����8�قǂ̏��������āA���̎q�̂��߂ɂ��̎�{���������̂��Ƃ����f�菑��������܂��B�����āA���̏㊪���Ԃ��Ɍ��G������܂��ĂˁA�_�����i�̂����̒��ŏ������������K���Ă���}���ڂ��Ă����ł��ˁB�c�Ɏ҂ł������ł��]�T������Έꐶ������K�������Ȃ����Ƃ������P�ł�����܂����A���ۂɂ��̂悤�ȏ����������ł���Ƃ�����̏�������Ȃ����Ǝv���܂��B �@���̂悤�ɕ�i���ɂ͓s�����ł͂Ȃ��A�c�ɂł����M���w�Ԃ悤�ȏ����������o�Ă����̂ł��傤�B�@���̕ł̉E��Ɂu���M���ƕʈꗗ�v������܂��B����͈ȑO�Ɂw�]�ˊ�����ȍl�x�ł��Љ�����͍��v115�_�ł������A���̌㔭�����ꂽ���̂�����A���݂�133�_�ɂȂ��Ă��܂��B���̂�����ԍ�i�����������J�얭�[��24�_�B����������܂܂�Ă��܂��̂ŁA���ۂɂ�2�A3�_�̌덷�͂��邩������܂���B�����āA�����Óނ�15�_�A����ʂ�8�_�A��c�g��7�_�A�ȉ��A�t���{���ȂǂƁA�����ƕ���ł���܂��B �@���̂�����ʂ̒��J�얭�[�A���ꂩ��A�����Óނ��Ȃ��܂܂�Ȃ����Ǝ��͕s�v�c�Ȃ�ł����A�����Óނ͂Ƃ��āA���삨�ʂƑ�c�g�B���J�얭�[�A���삨�ʁA��c�g�B����3�l���A�]�ˌ���̖�����F���w���d���L�x�Ƃ��w�����M�L�x�Ƃ��������Łu���i�Ȍ�̏��O�\���v�ƌĂсA�ߐ����\���鏗�����ƂƏЉ�Ă��܂��B �@�o�œ_�����猩�Ă���i���������̂ŁA��\�I�ȏ������Ƃł��������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ���ł����A�����ւ̕����I�ȉe���Ȃǂ��l���Ă����܂��ƁA���́A��͂蒷�J�얭�[�Ƌ����Óނ��Q���Ă���Ǝv���܂��B �@���[�̏��͂��̐}�^�ɂ�����܂����A���̂悤�ɔ��ɓƓ��Ȏ��������܂��B���ň������悤�ȘA�ȑ̂̎��������܂����A���[�������ۑO��Ɉꐢ���r����킯�ł��ˁB�����đ�R�̎�{���o�ł���܂������A�����́w���T��x�A����3�N�i1713�j�̊��s�ł����A�����̏��M��{�̕��͋C���悭�`�����Ƃ��Ď����Ă��܂����B�����̕����C���p�N�g����܂��̂ŁA����������܂��B  �@��c�g�́w������x�̍�҂ƌ����Ă���܂����A�w������x�͎��͓�����ł���B�勝4�N�i1687�j�́w������x�ƁA��c�g�����������\13�N�i1700�j�́w������x�̓����܂��B��҂̌��\�Ō����ӂ��t�������̂��قƂ�Ǒ��݂��Ȃ��������߂ɁA���\����ʂɁw������x�ƌĂ�Ă��܂����A�����w�̐_�����ɂɁw�V������x�Ƃ��������ӂ�t�������̂�����܂��ĂˁB���ꂪ���͌��\�̌���ɈႢ�Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B�_�����ɖ{�ɂ͌��\13�N�̊��L�͂���܂��A�����͂���ƑS�������ł��B���炭��c�g���ŏ��ɏo�������̂́w�V������x�Ƃ��������ł������Ǝv���܂��B�����̕��͂��̓�́w������x���قƂ�Nj�ʂ��Ă��܂��A��c�g���������̂͌��\�̕��ł��B���́i���\�́j������ǂ݂܂��ƁA�勝�́w������x�����҂���̂́A���i��c�g�j���������w������x�̕����ǂ�����ł͂Ȃ��āA�����̍����̋Ȃ����Ă��鏊�����߂ɁA�����̉��߂̂��߂ɏ����L�����̂ł���ƌ����Ă��܂��B�����ǂތ���A�{���́w������x�͑�c�g�̑n��ł͂Ȃ����Ƃ����炩�ł��B�Ƃ������ƂŁA���̃^�C�g�����w�������ސ����̏��X�x�ƂȂ��Ă��܂��ˁB �@�����Óނ̍�i�́A�}�^�Ɂw�����ꋳ�E�����q���x���o�Ă��܂��ˁB����͑}�G�������������Óނ����������̂ł��B���ɃI�[�\�h�b�N�X�Ƃ����܂��������I�ȏ��ł��ˁB���ɂ��ꂢ�Ȏ��ł��ˁB���[�Ƃ��܂������Ă��āA���ɖ͔͓I�Ȏ��ł��ˁB �@���ꂩ�珬�삨�ʂł����A�i��i�́j�S����8�_�قǂł��B�c��5�N�̎�{���ŏ��Ƃ��āA���̍�i�̑������قƂ�Ǔ������e�ŁA�]�˒����܂ʼn��x�����O��ς��ďo�ł���Ă��܂����A���삨�ʂ̎�{�͓�����g�ݑւ��ďo�ł��ꂽ�Ǝv������̂�������ł��ˁB�c��5�N�͌������Ƃ�����܂��A����6�N�i1666�j�ȑO���s�́w���M��{�x�Ǝv������̂����̎茳�ɂ���܂��āA���\�w�l�G�����́x���A���ہi1716�`35�j�ȑO���w���M�t�̋сx���A�{���̑唼�������ł��B�������A�����̏o����͂���܂����B���������x�����x���g���g�ݑւ����āA�������ς����ďo�ł���Ă��܂��B�����ɂ́w���M�t�̋сx�̈ꕔ���ڂ��Ă����܂������B����A���Ə����Ă��邩������܂����B����͘a�̂Ȃ�ł����ǁA�U�炵�����̋ɒv�ƌ����Ă��悢���̂ł��ˁB�v����ɕ��������ɕ����Ă��܂��ĂˁA���̂悤�ȎU�炵��������������ł����A���͂�d�͂������ĕ����������Ă���悤�Ȋ����ł��ˁB�������悭����ƁA�����̍��E���t�]���Ă�����A�V�n���t�]���Ă�����A���ꂩ��A�M�����S���t���珑���Ă��鎚�܂ł���܂��B���ʂ́A������Ȃ��đS����C�ɏ����Ă����ł��ˁi�ꓯ���Q�̐��j�B �@�܂�A���ʂƂ��������̏��̑f���炵���Ƃ����܂����A�������Ƃ����܂����A�����[�I�ɕ\���Ă���Ǝv���܂��B�E�ォ�珇�Ԃɓǂ�ł݂܂��ƁA�u���ӂ��A���ɂ킩��T�A����_�́A�����Ă�Ȃ��A�N���S���v�Ə����Ă���܂��B�Ƃɂ����V�n���E���t�]���Ă��Ȃ��ʏ�̕����̕������|�I�ɏ��Ȃ���ł��ˁB�����̔��]�A�]�|�A�M���̋t�]�Ƃ������ƂŁA�U�炵�����̋ɒv�Ƃ����Ă悢�ł��傤�B �@���ɁA�t���{���ł����A�ޏ������J�얭�[�̏����w�������Ǝv���܂��B����9�N�i1724�j�́w���M����݂Ƃ�x�Ƃ�����{�ɂ́u�{���\��ΕM�v�Ə����Ă���܂��āA�������ɘb��ɂȂ����Ǝv���܂��B���Жژ^�Ȃǂɂ��킴�킴�u�\��v�Ə����āA������ɐ�`����Ă����ł��ˁB�{���͔d�������p�S�̕S���ł���t�����O�Y�̖��ŁA���̏t���Ƃ͂��̒n��̑可���������悤�ł��B���́w���M����݂ǂ�x���o�ł����{���͑��̋g�������s���q�ƌ����܂����A���̋g�����������p�S�̏t���Ƃ̈ꑰ�ŁA���̂ق��A�ޖ؏��̏t�������i���E�q��j�����ɂ�͂�g�������s���q���珬���ނ��o�ł��Ă��܂��B�����ꑰ�ł�����A�����ۛ��ڂ��������̂�������܂���ˁB�t���{��11�̕M�Ɛ�`�����w�i�ɂ͂��̂悤�Ȏ�����W���Ă�����������܂���B �@���ꂩ�獲�X�؏ƌ��́A���{���������Ƃ�����܂��A���\�`���ۍ��Ɋ������s�̏��ƂŁA���X�؎u�����Ƃ����L���ȏ����Ƃ̖��ł��B���̖��̍��X�؏ƌ��A�ƁA���邢�͗R��Ƃ������܂����A�ޏ��ɑ��āu���O���������菑�����w�Ȃ��ƁA�������₦�Ă��܂��̂ŁA�ꐶ�����C�s�����Ȃ����v�ƌ����ďC����ςݑ听�����Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ��w����P�x�Ƃ������q�p�����̋L���ɏo�Ă��܂��B�����āA���̕M�͂͐��������悤�ŁA�Ƃɂ����M�̐����A�͋����̓_�ŁA�ƂĂ����������������̂Ƃ͌����Ȃ������ƏЉ��Ă��܂��B �@���ꂩ�璷�J��D�i�O�I�D�j�ł����A�ŋ߂����������c��w���w���}���ق�����܂��āA���������M��{�ނ����������邱�Ƃ�m��܂��āA���̌������Ƃ��Ȃ����̂�3�_�قǂ���܂��āA���̈�����J��D�́w���M�t�̖�x�ł��B���{�ɂ͎O�I�Ə�������Ă��܂����A�ޏ������[�����������߂ɁA�ژ^�ł͒��J��D�ƏЉ�ꂽ�悤�ł��B �@���̂ق��ɁA���[����M�C�q�Ƃ����������p�������J��i�A�܂��A��قǏЉ���c���悢����E�c�₷�A���̂ق��ɒ��J�쎁�Ɩ���鐳�̕s���̏��Ƃ����܂��B�Ƃ������ƂŁA���M��{�̍�҂ɂ͐F�X�ȏ��������܂����A�c�O�Ȃ��ƂɂقƂ�ǎ��Ղ��������Ă��܂���B�ǂ̂悤�ȏ����ł���������������Ȃ��ꍇ���قƂ�ǂł��B���̂悤�Ȓ��ŁA��̎��Ղ��������Ă���̂������Óނł���A���J�얭�[�ł��B���̓�l�ɂ��Ă͂�����x�̂��Ƃ��������Ă��܂��B �i3�j�����Óނƒ��J�얭�[ �@�܂������Óނł����A�w�����ˏ��w���x�̏�������ԏڂ������ł��ˁB�����ǂނƁA�ޏ��͋��s���܂�ł͂Ȃ��A���s���班�����ꂽ�ꏊ�ɏZ��ł��āA�ǂ��Ő��܂ꂽ���͕�����܂��A�Ƃɂ����Ⴂ�����狞�s�ɏo�ď����w�сA���ꂩ��a�̂ł��Ƃ����̂ق��̏��|�\�����s�Ŋw�т����Ƃ����Ǝv���Ă����킯�ł��ˁB�u���s�ɍs���Ȃ��Ə����͊w�ׂȂ��v�Ƃ������Ă��܂��B���s�̕����I�Ȉʒu�Â���A���s�Ƌ��s�ȊO�̒n�̕����I�Ȋi���̑傫����������܂����A�Óނ͂��܂��ܑs�N�̍��A�u������g�v�ƂȂ����̂ŁA�������A���N���������Ă����O����ʂ��������Ƅ����u�s�N�v�����t�ʂ���߂��܂��ƁA30���ɂȂ�܂�������������30�����s�ɏo�ď����w�сA���̂ق��̏��|���w�悤�ł��B �@����ŁA���s�ɏZ��ł���20�N�ɂȂ�ƁA���̏����ɂ͏�����Ă��܂��B�w�����ˏ��w���x�͌��\3�N�i1690�j�ɏo�Ă���{�ł�����A���ꂩ��t�Z���āA����20�N�O��30���炢���������Ƃ��琄�肵�Ă����ƁA��̊��i17�N�i1640�j���̐��܂�ł��낤�ƁA�����O��͂���ł��傤���A��G�c�Ɍ����Ă��̍��̐��܂�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B �@�Ƃɂ���30���㋞���ď�����w�сA40��㔼�ɂ͏����ƁE��ƂƂ��Ċ��Ă����ł��낤�Ǝv���܂��B��قǂ̐}�^�Ō����w�����ꋳ�E�����q���x�Ȃǂł͑}�G���`���Ă��܂�����A�{�̑}�G��`���Ƃ������Ƃ͂��Ȃ�̃��x���������ƌ�����Ǝv���܂��B40��ɂ͏���Ƃ��ɑ����̈�ɒB���Ă����Ƃ������Ƃł��ˁB �@������48���ɍŏ��̒���ł���w���S�l���x��w�����͊Ӂx���Ă��܂��B�N��I�ɍŌ�̒���͌��\8�N�i1695�j�́w�����ꋳ�E�����q���x�ŁA52���̍�i�Ǝv���܂��B�����Óނ̍�i�ꗗ�ł͂���ȍ~�ɏo�ł���Ă�����̂�����܂����A�Óނ͋��炭���\���ɖS���Ȃ��Ă��āA����Ȍ�̍�i�͒Óނ̈�e���o�ł������̂ł��傤�B����ŁA�n���o�g�ł��邱�ƁA���ꂩ�疼�O���u�ȁv�Ƌ��ʂ��Ă��邱�ƁA���ꂩ��M�Ղ��悭���Ă��邱�Ƃ���A�E�c�Ȃ́A���邢�͋����ÓނƓ���l�ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B��قǒ勝4�N�w������x�̂��b�������܂������A�N���������āA�����̌��\9�N�ƑS���������̂ł��B 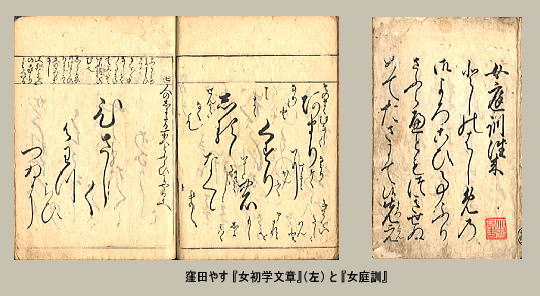 �@���̉����̍Ō�Ɂu�]�B��ÏZ�E�c�@�ہ^���ȕM�v�Ə����Ă���܂��B��قǂ����������w�����w���́x�͌E�c�₷�����������̂ł����A�����ɂ��قƂ�Ǔ����㏑���������āA�����Ɂu�]�B��ÏZ�E�c�@�ہ^�����₷�v�Ƃ���܂��āA�E�c�Ƃ͏��M��y�o�����ꑰ�������悤�ł��B�u�₷�v����ŁA���̖����u�ȁv�ł��ˁB �@��ÂƂ����̂͌䑶�m�̂悤�ɁA���s����d�Ԃɏ���ē�w�A���s�̎����R�Ȃł��̎�����Âł��ˁB����炢�R���z���čs���܂����A���ɋ��s����͋߂����ł��B����������10�q���邩�Ȃ����Ƃ������ł��ˁB����قNj߂���ł����A����ł������c�ɂƂ����ӎ��ł��ˁB����ŁA�s�ɂ͗��h�ȏ������Ƃ���R����ł��傤����A���Ȃǂ����̂悤�ȍ�i�������݂̂͜葽���̂ł����A����̗v�]��f���Ȃ��Ă����ʂ��ď����������ł���Əq�ׂĂ��܂��B �@���̂悤�ɓ����̏������A�s�Ŋw��ł��Ȃ��Ƃ������Ƃ̈����ڂ������Ă�����ł��傤�ˁB�ł�����A�����A�ꗬ�̏����w�ڂ��A�ꗬ�̌|�\��g�ɂ��悤�Ǝv������A���s�ɂ����Ȃ��ƃ_���Ȃ�ł��ˁB �@�}�^�́w�����ꋳ�x�ɂ��鋏���Óނ̎��Ɣ�ׂ�ƁA�E�c�Ȃ̕M�Ղ͂悭���Ă��܂��ˁB���̓�l�́u�ȁv�Ƃ�������������l�ł��邩������Ȃ��Ƃ����m���ȍ����͂Ȃ��A�P�Ȃ鉯���ł����A���Ȃ��Ƃ������悤�ȋ����ŏ��M���u���Ă����̂ł��傤�B �@���āA�����Óނ̍�i�Ȃ�ł����A��\�I�Ȃ��̂�3�قǏЉ�Ă����܂����A�܂��w�����͊Ӂx�ł��ˁB�勝5�N�ɏo�Ă��鏉���̍�i�ł��B�{���`����1�����̐}���f���Ă����܂������A�E�������\�ō����������ɂȂ�܂����A�܂��{�����厚5�s�ŏ�����Ă��܂��ˁB �@�u��x�͌䂱���̏��ɂӂ��ӂ��ƌ�A�ɂāA�ȂɎ����\�����A���Ă��Č�c�����܂��点��B�߂������ɂ��Ȃ炸���Ȃ炸��o�܂��܂��点��B�������v�ƁA�܂��A����������������̂ɁA�債�����\�������Ȃ��ŁA���킽���������A��ɂȂ����̂͂ƂĂ��c�O�Ȃ��Ƃł��A�߂������ɕK���₨�z���������Ƃ����悤�Ȏ莆�ł��ˁB �@�����ɍׂ������ŏ�����Ă���̂͒��ӏ����ł��B�Ⴆ�u��x�v�Ƃ������ɂ́A�u�����̕��[�ɂ������B�u�ЂƂЁv�u������v�u��������v�Ə����ׂ��v�ȂǂƏ�����Ă��܂��B�u��x�v�Ƃ����悤�Ȍ��t�͏������g���ׂ��ł͂Ȃ��A����ł��ˁA�����ŏ������t�łȂ��āA��a���A�����ŏ������t�ŏ����ׂ��ł���ƁB���́u�߂������v�ɂ����D�����K�ȕ\���ɒ����ׂ����Ƃ������ӏ���������܂��B �@�v����ɁA���̉E���ɏ����Ă��镶�͂͗ǂ��Ȃ����{�Ȃ�ł���B�Óނ͂�������u����܂蕶�́v�ƌ����Ă��܂��B���̍����ɁA����������������͂��o���Ă��܂��B �@�u���ƂЂ͂܂�̌�o�ɂČ����ɁA�����炳�܂ɂČ�A�A�Ȃɂ̕��������Ȃ��A���������̂����Ɏv�Ђ܂��点��B������ʔ�A�̂Ƃ₩�Ɍ䂠���ЂȂ����₤�Ɍ�o�҂��܂��点��B�������v�Ƃ������ƂŁA�����������炵�����͂̌��{�������āA���̂悤�ɏ����Ȃ�����Ƌ����Ă��܂��B �@�ȉ��A�S���A���̂悤�Ɉ�����Ɨǂ����ΏƂ����Ă��܂��B�u���땶��ΏƖ@�v�Ƃł������ׂ����@�œK�ȏ����̏����������������̂ł��B���̍Ō�ɂ��莆�̏������Ɋւ����{�I�ȍ�@�ɐG��Ă��܂��B�����ł��A���������t�����A�����炵���\���ȂǁA�莆�̏��������Ȍ��ɐ�����Ă��܂��B �@���́w�����ˏ��w���x�Ƃ����p���͂ł����A���p���͂̒��ł�����قlje���͂����������̂͂ق��ɂȂ��Ǝv���܂��B�����ł�C���łȂǔ��ɖ͕킪�������̂ł��B��قNj����Óނ̍�i���ꗗ�ɂ������̂����܂������A�����ɏ����Ă���ʂ�A���ɉ���{��������ł��ˁB���\11�N�i1698�j�́w���p���͑听�x����n�܂��āA�w�����ɍ����G�x�Ƃ��w�����ѕ�܁x�Ƃ��w���ʗp���܁x�Ƃ��A����{������5�{�����āA���\10�N�́w�����t�W�x�̗ᕶ���قƂ�ǂ��w�����ˏ��w���x�̊ێʂ��ł�����A�S��6��ނ�����܂��B�}�łł͉���{�́w�����ɍ����G�x���f���Ă���܂����A�����̕������u������`���v�ɕς���Ă��܂��ˁB�{���͑S�������ł���ˁB�����w�����ˏ��w���x�̕��́A���̗ᕶ�ɍׂ������߂����Ă��܂��B�ەt���̊������őΉ��W��������悤�ɂȂ��Ă��܂��B�{���̌��̌����ւ��\���⒍�߂ł��ˁB �@���q�p�̎莆���Ɋւ��鉝������300�_�ȏ゠��Ǝv���܂����A���̒��ŁA���ꂾ���ڍׂȎ{�����{�������̂͂ق��ɂ���܂���B���̂悤�ɒ��߂��O�ꂵ�Ă��邱�ƁA�C���ł����{�������悤�Ɍ㐢�ɑ���ȉe�����y�ڂ������Ƃł��A���Ƀ��j�[�N�Ƃ����܂����A�d�v�Ȉʒu�Â��̉������ł��B �@���ꂩ��Ō�́w�����͓s�D�x�ł����A�}�͍��瓹��ŏ��ЂB����Ƃ����e�[�}�ŏ����ꂽ�����̗ᕶ�Ȃ�ł����A�F�X�ȏ����A�ÓT�Ђ̖��O����ďЉ�����̂ł��B���͌`���͎莆�ł����A���̖{���͌ÓT�I���{�������邱�Ƃɂ���܂��B�ÓT�̒m�����R�ɓ���āA���̓��e�A��҂Ȃǂ��Љ���{�Ȃ�ł��ˁB�܂�A�莆���̐��`�Ƃ��������A�莆���̌`����������ČÓT�����������ȏ��ɋ߂���ł��B�ł����珗�p���͂̌`���ł����ǂ��A�����ȏ��p���͂Ƃ͈Ⴂ�܂��B���̂悤�Ȃ��̂����́u����������v�ƌ����Ă��܂��B�X�^�C���������������ł��ˁB�ł����ǂ����͂����ɏ����Ă���m������e�������邱�Ƃɂ���܂��B �@�ÓT�Ɋւ���L�x�Ȓm������Ƃ����_�Ō����ꍇ�ɁA���́w�����͓s�D�x�ɕ��ԏ��q�p�����͂Ȃ���ł��B������ƂĂ����j�[�N�ł��ˁB����1���̉������Ŏ���80�_�̏������Љ�Ă��܂��B�䉾���q�A����Ƃ����Ă��̕��ꂠ��A���j���ꂠ��A�R�L���ꂠ��A���b���ꂠ��A���M�A�̏W�A�ޑ�a�̏W�A���ꂩ�珗�P���Ƃ������ƂŁA�l�X�Ȗ{���Љ�Ă��܂��B �@���̂悤�ɋ����Óނ̏ꍇ�A���Ƀ��j�[�N�Ȗ{�������Ă���B�����炵�����t�����A�����炵�����Ƃ������Ƃɔ��ɏd�_��u���Ă��܂��B���ꂩ�珑�����f���炵���������A�G�`���ł��������Ƃ����_�ł��ˁB  �@���ɁA���M�̑o����S��������l�̏��������ƁA���J�얭�[�ł��ˁB�^�j��ȁu�����v�ŏ��M�S���������[�h�����ƌ��o���ɏ����Ă����܂������A���[�͏��M�̑S�������n���������ł��B �@���[�A��A�L�A�M�C�q�ȂǐF�X�Ȗ��O������܂����A���s�̏��ƂŁA�������ォ��䏊������āA12�N�ԁA�����Ƃ��������ɏ����w��ŁA���ތ�A���s�ŏ��M�w���������ł��ˁB��q�ɁA���J��i�A���J�����A���J��D�A���J�썲�삪���āA�Ō�̒��J�썲��͎��̌������Ԃ̐搶�����M�{����肵�ăR�s�[�𑗂��Ă���܂��āA�q�������疭�[�̏��Ƃ�������ł����B���̍�������[�̒�q�������Ǝv���܂��B����ɂ��Ă͏o�ł��ꂽ��{�͂���܂���B���ꂩ�玑���ɂ͏����Ă���܂��A�t���{�������炩�ɖ��[���ł��B�{���̍�i���ɂ����炩�ɖ��[�̍�i������p�����Ǝv����ӏ�������܂��B �@���̂悤�ɖ��[�̎��Ղ́A�}�^�ɏЉ���L���ɂ����̂ł����A���[�Ɋւ���L�^�͂��ꂾ���Ȃ�ł��ˁB����́w���p���͎��ԁx�Ƃ������q�p�����̒��ɏo�Ă��܂��B���a9�N�i1772�j�ɏo�ł��ꂽ�������ł����B���J�얭�[�Ɋւ��ď����ꂽ�L���͂��ꂵ������܂���B �@����Ŕޏ��́A���\7�N�i1694�j�́w���̂��T���x������3�N�i1753�j�܂�60�N�Ԃ�25�_�̏��M��{�������Ă���܂��āA��i�������|�I�ɑ����A�����N������ɒ�����ł��ˁB���\���A�����Óނ͂����炭50�ォ��60��ŁA60�O��ŖS���Ȃ����Ǝv���܂����A���̍��A���[�͎��̏������ƂƂ��Ĝa���̔@���o�ꂵ���B���̓����A���[��20��ł��傤�B�ȗ��A60�N�Ԃ����M�w��𑱂��Ă����킯�ł��B �@������������Ԃ̐搶���A���[�̒��M�{�Ǝv������̂������܂��ĂˁB���Ȃ�M���͎キ�Ȃ��Ă��܂����A���̎������M�d�Ȃ̂́A�Ō�Ɂu�M�C�q�^���J�쎁�^���厵�E���Ώ��v�Ə����Ă����āA������Ȃ�80�߂��܂Ő��������Ƃ������邱�Ƃł��B���炭���ɏ����ꂽ���̂ł��傤�ˁB���[�͔��ɒ��������č�i������ԑ����A���ۊ��𒆐S�ɂ��Ė��[�����u�[���ɂȂ�킯�ł��ˁB �@�ł�����A���[����͕킵����{���F�X�Əo���������A���ۍ��ɂȂ�ƁA���[�������̎�{�̉����Ɂu�M�C�q�̍��Ȃ����̂͐^�M�ɂ��炴����̂Ȃ�v�Ɩ��L���āA�ޏ���r�˂���悤�Ȃ��Ƃ��������悤�ɂȂ�܂��B����͗ގ��i�������o����Ă����̂ŁA�u���̂悤�ɏ����Ă���v�Ɣ����璍�����ꂽ�̂�������܂��B������ɂ��Ă����[����ςȐl�C���������Ƃ������Ă��܂��B �@�������A�����Óނ͖��[�̂悤�ȏ�������ǂ��v���Ă��܂���ł����B�w�����ˏ��w���x�̊����Łu�_�A���A�́A�͂˂Ȃǂ̏����Ȃ������܂�����v�ƈꌾ�����Ă����ł��ˁB����́u���[���v�Ƃ͏����Ă��܂��A���\������a���̔@���o�ꂵ�Ċ��n�߂����[�A�����5�N�A10�N�Ƃ����Ȃ������ɓc�ɂɂ������ɍL�܂�A�u���[���v�Ƃ��Ă͂₳��A�c�ɂł��u�s�ł́w���̂��T���x�����s���ĕ]�����v�Ɠ`����Ă����قǂł�����A�����ɒ��ڂ𗁂т��̂ł��傤�B�������Óނ́A����͐����h�̏������ł͂Ȃ��ƌ�������������ł��傤�B�w�����ˏ��w���x�̋L���͈Âɖ��[����ᔻ�������̂��Ǝv���܂��B���l�̖��[���̔ᔻ���w����ژa�P���x�̒��ɂ�������Ă��܂��B �@�ǂ���ɂ��Ă����ɓƓ��ȎU�炵�����ł��āA�j���ɂ͂Ȃ��悤�ȏ������ł��ˁB�]�ˎ���̏��̂͌�Ɨ�����{�ł����B�j�����������������͂��܂�ς������Ȃ���ł����A�����ɂ���đ����̍��͂���܂����A�唼����Ɨ��ł���قǑ傫�ȕω�������܂���B���ꂩ�炷��Ɩ��[���́A���ɓƑn�I���v�V�I�ŁA���I�Ȓj���̌�Ɨ��Ƃ͈قȂ�A�^�j��ȏ��@�ł������ƌ�����Ǝv���܂��B �@���ꂩ��A���[���̐_�����W�����t�Ɂu�����i�������j�v�Ƃ����̂�����܂��B����10�N�i1725�j�w�т̊C�x�̒��Ɂu��K�̎d�p�̎��v�Ƃ����L��������܂��B����͖��[������̏��_��W�J�����B��̋L���ƌ����Ă��悢���̂ł����A�����ɂ́A�����̑����ׂ��⎚�`�Ȃǃ����n�������āA�o�����X�ǂ������Ȃ���ΐ��������Ƃ͂����Ȃ��B���[��栂��ł́A�l�Ԃ̊�ɉ��ʂ��Ȃ��ĉZ�̂悤��������A�����ē����悤�Ȑl�Ԃ̊�ł͂Ȃ��B�葫���_�̂悤�ł͔����������Ƃ��Ȃ��Ƃ����킯�ł��B�����̂��݂��݂܂Ő_�o���s���͂��Ă���Ƃ����悤�Ȃ��Ƃł��傤���A���̂悤�Ȏ����u�����v�ƌĂ�ł��܂��B �@����Łu�����v�Ƃ����̂́A���[���ŏ��Ɍ��������t�Ȃ̂��ȂƎv���Ă��܂������A�F�X�ƒ��ׂĂ���܂�����A���\6�N�i1693�j�́w��K�d�p�W�x�̒��ɂ��o�Ă���A�����̐��E�ł͈�ʂɎg���Ă����p��̂悤�ł��B�����ɐ����������Ă悭�����A�����������Ă��鎚�A���������߂�ꂽ�����u�����v�ł���A�t�ɁA�_��̃o�����X���Ƃ�Ă��Ȃ����́u�����v���ƌ����Ă��܂��B���̒��Ԃ��炢���u�a���v�ƌ����̂��ƁA�����̐��E�ł͎g���Ă����݂����ł��ˁB �@���̂悤�ɖ��[�ƒÓނ̓�l�̏��ƁA�Óނ͊m���ɖ��[�̂悤�ȏ���ᔻ���Ă��܂����ǁA���ʓ_�Ƃ��ẮA���M����ՂƂ��ď����炵���A���邢�͏����̎��Ȏ咣�Ƃ����܂����A�����炵�������⏗���炵�����t�����Ȃǂ��A�����������ɑ��Ď咣�����A���M��{�Ȃǂ̏o�ŕ���ʂ��Ĕ��M���Ă������Ƃ����_�ł͋��ʂ���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B �i4�j���M�̎���̈Ӌ` �@���̂悤�ȏ��M�̎���̈Ӌ`�Ƃ��ẮA���ۊ����s�[�N�Ƃ���100�N�Ԃ����M�̎���ŁA���̎���ɏ������Ƃ��y�o�������Ƃł��B���M��{�����āA���̂悤�ɏ������炢���ȂƏC�������������A�₪�đ听���Ď��珗�M��{���o���Ƃ�����A��قǂ̖������߂̂悤�ȗႪ����܂������A���ꂩ��킸��11�ŏ��M��{���������t���{���Ƃ������������܂����B���̂悤�ȏ����B�����X�Ɠo�ꂵ���킯�ł��B �@���̔w�i�ɉ����������̂����l���Ă݂܂��ƁA�u������������ւ̌x���v�Ƃ������Ƃ��������Ǝv����ł��ˁB�ǂ����Ă��Ƃ����܂��ƁA���\�����牼�������Ȃǂ̓`���I�ȕ������ǂ�ǂ���n�߂Ă���Ƃ����뜜���w�E����ӌ����F�X�Əo�Ă��܂��B �@��͌��\5�N�i1692�j�́w���d��L�x�ŁA�c���䔌�����������̂ł��ˁB�����Ɂu�����͂���ɂ��j�̏������{�A�悫��Ȃ�Ƃ��Ȃ�Ћ��ӂׂ��炸�B�j�̎���Ȃ�Ђ��鏗�M�́A�M���Ă���ǂɂ݂ցA���͂����Ƃ��Ă��j�炵�����ԁX������̂Ȃ�B�悫���M����{�Ƃ����ӂׂ��v�Ə����Ă���܂��B �@�w��̐Ԃ݁x�Ƃ������P���ɂ��A�^���A�܂芿���͒j�q���u�߁i���݂����j�v��g�ɂ����悤�Ȃ��̂ŁA�����͏��������������悤�Ȃ��̂��Ƃ��āA���ꂪ�t�ɂȂ�����A�܂�A�������߂𒅂āA�j�q���������Ȃǂ�������ӂ��킵���Ƃ����܂����ƌ����Ă��܂��B �@���ꂩ�炱��ɂȂ�������̂ł��傤���A��i2�N�i1705�j�́w���M�q�����x�Ƃ�����{������܂��āA�������j�̕M�Ɋw�ԂƁA���t���I�݂ł��₵���Ȃ�A�u�悩��ʏ��ɏ㉺�̂͂��܂������邪���Ƃ��v�Ƃ���A�ŋ߂̎�{���j�M�ɋ߂��āA�������Ȃ��Ǝw�E���Ă��܂��B�䏊���̐l�ɂ��̂悤�Ȃ��Ƃ���������w���M�q�����x�̍�҂��A20�N�����ď��M�̖͔͓I�ȏ����W�߁A������ʂ��ď����āw���M�q�����x�Ƃ�����{���o�ł�����ł��ˁB �@���l�ɁA��i4�N�i1707�j�́w�킩�݂Ƃ�x�ɂ��u���Ԃɔs�̏��M�����L�V�Ƃ����A�����͒j�M�ɂāA�����̎�{�ɐ��������v�Ƃ���܂��B  �@�܂��A�`���I�ȕ����̑r���Ƃ����_�Ō����܂��ƁA�c��3�N�i1650�j�ɏo�ł��ꂽ�����厺�́w�Ќ��x�̒��ɂł��ˁA����͌���Ɋւ��ĐF�X�������{�ł����ǁA���̒��ɁA�s�̌��t�͐̂͗ǂ���������ǂ��A���̂܂ɂ��c�Ɍ��t���������Ă��āA�����Ȃ��Ă����Ə����Ă���܂��B�s�̕������n���֍L����A�n���̕������s�ɓ����Ă���Ƃ����������̌𗬂��i�߂A���R�A�`���I�Ȃ��̂₻�̒n��ɓƓ��ȕ������i�X�ƕ���Ă����킯�ł��ˁB���̍�҂��A���̕������ǂ�ǂ����Ă����Ă��āA���Ɍ��t�̗���͂Ђǂ��ƌ������������̂ł��傤�ˁB����ŁA���������A���̂悤�ȋ��s�̕����̗���́A���m�̗��Ɏn�܂����ƌ����킯�ł��ˁB �@�܂��A�`���I�ȕ����̑r���Ƃ����_�Ō����܂��ƁA�c��3�N�i1650�j�ɏo�ł��ꂽ�����厺�́w�Ќ��x�̒��ɂł��ˁA����͌���Ɋւ��ĐF�X�������{�ł����ǁA���̒��ɁA�s�̌��t�͐̂͗ǂ���������ǂ��A���̂܂ɂ��c�Ɍ��t���������Ă��āA�����Ȃ��Ă����Ə����Ă���܂��B�s�̕������n���֍L����A�n���̕������s�ɓ����Ă���Ƃ����������̌𗬂��i�߂A���R�A�`���I�Ȃ��̂₻�̒n��ɓƓ��ȕ������i�X�ƕ���Ă����킯�ł��ˁB���̍�҂��A���̕������ǂ�ǂ����Ă����Ă��āA���Ɍ��t�̗���͂Ђǂ��ƌ������������̂ł��傤�ˁB����ŁA���������A���̂悤�ȋ��s�̕����̗���́A���m�̗��Ɏn�܂����ƌ����킯�ł��ˁB�@���ꂩ��A��قǂ��o�܂����w���d��L�x�ɂ��A�����̓s�̗��s���A���s�̏����{���́u���ɂ₳�����v���Ƃ͂������ꂽ�u�����A�[�i�͂����j�̕��v�ł���Ə����Ă���܂��B�v����ɁA���s�{���̕������ώ����Ă��鍡�A���ƌ����Ă����\����ł����A�n���������Ă����l���A���̓����̋��s�̗l�q�����āu���ꂪ���s���v�ƌ�������̂́A�S���u�Ԃ̓s�̒p�v�ł���ƌ����Ă��܂��B �@�ł�����A�����Óނ����s�ɍs�����̂͌��\��������O�ł����A���̂悤�ɒn���̐l�����֍s�������A�s�������Ǝv���ď㋞���Ă��A�����ɂ���̂́A�n���̐l���炷��Ζ{���̋��s�̕����ł͂Ȃ��Ƃ����ӎ�����������ł��傤�ˁB �@���̂ق��w�w�l��̌����x�ŗL���Ȑ^���O�Y�搶���A���\�����i���ɏ��[���������֕��y���Ă������Əq�ׂ��Ă��܂����A�䏊�ȂǏ㗬�Љ�̌��t���ǂ�ǂ��ɍL�����Ă������킯�ł����A���̉ߒ��Ō��t�����X�ɕ���Ă�������ł��ˁB�䏊���t���䏊�������O�֏o�čL�����Ă��������ɁA����͈���Ō��t�̕ώ��Ƃ����ɂȂ����Ă������Ǝv���܂��B �@�����Ɂu�����Ɗ����̊�ȊW�v�Ə����Ă����܂������A���M��{�ł́A�����͒j���t���g���ׂ��ł͂Ȃ��A���������܂�g���ׂ��ł͂Ȃ��Ƃ����l��������ʓI�ł����B�w���d��L�x�ł������͊����̒m���͕K�v�ł��A��b��莆�ɂ͎g���Ă͂����Ȃ��Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ�������Ă��܂��B���l�ɕ��9�N�i1759�j�́w����ژa�P���x�ɂ������悤�Ɂu������m���Ă��Ă��A�����Ďg���Ă͂����Ȃ��v�Ə�����Ă��܂��B�m���Ă��Ă��悢����ǁA�g���Ă͂����Ȃ��Ƃ����̂ł��ˁB���̍l�����͖����ɂȂ��Ă������Ƒ����Ă��܂����B �@���̒��Œ�������O�I�Ȃ̂́A�V��9�N�́w�����͎l�G���Ӂx�ŁA������������̂͒j���ł��傤���A�}�G�͖k�������Ƃ����L���ȉ�Ƃł����A�����̔ʼn��͈�l�̉�Ƃ��}�G�����͂��S�������Ă��܂����Ƃ����Ȃ��Ȃ��̂ŁA�S�Ėk�������̑n��Ƃ��v���܂��B �@����ɂ́A���Ƃ������ł����Ă��A�l����n�����L�ڂ��鎞�ɂ͓K�x�Ɋ������g���ׂ����Ə�����Ă��܂��B���̗��R�͗Ⴆ�u�l�Y���q�v��u���Y���q�v�́A�������ł͑��_�̗L���ŋ�ʂ����Ȃ��Ȃ�܂����A�u�ЂƂ�Ȃ��v�������ŏ����u����v��2�����ōς݁A�������g�������ԈႢ�����Ȃ��č����I�����A���������������Ȃ����ʂ��Ȃ��Ǝ咣���Ă��܂��B �@����͂ǂ��炩�ƌ����Η�O�ł����āA�����ɂ͊������Ȃ��܂Ȃ��Ƃ�����̂��唼�ł����B �@���������ۂɁA���M��{�Ə��p���͂̊����g�p�����r���Ă݂�ƁA�ʔ������Ƃ�������܂��B��̎莆���̒��Ŋ����ƕ������̕������̔䗦���ǂ̂悤�ɕω�����̂��ׂĂ݂܂����B���M��{�͉�����������̂ł�����A�����������Č����鏑�ł�����A�������������̕����K���Ă��܂��A�U�炵�����ɂ��Ă����ɂ��Ă��B�]���āA�����g�p���Ɏ���I�ȕω������܂肠��܂���B �@�ł����ǂ����p���͈͂Ⴂ�܂��B�����g�p�����i�X�オ���Ă����ł���A�]�˒��������]�ˌ���Ȃ�Ȃ�قǁB�����̎g�p�����������Ȃ��Ă��܂��B���p���͂̍ŏ��̎莆��1�ʂɂ��Ē��ׂ�ƁA�]�ˑO���̊����g�p����13�`37���ł����A�]�ˌ���ɂȂ��30�`46���ł����B �@���p���͎͂��p�{�ʂɕ҂܂�Ă��܂��̂ŁA����g���莆�̖͔͕��ł�����A�������ɑ������`�ō���邱�Ƃ������킯�ł��B���̏��p���͂ɂ����Ċ������g���������ǂ�ǂ��Ȃ��Ă���̂́A���Ԃ��Č����ƁA�����̐����̒��Ŋ������g���p�x�����܂��Ă����A���邢�͏����̌��t�̒���A�����̌��ꐶ���̒��Ɋ���⊿���������Ă��������ʁA�j���g���悤�Ȍ��t�����������ʂ��Ďg���悤�ɂȂ��Ă������Ƃ������Ƃ�������Ǝv���܂��B���ꂩ�珗�p���͂͂قƂ�ǂ��j�������������̂ł�����A�j�����������p���͂Ƃ����̂́A���R�Ɗ������g�������������Ȃ�����A�j�����j���I�ȕ\�������X�ɓ����Ă������̂�������܂���B �@�����āA�]�ˌ���̉Éi���ɏo���w���p���͑����x�ɂ��ʔ����L���������ł����ǁA�����Ɋ����ɐU�艼����t���闝�R��������Ă����ł��ˁB�����̎莆���͉�����̂ŏ����ׂ������A�����ɂ͕������������Łu�����v�Ƃ����̂͊����̂��Ƃł����A�Ƃɂ����������o���邽�߂ɁA�����Ċ����𑽂߂Ɏg���Ă��邪�A���ۂɏ����莆�͉����������]�܂����Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ�������Ă����ł��ˁB���̏��p���͂̕���ł́A�������킴�Ƒ�R�g���Ă��܂���A����͊������o���Ă��炤���߂ł��A�����ǂ����i�g���ꍇ�ɂ͂Ȃ�ׂ��������𑽂��g���悤�ɂ��������悢�Ƃ����킯�ł��ˁB �@�����ɂȂ�ƁA���ꉻ�͂���ɐi�݂܂����B����11�N�i1878�j�́w�����p����x�����܂��ƁA�ɒ[�Ɋ��ꉻ���ꂽ���q�������Ƃ���܂����A�{���ɂ��ꂪ���q�̎莆���Ȃ̂��Ǝv���悤�ȗᕶ�ł��B�u�V�N�̌�g�c�痢�����ڏo�x�j�[��c�v�Ƃ܂��ɒj���������悤�Ȏ莆�ł��ˁB�Ōオ�u�����ތ��v�ł�����B���́w�����p����x�͑S������Ȋ����̕��͂Ȃ�ł��ˁB���̂悤�ȋɒ[�ȗ������܂����B �@�������A���N��̏��p���͂ɂ��A�����̓C���e���ł�����͂��܂�g��Ȃ������ǂ��Ƃ��A���ʂ̐l�̑O�Ő��m���t�͎g���ׂ��ł͂Ȃ��Ƃ������S����������Ă��܂��B�v����ɁA����ɕ�����Ȃ����t�ł͂Ȃ��A����ɕ�����₷�����t���g���������A�D����������Ƃ��A�_�a���Ƃ������Ƃ�����킯�ł��ˁB�����������ƂŁA�]�ˎ���ȗ��̗��O�������ɂȂ��Ă����@���ꂸ�Ɉ���Ă����Ƃ������Ƃł��B �@���̂悤�ɁA�ߐ�����ߑ�ւƎ��オ�ڂ�ς���Ă������ɁA���M�����͂����Ȃ�ϑJ�𐋂����̂��A�܂�A���M�̕����͌p�����ꂽ�̂��A����Ƃ����ł����̂��Ƃ������Ƃł����A��͏����炵�����t����������ׂ����Ƃ����l�����͋ߑ�ɂ��p����܂����B���ꂩ��A�Ȍ��ȏ������D��ł����A������匳�𐳂��ƁA�܂������Óނ������̎莆�̏�������10�ӏ��ɂ܂Ƃ߂܂����B�����̎莆�̏������ɂ��Ă̋��P�͌c��3�N�́w���ނȂ��T�݁i������`���j�x�ɂ��o�Ă��܂����A�����ł͗Ⴆ�Α���̐g���ɉ�����6�i�K���炢�ɏ���������A���o�l�̖��O�ƈ����l�̖��O�̍���������ɕς�����A�����̂��������ɂ���Ă����6�i�K���炢�ɏ�����������A���̂ق��ׁX�Ƃ�����@������܂����B����������Óނ͂�������10�ӏ��ɂ܂Ƃ߂Ă��܂��A�����ŒÓގ��g�������Ă��܂����A�����͂���Ȃɏڂ�����@��m��Ȃ��Ă��悢�ƁA�厖�Ȃ��Ƃ͏����炵�����������t�����ł����āA���܂�g���ɉ�����6�i�K�ɏ���������悤�Ȃ��Ƃ��قƂ�Nj��߂Ă��܂���B�܂�A�g���������������d�����Ă����ł��ˁB �@�j�����ł͓��Ă��ĕ��G�ȏ��D�炪�W�J�������������̂��A�Ȍ��Ȃ��̂ɐ�ւ����̂������Óނł���A���J�얭�[�ł������킯�ł��B�����Óނ̍�������D��Ȃǂ́A�������ɏo���������{���i����30�N�i1897�j�w���{���玮��S�x�j�Ȃǂɂ��قƂ�NJێʂ�����Ă��܂��B���\���̏��D�炪�A�قƂ�Ǖ�����ς����ɖ�������̊����{�ɂ��ڂ��Ă����ł��ˁB �@���ꂩ��ᕶ�̑��l���Ȃǂ��ߐ��ł��ߑ�ł����l�ł��B�܂��A�����⊿��̎g�p�͋ߑ�ɓ����ċ������ꂽ���̂�����܂��̂ŁA������p����Ă��܂��B �@���ǁA�ߑ�ɓ����ď����Ă������ő�̏��M�����Ƃ����̂́A�U�炵�����Ȃ�ł��ˁB����30�N��ɓ���ƎU�炵�����������Ă����܂��B�Ƃ����̂��A�����̏��p���͂��{���ؔō��肩�犈�ň���ɕς��܂��B���Ȃ킿�A�����������ɂȂ������_�ŁA��������������A�ȑ͕̂\���ł��܂���B�܂��Ă�U�炵�����Ȃǂ͕����̑傫����A����������ς���Ƃ��������Ƃ��K�v�ł����A�������������Ƃ���ؐ�̂ĂȂ��Ɗ����ɂȂ�Ȃ��킯�ł���B�����ɂ���ĎU�炵�����͊��S�ɏ����邱�ƂɂȂ�܂����B �@�������������Ƃ܂��āA�Ō�Ɂu���M�̎���v�̈Ӌ`���܂Ƃ߂Ă݂܂��ƁA���ɏ����Ǝ��̕������W�J��������ł���Ƃ������Ƃł��B�����I�ȑ��ʂ���̓����ł����A�����������炵�����A�����炵�����t�����A�����炵�����D��A�����Ė��[�̂悤�ɒj���ɂ͂Ȃ��v�V�I�ȏ��Ȃǂł��ˁB������F��������M�͏��������̌���������d�v�Ȏw�W�̈���Ǝw�E���Ă��܂����A���ɁA���M�̎���͂��̂悤�ȕ��������ɏ������܂ޕ��L���w�ɍL�����Ă������_���d�v���낤�Ǝv���܂��B���삨�ʂ����ɏ��M�����ɂ����ďd�v�Ȗ����������܂������A���ʂ̏ꍇ�͂܂��܂��㗬�Љ���S�������Ǝv���܂��B���̓_�A���[�⋏���Óނ̓����͏����K�����܂ލL���w�̏����ɉe����^�����킯�ł��B �@��ԖڂɁA���������M��ʂ��Ď��Ȏ咣��������Ƃ����A�ӎ��I���ʂ̓��F�ł��B���������̍˔\�A�\���ł��邱�Ƃ��܂߂āA�Ƃɂ��������̍˔\��ɂł�������ł����B���ɗD��Ă��邱�ƂŁA���g�o���̃`�����X���^����ꂽ�Ƃ������Ƃł��ˁB�����āA���Ȏ咣�̈�̗�Ƃ��āA����������̍�i�ɏ���������悤�ɂȂ������Ƃ�����܂��B���̂悤�ȓ����́A���Ȃ��Ƃ��o�ŕ��ł͏��M��{���ŏ��������Ǝv���܂��B�����A�E�c�₷��E�c�Ȃɂ́u�s�ɂ͂�낵�����M���܂����͂��܂��ւ���́c�v�Ƃ���������������܂����A���M�̉�������ł��钷�J�얭�[�̎���ɂȂ�܂��ƁA�u�M�C�q�̍��Ȃ����̂͐^�M�ɂ��炴��Җ�v�Ƃ������ƂŁA����Ɏ��Ȏ咣�̋����p����������悤�ɂȂ�܂��B �@���ꂩ���O�ɁA�������Љ�i�o�̉\�����L��������Ƃ����ӂ��Ɍ�����Ǝv���܂��B�]�ˎ������̕���4�N�i1821�j�ɏo���w�M���t�Ɛl���^�x�Ƃ����̂�����܂����A����͍]�ˎs���̏��Ƃ̐l���^�ł��ˁB�����ɏ����ƂƂ��ɏ��Ƃ̖��O�ƏZ���������ꂽ����܂����A��Ɨ��𐔂����375�l�̏����Ƃ̖��O������Ă��܂����A���̂���120�l�������ł��B��G�c�Ɍ����Ė�3����1�������B���̂��Ƃ͂��傤�Ǎ]�ˌ���̍]�˂̎��q����3����1�����t���ł������ƌ����܂����A����Ƃ��悭�������邱�Ƃł��B �@�]�ˌ���ɂ͂��Ȃ�̏������Љ�ɐi�o���Ă������Ǝv���܂��B���̂ق��̐l���^�Ȃǂ����Ă��A12�Ƃ��A7�Ƃ������{���ɎႢ���オ�����ƂƂ��Ė��O��A�˂Ă��āA�����̖{�͏����̎t�͂�T���ۂ̃K�C�h�u�b�N�ŁA�t���̖��O��Z�������łȂ��A���ɂ͎���G�Ȃǂ��ڂ��Ă��܂�����B������7�̏��q�܂ł������Ă���킯�ł��B �@���̂悤�ɁA���M�����⏗�M��{�̉e���ɂ���āA�����̎Љ�i�o���m���ɐi�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B ���z�t�����@1�`3�� �iPDF�@416KB�j �@ �z�t�����@4�`6�� �iPDF�@1.08MB�j �@ �z�t�����@7�`9�� �iPDF�@203KB�j ���u���^�i�S���j �iPDF�@256KB�j |
|