|
�������w�Љ���Ȋw�����Ȃɒ�o�����w�ʘ_���v�|�ł��i�������}�ł͕ʁj�B |
|
| �_���薼 | |
| �ߐ��̏��M��{ �� �������߂��鏔��� �� |
|
| �p���薼 | |
| The Calligraphic Model Textbooks for Women
in the Edo Period���� On the Various Problems Relating to the Female Epistolary Writing |
|
| �p���v�� | |
This thesis aims at presenting a comprehensive exposition on the calligraphic model textbooks for women published during the Edo period, on the basis of a close examination of most of the extant materials on this subject, rather than a partial study which the existing works tend to be. �@�@�@ |
|
| �a�@�� | |
�@�{�_���́A�]���̘_�l�������I�����ł���̂ƈقȂ�A�]�ˎ��㊧�s�̏��M��{�ɂ��Č����{�̖w�ǂɑ���Ȗ��Ȓ����Ɋ�Â��đ����I�Ȑ��������݂����̂ł���B |
|
| �w�ʘ_���v�| | |
| �@���a�Z��N�i��㔪���j�l�����牝�����̏N�W�ƌ������n�߂č��N�ő��������N�ɂȂ邪�A���̐��N���A�����S�Ɩ��ӎ�������Ă����̂��u���M��{�v�ł������B �@�����A���M��{�Ɋւ���_�l�͋ɂ߂ď��Ȃ��A���̋^��ɏ\���ɓ����Ă���镶���ɏo����Ƃ͂Ȃ������B���M��{�ɐG�ꂽ��̘_�l���A�_�҂ɂ���ď��M��{�̒�`��͈͂��܂��܂��ł�������A����ꂽ���Ⴉ���ʘ_��W�J���悤�Ƃ������̂��唼�ł������B �@�]���āA�������鏗�M��{�i�����M�̎�{�͖���Z�_���s���ꂽ���A���̔����͌������Ȃ��j���Ԃ��Ɏ������āA���̑S�̑��𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ��A�{�����̓��@�ƂȂ�ڕW�ƂȂ����B �@�����āA���M��{�ނɊւ���d�v�Ȍ܂̘_�_�������Ȃ킿�A���Ɂu���M�v�Ƃ������t�̈Ӗ��A���Ɂu���M��{�v�͈̔͂Ɨތ^�A��O�ɏ��M��{�ނɓ��L�́u�U�炵�����v�Ə��~��u�������v�̗p�@�A��l�ɏ��M��{�ނ̕M�ҁi�������Ɓj�A��܂ɏ������D�焟�����{�e�̒��ƂȂ��Ă���B �@�܂��A�u���M�v�̈Ӗ�����Ƃ���ł���B�]�ˑO�����{�̏ꍇ�A���ӂɁu���M�v�Ƃ�����̂́A���ۂɏ����M�������ꍇ�����|�I�ɑ����B�ŏ��̏��Жژ^����w������N���ځx�Ɋ��Ɂu���M��{�v�̏�����������悤�ɁA�u���M�����v�Ə̂����{�͍]�ˏ�������o�ꂵ�Č��\������ڗ����n�߁A�Ő����̋��ۊ��ɂ͌����݁u���M�����v�̏����ŏo�ł��ꂽ�B �@�������A�����p��{�̑S�Ă������M�Ƃ����킯�ł͂Ȃ������B�j���M�ł���Ȃ���u���M�v�Ə̂��錳�\�Z�N�i��Z��O�j���w���M�l�G���́x�̔@����{�����݂����悤�ɁA��������u���M�����v�̏����ɂ́u�����M�v�Ɓu�����p�v�̓�̈Ӗ������݂��Ă����̂ł���B�����āA�u���M�����v�Ɩ��ł�����{������Ɋ��s���ꂽ�̂����܂łŁA�₪�ď���������u���M�v�̓͏����Ă����A�����ɏ������Ƃɂ���{���������Ă������B���M��{�ނ̕ϑJ��A���M�ƒj�M�͋����[���ΏƂ��Ȃ��̂ł���A����ߖڂɂ��āu���M�v�̎��ォ��u�j�M�v�̎���ւƓ˓����Ă����̂ł���B �@�u���M�v�Ɋւ���]���̌����Ɍ�������_�̈�́A���M��{��S�āu�U�炵�����v���邢�́u���q�������i�����j�v�Ɍ��肷�邱�Ƃł���B�����͏��M��{�ɑ�����������F�ł���B�������A�S�����u�������v�̎�{��A�w������x�̂悤�ȁu��������v�̎�{�������ď��Ȃ��Ȃ��A�܂��A�ꌩ�����ł����̎��͏��m����S���ɏd�_���u���ꂽ�u����������v�������̂ł���B���̂ق��A�ړI�E�p�r�E�ҏW�`�����ɂ����Ċ�{�I�Ɉَ��ł���u��{�v�Ɓu�p���́v����ʂ��邱�ƂŁA���M�E�j�M�Ƃ̊W�₻���̐�������������ɂȂ�̂ł���B �@�@�@�����M�q���� 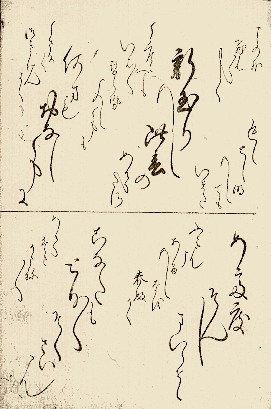 �@�����ŁA���M��{�E���M�p���́E���M�������E�j�M���p��{�E�j�M���p���͂̌ܗތ^�i�{�e�ł͂������u���M��{�ށv�Ƒ��́j���番�͂���ƁA���̂悤�ȏo�œ��������炩�ƂȂ�B �@�����ŁA���M��{�E���M�p���́E���M�������E�j�M���p��{�E�j�M���p���͂̌ܗތ^�i�{�e�ł͂������u���M��{�ށv�Ƒ��́j���番�͂���ƁA���̂悤�ȏo�œ��������炩�ƂȂ�B�@�@�i�P�j���M��{�c�]�ˏ�������]�˒����i���܂Łj�ɂ����ĖZ�_���s�B�s�[�N�͋��ۊ��B �@�@�i�Q�j���M�p���́c�i�P�j�Ɠ��l�̐��ڂ�H�邪�A���s�_���́i�P�j�������Ȃ��A��O�Z�_�B �@�@�i�R�j���M�������c���Ƀs�[�N�͌���ꂸ�A�]�˒����ɘZ�_�قNJ��s�B�i�P�j�A�i�Q�j�ɔ�ׂ��������B �@�@�i�S�j�j�M���p��{�c���ȍ~���s�[�N�ŁA�]�˒��E����ɖ�O�Z�_���s�B �@�@�i�T�j�j�M���p���́c�]�˒����i���ȍ~�j����]�ˌ���ɂ����Ė��Z�_���s�B �@���Ȃ킿�������ɁA��́u���M�v����u�j�M�v�ւ̈ڍs�A������́u��{�v����u�p���́v�ւ̐��ڂ����ĂƂȂ�B�����āA�u���M�v�́u��{�v���S�A�u�j�M�v�́u�p���́v���S�ł��邱�Ƃ���������B���̕ω��͎��p���̏d����o�ŕ��̏������X���ɘA��������̂ł��낤�B �@���\�ܔN�i��Z���j���w���d��L�x���i��N�i�ꎵ�Z�܁j���w���M�q�����x�����Ɍ�����u���M�v�̋����́A���M�ɂ����鏑���̕ω��⏗�M�̒j�������ۂɑ���x���ł������ƌ��Ȃ��邪�A���̍����珗�M��{�̏o�ł�����ɂȂ��Ă����̂ł���B�����āA�܂��ɂ��̎����Ɋ����������Ƃ������Óނł������B�Óނ́A���\�O�N�i��Z��Z�j���w�����ˏ��w���x�⌳�\���N���w�����ꋳ�E�����q���x�̍�҂Ƃ��Ēm���邪�A�ޏ��͉������j��A�ł��d�v�Ȑl���̈�l�ł���A�M���ɂ�����ׂ������[�։Ƃł������B �@���Ƃ��A���M��{�ނ̍�҂Ɋւ��Ă���ꂪ�m�蓾����͋ɂ߂ĖR�������A�ߐ����M�̑o�����鋏���Óނƒ��J�얭�[�ɂ��ẮA���̍�i�Q����ӎ�������̒f�Џ��ɂ�莖�Ղ◝�O�ւ̃A�v���[�`�����݂��B �@�܂��A�����Óނł́w�����͊Ӂx�w�����ˏ��w���x�w�����͓s�D�x�̎O�_�ɏœ_�Ă��B�勝�ܔN�i��Z�����j���w�����͊Ӂx�ł́u�����������炵�����t�����v���������ꂽ���A����͒Óނ̑��̒���ɂ����ʂ��闝�O�ł������B�܂��A�w�����ˏ��w���x�͏��p���͒��ł��ڍׂȎ{����Ȍ��ȏ������D��Ȃǂ̓_�ŗD�ꂽ���̂ł������B�{���̉e�����ɕ҂܂ꂽ���X�̗ޖ{�̉e�����l����ƁA�w�����ˏ��w���x�قǑ����̏����ɓǂ܂ꂽ���p���͂͂Ȃ��ƌ�����B�{�������X�Ȃ�ʕ��y�����������R�́A�i�P�j���p���̍����A�i�Q�j�������g�̒���A�i�R�j�����̋����ɑ���g�����̒��z�̎O�_�ɋA���邱�Ƃ��ł��悤�B����ɉ����l�N�i�ꎵ�l���j���w�����͓s�D�x�́A�����̑̍قŌÓT�̋��{���L�����u����������v�ł������B���̕��@�_�Ɏa�V���͂Ȃ��������A�w�����L�x���̌R�����܂ޕ��L������̌ÓT�I���{�������ɋ��߂��_���ِF�ł������B �@���̂悤�ɁA�Óނ̒���͓Ƒn�I�����I�ł��������A����A���M��{�̍ő���Ƃł��钷�J�얭�[�́A���M��{�ނ̕��y�ɍł������ȓ������Ȃ����l���ł���A�]���̐����I���M�̐M��҂ɂ͎�e����Ȃ��悤�ȓƓ��ȎU�炵�����ňꏑ�����Ȃ����������Ƃł������B �@�ޏ��̎�{�͌��\���N�i��Z��l�j���w���̂��T���x���ŏ��Ƃ��ĕ��N�܂ŘZ�Z�N�Ԃɂ킽���Ċ��s���ꂽ���A���̕M�@�̓Ǝ������i���̑����ɔ����āA���e�ʂł̓��F�͂��܂茩���Ȃ��B�킸���ɋ��ۈ�Z�N�i�ꎵ��܁j���w�єT�C�x�́u��K�̎d�p�̎��v�ɕM�����O�̈�[���M�������ł���B�����ŁA���[�́u�����ɂ͏����炵�������������邪�A��ɏ_�a��ӓ|�̕M�v�ł͂Ȃ炸�A�ɋ}���݂ŕω��ɕx�݂Ȃ���A�Ȃ����S�̂̒��a���Ƃꂽ�����łȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Əq�ׂĂ��邪�A���́u�����v�������[���̐^���ł������B �@�Óނ��A�����́u�_�A���A�́A�͂˂Ȃǂ̏����Ȃ������܂�����v�i�w�����ˏ��w���x�j�Əq�ׂ��̂́A���炭�A���\�����痬�s���n�߂����[���ɑ���ᔻ�ł��낤�B�����̗��z���u�₳�����v�ɋ��߂��ÓނƁA������u���炩���v�Ɍ��o�������[�ɂ͋��ʂ���ʂ�����ꂽ�B���������[�́A�u���炩���v����Ƃ��Ȃ�����A�����ɍ��߂�ꂽ�����A�_��⎚�z��ɂ�����ω��ƒ��a����`�Ƃ��Ă���A�|�p�ƂƂ��ď���Nj�����p�������������B �@���ۊ����s�[�N�Ƃ�����I�Ԃ͏��M��{�ނ̉�������ŁA���̎����ɏ������Ƃ��y�o���A�����̏��M��{���o�ł��ꂽ�B�������A���d�v�Ȃ̂́A���M�̐����������ɐ��݂��Ă�����ނ��@��N���������Ƃł���B�킸�����Łw���M����݂ǂ�x���������V�ˏ����E�t���{���́A���͔d�B���p�S�V�h���̕S���̖��ł������B�ޏ���̏r�˂𐢂ɒm�炵�߂��̂͏���̌��т��傫���B����͏o�ł��ׂ��\���̕M�Ղ����߂Ă�܂Ȃ������̂ł���B �@���āA���M��{�ɕp�o����u�U�炵�����v�Ɓu�������i���j�v�ɂ��ẮA�����̗ᕶ���f�����~�X�_�q�����B�u�U�炵�����v�͕��������ȍ~�̋M���Љ�ɍL�����Ă������@�ł��������A�₪�ĕ��Ə����ɂ��g�y���A�]�ˎ���ɂ͏��M��{�ނɂ���ď����ɂ����y�����B�������ߐ��ł́A�����ȗ��̏��l���ɍS�D���邱�Ƃ͂Ȃ��A���i�ɂ������镡�G�ȎU�炵�����i�ԏ��j�ȂǓƎ��̓W�J���������B�܂��A�U�炵�����ɂ͓��ʂȊ�����߂��邱�Ƃ��������߁A�j�����Ă̎莆�ɂ͕s�K���Ƃ���A�t�ɁA�j�V��ɂ͍D�܂��X��������ꂽ�B���̂ق��A�U�炵�����͌|�p���̟��{�ɂ��𗧂����Ǝv����B �@���Èȗ��́u�����v����h�������u�������i���j�v�́A�ߐ��ł́u�߂ł����������v���ł���ʓI�Ȍ`�ƂȂ������A�������̏��Ȃɂ�����u�����������v�u���X�������v��A���M��{�ނɂ�����u�������v�̏d���I�g�p�ȂǁA���ꎖ����������B�܂��A�u�������v�̗p��Ɗ֘A���Ē���̕ω����������A�]�ˌ���ɂ́A������ɑ���ׂ��Ƃ��ꂽ����̗��r�I�Z���Ԃ̂����ɏ����ꂽ���Ƃ��������鎖���A����ɂ���������I�ȕ��ʂ⍁���̋�̓I�L�ڂ��ڗ��悤�ɂȂ����B �@�����ɂ����ď������D��͂قƂ�Ǖ҂܂�邱�Ƃ͂Ȃ��A�j�����珗�����Ă̎莆�̍�@�������ɂ����f���ꂽ�ƍl������B�����������̏�����@���w���[�i�ށx�w���[�M�@�x���Ɍ�����̂��������D��̐��I����Ƃ���邪�A�����̗�@���͔�`���I���i���F�Z���A�܂��A��������ꂽ�����̂��߂̂��̂ł������B����A�ߐ��ŏ��̏�����@���ł��閜���O�N�i��Z�Z�Z�j���w������W�x�́A������@�����J���A���Ƃ��珎���ւƍL����_�@�������炵���_�ŏd�v�ȈӋ`��S�����̂ł��������A�{���ɂ͏������D��͊܂܂�Ă��Ȃ������B �@�������Ɍc���O�N�i��Z�܁Z�j���w���ނȂ��T���i������`���j�x�ɂ́A�]���ɂȂ��ڍׂȏ������D�炪����ꂽ�B��y�E���y�E���y�ȂǘZ�K���̑��ڕʗᕶ���f������̐���A�����I�ōs���͂������ӂȂǁA�{���ɂ͋ߐ��̏������D��̓��F�������ł������B�܂��A���\���A�����Óނ́u�������₤�̎w��\�����v�͕K�v�ŏ����̏��D���I�m�ɂ܂Ƃ߂Ă���A�ߐ��ł͍ł����y�����������D��ł������B�����A���J�얭�[�́u���������₤�S���̎��v�i�������J���j���R���p�N�g�ȏ��D��ł���A�㑱�̏��D��ɉe����^�����B���̂ق��A�����Z�N�i�ꎵ�l��j���w�������ؕ��Ɂx�⊰���l�N�i�ꎵ�܈�j���w�����爻�сx�A�V�ۈ��N�i�ꔪ�l��j���w�V�� �����爻�сx�Ȃǂ̏��D����A��s�����Ɋ�������Ȃ�����Ǝ��̓��e���܂�ł����B �@������ɂ��Ă��A�����ߐ��̏������D��̓��F�́A�i�P�j���D��̏������A�i�Q�j�j�����̋����A�i�R�j���ۓI�E��̓I�L�q�Ɍ��o����B���Ȃ킿�A�����͕��ƎЉ�̏��D������̂܂�e�����̂ł͂Ȃ��A�����̎���܂��Ȃ���K�X�C���������Ă������̂ł���B |
|